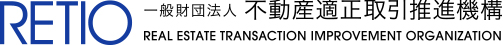昭和41年~昭和50年
該当件数 件
※判 決 日 クリックにより年月日順の並び替えができます。
| No. | 判決日 | 概要 | 事件番号 | RETIO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | S50.12.26 |
売主又は買主の一方から仲介の委託を受けた宅地建物取引業者が、委託を受けない当事者に対して報酬請求権を取得するためには、客観的にみて、当該業者が相手方当事者のためにする意思をもつて仲介行為をしたものと認められることを要するとした事例 |
RETIO 113-098
|
|
| 2 | S50.12.25 |
土地区画整理法による土地区画整理のための換地予定地を不法に占有する者がある場合、従前の土地所有者は、これに対し所有権に基づく物上請求権と同様の権利を行使することができるとされた事例 |
||
| 3 | S50.12.23 |
甲から所有権を譲り受けてその登記を経由した乙は、登記簿滅失による回復登記申請期間を徒過しても、乙の登記後甲から所有権を譲り受けた丙に対し、自己の所有権取得を対抗できるとされた事例 |
||
| 4 | S50.12.18 |
地方税法73条の21第1項にいう「固定資産課税台帳に固定資産の価格が登録されている不動産」とは、不動産を取縛した日の属する年の1月1日における当該不動産の価格が固定資産課税台帳に登録されている不動産を指すとされた事例 |
||
| 5 | S50.12.1 |
不動産の譲渡が詐害行為であるとして取り消され、受益者が現物返還に代わる価格賠償をすべきときの価格は、特別の事情がないかぎり、当該詐害行為取消訴訟の事実審口頭弁論終結時を基準として算定されるとした事例 |
||
| 6 | S50.11.28 |
土地賃借人が建物保護に関する法律1条によりその賃借権を第三者に対抗しうるためには、賃借人が借地上に自己名義で登記した建物を所有していることが必要であり、自己の子名義で登記をした建物を所有していても、その賃借権を第三者に対抗しえないとした事例 |
||
| 7 | S50.11.28 |
仮登記担保権者が、目的不動産を自己の所有とすると意思表示をしただけで清算をせず、仮登記のまま目的不動産を第三者に譲渡し、第三者が本登記を経た場合において、本登記が債務者の意思に基づかずにされたときは、債務者は第三者に対して本登記の抹消登記手続を請求することができるとした事例 |
||
| 8 | S50.11.21 |
物上保証人に対する抵当権の実行により、競売裁判所が競売開始決定をし、これを債務者に告知した場合には、被担保債権についての消滅時効は中断するとされた事例 |
||
| 9 | S50.11.21 |
宅地建物取引業法(昭和46年法律第110号による改正前のもの)11条の2第2項にいう「その者が、みずから主として業務に従事する事務所」とは、当該事務所の業務を主として取引業者みずから行う事務所であることを要するにとどまらず、当該取引業者が取引業務を自己の主たる業務として行う事務所であることを要するとした事例 |
||
| 10 | S50.11.7 |
共同相続人の一部から遺産を構成する特定不動産の共有持分権を譲り受けた第三者が当該共有関係の解消のためにとるべき裁判手続は、遺産分割審判ではなく、共有物分割訴訟であるとされた事例 |
||
| 11 | S50.10.28 |
建物新築による不動産工事の先取特権保存の登記につき、建物所在地番の更正が許されないとされた事例 |
||
| 12 | S50.10.14 |
第三者の売買予約に基づく所有権移転請求権保全の仮登記が存在する建物の競落人は、後日売買予約の完結により仮登記の本登記がなされ、目的物件の所有権を喪失した場合には、当該建物の売買(競落)を解除することができるとした事例 |
||
| 13 | S50.10.2 |
バッティング練習場として使用する目的の土地の賃貸借契約について、承諾を受けて建築する建物も仮設のバラック式のものに限られていた等の事実関係のもとでは、同契約は借地法1条にいう建物の所有を目的とする賃貸借には当たらないとした事例 |
||
| 14 | S50.9.25 |
時効による農地所有権の取得については、農地法三条の適用はないとされた事例 |
||
| 15 | S50.9.11 |
借地人が、地上建物を改築するにあたり、旧建物を一時に全部取り毀さず、新建物の建築工事と並行してその進行状況に応じて順次取り毀し、新建物完成の時に全部取り毀したときでも、旧建物の取毀しは、借地法7条にいう建物の滅失にあたるとした事例 |
||
| 16 | S50.9.9 |
仮登記担保権者は、目的不動産につき後順位権利者があるときは、債務者に対する被担保債権以外の金銭債権をもって自己の負担する清算金支払債務と相殺することができないとされた事例 |
||
| 17 | S50.7.17 |
仮登記担保権を有する債権者が予約完結権を行使した場合において、債権者が清算金を支払う必要があり、債務者はその支払があるまで目的不動産の本登記手続の履行を拒みうるときは、目的不動産の所有権は、予約完結権の行使により直ちに債権者に移転するものではないとした事例 |
||
| 18 | S50.7.14 |
建物につき改造が施され、物理的変化が生じた場合、新旧の建物の同一性が失われたか否かは、新旧の建物の材料、構造、規模等の異同に基づき社会観念に照らして判断すべきであり、建物の物理的変化の程度によつては、新旧の建物の同一性が失われることもあり得るとした事例 |
||
| 19 | S50.7.10 |
借地上建物の賃借人の敷地利用が敷地の使用収益権の範囲を逸脱したものとして、土地所有者より建物賃借人に対する建物の築造その他工作物を設置することの禁止及び本件土地上に設置した物件の収去請求が認められた事例 |
||
| 20 | S50.6.27 |
売買契約の買主が口頭で代金の受領を求める旨の催告を売主の同居する家族で通常人の理解能力を有する者に対してした場合には、右催告は、売主本人に到達したものと解すべきであるとされた事例 |
||
| 21 | S50.6.26 |
道路工事中であった県道の工事標識板や赤色灯が、直前に通過した車両により倒され灯りが消され状態であったために引き起こされた事故について、道路管理に瑕疵はなかったとして国賠法に基づく請求が棄却された事例 |
||
| 22 | S50.5.27 |
財産分与としてされた不動産の譲渡は、譲渡所得課税の対象となるとされた事例 |
||
| 23 | S50.5.27 |
それぞれ登記がされている隣接する二棟の建物につき、2階の隔壁の一部を除去し連絡したという事実のみで、両建物がそれぞれの建物としての独立性を失い一棟の建物になつたものと判断することはできないとした事例 |
||
| 24 | S50.4.25 |
民法94条2項にいう第三者とは、虚偽表示の当事者又はその一般承継人以外の者であって、その表示の目的につき法律上利害関係を有するに至った者をいい、甲乙間における虚偽表示の相手方乙との間で表示の目的につき直接取引関係に立った丙が悪意があっても、丙からの転得者丁が善意であるときは、丁は同条項にいう善意の第三者にあたるとした事例 |
||
| 25 | S50.4.25 |
土地又は建物の賃借人は、賃借物に対する権利に基づき自己に対して明渡を請求することができる第三者からその明渡を求められた場合には、それ以後、賃料の支払を拒絶することができるとした事例 |
||
| 26 | S50.4.22 |
賃借地の一部に属するものと信じて賃貸人以外の第三者所有の隣地を占有していた者が、国に物納された右賃借地の払下を受け、以後所有の意思をもって第三者の所有地を占有するに至ったというだけでは、これを自己の所有と信ずるにつき過失がなかったとはいえないとされた事例 |
||
| 27 | S50.4.18 |
土地賃借人が借地上に所有する建物につき、第三者名義で保存登記をし、あるいは第三者に所有権移転登記をした場合でも、それが登記上の名義のみであって建物所有権の帰属に変動がないときは、敷地賃借権について民法612条(賃借権の譲渡及び転貸の制限)所定の譲渡又は転貸はないとした事例 |
||
| 28 | S50.4.11 |
農地の買主が売主に対して有する知事に対する所有権移転許可申請協力請求権の消滅時効は、10年であるとした事例 |
||
| 29 | S50.4.11 |
文化財保護法が、史跡名勝天然記念物に関する現状変更行為禁止の代償として補償規定を定めなかったことをもって、違憲無効ということはできないとした事例 |
||
| 30 | S50.4.10 |
いわゆる仮登記担保契約は、被担保債権額と目的不動産の価額との間に著しい較差がある場合であっても、特段の事情のないかぎり、暴利行為として公序良俗に反するものということはできないとした事例 |
||
| 31 | S50.4.10 |
分譲住宅において、共有物であるバルコニーの改築禁止の建築協定は公序良俗に反しないとして、団地住宅管理組合の、分譲住宅購入者が行ったバルコニー温室工事に対する原状回復請求を認めた事例 |
||
| 32 | S50.4.8 |
養子とする意図で他人の子を嫡出子として出生届をしても、出生届をもって養子縁組届とみなし、有効に養子縁組が成立したものとすることはできないとされた事例 |
||
| 33 | S50.4.4 |
宅地建物取引業者が行った法律事務の取扱いについて、商法503条により商行為となるが、それが一回限りであり、かつ、反復の意思をもってなされたものでないとして、弁護士法72条に触れないとした事例 |
||
| 34 | S50.3.6 |
土地の売主の共同相続人の一部の者が登記手続義務の履行を拒絶しているため、買主が代金支払いを拒絶している場合に、他の相続人は履行を拒絶している相続人に対し、買主に代位して買主の所有権移転登記手続請求権を行使することができるとした事例 |
||
| 35 | S50.2.28 |
経年などにより、骨組みである丸太の損傷が激しく、特に土と接している根元部分は腐触しいつ倒壊するかわからない危険な状態となっていた簡素な作業場兼資材置場用の建物について、借地法2条1項にいう建物の朽廃に当たるとされた事例 |
||
| 36 | S50.2.25 |
いわゆる仮登記担保権者は、目的不動産の換価処分前においては、自己が不動産を使用収益することができる旨の約定がある等特段の事情のないかぎり、仮登記に遅れて不動産を賃借し占有する第三者に対し、賃料相当の損害金の賠償を請求することができないとされた事例 |
||
| 37 | S50.2.20 |
大型ショッピングセンター内の建物賃貸借において、借主の賃貸借契約の特約違反のみならず信頼関係の破壊があったとして、貸主の契約解除を認めた事例 |
||
| 38 | S50.2.13 |
借地人が借地上に自己を所有者と記載した表示の登記のある建物を所有する場合は、建物保護に関する法律一条にいう登記したる建物を有するときにあたるとした事例 |
||
| 39 | S50.1.31 |
農地について締結された賃貸借契約に確定期限が付されている場合において賃借権設定許可申請手続がされないままその期限が到来したときは、賃貸人の賃借人に対する許可申請手続義務は消滅するとされた事例 |
||
| 40 | S50.1.31 |
第三者の不法行為又は債務不履行により家屋が焼失した場合、その損害につき火災保険契約に基づいて家屋所有者に給付される保険金は、第三者が負担すべき損害賠償額から損益相殺として控除されるべき利益にはあたらないとした事例 |
||
| 41 | S49.12.24 |
債権担保のため、債務者の不動産に所有権移転の仮登記に代えて、他の債権者の所有権移転の仮登記が被担保債権の消滅にかかわらず残存しているのを利用して新債権者への請求権移転の附記登記をした場合、附記登記後に不動産につき利害関係を有するに至った第三者は、流用による登記の無効を主張することができないとされた事例 |
||
| 42 | S49.12.24 |
約1年9ヶ月前に日本に帰化した遺言者の、署名は存するが押印を欠く英文の自筆遺言証書について有効とされた事例 |
||
| 43 | S49.12.20 |
準禁治産者である権利者が保佐人の同意を得られないため訴を提起できない場合でも、その権利についての消滅時効の進行は妨げられないとされた事例 |
||
| 44 | S49.12.20 |
不動産競売手続において再競売が実施された場合には、再競売の競落期日の終りに至るまで配当要求をすることができるとされた事例 |
||
| 45 | S49.12.20 |
所有権又は賃貸権限を有しない者から不動産を賃借した者が同一物について真の権利者とさらに賃貸借契約を締結したときは、はじめの賃貸借は賃貸人の使用収益させる義務の履行不能によって終了するとした事例 |
||
| 46 | S49.12.17 |
転用目的の農地の売主は、特別の事情がないかぎり、買主に対し、農業委員会が農地法五条の許可の判断資料として事実上提出を求めた隣接農地所有者の承諾を取得すべき義務を負うものではないとされた事例 |
||
| 47 | S49.12.17 |
商法266条の3第1項前段所定の第三者の取締役に対する損害賠償請求権の消滅時効期間は10年と解すべきとした事例 |
||
| 48 | S49.12.16 |
宅地建物取引業法12条1項にいう「宅地建物取引業を営む」とは、営利の目的で反復継続して行う意思のもとに宅地建物取引業法2条2号所定の行為をなすことをいうとした事例 |
||
| 49 | S49.12.6 |
抵当権の実行による不動産競売手続において配当表が作成された場合、配当期日に出頭した債務者又は抵当不動産の所有者が債権者の債権に対し異議を申し立て期日に異議が完結しなかつたときは、債務者又は所有者は、配当表に対する異議の訴を提起することができるとした事例 |
||
| 50 | S49.11.22 |
建物が売買により順次占有が承継され、当初建物占有者の占有開始から20年の経過により、現建物所有者につき取得時効が完成した旨の主張は、仮にその占有の間に占有承継人として別の者が介在することが証拠上認められるならば、その者の占有を取得時効の期間として主張する趣旨を含むと解されるとした事例 |
||
| 51 | S49.11.14 |
特定の事項について共同代表取締役の意思が合致した場合において、代表取締役のある者が他の代表取締役に意思を外部に表示することにつき代表権の行使を委任することは、共同代表の定めに反しないとされた事例 |
||
| 52 | S49.11.5 |
信用保証協会が債務者及び保証人と、協会の代位弁済による求償債権の損害金につき法定利息と異なる約定をしても、協会は約定を第三者に対抗することはできないとされた事例 |
||
| 53 | S49.10.24 |
借地法6条(法定更新)の規定は、その要件を満たす事実が存在するかぎりこれに適用され、その適用回数についてなんら制限はないとされた事例 |
||
| 54 | S49.10.24 |
土地所有権に基づく物上請求権の訴訟においては、現実に家屋を所有してその土地を占拠し、土地所有権を侵害している者を相手方とすべきであるとし、家屋収去土地明渡請求の確定判決の効力は、事実審口頭弁論終結前に家屋を譲り受けた第三者に対し及ばないとされた事例 |
||
| 55 | S49.10.23 |
金銭債権担保のため不動産について代物弁済予約又は売買予約等の形式をとる契約が締結され、所有権移転請求権保全等の仮登記がされた場合における右契約の性質及び内容 |
||
| 56 | S49.9.26 |
借地法8条ノ2第2項の借地条件変更に関する裁判は、憲法32条、82条に違反しないとした事例 |
||
| 57 | S49.9.26 |
甲を欺罔してその農地を買い受けた乙が、農地法五条の許可を条件とする所有権移転仮登記を得たうえ、売買契約上の権利を善意の丙に譲渡して仮登記移転の附記登記をした場合には、丙は民法96条3項にいう第三者にあたるとされた事例 |
||
| 58 | S49.9.20 |
民法216条にいう工作物の破潰又は阻塞は、それが、自然力ないしは不可抗力によって生じた場合に限らず、工作物の所有者の故意過失によって生じた場合も含むとされた事例 |
||
| 59 | S49.9.20 |
借地法4条1項但書の正当事由の有無の判断基準時を賃貸借期間終了の時とし、その後の事情を判断基準時の事実関係を認定するための資料とした原審の認定判断は正当であるとされた事例 |
||
| 60 | S49.9.20 |
相続の放棄は、民法424条の詐害行為取消権行使の対象とならないとした事例 |
||
| 61 | S49.9.20 |
相続税の課税価格の算出上控除すべき弁済期未到来の金銭債務の評価方法 |
||
| 62 | S49.9.4 |
他人の権利の売主が死亡し、その権利者において売主を相続した場合、権利者は相続により売主の売買契約上の義務ないし地位を承継するが、相続前と同様その権利の移転につき諾否の自由を保有し、特別の事情のないかぎり、売買契約上の売主としての履行義務を拒否することができるとした事例 |
||
| 63 | S49.9.2 |
家屋の賃貸借終了に伴う賃借人の家屋明渡債務と賃貸人の敷金返還債務とは、特別の約定のないかぎり、同時履行の関係には立たないとした事例 |
||
| 64 | S49.7.12 |
賃借人の債務不履行により契約が解除され、土地賃貸借が終了した場合には、借地法6条1項の法定更新は適用されないとした事例 |
||
| 65 | S49.5.30 |
賃借家屋につき適法に転貸借がなされた場合であっても、賃貸人が賃借人の賃料延滞を理由として賃貸借契約を解除するには、賃借人に対して催告すれば足り、転借人に対して延滞賃料の支払の機会を与えなければならないものではないとした事例 |
||
| 66 | S49.5.8 |
土地売却の仲介をした宅建業者が売主との契約により売却にかかる土地の再評価税を自己の負担において代納付した場合、その代納付金が当該土地の仲介手数料を得た年度の収入を得るために支出した費用であって、その金額も算定可能であったときは、代納付金は同年度の経費として計上すべきであるとした事例 |
||
| 67 | S49.4.26 |
土地賃貸借の合意解除が、土地賃借人と建物賃借人との関係等により建物賃借人に対抗できるとされた事例 |
||
| 68 | S49.4.26 |
不動産賃貸借において、賃借人が約9年10月賃料を支払わず、その間、当該不動産を自己の所有と主張して賃貸借関係の存在を否定し続けた事情があるときは、賃貸人は、催告を要せず賃貸借を解除することができるとした事例 |
||
| 69 | S49.4.26 |
相続財産の限度での支払を命ずる判決が確定した場合における判決の効力 |
||
| 70 | S49.4.9 |
民法210条の囲繞地通行権の対象となる通路の幅員につき、建築基準法43条の規定基準を判断資料とすることができるとした事例 |
||
| 71 | S49.3.19 |
賃貸中の宅地を譲り受けた者は、その所有権の移転につき登記を経由しないかぎり、賃貸人たる地位の取得を賃借人に対抗できないとした事例 |
||
| 72 | S49.3.8 |
雑所得として課税された金銭債権が後日貸倒れにより回収不能となった場合、当該課税処分そのものが取消又は変更されなくても、国は、同処分に基づいて先に徴収した所得税のうち貸倒額に対応する税額を不当利得として納税者に返還する義務を負うとした事例 |
||
| 73 | S49.3.7 |
・指名債権が二重に譲渡された場合、譲受人相互の問の優劣は、確定日付ある通知が債務者に到達した日時又は確定日付ある債務者の承諾の日時の先後によって決するとした事例 |
||
| 74 | S49.2.7 |
不動産につき贈与を原因とする所有権移転仮登記が経由されているにとどまるときは、これにより仮登記権利者の所有権取得又は仮登記の当事者間における贈与契約の成立を推定することはできないとされた事例 |
||
| 75 | S49.2.5 |
行政財産である土地について建物所有を目的とし期間の定めなくされた使用許可が当該行政財産本来の用途又は目的上の必要に基づき将来に向って取り消されたときは、使用権者は特別の事情のないかぎり、取消による土地使用権喪失についての補償を求めることはできないとした事例 |
||
| 76 | S48.12.21 |
土地区画整理事業による換地処分確定後の換地につき、売買による所有権の移転があっても、換地に関する清算交付金請求権は、売買当事者間において清算交付金の帰属についての特段の合意がないかぎり、売買当事者の関係のみならず、整理事業施行者に対する関係でも、買主には移転しないとした事例 |
||
| 77 | S48.12.14 |
抵当不動産の譲渡を受けた第三者は、抵当権の被担保債権の消滅時効を援用することができるとした事例 |
||
| 78 | S48.12.11 |
農地の売買契約締結後、その現況が宅地となった場合には、特段の事情のないかぎり、売買契約は知事の許可なしに効力を生ずるとされた事例 |
||
| 79 | S48.12.7 |
従前地の一部の賃借人は、土地区画整理事業施行者から仮換地につき使用収益すべき部分の指定を受けなかったとしても、従前の土地所有者との間で、仮換地の特定部分について使用収益できる旨合意し、かつ、特定部分がそのまま本換地の一部となることを条件として換地処分終了後もこれを賃貸借する旨合意した場合には、従前の土地所有者との関係では特定部分について賃借権を主張することができるとした事例 |
||
| 80 | S48.11.22 |
破産者がした債務の弁済が破産管財人により否認され、その給付したものが破産財団に復帰したときは、さきにいったん消滅した連帯保証債務は、当然復活するとされた事例 |
||
| 81 | S48.11.16 |
昭和36年法律第74号による改正前の地方税法のもとにおいても、譲渡担保による不動産の取得は、同法73条の2第1項にいう「不動産の取得」にあたるとして、不動産取得税の課税が容認された事例 |
||
| 82 | S48.10.30 |
代理人がした商行為による債権につき本人が提起した債権請求訴訟の係属中に、相手方が商法504条但書に基づき債権者として代理人を選択したときは、本人の請求は、右訴訟が係属している間代理人の債権につき催告に準じた時効中断の効力を及ぼすとされた事例 |
||
| 83 | S48.10.30 |
・土地賃借人が破産しても、土地賃貸人の解約には正当な事由が必要であるとされた事例 |
||
| 84 | S48.10.18 |
旧都市計画法(大正8年法律第36号)16条1項に基づき土地を収用する場合、被収用者に対し土地収用法72条(昭和42年法律第74号による改正前のもの)によって補償すべき相当な価格を定めるにあたっては、当該都市計画事業のため同土地に課せられた建築制限を斟酌してはならないとした事例 |
||
| 85 | S48.10.12 |
農地売買につき、売主が買主と協力して農地法五条の許可申請をしたが手続上の不備で受理を拒まれたときは、許可申請をしたことをもって売主の買主に対する売買契約上の許可申請義務を果たしたとはいえないとされた事例 |
||
| 86 | S48.10.12 |
賃貸借における期間の定めは、当事者において解約権留保の特約をした場合には、その留保をした当事者の利益のためになされたものということができるが、そうでない場合には、賃貸人、賃借人双方の利益のためになされたものというべきであって、期間の定めのある賃貸借については、解約権を留保していない当事者が期間内に一方的にした解約申入は無効であり、賃貸借はそれによって終了することはないとした事例 |
||
| 87 | S48.10.12 |
土地賃借人の会社の代表者である賃貸人が、賃借人会社の自己破産を申し立て、これを理由に転賃貸権の消滅を主張することは信義則に反するとして、土地賃貸借契約は終了するとしても転借権は消滅しないとされた事例 |
||
| 88 | S48.10.11 |
債権者は、金銭を目的とする債務の不履行による損害賠償として、債務者に対し弁護士費用その他の取立費用を請求できないとした事例 |
||
| 89 | S48.10.9 |
権利能力のない社団の代表者が社団の名においてした取引上の債務は、社団の構成員全員に一個の義務として総有的に帰属し、社団の総有財産だけがその責任財産となり、構成員各自は、取引の相手方に対し個人的債務ないし責任を負わないとされた事例 |
||
| 90 | S48.10.5 |
入会部落の総有に属する土地の譲渡を受けた同部落の構成員は、譲渡前にこれを時効取得した者に対する関係において、民法177条にいう第三者にあたるとされた事例 |
||
| 91 | S48.10.5 |
抵当権の設定されている建物の買主は、抵当権の実行により建物が他に競落されたのち、不法占有中に建物に支出した費用に関し留置権を主張することはできないとした事例 |
||
| 92 | S48.10.5 |
重量鋼造り組立式工場が、堅固な建物に該当しないとされた事例 |
||
| 93 | S48.10.4 |
根抵当権者は、後順位担保権者など配当をうけることのできる第三者がなく、競売代金に余剰が生じた場合においても、極度額を越える部分について、当該競売手続においては、その交付をうけることができないとされた事例 |
||
| 94 | S48.9.18 |
土地およびその地上建物の所有者が建物の取得原因である譲受につき、所有権移転登記を経由しないまま土地に対し抵当権を設定した場合であっても、法定地上権は成立するとした事例 |
||
| 95 | S48.9.7 |
手形債務を主たる債務として手形外の連帯保証契約が締結されている場合において、連帯保証人に対し裁判上の請求がされたときは、手形債務についても消滅時効が中断するとされた事例 |
||
| 96 | S48.9.7 |
建物とともにその敷地の賃借権を譲り受けた者の有する借地法10条の建物買取請求権は、賃貸人が賃借人である譲渡人との間で賃貸借契約を合意解除しても、特段の事情がないかぎり消滅しないとした事例 |
||
| 97 | S48.7.19 |
無断転貸を理由とする賃貸借契約解除の意思表示は、それ以外の理由によつては解除をしないことが明らかにされているなど特段の事情のないかぎり、同時に借家法1条の2の解約申入としての効力をも有するとした事例 |
||
| 98 | S48.7.17 |
賃借人が賃借建物に附加した増・新築部分が、賃貸人に返還される以前に、賃貸人、賃借人いずれの責にも帰すべきでない事由により滅失したときは、特段の事情のない限り有益費償還請求権は消滅するとした事例 |
||
| 99 | S48.7.12 |
抵当不動産の第三取得者が、民法391条にもとづく優先償還請求権を有しているにもかかわらず、抵当不動産の競売代金が抵当権者に交付されたため優先償還を受けられなかつたときは、第三取得者は、抵当権者に対し不当利得返還請求権を有するとされた事例 |
||
| 100 | S48.7.12 |
数量の不足又は一部滅失の場合における売主の瑕疵担保責任の除斥期間は、善意の買主が、売買目的物の数量不足を知ったが、その責に帰さない事由により売主を知ることができなかった場合には、売主を知った時から起算されるとした事例 |
||
| 101 | S48.7.7 |
営利の目的であることが宅地建物取引業法12条1項の規定に違反して宅地建物取引業を営んだと認めるための要件とされた事例 |
||
| 102 | S48.7.3 |
無権代理人を相続した本人は、無権代理人が民法117条により相手方に債務を負担していたときには、無権代理行為について追認を拒絶できる地位にあったことを理由として、債務を免れることができないとした事例 |
||
| 103 | S48.6.28 |
未登記建物の所有者は、その建物が固定資産課税台帳上他人の所有名義で登録されていることを知りながら、これを明示または黙示に承認していた場合には、民法94条2項の類推適用により、名義人が所有権を有しないことを善意の第三者に対抗することができないとした事例 |
||
| 104 | S48.6.21 |
通謀による虚偽の登記名義を真正なものに回復するための所有権移転登記手続請求訴訟における被告敗訴の確定判決は、口頭弁論終結後被告から善意で当該不動産を譲り受けた第三者に対してその効力を有しないとされた事例 |
||
| 105 | S48.5.25 |
農地法20条2項各号所定の事由は、都道府県知事が同条による許可を与えるについての要件であって、農地の賃貸借の解約権の発生ないし行使の実体的要件をなすものではないとされた事例 |
||
| 106 | S48.4.26 |
甲が所有土地につき、乙の同意のないままに乙への所有権移転登記を経由し乙名義で丙に売却した等の事情のある場合において、乙に譲渡所得があるとした課税処分は無効であるとした事例 |
||
| 107 | S48.4.24 |
親権者が共同相続人である数人の子を代理してした遺産分割の協議は、民法826条2項の利益相反行為に当たるとして、追認のない限り無効であるとした事例 |
||
| 108 | S48.4.13 |
建物所有を目的とする土地賃貸借契約の借地人が、無断増改築等禁止の特約に違反して行った建物改修工事が、賃貸人に対する信頼関係を破壊するものと認められた事例 |
||
| 109 | S48.4.13 |
土地に対する使用貸借上の借主の権利の時効取得が成立するためには、土地の継続的な使用収益という外形的事実が存在し、かつ、その使用収益が土地の借主としての権利の行使の意思に基づくものであることが客観的に表現されていることを必要とするとした事例 |
||
| 110 | S48.4.6 |
入札売買において第三者が買受希望者に対し売主の処分権を否定する虚偽の表示をした場合において、その行為が第三者の権利保全の目的から出たもので、その表示事実を真実と信じ、、かつ、その表示が社会的に相当な方法でなされたときは、不法行為は成立しないとされた事例 |
||
| 111 | S48.3.13 |
・入会権確認訴訟において、入会権者が死亡した場合には、入会慣行に従って死亡者に代わり入会権を取得した者が、その訴訟手続を承継するとした事例 |
||
| 112 | S48.2.2 |
・家屋賃貸借における敷金は、賃貸借終了後家屋明渡義務履行までに生ずる、賃貸人の賃借人に対する一切の債権を担保するものであり、敷金返還請求権は、賃貸借終了後家屋明渡完了の時において、それまでに生じた被担保債権を控除しなお残額がある場合に発生するとした事例 |
||
| 113 | S48.1.26 |
不動産の交換契約の当事者甲が、契約に基づき相手方乙の提供した不動産の占有を開始しても、甲が契約の締結に際し詐欺を行ない、そのため契約が乙の錯誤により無効と認められるときは、甲の占有は所有の意思をもって善意・無過失で開始されたと認めるべきではないとした事例 |
||
| 114 | S47.12.22 |
無権代理人に対する無権代理行為の追認は、その事実を相手方が知らなかったときは、これをもって相手方に対抗することはできないが、相手方において追認のあった事実を主張することは何ら妨げないとされた事例 |
昭47(オ)86号 |
|
| 115 | S47.12.19 |
契約の一部が要素の錯誤により無効であっても、他の部分の効力には影響がないとされた事例 |
||
| 116 | S47.12.14 |
従前地の一部につき、甲の賃借権を乙が譲り受けたが、別に賃借権を主張する者があったため、土地区画整理事業施行者が紛争の経緯を考慮して、甲に対し従前地に対する換地予定地につき賃借権の目的となる部分の指定通知をしたときは、乙は同部分につき使用収益権を取得するとした事例 |
||
| 117 | S47.12.7 |
建物の登記簿上の所有名義人にすぎない者は、たとえ、所有者との合意により名義人となった場合でも、建物の敷地所有者に対して建物収去義務を負わないとした事例 |
||
| 118 | S47.11.28 |
甲が、乙と相通じ、仮装の所有権移転請求権保全の仮登記手続をする意思で、乙の提示した所有権移転登記手続に必要な書類に、これを仮登記手続に必要な書類と誤解して署名押印したところ、乙がほしいままに書類を用いて所有権移転登記手続をしたときは、甲は、乙の所有権取得の無効をもって善意・無過失の第三者に対抗することができないとされた事例 |
||
| 119 | S47.11.28 |
代金を5年間の分割払いとしてその完済後売主が所有権移転登記をするとし、その支払期間中の公租公課は買主が負担するとした土地売買契約において、買主の公租公課負担義務の不履行を理由とする売主の契約解除を認めた事例 |
||
| 120 | S47.11.21 |
法人における民法192条(即時取得)の善意・無過失は、その法人の代表者について決するが、代理人が取引行為をしたときは、その代理人について決すべきであるとされた事例 |
||
| 121 | S47.11.16 |
甲の所有建物を買受けた乙が、売買代金を支払わないままこれを丙に譲渡した場合には、甲は、丙からの物の引渡請求に対して、末払代金債権を被担保債権とする留置権の抗弁権を主張することができるとした事例 |
||
| 122 | S47.11.16 |
・賃貸借契約の当事者一方が、信義則上の義務に違反して信頼関係を破壊し、賃貸借関係の継続を著しく困離ならしめたときは、他方の当事者は催告なく賃貸借契約を解除することができるとした事例 |
||
| 123 | S47.11.9 |
民法936条1項の規定により相続財産管理人が選任された場合において、相続財産に関する訴訟については、相続人が当事者適格を有し、相続財産管理人は、相続人全員の法定代理人として訴訟に関与するものであって、相続財産管理人としての資格では当事者適格を有しないとされた事例 |
||
| 124 | S47.11.9 |
従前の土地につき賃借権を有する者は、仮換地につき、土地区画整理事業の施行者から仮にその権利の目的となる土地またはその部分の指定を受けないかぎり、当該仮換地を使用収益することができないとされた事例 |
||
| 125 | S47.11.2 |
土地の抵当権設定当時その土地が更地であつた場合には、その後に地上に建物が建築されることを抵当権者が承認した事実があっても、土地の競売により建物のため法定地上権が成立するものではないとされた事例 |
||
| 126 | S47.10.26 |
代物弁済予約形式の債権担保契約を締結した債権者が、その担保目的を実現するにあたって、後順位債権者に優先して弁済を受けうる利息・損害金については、民法374条(抵当権の順位の変更)の規定は準用されないとされた事例 |
||
| 127 | S47.9.8 |
共同相続人の一人が相続財産につき単独所有者としての自主占有を取得したと認められた事例 |
||
| 128 | S47.9.7 |
売買契約が詐欺を理由として取り消された場合における当事者双方の原状回復義務は、同時履行の関係にあるとした事例 |
||
| 129 | S47.7.25 |
位置指定道路の廃止処分につき、敷地所有者の承諾はないものの、同所有者において道路が従前よりは狭くなる程度のことを承知のうえで廃止申請書添付の図面に押印したという判示の事情があるときは、特別の場合を除き、同道路の廃止処分を当然無効とすることはできないとした事例 |
||
| 130 | S47.7.18 |
・生前相続による不動産所有権の取得は、登記を経なければ第三者に対抗できないとされた事例 |
||
| 131 | S47.7.18 |
借地上の建物の所有権が第三者に移転する場合には、それが任意売買・強制競売によるを問わず、特別の事情がないかぎり、その敷地の借地権は、建物の所有権とともに当然に第三者に移転するとした事例 |
||
| 132 | S47.7.13 |
土地の賃借人は、借地上に妻名義で保存登記を経由した建物を所有していても、その後その土地の所有権を取得した第三者に対し、建物保護に関する法律一条により、その土地の賃借権をもって対抗することができないとされた事例 |
||
| 133 | S47.7.6 |
登記簿上後順位の抵当権者または仮登記担保権者であった者でも、先順位の仮登記担保権者から本登記手続承諾請求を受けた当時、既に他にその登記につき附記登記による権利移転の登記を経由した者は、仮登記担保権者に対して清算金を受けるべき地位にあることを主張できないとされた事例 |
||
| 134 | S47.6.30 |
不動産の任意競売の申立人は、被担保債権につき、申立書に表示した債権の額に制限されないで、競売代金から配当を受けることができるとされた事例 |
||
| 135 | S47.6.27 |
隣接居宅の日照通風を妨害する建築基準法に違反した建物建築につき、不法行為の成立が認められた事例 |
||
| 136 | S47.6.23 |
土地賃貸借の期限付合意解約が借地法11条に該当しないとされた事例 |
||
| 137 | S47.6.22 |
土地の賃借人は、借地上に妻名義で保存登記を経由した建物を所有していても、その後その土地の所有権を取得した第三者に対し、建物保護に関する法律一条により、その土地の賃借権をもって対抗することができないとされた事例 |
||
| 138 | S47.6.15 |
賃貸家屋の一部の無断転貸を理由に賃貸借契約が解除された後、建物所有者より家屋を譲り受けた転借人の賃借人に対する明渡請求が、信義則違反または権利の濫用にあたるとして棄却された事例 |
||
| 139 | S47.6.2 |
権利能力なき社団の資産たる不動産については、社団の代表者が、社団の構成員全員の受託者たる地位において、個人の名義で所有権の登記をすることができるにすぎず、社団を権利者とする登記をし、または、社団の代表者である旨の肩書を付した代表者個人名義の登記をすることはできないとされた事例 |
||
| 140 | S47.5.30 |
伐採を目的とする山林立木の売買契約における売主の履行義務は、立木の引渡をもって完了するものではなく、売主は、立木の伐採、造材、搬出に必要な相当の期間、買主を山林敷地を使用させる義務を負うとされた事例 |
||
| 141 | S47.5.25 |
民法974条3号(証人及び立会人の欠格事由)にいう「配偶者」には、推定相続人の配偶者も含まれるとされた事例 |
||
| 142 | S47.5.25 |
死因贈与の取消については、民法1022条(遺言の撤回)がその方式に関する部分を除いて準用されるとされた事例 |
||
| 143 | S47.5.23 |
借地法10条の建物買取請求における買取価格は、建物の存在する場所的環境を参酌すべきであり、建物自体の価格のほか、建物およびその敷地、その所在位置、周辺土地に関する諸般の事情を総合考察することにより、建物が現存する状態における買取価格を定めるべきとした事例 |
||
| 144 | S47.5.19 |
表示された動機が、民法95条にいう法律行為の要素には該当しないとされ、錯誤無効の主張が棄却された事例 |
||
| 145 | S47.4.25 |
建物所有を目的とする土地の賃借人が、賃借土地を賃借人の個人企業と実質を同じくする会社に使用させた場合において、背信行為と認めるに足りない特段の事情があるというべきとして、賃貸人の民法612条2項による賃貸借契約の解除を否定した事例 |
||
| 146 | S47.4.20 |
売買不動産の価格が売主の所有権移転義務の履行不能後も騰貴を続けており、かつ、履行不能の際に売主がその事情を知っていた等の特別な事情がある場合において、購入目的が自己使用である買主の売主に対する騰貴後の不動産の現在価格を基準とした損害賠償請求が認められた事例 |
||
| 147 | S47.4.20 |
不動産の貸借人が賃貸人から当該不動産を譲り受けたが所有権移転登記をしない間に、第三者が不動産を譲り受け所有権移転登記をしたため、賃借人が不動産の所有権取得を第三者に対抗できなくなった場合、いったん混同により消滅した賃借人の賃借権は、第三者が所有権を取得すると同時に、同人に対する関係では消滅しなかったことになるとした事例 |
||
| 148 | S47.4.14 |
袋地の所有権を取得した者は、所有権取得登記を経由していなくても、囲繞地の所有者ないし利用権者に対して、囲繞地通行権を主張することができるとした事例 |
||
| 149 | S47.4.13 |
詐害行為取消の消滅時効の進行時点である、取消権者が取消の原因を覚知した時とは、取消権者が詐害行為取消権発生の要件たる事実、すなわち、債務者が債権者を害することを知って当該法律行為をした事実を知ったことを意味し、単に取消権者が詐害の客観的事実を知っただけでは足りないとした事例 |
||
| 150 | S47.4.7 |
仮差押登記がなされた土地上に存する土地所有者の所有建物について抵当権が設定された場合には、抵当権の実行による建物の競落人は、法定地上権を取得するが、仮差押が本執行に移行してなされた強制競売手続により土地を競落取得した者に対しては、法定地上権をもって対抗することはできないとされた事例 |
||
| 151 | S47.3.30 |
賃借建物の敷地の一部分について、これを賃貸人の請求あり次第明け渡す旨の特約は、当該敷地部分が賃借建物の使用収益に不可欠なものである場合には、借家法6条にいう賃借人に不利な特約にあたるとした事例 |
||
| 152 | S47.3.30 |
建物の従前の賃借人が、賃借中支出した費用の償還を請求するためその建物につき留置権を行使した場合には、賃借中と同一の態様をもって建物の占有・使用を継続することは、特段の事情のないかぎり、留置権に基づく適法な行為であるとされた事例 |
||
| 153 | S47.3.24 |
建物の占有者は、他人に対する債務名義に基づく建物収去土地明渡の強制執行に対しては、占有の侵害を受忍すべき理由のないかぎり、対抗しうる本権の有無を問わず、占有権に基づき第三者異議の訴を提起し執行の不許を求めることができるとされた事例 |
||
| 154 | S47.3.23 |
請負契約が請負人の債務不履行により、請負人が注文主に対し前払金返還債務を負担することを約した場合、特段の事情がない限り、保証人も約定の債務について賠償責任を負うとされた事例 |
||
| 155 | S47.3.21 |
債権者のする破産宣告の申立は、債権の消滅時効の中断事由たる裁判上の請求にあたるとした事例 |
||
| 156 | S47.3.17 |
危急時遺言の遺言書に遺言をした日附ないしその証書の作成日附を記載することは、遺言の有効要件ではなく、遺言書に作成の日として記載された日附が正確性を欠いていても、遺言は無効ではないとされた事例 |
||
| 157 | S47.3.9 |
借地上の建物売買契約を締結した場合、特別の事情のないかぎり、売主は買主に対しその敷地の賃借権をも譲渡したものであり、特約または慣行がなくても、建物の売主は買主に対しその敷地の賃借権譲渡につき賃貸人の承諾を得る義務を負うとした事例 |
||
| 158 | S47.3.7 |
土地の賃貸人の地代未払による土地賃貸借の合意解約がなされた後に、地上建物の抵当権が実行されたとして、賃貸人は同解約をもって競落人に対抗することができるとされた事例 |
||
| 159 | S47.3.2 |
私人と国との間の土地売買契約において、目的土地の利用方法に関する特約は当事者にとって極めて重要な特約であるから、予算決算等に基づき契約書が作成された以上、かかる特約の趣旨は通常契約書に記載されるものであり、これに記載されていないときはかかる特約は存在しないとされた事例 |
||
| 160 | S47.2.24 |
登記簿の記載から賃借権の消滅を信頼した建物の競落人について、民法94条2項(通謀虚偽表示)の類推適用がないとされた事例 |
||
| 161 | S47.2.22 |
借地権の消滅前に建物が滅失し、借地権者が建物を再築したのに対して、土地所有者が遅滞なく異議を述べた場合でも、借地契約が残存期間の満了に伴い借地法6条により更新されたときは、更新後の借地権は、その後滅失建物の朽廃すべかりし時期が到来しても消滅しないとした事例 |
||
| 162 | S47.2.18 |
未成年者の無権代理人が後見人となった場合において、先になされた無権代理行為の効果が未成年者に及ぶとされた事例 |
||
| 163 | S47.2.18 |
建物の賃借人がその責に帰すべき事由によつて賃借建物に火災を発生させ、これを焼失させた場合には、賃貸人は、特段の事情のないかぎり、催告を経ないで賃貸借契約を解除することができるとした事例 |
||
| 164 | S47.2.10 |
土地賃貸借契約が、一時使用のための借地権を設定したものと認められた事例 |
||
| 165 | S47.1.25 |
不動産の所有者でない者が、登記簿上その所有者として登記されているため、不動産に対する固定資産税を課せられ納付した場合には、所有名義人は真の所有者に対し、不当利得として納付税額相当額の返還を請求できるとした事例 |
||
| 166 | S46.12.21 |
建物の共有者の一人がその敷地を所有する場合において、土地に設定された抵当権が実行され、第三者がこれを競落したときは、土地につき建物共有者全員のために法定地上権が成立するとされた事例 |
||
| 167 | S46.12.16 |
不動産の二重売買において、所有権移転登記未了の間に、他の買主のために売買予約を原因とする所有権移転請求権保全の仮登記がなされたというだけでは、売買契約上の義務が履行不能になったとして違約解除することはできないとした事例 |
||
| 168 | S46.12.9 |
隣接する土地の一方または双方が共有に属する場合の境界確定の訴えは、固有必要的共同訴訟と解すべきであるとした事例 |
||
| 169 | S46.12.7 |
賃貸家屋の明渡訴訟において、当事者の明示の申立額(500万円)を超える立退料(1000万円)の支払と引換えに明渡請求を認容することを相当と認めた事例 |
||
| 170 | S46.12.3 |
貸家の譲受人は、所有権移転登記を経由していないときは、賃借人に対し賃貸人の地位承継を主張できないが、賃借人がこの事実を認め、譲受人に対して承継後の賃料を支払う場合には、その支払が仮に承認前に遡つて賃料を支払う場合においても、債権者に対する弁済として有効であり、譲渡人は賃借人に対し賃料の支払を妨げることができないとした事例 |
||
| 171 | S46.11.30 |
・土地区画整理事業の施行者が仮換地上の建物の移転除却を怠った不作為につき、土地所有者に対する損害賠償責任が認められた事例 |
||
| 172 | S46.11.30 |
相続人が、被相続人の死亡により、相続財産の占有を承継したばかりでなく、新たに相続財産を事実上支配し、所有の意思を持って占有を開始した場合においては、被相続人の占有が所有の意思のないものであったときでも、相続人は民法185条にいう「新権原」により所有の意思をもって占有を始めたものであるとした事例 |
||
| 173 | S46.11.30 |
甲乙丙三者間において中間省略登記の合意が成立した場合においても、中間者乙は、当然には甲に対する移転登記請求権を失うものではないとした事例 |
||
| 174 | S46.11.26 |
換地予定地の指定通知が従前の土地の所有者に対してなされた後においては、当該換地予定地を占有するのでなければ、従前の土地を占有したからといって、その従前の土地の所有権地上権または賃借権を時効によつて取得することはできないとされた事例 |
||
| 175 | S46.11.26 |
地上権の時効取得が成立するためには、土地の継続的な使用という外形的事実が存在するほかに、その使用が地上権行使の意思に基づくものであることが客観的に表現されていることを要するとした事例 |
||
| 176 | S46.11.25 |
借家法1条の2に基づく解約を理由とする店舗の明渡訴訟において、当事者の申立額(300万円)をこえる立退料(500万円)の支払いと引換えに明渡請求を認めた事例 |
||
| 177 | S46.11.25 |
不動産の売主が売買契約の効力の発生を争うとともに仮定的にその取得時効を援用した場合に、売買契約の効力につき判断することなく、売主のため取得時効の完成を認めることを妨げないとした事例 |
||
| 178 | S46.11.25 |
土地所有権の取得時効の要件として無過失と認められた事例 |
||
| 179 | S46.11.16 |
被相続人が、生前不動産をある相続人に贈与するとともに、他の相続人にもこれを遺贈した後、相続の開始があった場合、贈与および遺贈による物権変動の優劣は、対抗要件たる登記の具備の有無をもって決するとされた事例 |
||
| 180 | S46.11.11 |
民法162条2項の10年の取得時効を主張するものは、その不動産を自己の所有と信じたことにつき無過失であったことの立証責任を負うとした事例 |
||
| 181 | S46.11.9 |
知事の許可のない使用貸借契約に基づいて引き渡された農地の返還請求が、その権利の行使において信義誠実の原則に従ったものとはいえず排斥を免れないとされた事例 |
||
| 182 | S46.11.5 |
不動産の二重譲渡において、登記未経由のまま占有していた買主が時効取得を主張する場合の起算点は、占有開始の時点であるとした事例 |
||
| 183 | S46.11.4 |
建物の賃貸人が賃借人の無断転貸を理由に賃貸借契約の解除を求めた事案において、転借人は賃借人らにより税務対策上設立された有限会社である等の事情により、信頼関係を破壊すると認めるに足りない特段の事由があるとしてその請求が棄却された事例 |
||
| 184 | S46.10.28 |
不法の原因により既登記建物を贈与した場合、その引渡しをしただけでは、民法708条にいう不法原因給付があったとはいえないとされた事例 |
||
| 185 | S46.10.14 |
賃貸人の賃料増額の意思表示に対し、賃借人が書面をもって応じない旨を回答し、賃料についても従前の額に従って供託している等の事情があるときは、賃貸人と賃借人との間において借賃の増額協議が調わなかった場合にあたるとされた事例 |
||
| 186 | S46.10.14 |
所有権と賃借権とが同一人に帰属した場合であっても、その賃借権が対抗要件を具備し、かつ、その対抗要件を具備した後に土地に抵当権が設定されていたときは民法179条1項但書(混同)の準用により、賃借権は消滅しないとされた事例 |
||
| 187 | S46.10.14 |
建物の賃貸借契約が営業利益分配契約的要素を具有するもので、その賃料額が営業売上金額に一定の歩合率を乗じて算出される場合であっても、借家法7条本文所定の要件を充足するときは、当事者は、その賃料の増減額を請求することができるとした事例 |
||
| 188 | S46.7.16 |
建物の賃借人が、債務不履行により賃貸借契約を解除された後、権原のないことを知りながら建物を不法に占有する間に有益費を支出しても、民法295条2項の類推適用により、費用の償還請求権に基づいて建物に留置権を行使することはできないとされた事例 |
||
| 189 | S46.7.14 |
弁護士法72条は、弁護士でない者が、報酬を得る目的で、業として同条本文所定の法律事務を取り扱いまたはこれらの周旋をすることを禁止する規定であるとした事例 |
||
| 190 | S46.7.1 |
建物借主の家屋の無断築造につき、約3坪の既存の居宅兼物置を取り壊し、それと面積、位置がほぼ同様の簡単な構造の作業場を新築したにすぎない場合は、借主に賃借家屋及び敷地の使用収益権の範囲の逸脱、保管義務違反があるとはいえないとした事例 |
||
| 191 | S46.6.22 |
土地賃借人の借地権の一部の無断譲渡について、従来の事情から賃貸人の承諾を得られるものと思い、名義書換料相当の金員の支払いを予定していたなどの事情から、賃貸人に対する背信行為と認められない特段の事情があるとされた事例 |
||
| 192 | S46.6.18 |
不動産の共有物分割訴訟においては、共有者間に持分の譲渡があっても、その登記が存しないため、譲受人が持分の取得をもって他の共有者に対抗することができないときは、共有者全員に対する関係において、持分がなお譲渡人に帰属するものとして共有物分割を命ずべきであるとした事例 |
||
| 193 | S46.6.17 |
借家の賃貸人の賃借人に対する立退料の提供の申し出は、賃貸借契約解約申入れの正当事由の補完事由になるとされた事例 |
||
| 194 | S46.6.17 |
宅地建物取引業法2条1号にいう宅地とは、現に建物の敷地に供せられている土地に限らず、広く建物の敷地に供する目的で取引の対象とされた土地を指称し、その地目、現況のいかんを問わないものであるとした事例 |
||
| 195 | S46.6.11 |
農地の売主と買主の地位の譲受人との間における知事の許可申請手続等に関する合意が有効とされた事例 |
||
| 196 | S46.6.3 |
本人より登記申請を委任され必要な権限を与えられた者が、権限をこえて第三者と取引行為をした場合において、その申請が本人の私法上の契約による義務の履行のためになされるものであるときは、その権限を基本代理権として、第三者との間の行為につき表見代理の成立を認めることができるとした事例 |
||
| 197 | S46.5.25 |
売買一方の予約において予約完結権を行使するには、買戻の場合と異なり、代金を提供する必要はないとした事例 |
||
| 198 | S46.5.20 |
停止条件付代物弁済契約において、債権につき清算がされていない場合でも、債権者が代物弁済を受け目的物の所有権を取得したとして、善意の第三者に譲渡し所有権移転登記がされた後は、債務者は第三者から目的物を取り戻すことはできず、債権者に対して清算金を請求するほかに方法がないとした事例 |
||
| 199 | S46.4.23 |
工作物が本来備えるべき安全性を欠く場合には、工作物の設置又は保存に瑕疵があるものとして、民法717条(工作物責任)所定の帰責原因となるとされた事例 |
||
| 200 | S46.4.23 |
土地の賃貸借契約における賃貸人の地位の譲渡において、新所有者が旧所有者の賃貸人としての権利義務を承継するには、特段の事情のないかぎり賃借人の承諾を必要とせず、旧所有者と新所有者間の契約をもってこれをなすことができるとした事例 |
||
| 201 | S46.4.21 |
仮登記名義人が本登記を申請する場合、第三者の承諾書またはこれに対抗しうべき裁判の謄本の添付を要するとした不動産登記法105条1項は、憲法29条に違反しないとされた事例 |
||
| 202 | S46.4.20 |
第三者の金銭債務について、親権者が連帯保証をするとともに、子の代理人として、同一債務につき連帯保証をし、親権者と子が共有する不動産について抵当権を設定する行為は、民法826条の利益相反行為にあたるとした事例 |
||
| 203 | S46.4.9 |
賭博の債務履行のために第三者振出の小切手の交付を受けた所持人が、振出人との間で小切手金支払に関し和解契約を締結した場合、振出人の所持人に対する金銭支払の約定は公序良俗に違反し無効であるとされた事例 |
||
| 204 | S46.4.8 |
不動産が甲から乙丙丁と順次譲渡され所有権移転登記は、甲が同意しないのに甲から直接丁に対し経由された場合において甲が登記を無効としてその抹消を求めることが許されないとされた事例 |
||
| 205 | S46.4.6 |
農地の買主が目的農地を転売した場合に、転買人が当初の売主に対して直接農地法五条所定の知事に対する許可申請手続を求めることは許されないとした事例 |
||
| 206 | S46.3.30 |
不動産の競買手続開始前に締結され対抗要件を経由した建物の賃借権であっても、これに優先する抵当権に対抗しえない場合には、競落により抵当権とともに消滅するとされた事例 |
||
| 207 | S46.3.25 |
不動産譲渡担保による金銭賃貸借契約において、債務者が弁済期に債務の弁済をしない場合においては、債権者は目的不動産を換価処分し、またはこれを適正に評価した価額から、債権額を差し引き、なお残額があるときは、これに相当する金銭を清算金として債務者に支払うことを要するとした事例 |
||
| 208 | S46.3.9 |
購入土地の一部につき、買受人が農業委員会作成の図面または法務局備付の図面を閲覧し、実地調査をすれば、当該土地が売買に含まないことを容易に知り得たにもかかわらず、この調査をせず自己の所有に属するとして開始した占有には、自己の所有と信じたことに過失があるとされた事例 |
||
| 209 | S46.3.5 |
請負人が材料全部を提供して建築した建物が、完成と同時に注文者の所有に帰したものと認められた事例 |
||
| 210 | S46.2.25 |
競売開始決定が所有者に対して送達されていなかった競売手続の瑕疵を理由とする競落許可決定の無効主張は許されないとした事例 |
||
| 211 | S46.2.23 |
地積更正登記は土地の表示に関する登記(不動産登記法78条)であって、権利に関する登記ではないから、これについては、不動産登記法66条、56条の適用はないとした事例 |
||
| 212 | S46.2.19 |
建物の賃借人が有益費を支出した後、建物の所有権譲渡により賃貸人が交替したときは、特段の事情のないかぎり、新賃貸人が有益費の償還義務を承継し旧賃貸人は償還義務を負わないとされた事例 |
||
| 213 | S45.12.24 |
無権代理人甲が乙の代理人と称して丙と締結した抵当権設定契約を乙が追認したのち、甲が乙の代理人と称して丁と抵当権設定契約を締結した場合において、丁が甲に乙を代理して抵当権設定契約をする権限があると信ずべき正当の事由を有するときは、乙は民法110条および112条の類推適用により、甲の抵当権設定契約につき責任を負うとされた事例 |
||
| 214 | S45.12.24 |
土地賃貸借が賃借人の債務不履行により解除されたとしても、借地上の建物の賃貸借はただちに終了するものではなく、土地賃貸人と建物賃借人との間で建物敷地の明渡義務が確定されるなど、建物の使用収益が現実に妨げられる事情が客観的に明らかになり、または建物賃借人が現実の明渡を余儀なくされたときに、はじめて、賃貸人の債務の履行不能により終了するとされた事例 |
||
| 215 | S45.12.24 |
清算型代物弁済予約の予約権者が、登記上利害関係を有する後順位債権者に本登記の承諾を求める場合においては、予約権者は、清算金をそれらの者に対し、その債権額および優先順位に応じて交付すべきであり、後順位債権者とは、その支払と引換えにのみ承諾義務の履行をすべき旨を主張しうるとした事例 |
||
| 216 | S45.12.22 |
家屋の塀における器物毀棄罪につき、被害物件の所有者の妻に告訴権を認めた事例 |
||
| 217 | S45.12.18 |
仮換地の指定後に、従前の土地を所有する意思をもって当該仮換地の占有を始めた者は、換地処分の公告の日までに民法162条所定の要件を満たしたときは、取得により従前の土地の所有権を取得するとされた事例 |
||
| 218 | S45.12.15 |
不動産の賃借人は、賃借権に基づいて、賃貸人に代位し、賃借不動産について権原なく所有権取得登記を有する第三者に対し、賃貸人の物上請求権を代位行使し、その登記の抹消手続を求めることはできないとした事例 |
||
| 219 | S45.12.15 |
寺院境内地についての土地賃借権の時効取得が認められた事例 |
||
| 220 | S45.12.15 |
民法109条、商法262条は、会社を訴訟上代表する権限を有する者を定めるにあたっては適用されないとした事例 |
||
| 221 | S45.12.15 |
無権代理人が、無権代理による契約後にその目的物の共有持分を譲り受けた場合においても、契約の相手方が民法117条にいう履行を選択した事実がないときは、持分に対する部分につき、契約が有効となるものではないとした事例 |
||
| 222 | S45.12.11 |
土地賃借権の無断譲渡が背信行為にあたらない場合、譲受人のみが賃借人となり、譲渡人たる前賃借人は、賃貸借契約関係から離脱し、賃貸人に対して契約上の債務を負わないとされた事例 |
||
| 223 | S45.12.10 |
乙が甲から所有権移転登記を経た不動産について、甲より登記原因の無効を理由とする予告登記がなされた後、乙より丙に所有権移転登記がされ、ついで甲勝訴の判決が確定した場合において、甲の丙に対する所有権移転登記抹消請求の訴えを排訴することは、予告登記の効力により妨げられるものではないとされた事例 |
||
| 224 | S45.11.26 |
農地の売買契約において、本件土地が宅地化されるに至った原因およびその経緯に鑑み、宅地化により本件各売買契約は、農地法所定の許可を経ることなくその効力を生ずるに至ったとされた事例 |
||
| 225 | S45.11.24 |
地主の承諾を得て土地賃借権の譲渡を受け、土地上の所有建物につき登記を経由して第三者に対する対抗力を備えた者は、土地の一部についての賃借権の二重譲渡を受け、これに建物を建てその占有をなす者に対し、直接その建物の収去明渡請求をすることができるとされた事例 |
||
| 226 | S45.11.19 |
不動産の買主が、売主に対する貸金を債権とした抵当権設定登記および所有権移転請求権保全の仮登記を経た場合において、売主より不動産を買い受け所有権登記を経た善意の第三者に対して、買主は自己の登記が実体上の権利関係と相違し仮登記を経由した所有権者であると主張することはできないとした事例 |
||
| 227 | S45.11.6 |
数個の共有建物が一筆の土地上にあり外形上一団の建物とみられる場合に、民法258条により建物につき現物分割をするには、建物を一括して分割の対象とし、共有者がそれぞれ各個の建物の単独所有権を取得する方法によることも許されるとした事例 |
||
| 228 | S45.11.5 |
売買代金に関し宅地のみの価額は別に定めず行われた土地建物の売買契約において、宅地につきいわゆる数量指示売買に該当しないとされた事例 |
||
| 229 | S45.10.29 |
占有における所有の意思の有無は、占有取得の原因たる事実によって客観的に定められるべきものであるから、所有権譲受を内容とする交換契約に基づき開始した占有は、所有の意思をもってする占有であるとされた事例 |
||
| 230 | S45.10.23 |
借地権の設定に際し土地所有者が受け取る権利金は、長期の存続期間を定め、かつ、借地権の譲渡性を認める等、所有者が当該土地の使用収益権を半永久的に手離す結果となる場合に、その価額が更地価格の極めて高い割合の金額であるなど、明らかに所有権の権能の一部を譲渡した対価であるものでないかぎり、譲渡所得にはあたらないとされた事例 |
||
| 231 | S45.10.22 |
間もなく買受契約が成立に至る状態にあったのに、土地等の買受人が依頼していた宅地建物取引業者を排除して直接売買契約を締結した事案において、宅地建物取引業者の報酬請求権が認められた事例 |
RETIO 125-110
|
|
| 232 | S45.10.21 |
不法の原因により未登記建物を贈与した場合、1)その引渡は民法708条にいう給付にあたる、2)贈与者は所有権を理由とする建物返還請求はすることができない、3)贈与者が給付物の返還請求ができない反射的効果として、建物所有権は受贈者に帰属する、4)建物所有権が受贈者に帰属した場合、贈与者が建物の所有権保存登記を経由しても、受贈者は贈与者に対し同保存登記につき抹消登記手続を請求できる、とした事例 |
||
| 233 | S45.10.16 |
礼拝堂の建築所有を目的とする土地の使用貸借が相当の期間の経過により終了した旨の判断に審理不尽・理由不備の違法があるとされた事例 |
||
| 234 | S45.10.13 |
賃貸人の賃借人に対する賃貸物を使用収益させる義務につき、民法492条(弁済の提供の効果)を適用し、賃貸人が債務不履行の責めを負わないとした事例 |
||
| 235 | S45.9.24 |
数個の不動産上に代物弁済予約形式の債権担保契約を締結し、これを原因とする所有権移転請求権保全の仮登記を経由した債権者は、債務者が弁済期に債務の弁済をしないため予約完結権を行使して担保目的の実現をはかるため同一訴訟手続で本登記手続を求めた場合に、債務者が清算金の支払と引換えに履行する旨の主張をしたときは、特段の事情のないかぎり、各不動産の価額に準じて債権者の有する債権額を按分したうえで、債務者への清算金の額を算定して、その清算金の支払と引換えに右請求を認容すべきであるとされた事例 |
||
| 236 | S45.9.22 |
不実の所有権移転登記が所有者の承認のもとに存続せしめられていたものとして、民法94条2項を類推適用すべきものとされた事例 |
||
| 237 | S45.9.18 |
賃貸借契約において敷金が差し入れられていても、貸主は賃料延滞を理由として契約を解除することができるとした事例 |
||
| 238 | S45.8.20 |
・国道への落石の事故につき道路の管理に瑕疵があると認められた事例 |
||
| 239 | S45.8.20 |
建物の賃貸人が現実に提供された賃料の受領を拒絶した場合、その後における賃料不払を理由とする契約解除をするためには、単に賃料の支払催告だけでは足りず、受領拒絶の態度を改め賃料の提供あれば受領する旨を表示する等の措置を講じる必要があるとした事例 |
||
| 240 | S45.8.20 |
代物弁済予約形式の債権担保契約における債権者の清算義務と後順位抵当権者および第三取得者の地位 |
||
| 241 | S45.7.28 |
白紙委任状、名宛人白地の売渡証書などの登記関係書類を転交付を受けた者が行った行為について、民法109条と110条による表見代理の成立を認めた事例 |
||
| 242 | S45.7.24 |
・不動産の所有者甲が、乙にその意思がないのに乙の名義を承諾なく使用し他からの所有権移転登記を受けた事案において、民法94条2項の類推適用により、甲は、乙が不動産の所有権を取得しなかったことをもって、善意の第三者に対抗できないとした事例 |
||
| 243 | S45.7.21 |
借地法9条にいう一時使用の賃貸借というためには、その期間は少なくとも借地法自体が定める借地権の存続期間より相当短いものであることを要するとして、裁判上の和解により成立した期間20年の土地賃貸借につき一時使用の賃貸借に該当しないとされた事例 |
||
| 244 | S45.7.16 |
抵当権者が被担保債権を被保全債権として抵当不動産の仮差押をした場合において、仮差押債務者が仮差押解放金を供託して仮差押執行の取消を得たときには、抵当権の効力は、物上代位の規定の趣旨により、仮差押解放金の取戻請求権に及ぶとされた事例 |
||
| 245 | S45.7.16 |
土地に対する抵当権の設定当時地上建物が存在しなかった場合、抵当権と同一債権の担保を目的として重ねて土地に停止条件付代物弁済契約が結ばれた当時には地上に債務者所有の建物が存在したときでも、代物弁済契約の条件成就後の法律関係につき、法定地上権の成立を認めることはできないとした事例 |
||
| 246 | S45.7.16 |
不動産譲渡担保契約において、債権者が予約完結権を行使し不動産を譲り受け、登記上利害関係を有する第三者にその承諾を求める場合、債権者は目的不動産の適正な評価額のうち、自己の債権額超過部分の金銭を第三者に支払うことを要し、第三者は金銭の支払と引換えにのみ承諾義務の履行をなすべき旨を主張できるとした事例 |
||
| 247 | S45.7.16 |
現存する建物の所有者が、その建物の所在地上に以前存在していた旧建物の所有名義人に対し、旧建物の滅失登記手続を訴求する利益はないとされた事例 |
||
| 248 | S45.7.15 |
弁済供託における供託金取戻請求権の消滅時効は、供託の基礎となった債務について紛争の解決などによってその不存在が確定するなど、供託者が免責の効果を受ける必要が消滅した時から進行し、10年をもって完成するとされた事例 |
||
| 249 | S45.6.18 |
占有における所有の意思の有無は、占有取得の原因たる事実によって外形的客観的に定められるべきものであるから、賃貸借が法律上効力を生じない場合にあっても、賃貸借により取得した占有は他主占有というべきであるとされた事例 |
||
| 250 | S45.6.16 |
期間の定めのない建物所有を目的とする土地の賃貸借は、民法395条により抵当権者に対抗しうべき賃貸借に当たらないとされた事例 |
||
| 251 | S45.6.4 |
借家法7条に基づく賃料増額の請求がされたときは、その意思表示が賃借人に到達した日に増額の効果が生ずるとされた事例 |
||
| 252 | S45.6.2 |
甲が融資を受けるため、乙と通謀して不動産の売買を仮装して乙に所有権移転登記をし、乙がさらに丙に融資の斡旋を依頼して不動産の登記手続に必要な登記済証等を預け、丙がこれらの書類により乙よりの所有権移転登記を経たときは、甲は丙の所有権取得の無効をもって善意無過失の第三者に対抗できないとした事例 |
||
| 253 | S45.5.29 |
抵当権設定契約が錯誤により無効であっても、これを締結する前提として同時に約定された準消費貸借契約に要素の錯誤がないとされた事例 |
||
| 254 | S45.5.28 |
地上権の時効取得が成立するためには、土地の継続的な使用という外形的事実が存在するほかに、その使用が地上権行使の意思に基づくものであることが、客観的に表現されていることを要するとされた事例 |
||
| 255 | S45.5.22 |
後見人が未成年者を代理して、後見人の内縁の夫に対し未成年者所有の土地を無償譲渡する行為は、旧民法915条4号にいう「後見人と被後見人との利益相反する行為」にあたるとした事例 |
||
| 256 | S45.5.22 |
不動産の賃借人が賃貸人の相続人に対して賃借権の確認を求める訴訟は、相続人が数人あるときでも、必要的共同訴訟ではないとした事例 |
||
| 257 | S45.5.21 |
債務者が、消滅時効の完成後に、債権者に対し当該債務を承認した場合においても、以後ふたたび時効は進行し、債務者は、再度完成した消滅時効を援用することができるとされた事例 |
||
| 258 | S45.5.19 |
・借地条件変更の裁判をする裁判所は、その前提となる借地権の存否につき当事者間に争いがあるときでも、その手続において、借地権の存否を判断したうえで、裁判をすることができるとした事例 |
||
| 259 | S45.5.19 |
家屋の賃借人が破産したことを理由として賃貸借契約の解約を申し入れる場合には、借家法1条の2の適用はないとした事例 |
||
| 260 | S45.4.21 |
証人または当事者本人として真実を陳述することに対する対価として金員を支払う旨の契約が公序良俗に反するとされた事例 |
||
| 261 | S45.4.16 |
未登記建物の所有者が、その建物につき家屋台帳上他人の所有名義で登録されていることを知りながら、これを明示または黙示に承認した場合には、その所有者は台帳上の名義人から権利の設定を受けた善意の第三者に対し、民法94条2項の類推適用により対抗することができないとされた事例 |
||
| 262 | S45.4.10 |
・仮換地の土地一部分の売買契約において、売主は所有権移転登記に関し、仮換地全体に対する目的土地の地積に応じた従前地の持分権の移転登記手続を履行する義務を負い、買主が売主に対し仮換地指定変更申請に協力しないことが、同義務に影響を及ぼすものではないとした事例 |
||
| 263 | S45.3.26 |
契約を解除した当事者が第三者の登記の欠缺を主張することが信義則上許されないとされた事例 |
||
| 264 | S45.3.26 |
・詐欺罪の成立と財産的処分行為の要否 |
||
| 265 | S45.3.26 |
建物の登記が所在地番の表示において実際と多少相違する事案において、建物保護に関スル法律1条1項の「登記したる建物を有する」に当たるとされた事例 |
||
| 266 | S45.3.26 |
土地について締結された停止条件付代物弁済契約につき、公序良俗違反による無効が主張された事案において、債権者において清算義務を負担する担保契約であり、また、契約締結時に先順位の担保権者が存在するなどの事情を検討し公序良俗違反とはいえないと判断された事例 |
||
| 267 | S45.3.24 |
期間を10年と定めた普通建物の所有を目的とする土地の賃貸借契約につき、借地法2条により期間が30年であると認められた事例 |
||
| 268 | S45.3.17 |
建物収去土地明渡の判決においては、土地の地積および建物の床面積を、計量法所定の計量単位によらないで、尺貫法による計量単位によって表示しても違法ではないとされた事例 |
||
| 269 | S45.3.12 |
借地法9条所定の一時使用のための借地権に当たるとされた事例 |
||
| 270 | S45.2.27 |
賃貸人が、借地上の賃借人所有の建物に対し占有移転禁止等の仮処分を執行したことにより、賃借人の借地の使用収益を妨げたとしても、そのために借地法12条に基づく賃料増額請求が許されなくなるものではないとした事例 |
||
| 271 | S45.2.26 |
宅地建物取引業法17条1項および2項は、宅地建物取引の媒介の報酬契約のうち建設大臣の定めた額をこえる部分の効力を否定する趣旨であり、報酬契約のうち同額をこえる部分は無効であるとした事例 |
||
| 272 | S45.2.26 |
一個の売買に関し宅地建物取引業者である媒介者が数人ある場合、媒介者らの報酬の合計額は、法定の最高報酬額を超えることができないとした事例 |
||
| 273 | S45.2.24 |
登記の欠缺を主張することができない、いわゆる背信的悪意者にあたるとされた事例 |
||
| 274 | S45.2.12 |
下請負人の被用者の加害行為につき元請負人の使用者責任が認められた事例 |
||
| 275 | S45.1.23 |
不動産の二重譲渡において双方の買主がそれぞれ売主に対して処分禁止の仮処分を執行した後、第一次仮処分債権者が本案の勝訴判決に基づいて所有権移転登記を経由した場合、その買主は第二次仮処分債権者に対し自己の所有権を対抗できるとした事例 |
||
| 276 | S44.12.23 |
建物保護に関する法律1条は、登記した建物をもって土地賃借権の登記に代用する趣旨であり、当該建物の登記に所在の地番として記載されている土地についてのみ、同条による賃借権の対抗力を生ずるとした事例 |
||
| 277 | S44.12.19 |
不動産の買主が売主に対して処分禁止の仮処分をした場合に、不動産の他の買主が同一不動産について第二次の処分禁止の仮処分をすることは妨げられないが、第一次仮処分の債権者が、被保全権利の実現として、売買契約に基づく所有権移転登記を経由したときは、第二次仮処分の債権者は、自己の仮処分の効力を主張して所有権の取得を否定することはできないとした事例 |
||
| 278 | S44.12.19 |
譲渡担保の設定が詐害行為にならないとされた事例 |
||
| 279 | S44.12.19 |
代理人が直接本人の名において権限外の行為をした場合において、相手方がその行為を本人自身の行為と信じたときは、そのように信じたことについて正当な理由があるかぎり、民法110条の規定を類推して、本人はその責に任ずるとされた事例 |
||
| 280 | S44.12.18 |
特定の土地の引渡を求める訴訟の判決に添付された目的土地の特定のための実測図に基点が脱落していても、測量図によれば基点の所在が明らかで、判決添付図面を作成する際、基点の記載を脱落したにすぎないときは、更正決定をすれば足り、主文不特定の違法はないとした事例 |
||
| 281 | S44.12.18 |
・民法761条は、夫婦が相互に日常の家事に関する法律行為につき他方を代理する権限を有することをも規定しているものと解すべきとした事例 |
||
| 282 | S44.12.18 |
不動産を買い受け所有権に基づいてこれを占有する買主は、売主との関係においても、自己の占有を理由として不動産につき時効による所有権の取得を主張することができるとした事例 |
||
| 283 | S44.12.11 |
所有権に基づいて不動産を占有するものについて、所有権の取得時効の適用があるとした事例 |
||
| 284 | S44.12.11 |
抵当権設定後競売開始決定までの間に設定された短期賃貸借は、民法602条所定の期間後は当然に効力を失い法定更新されないとした事例 |
||
| 285 | S44.12.4 |
道路法の道路について、その後所有権を取得し登記した第三者は、道路管理者に対し対抗要件の欠缺を主張できる場合であっても、道路管理者の不法占有を理由とする損害賠償請求は許されないとされた事例 |
||
| 286 | S44.11.27 |
債務者兼抵当権設定者が債務の不存在を理由として提起した抵当権設定登記抹消登記手続請求訴訟において、債権者兼抵当権者が請求棄却の判決を求め被担保債権の存在を主張したときは、その主張は裁判上の請求に準ずるものとして、被担保債権につき消滅時効中断の効力を生ずるとした事例 |
||
| 287 | S44.11.26 |
普通建物の所有を目的とする土地の賃貸借契約において期間を3年と定めた場合には、存続期間の約定は、借地法11条により定めのなかったものとみなされ、賃貸借の存続期間は同法2条1項本文により契約の時から30年と解されるとした事例 |
||
| 288 | S44.11.26 |
・取締役の悪意又は重過失による任務懈怠と第三者の損害との間に相当因果関係があるかぎり、これにより会社が損害を被り、ひいて第三者に損害が生じた場合であると、直接第三者が損害を被った場合であるとを問わず、当該取締役は直接第三者に対し損害賠償責任を負うとした事例 |
||
| 289 | S44.11.21 |
被用者の取引行為を職務権限内の行為と信じた相手方に重大な過失がないとされた事例 |
||
| 290 | S44.11.21 |
建物賃貸借の賃料増額請求をめぐる紛争に際し、賃借人が自発的に一定額の増額をした賃料を供託した等の事情のもとにおいては、本件賃料債務の不履行については、未だこれを賃貸借契約の解除原因としての背信行為と認めるに足りない特段の事情があるとされた事例 |
||
| 291 | S44.11.21 |
土地の買受人が、地上に自己の親族が賃借人として建物を所有し営業していることを知って、賃借権付評価額以下の価額で土地を取得しながら、賃借権の対抗力の欠如を奇貨として、賃借人に対しその損失を意に介さず建物収去土地明渡請求をすることは権利の濫用にあたるとした事例 |
||
| 292 | S44.11.20 |
無効な二重保存登記を基礎として設定登記がされている抵当権について競売手続がされても、これに基づく競落はその効力を生ぜず、これによって有効な保存登記を基礎として設定登記がされている抵当権が当然消滅するいわれはないとした事例 |
||
| 293 | S44.11.18 |
住宅建設・販売事業を営む事業者の被用者との間で、土地・建物の購入契約をし代金を支払ったが、被用者にその権限がなかった事案において、権限がないことを知らなかったことに重大な過失はなかったとして、買受人の事業者に対する使用者責任に基づく損害賠償請求が認められた事例 |
||
| 294 | S44.11.13 |
賃貸人の承諾を得ないでした家屋の転貸について民法612条(賃借権の譲渡及び転貸の制限)2項に基づく解除が許されない場合、賃貸人は転借人に対し明渡請求をすることはできないとした事例 |
||
| 295 | S44.11.13 |
土地(地番A)の賃借人が、賃借地上の所有建物を、自己所有地(地番B)上の所有建物に合併登記したところ、建物所在地が地番B番とのみ表示され、地番Aの表示がされない場合であっても、合併登記をもって賃借人は賃借地(地番A)上に建物保護法1条にいう登記した建物を所有するとされた事例 |
||
| 296 | S44.11.13 |
公道に面する一筆の土地所有者が、公道に面しない部分を他に賃貸しその残余地を自ら使用している場合には、別段の特約がなくとも所有者は賃貸借契約に基づく義務として、賃借人に残余地を契約目的に応じて通行させる義務があり、したがってその賃借地につき民法210条1項は適用されないとした事例 |
||
| 297 | S44.11.13 |
土地の賃貸借契約の期間が、口頭弁論終結後約6年半後に満了する場合において、貸主がその期間満了による土地の返還を求める将来の給付請求は、その請求の基礎となる権利関係を確定することのできない請求権を訴訟物とするものであって不適法であるとした事例 |
||
| 298 | S44.11.6 |
借地上の家屋に関する費用償還請求権は、その家屋の敷地自体に関して生じた債権でもなければ、その敷地の所有者に対して取得した債権でもないから、請求権を有する者であっても、その家屋の敷地を留置する権利は有しないとした事例 |
||
| 299 | S44.11.6 |
不特定物の売買においては、特段の事情のないかぎり、その目的物が特定すると同時に、当然にその目的物の所有権は売主から買主に移転するとした事例 |
||
| 300 | S44.11.4 |
従前の土地の所有者の所有する仮換地上の建物が抵当権の実行により競落されたときは、従前の土地について法定地上権が成立し、競落人は、法定地上権に基づいて仮換地の使用収益が許されるとされた事例 |
||
| 301 | S44.10.31 |
農地を目的とする売買契約締結後に、買主がこれに地盛りをし売主の承諾のもと建物を建築するなどしたため、土地が完全に宅地に変じた場合には、売買契約は知事の許可なしに効力を生ずるとした事例 |
||
| 302 | S44.10.30 |
土地を占有していた被相続人が死亡し相続が開始した場合には、特別の事情のないかぎり、被相続人の土地に対する占有は相続人によつて相続されるとした事例 |
||
| 303 | S44.10.28 |
乙所有の土地(乙地)を借り受け、同士地上に保存登記を経由した建物を所有する者が、甲所有の隣接土地(甲地)を建物の庭として使用するため借り受けた場合においては、甲地が乙地と一体として建物所有を目的として賃借されているものであるか否かにかかわらず、賃借権の対抗力は甲地に及ばないとした事例 |
||
| 304 | S44.10.16 |
不動産に関する代物弁済の予約につき請求権保全の仮登記が経由されている場合においては、不動産の所有権が第三者に移転したときであっても、代物弁済予約権者は、予約の相手方に対して予約完結の意思表示をすべきであるとした事例 |
||
| 305 | S44.10.7 |
二年間同一町内において相手方と同一業種であるパチンコ店営業をしない旨の契約は、特段の事情のないかぎり、公序良俗に違反するものではないとした事例 |
||
| 306 | S44.10.7 |
同一町内でパチンコ店が開店した時は賃貸借契約を終了させる特約につき、判示の事実関係のもとにおいては、借家法6条所定の賃借人に不利な特約に当たらないとした事例 |
||
| 307 | S44.9.25 |
日本住宅公団を借主とする住宅団地敷地の借地契約について、地主のした賃料増額請求による相当地代額の算定に違法があるとした事例 |
||
| 308 | S44.9.12 |
請負契約に基づき建築された建物所有権が原始的に注文者に帰属するとした事例 |
||
| 309 | S44.9.11 |
賃借権存在確認の訴において、原告が確定を求めていない賃料額、存続期間または契約の成立年月日を主文に掲記することは必要でないとした事例 |
||
| 310 | S44.9.11 |
会社の代表取締役が不動産を買い受けた場合において、これが代表取締役個人のためにした売買契約であるとした事実認定に経験則違背の違法があるとされた事例 |
||
| 311 | S44.9.2 |
共有不動産につき、共有者の一人が単独所有権として登記を経由した場合において、他の共有者は、単独所有権の取得登記を共同所有権の取得登記に更正登記手続を求めることができるとされた事例 |
||
| 312 | S44.8.29 |
商人間の土地の売買において、当事者の意思表示により、一定の日時または一定の期間内に履行をなさなければ、契約をした目的を達することができないときは、その売買は確定期売買であるとされた事例 |
||
| 313 | S44.7.31 |
一時使用のため借地権を設定したことが明らかな場合と認めることができるとした事例 |
||
| 314 | S44.7.25 |
建物の賃借人が承諾を得て二階部分を増築した場合に、区分所有権が成立しないとされた事例 |
||
| 315 | S44.7.25 |
民法112条の表見代理が成立するためには、相手方が、代理権の消滅する前に代理人と取引をしたことがあることを要するものではなく、かような事実は、同条所定の相手方の善意無過失に関する認定のための一資料にとどまるとされた事例 |
||
| 316 | S44.7.24 |
賃貸借契約終了または所有権に基づく家屋明渡請求権を共同相続した者の賃借権者または不法占有者に対する家屋明渡請求訴訟は、必要的共同訴訟ではないとされた事例 |
||
| 317 | S44.7.24 |
家屋の賃貸借契約の成否につき争いがある事案において、家屋の所有者が家賃の弁済として供託された金員の還付を受けた事実をもって、家屋の賃貸を承認したものとはいえないとされた事例 |
||
| 318 | S44.7.24 |
一筆の土地の一部の賃借人が賃借地を含む土地に対する仮換地の指定に際し賃借権の届出をしたが土地区画整理事業施行者から使用収益すべき部分の指定がない場合、賃借人は仮換地につき現実に使用収益をする権能を有しないとした事例 |
||
| 319 | S44.7.17 |
建物賃貸借契約において、当該建物の所有権移転に伴い賃貸人たる地位に承継があった場合には、旧賃貸人に差し入れられた敷金は、未払賃料債務があればこれに当然充当され、残額についてのみその権利義務関係が新賃貸人に承継されるとした事例 |
||
| 320 | S44.7.15 |
建物賃借人は、建物賃貸人による敷地所有権の取得時効を援用することはできないとされた事例 |
||
| 321 | S44.7.8 |
建物の所有者がその敷地を占有する権原のない場合に、建物の所有者を代表者とする会社がその建物を借り受け占有しているときは、同会社は敷地の所有者に対し敷地の不法占有による損害賠償責任を負うとした事例 |
||
| 322 | S44.7.8 |
他人の土地の用益がその他人の承諾のない転貸借に基づくものである場合において、土地の継続的な用益という外形的事実が存在し、かつ、その用益が賃借の意思に基づくものであることが客観的に表現されているときは、その土地の賃借権ないし転借権を時効により取得することができる |
||
| 323 | S44.7.3 |
甲乙不動産の先順位共同抵当権者が、甲不動産に次順位の抵当権が設定されているのに、乙不動産の抵当権を放棄し、甲不動産の抵当権を実行した場合であっても、乙不動産が物上保証人の所有であるときは、先順位抵当権者は、甲不動産の代価から自己の債権の全額について満足を受けることができるとした事例 |
||
| 324 | S44.6.26 |
・法人格のない財団として設立中の財団法人に訴訟上の当事者能力が認められた事例 |
||
| 325 | S44.6.26 |
宅地建物取引業者は、売主からの委託を受けず、また、売主のためにする意思を有しないでなした売買の媒介については、売主に対し報酬請求権を有しないとした事例 |
||
| 326 | S44.6.24 |
所有権に基づく登記請求を認容した確定判決は、その理由において所有権の存否を確認している場合であっても、所有権の存否について既判力およびこれに類似する効力(いわゆる争点効)を有するものではないとされた事例 |
||
| 327 | S44.6.24 |
民法110条にいう「正当な理由があるとき」とは、無権代理行為がされた当時存した諸般の事情を客観的に観察して、通常人においてその行為が代理権に基づいてされたと信ずるのがもっともだと思われる場合、すなわち、第三者が代理権があると信じたことが無過失である場合をいい、その諸般の事情には本人の言動を含むと解されるとした事例 |
||
| 328 | S44.6.19 |
建物保護に関する法律1条2項(昭和41年法律第93号による削除前のもの)は、建物の朽廃以外の滅失の場合にも適用があるとされた事例 |
||
| 329 | S44.6.17 |
建物の一部の賃借人が、賃貸人の承諾を得ず賃貸目的以外の部分を改造し使用している行為が、著しい不信行為であるとして、無催告の賃貸借契約の解除を許容した事例 |
||
| 330 | S44.6.17 |
甲所有の従前地につき換地処分がされたときは、換地処分公告の翌日から従前地とみなされる換地につき甲は所有権を取得し、当該換地部分につき乙が所有権を有していたとしても、これに対しなんらの換地処分等がされないときは、公告の翌日以後は当該換地部分につき乙の所有権を認めることはできないとした事例 |
||
| 331 | S44.6.12 |
特定地域の土地が、甲乙間において、甲所有の丙地に含まれるか、乙所有の丁地に含まれるかが争われている場合には、甲がその主張の丙地について所有権取得登記を経由していなくても、乙はこの一事によつて甲の土地に対する土地所有権取得を否定することはできないとされた事例 |
||
| 332 | S44.6.12 |
・敷金の授受があったときでも、延滞賃料支払の催告は延滞賃料全額についてすることができるとした事例 |
||
| 333 | S44.6.3 |
賃貸建物につき売買契約に基づく所有権移転請求権保全の仮登記が経由された後に、仮登記義務者が賃料債権を第三者に譲渡しても、賃料債権譲渡は仮登記に基づく所有権移転の本登記が経由されたことによって、その効力を否定されるものではないとされた事例 |
||
| 334 | S44.5.30 |
従来母屋に接続する簡単なバラック建付属建物であった部分を拡げて店舗に改造し、母屋との間に板壁による間仕切りをし、母屋と全く別個に使用できるようにした場合においては、柱および板壁を共通とし、建物が屋根続きで外観上は一体の建物の観を呈していても、改造部分につき区分所有権が成立するとした事例 |
||
| 335 | S44.5.29 |
共有者の一人の単独名義に所有権登記されている場合、その登記が保存登記で、かつ、第三者のための登記が存在しないときでも、他の共有者はその所有権登記につき、自己の持分についてのみ一部抹消(更正)登記手続を求めることはできるが、その全部の抹消登記手続を求めることはできないとされた事例 |
||
| 336 | S44.5.27 |
甲が乙の承諾のもとに乙名義で不動産を競落し、丙が善意で乙からこれを譲り受けた場合において、甲は丙に対し登記の欠缺を主張して不動産の所有権の取得を否定することはできないとした事例 |
||
| 337 | S44.5.27 |
農地の二重売買につき、第一の買主が売主の履行不能を理由とする損害賠償を求めた事案において、第二買主の所有権移転請求権保全の仮登記を経由をもって売主の履行不能が確定したとはいえないし、同仮登記により農地法の許可が得られない証拠もないとして、その請求を棄却した事案 |
||
| 338 | S44.5.22 |
都市計画において公園とされている市有地について、民法162条による取得時効の成立が認められた事例 |
||
| 339 | S44.5.20 |
土地賃貸借の期限付合意解約は、合意に際し賃借人が真実解約の意思を有すると認められる合理的客観的理由があり、かつ、他に合意を不当とする事情が認められないかぎり、借地法11条に該当しないとした事例 |
||
| 340 | S44.5.2 |
中間省略登記が中間取得者の同意なしにされた場合においても、中間取得者でない者は、登記の無効を主張してその抹消登記手続を求めることはできないとされた事例 |
||
| 341 | S44.4.24 |
所有権移転登記申請手続が登記義務者の意思に基づいてなされたものである以上、代理人による登記申請書に適式の代理委任状その他代理権限を証する書面が添付されなかった一事によって、登記の効力が生じないと解すべきものではないとした事例 |
||
| 342 | S44.4.24 |
土地賃借人の夫が借地上の建物の所有者である妻に、離婚に伴い、賃貸人の譲渡承諾を得ず借地権を譲渡したことにつき、賃貸人に対する背信行為とは認められない特別の事情があるとされた事例 |
||
| 343 | S44.4.22 |
甲所有不動産について、乙のためにされた抵当権設定登記および所有権移転請求権保全の仮登記につき、それぞれ丙に権利移転の附記登記が経由された場合において、甲が、抵当債務の弁済、代物弁済契約の無効を理由に登記の抹消請求をするには、丙のみを被告とすれば足り、乙を被告とすることを要しないとした事例 |
||
| 344 | S44.4.22 |
従前の土地の一部の賃借人は、特段の事情のないかぎり、土地区画整理事業の施行者から、使用収益部分の指定を受けることによって、はじめてその部分について現実に使用収益をすることができるとした事例 |
||
| 345 | S44.4.17 |
不動産について、被相続人との間に締結された契約上の義務の履行として、所有権移転登記手続を求める訴訟は、その相続人が数人いるときでも、必要的共同訴訟ではないとした事例 |
||
| 346 | S44.4.15 |
建物所有を目的とする借地契約においては、その借地上の建物に対し通常の域をこえる大修繕をした場合には、その借地契約は、建物が現実に朽廃していなくても、その修繕前の建物が朽廃すべかりし時期に終了するものと解すべきであるとした事例 |
||
| 347 | S44.4.15 |
借家法7条による賃料値上請求に基づき値上賃料支払請求訴訟を提起中、値上を相当とする事由が生じた場合、新たに値上の請求をしない限り、先にした請求の範囲内においてさらに値上の効力を生ずるものではないとした事例 |
||
| 348 | S44.4.15 |
社宅の利用関係につき、鉱員たる資格の存在をその使用関係存続の前提とする社宅に関する特殊な契約関係であって、借家法の適用はないとされた事例 |
||
| 349 | S44.3.28 |
宅地に対する抵当権の効力は、特段の事情のないかぎり、抵当権設定当時宅地の従物であつた石灯篭および庭石にも及び、抵当権の設定登記による対抗力は従物についても生ずるとした事例 |
||
| 350 | S44.3.27 |
共有不動産につき共有者の一人が持分権を放棄した場合、他の共有者は放棄にかかる持分権の移転登記手続を求めるべきであって、放棄者の持分権取得登記の抹消登記手続を求めることは許されないとされた事例 |
||
| 351 | S44.3.25 |
改築後の新建物が旧建物と同じく木造平屋建一棟の居宅であって、旧建物を支えていた柱も相当数のものが残って新建物の支柱となり、旧建物の残存部分が新建物の主たる構成部分をなしているなどの事実関係のもとにおいては、新・旧両建物は社会通念上同一性を有するとした事例 |
||
| 352 | S44.3.20 |
主債務の消滅時効完成後に、主債務者が当該債務を承認し、保証人が、主債務者の債務承認を知って、保証債務を承認した場合には、保証人がその後主債務の消滅時効を援用することは信義則に照らして許されないとした事例 |
||
| 353 | S44.3.4 |
所有権移転請求権保全の仮登記が登記原因たる実体上の権利を欠き無効であるとされた事例 |
||
| 354 | S44.2.27 |
土地に抵当権を設定した当時、土地上に建物がなく、その後建物が土地上に建築された場合においては、土地建物が同一の所有者に属するときでも、民法388条(法定地上権)の規定は適用されないとした事例 |
||
| 355 | S44.2.18 |
賃貸人の承諾を得ない賃借権の譲受または転借が賃貸人に対抗できる場合、その主張・立証責任は譲受人または転借人が負うとした事例 |
||
| 356 | S44.2.14 |
抵当権設定当時土地および建物の所有者が異なる場合においては、その土地または建物に対する抵当権の実行による競落の際、土地および建物が同一人の所有に帰していても、法定地上権は適用または準用されないとした事例 |
||
| 357 | S44.2.13 |
賃借権譲渡に賃貸人の承諾を要する特約に反して賃借人が賃借権を譲渡した場合において、特約の趣旨その他諸般の事情に照らし、譲渡が賃貸人に対する背信的行為と認めるに足りない特段の事情が存する事を賃借人が立証したときは、特約に基づく賃貸借の解除は許されないとした事例 |
||
| 358 | S44.2.13 |
・民法21条の「詐術を用いたとき」とは、積極的術策を用いた場合に限るものではなく、無能力者が、ふつうに人を欺くに足りる言動を用いて相手方の誤信を誘起し、または誤信を強めた場合も含むとした事例 |
||
| 359 | S44.1.31 |
・借地契約において無断譲渡、無断転貸等を禁ずる特約が付されていても、特段の事情があるときは、賃貸人は同特約に基づく借地契約の解除はできないとした事例 |
||
| 360 | S44.1.31 |
他人の財産権を贈与の目的物とする贈与契約も有効に成立するとした事例 |
||
| 361 | S44.1.28 |
土地改良区の土地改良事業の施行にあたり、一時利用地の指定を受けながらこれに対応する換地を交付されなかった者は、一時利用地を他人の換地とした処分の無効確認を求める利益を有しないとされた事例 |
||
| 362 | S44.1.28 |
遺留分権利者が受遺者に対して行なう減殺請求権は形成権であり、必ずしも裁判上の請求による必要はなく、いったんその意思表示がされた以上、法律上当然に減殺の効力を生ずるとした事例 |
||
| 363 | S43.12.24 |
民法162条2項の占有者の善意・無過失とは、自己に所有権があるものと信じ、かつ、そのように信ずるにつき過失のないことをいい、占有者において、占有の目的不動産に抵当権が設定されていることを知り、または、不注意により知らなかった場合でも、善意・無過失の占有者ということを妨げないとした事例 |
||
| 364 | S43.12.24 |
仮換地の指定後、従前の土地が分割譲渡され所有者を異にする二筆以上の土地となった場合、施行者により各筆に対する仮換地を特定した変更指定処分がされないかぎり、各所有者は仮換地全体につき、従前の土地に対する各自の所有地積の割合に応じ使用収益権を共同して行使すべきいわゆる準共有関係にあるものとされた事例 |
||
| 365 | S43.12.24 |
宅地建物取引業者の報酬について、法定の最高額をもつて相当額と認めた原審の判断に、審理不尽・理由不備の違法があるとされた事例 |
||
| 366 | S43.12.24 |
請負人が第三者に損害を与えた場合において、注文者に注文または指図について過失があるとされた事例 |
||
| 367 | S43.12.24 |
弁護士でない者に、自己の法律事件の示談解決を依頼し、これに報酬を与えもしくは与えることを約束しても、弁護士法第72条違反の罪の教唆犯は成立しないとされた事例 |
||
| 368 | S43.12.24 |
不動産所有権譲渡をもって代物弁済をする旨の契約は、債務の弁済が代物弁済による所有権移転の意思表示の後にされても、その所有権移転登記手続の完了前にされたときは、その意思表示は弁済による既存債務の消滅によってその効力を失うとした事例 |
||
| 369 | S43.12.20 |
建物の土台の一部が低下し、柱の一部も土台との接合部において腐蝕し、このため建物が傾斜している場合であっても、通常の補修を加えれば、倒壊の危険を免れ、なお相当期間建物の効用を果たすことができるときは、建物の朽廃によりその賃貸借契約が終了したと認めることはできないとされた事例 |
||
| 370 | S43.12.20 |
民法1013条(遺言の執行の妨害行為の禁止)の規定が適用される場合においても、取引の安全をはかる見地から設けられた民法478条(債権の準占有者に対する弁済)の規定は排除されないとした事例 |
||
| 371 | S43.12.20 |
民法第565条にいういわゆる数量指示売買とは、当事者において目的物の実際に有する数量を確保するため、その一定の面積・容積・重量・員数または尺度のあることを売主が契約において表示し、かつ、この数量を基礎として代金額が定められた売買を指称するものであるとされた事例 |
||
| 372 | S43.12.4 |
仮登記が仮登記権利者不知の間に不法に抹消された場合には、登記上利害の関係を有する第三者は、その善意、悪意または回復登記により受ける損害の有無、程度にかかわらず、仮登記権利者の回復登記手続に必要な承諾を与えなければならないとされた事例 |
||
| 373 | S43.11.28 |
不動産の賃貸人が特約に基づき賃借権設定登記をする義務を負っていても、賃料支払義務と同時履行の関係とする特約がなく、かつ、登記がないと契約目的を達することができないという特段の事情もない場合には、賃借人は登記義務の履行がないことを理由に賃料の支払を拒むことはできないとした事例 |
||
| 374 | S43.11.27 |
・河川附近地制限令第4条第2号、第10条は、憲法第29条第3項に違反しないとした事例 |
||
| 375 | S43.11.26 |
土地所有権に基づく同土地上に存する水道用配水管設備等の撤去請求が、権利の濫用とされた事例 |
||
| 376 | S43.11.21 |
家屋賃貸借契約において、1カ月分の賃料遅滞を理由に無催告で契約解除ができる旨の特約条項は、賃料遅滞を理由とする契約解除において、催告をしなくても不合理とは認められない事情が存する場合には、効力を有するとした事例 |
||
| 377 | S43.11.21 |
建物の賃借人が差押を受けまたは破産宣告の申立を受けたときは、賃貸人はただちに賃貸借契約を解除することができる旨の特約は、借家法第6条により無効であるとした事例 |
||
| 378 | S43.11.21 |
不動産の二重売買において、第二の買主の所有権移転登記がされた場合、第一の買主は、第二の買主の明渡請求に対し、売買契約不履行に基づく損害賠償債権をもって、留置権を主張することはできないとされた事例 |
||
| 379 | S43.11.19 |
不動産の譲受人が登記を経ないうちに、不動産について、第三者から譲渡人を仮処分債務者とする処分禁止の仮処分が執行された場合においても、譲受人が登記なく仮処分債権者に権利取得を対抗しうる地位にあったときは、譲受人は仮処分執行後も仮処分債権者に対し所有権の取得を対抗できるとした事例 |
||
| 380 | S43.11.19 |
不動産所有権の譲渡をもって代物弁済をする場合に、債権者が不動産の所有権移転登記手続に必要な一切の書類を債務者から受領しただけで直ちに代物弁済による債務消滅の効力が生ずる特約が存するときには、債権者が債務者から書類を受領した時に代物弁済による債務消滅の効力が生ずるとした事例 |
||
| 381 | S43.11.19 |
一時使用の目的で賃借した土地上に建築された仮設建物を譲り受けた者と、土地所有者との間で締結された10年の賃貸借契約について、土地賃貸借契約締結の経緯等から、一時使用のための土地の賃貸借に該当するとされた事例 |
||
| 382 | S43.11.15 |
甲の乙に対する山林の贈与に関し、立会人として示談交渉に関与した丙につき、いわゆる背信的悪意者として、乙の所有権登記の欠缺を主張する正当な利益を有する第三者にあたらないとされた事例 |
||
| 383 | S43.11.15 |
部落民全員が、その総有に属する土地について、入会権者として登記の必要に迫られ、単に登記の便宜から、部落民の一部の者のために売買による所有権移転登記を経由した場合には、民法94条2項の適用または類推適用がないとした事例 |
||
| 384 | S43.11.13 |
所有権に基づく登記手続請求の訴訟において、被告が自己に所有権があることを主張して請求棄却の判決を求めることは、原告のための取得時効を中断する効力を生ずるとした事例 |
||
| 385 | S43.11.7 |
借家法に基づく増額請求により賃料が増額された後における賃借人の賃料債務の不履行が賃貸借の基礎たる信頼関係を破壊するものとして賃貸借契約の解除が認められた事例 |
||
| 386 | S43.11.5 |
「数量指示売買」とは目的物が実際に有する数量を確保するため、その一定の面積、容積、重量、員数または尺度あることを売主が契約において表示し、かつ、この数量を基礎として代金額が定められた売買をいうとした事例 |
||
| 387 | S43.10.31 |
賃借権の譲渡転貸許容の特約がされその旨の登記がされている土地賃貸借において、賃借権の消滅を第三者に対抗するためにはその旨の登記を経由する必要があるとした事例 |
||
| 388 | S43.10.29 |
借地法10条に基づく買取請求権の行使により、借地上建物の所有権が移転した場合においても、建物の賃借人は借家法1条によつて賃借権を対抗できるとした事例 |
||
| 389 | S43.10.18 |
譲渡担保が暴利行為により公序良俗に違反するかどうかの判断に当っては、その契約により担保される債権の額とその譲渡担保の対象となつた全物件の価格を比較すべきであるとした事例 |
||
| 390 | S43.10.17 |
不動産の売買予約を仮装して所有権移転請求権保全の仮登記手続をした場合において、外観上の仮登記権利者が仮登記に基づき所有権移転の本登記手続をしたときは、外観上の仮登記義務者は本登記の無効をもって善意無過失の第三者に対抗できないとした事例 |
||
| 391 | S43.10.17 |
主たる債務者の債務の短期消滅時効期間が民法174条ノ2の規定によつて10年に延長される場合には、これに応じて保証人の債務の消滅時効期間も同じく10年に変ずるものと解されるとした事例 |
||
| 392 | S43.10.8 |
土地の継続的な用益という外形的事実が存在し、かつ、それが賃借の意思に基づくことが客観的に表現されているときは、土地賃借権を時効により取得することができるとした事例 |
||
| 393 | S43.10.8 |
・抵当権の設定契約が無効のときには、その抵当権に基づく競売により、抵当物件が競落されても、競落人はその所有権を取得することができないとした事例 |
||
| 394 | S43.10.8 |
予告登記の存することの一事から、これに後行して係争不動産につき物権の得喪変更に関する法律行為をなした第三者が当該登記原因の瑕疵につき悪意と推定されるべきではないとされた事例 |
||
| 395 | S43.9.27 |
家屋の共同賃借人の一人がなした貸主に対する暴行行為およびガレージの無断築造が、賃貸借契約の即時解除の原因となるとした事例 |
||
| 396 | S43.9.26 |
・物上保証人は、被担保債権の消滅時効を援用することができるとした事例 |
||
| 397 | S43.9.20 | ・売買代金の支払時期について不確定な期限を定めたものと認められた事例 |
||
| 398 | S43.9.17 |
個人が土地を賃借し、建物はその個人企業が所有し使用している事案において、個人企業を会社組織に改め、土地をその会社に使用させたことにつき、背信行為と認められない特段の事情があるとして、土地賃貸人の民法612条2項による契約解除を否定した事案 |
||
| 399 | S43.9.12 |
家屋の所有権を贈与により取得したとした者の、贈与者の相続人らに対する所有権移転登記請求訴訟において、裁判所が贈与の主張は死因贈与の主張を包含するものと解し、死因贈与による所有権移転を認定することは、当事者の主張しない事実を認定したものとはいえないとした事例 |
||
| 400 | S43.9.12 |
家屋の賃貸借契約が無断転貸禁止条項を含む調停によるものであり、賃貸人が解除前転借人に対し無断転借は承認できない旨を告知している等の事情のもとでの賃借人の家屋の一部無断転貸は、賃貸人に対する背信行為であるとして賃貸人の契約解除を認めた事例 |
||
| 401 | S43.9.6 |
・買収農地の売渡を受けて農業用施設として占有している者は、その売渡処分が当然無効であっても、その占有の始めに善意・無過失というべきであるとした事例 |
||
| 402 | S43.9.6 | 建物収去土地明渡の強制執行が権利の濫用にあたるとされた事例 |
||
| 403 | S43.9.3 | ・不動産売買の媒介契約は、報酬を支払う約定があっても、依頼者は民法第651条第1項に基づき契約を解除することができるとした事例 |
||
| 404 | S43.9.3 |
対抗力を具備しない土地賃借権者に対し建物収去土地明渡を求めることが権利濫用となる場合においても、土地所有権の取得者が賃借権者に対し、違法に土地を占有するものであることを理由に損害の賠償を請求することは許されるとした事例 |
||
| 405 | S43.9.3 |
建物を所有し営業している土地の賃借人が存する土地につき、著しく低廉な賃借権付評価額で取得した土地の買受人が、賃借権の対抗力の欠如を奇貨とし、不当の利益を収めようとして、賃借人に対し行った建物収去土地明渡請求が権利の濫用として許されないとした事例 |
||
| 406 | S43.8.20 |
・数量指示売買とは、当事者において目的物の実際に有する数量を確保するため、その一定の面積、容積、重量、員数または尺度あることを売主が契約において表示し、かつ、この数量を基礎として代金額が定められた売買をいうとした事例 |
||
| 407 | S43.8.20 |
宅地建物取引業者の報酬額に関する規則は、業者が不当に多額の報酬を受領することを抑止する目的で最高額を定めたものであり、この最高額が授受されることが通常であるとか、慣行があるということはできないとされた事例 |
||
| 408 | S43.8.2 |
甲から山林を購入した乙が23年間これを占有していたところ、丙がその事実を知りながら、乙の未登記に乗じて乙に高値で売却する目的で、甲から当該山林を購入し登記を経たという事情の下では、丙は、いわゆる背信的悪意者として、乙の登記がないことを主張する正当の利益を有する第三者に当たらないとされた事例 |
||
| 409 | S43.7.18 |
建物保護法による対抗力を有しない賃借人の土地賃借権が、賃貸人の土地譲渡により消滅に帰したとしても、賃貸人の賃借人に対する不法行為が成立するものではないとした事例 |
||
| 410 | S43.7.16 |
一筆の土地を賃借し二棟の建物を所有する借地人が、各一棟を養女とその夫にそれぞれ贈与しその後死亡した事情のもとでの、土地賃貸人の借地権無断譲渡を理由とする各建物を受贈した養女およびその夫それぞれに対する土地明渡し請求は権利濫用に当たるとした事例 |
||
| 411 | S43.7.9 |
民事訴訟法の剰余の見込なき場合の競売取消等の規定に違反してされた競売につき、債務者から同法の不遵守を理由に損害賠償の請求をすることはできないとした事例 |
||
| 412 | S43.7.5 |
借地法第12条の賃料増額請求において、裁判所は同条所定の諸契機を考量し、具体的事実関係に即し、相当賃料を確定すべきであり、その際、底地価格に利子率を乗ずる算定方法(土地価格の利廻り算定方式)は一つの合理的尺度となるものであるが、他の算定方式に比べ本則であるとまで解すべきものではないとした事例 |
||
| 413 | S43.6.28 |
境界標を損壊しても、いまだ境界が不明にならない場合には、境界毀損罪は成立しないとした事例 |
||
| 414 | S43.6.27 |
地代増額請求権の行使によって適正額の増額の効果が生ずるのは、増額請求の意思表示が相手方に到達した時であるとした事例 |
||
| 415 | S43.6.27 |
期間の定のない店舗の賃貸借において、場所的利益の対価としての性質を有する権利金名義の金員が賃借人から賃貸人に交付されていた場合には、賃貸借が2年9カ月で合意解除されたとしても、賃借人はそれだけの理由で賃貸人に対しその金員の返還請求をすることはできないとした事例 |
||
| 416 | S43.6.21 |
土地所有者が地代不払を理由に借地契約の解除を請求した事案において、借地人が地代不払に至った事情には土地所有者にも原因があるなどの事情から、地代不払の一事をもって賃貸借の基礎たる信頼関係の破壊があるとまではいえないとしてその請求を棄却した事例 |
||
| 417 | S43.6.21 |
私文書の作成名義人の印影が名義人の印章によつて顕出されたことが認められたときは、反証のないかぎり同印影は、名義人の意思に基づいて顕出されたものと推定され、その私文書は真正に成立したものと推定されるとした事例 |
||
| 418 | S43.6.21 |
売主および買主が連署のうえ農地法5条による許可申請書を知事あてに提出したときは、特約その他特別の事情のないかぎり、民法557条1項にいう「契約の履行に著手」したと解されるとした事例 |
||
| 419 | S43.6.13 |
建物の附合の成否について、新築部分の構造、利用方法を考察し、従前の建物に接して築造され、構造上建物としての独立性を欠き、一体となって利用され取引されるべき状態にあるときは、附合したものと解すべきであるとした事例 |
||
| 420 | S43.5.30 |
売買代金を分割払いとする土地の売買において、買主が所有権を取得し引渡しを受けた後に、売主が、買主不知の間に、第三者のため売買土地に根抵当権・地上権の設定登記を行った事情のもと、売主催告の残代金を買主が支払わなかったことを理由とする契約解除は、信義則に反し無効であるとした事例 |
||
| 421 | S43.5.28 |
無断転貸を賃貸人に対する背信行為と認めるに足りないものとした特段の事情が解消された場合は、また、その時点において別途判断すれば足りるとした事例 |
||
| 422 | S43.5.28 |
土地所有者がその所有権にもとづいて地上の建物の共同相続人を相手方として建物収去土地明渡を請求する訴訟は、いわゆる固有必要的共同訴訟ではないとされた事例 |
||
| 423 | S43.5.23 |
従前の土地の一部について賃借権を有する者は、土地区画整理事業の施行者から、権利の目的となるべき土地としての指定通知を受けないかぎり、たとえ施行者からの通知により賃借地上の建物を解体移転したとしても、当然には仮換地について現実に使用収益をすることができないとした事例 |
||
| 424 | S43.4.16 |
土地の一部につき無断転貸などの違反行為があったにすぎない場合でも、建物と土地とが一個の賃貸借の目的となっているときには、賃貸借全部を解除することができるとした事例 |
||
| 425 | S43.4.4 |
共有者の一人が、権限なく、共有物を自己の単独所有に属するものとして他に売り渡した場合でも、売買契約は有効に成立し、自己の持分をこえる部分については、他人の権利の売買としての法律関係を生ずるとともに、自己の持分の範囲内においては、約旨に従った履行義務を負うとした事例 |
||
| 426 | S43.4.2 |
・仲介業者が、不動産の売買契約成立のため、買主の現場案内、売買代金の価格合意、契約立会い、目的物の受渡し、代金授受に関与した等の事情のもとにおいて、買主との間に明示の媒介契約がなくとも、黙示の媒介契約がなされていたとして、商法第512条による媒介報酬請求を認めた事例 |
||
| 427 | S43.3.29 |
賃借権の無断譲渡が賃貸人に対する背信行為と認めるに足りない旨の特段の事情の存在と主張・立証責任は、賃借人にあるとした事例 |
||
| 428 | S43.3.28 |
土地の賃借人は賃借権を保全するため、賃貸人たる土地所有者に代位して土地の不法占拠者に対し建物収去及び土地明渡を請求することができ、かつその場合、直接自己に対して収去明渡をなすべきことを請求できるとした事例 |
||
| 429 | S43.3.28 |
裁判上の和解により成立した土地賃貸借についても、土地の利用目的、地上建物の種類、設備、構造、賃貸期間等諸般の事情から、賃貸借当事者間に短期間にかぎり賃貸借を存続させる合意が成立したと認められる場合には、借地法第9条にいう一時使用の賃貸借に該当し、同法第11条の適用は受けないとした事例 |
||
| 430 | S43.3.28 |
一筆の土地Aよりその一部土地Bを分筆し譲渡した結果、土地Bが公路に通じないこととなっても、譲受人が土地Bと隣接し公路に通ずる土地Cを所有している場合には、譲受人は土地Bのため民法213条の囲繞地通行権を有しないとした事例 |
||
| 431 | S43.3.15 |
土地の所有者がその所有権に基づいて地上の建物の所有者である共同相続人を相手方とし、建物収去土地明渡を請求する訴訟は、いわゆる固有必要的共同訴訟ではないとした事例 |
||
| 432 | S43.3.8 |
弁護士が登記申請の双方代理をしても、その弁護士の行為は、特段の事由のないかぎり、弁護士法第25条第1号に違反しないとした事例 |
||
| 433 | S43.3.8 |
工場備付の機械を目的物とする処分清算型の譲渡担保権者が、優先弁済権の実行のため目的物を工場から搬出する行為は、同人の権利を実行するための必須の行為であって不法行為とはいえないとした事例 |
||
| 434 | S43.3.7 |
甲不動産につき抵当権設定契約および代物弁済予約形式の合意がされるとともに乙不動産につき同一債権の担保を目的とする所有名義移転の合意がされた場合において、債権者は両不動産を換価処分して得た金員から元利金の弁済を受けることができるにとどまるとされた事例 |
||
| 435 | S43.3.1 |
相続人が登記簿に基づき実地に調査すれば、相続した土地の範囲に甲地を含まないことを容易に知ることができたにもかかわらず、この調査をしなかったために、甲地が相続した土地に含まれると信じて占有をはじめたときは、相続人は占有のはじめにおいて無過失ではないとした事例 |
||
| 436 | S43.3.1 |
一筆の従前地全部を賃借する者が適法な賃借権の届出をした場合であっても、施行者から通知がない以上、賃借人は換地予定地について使用収益権を有しないとされた事例 |
||
| 437 | S43.2.29 |
抵当権の設定と同時に代物弁済予約が締結された不動産において、抵当権の実行による競売手続が開始したときは、競売手続が競売申立の取下その他の事由により終了しないかぎり、債権者が代物弁済の予約の完結権を行使することは許されないとした事例 |
||
| 438 | S43.2.23 |
法定地上権の地代確定訴訟の係属中、法定地上権が譲渡され、その後訴訟の判決が確定した場合、その譲受人は、判決によって譲渡人と地主との間で確定された譲受当時の地代を譲受の時に遡って支払う義務を負うとした事例 |
||
| 439 | S43.2.23 |
土地の売買契約において、所有権移転登記手続は代金完済と同時とし、代金完済までは買主は土地の上に建物等を築造しない旨の付随的約款に違反したとした、契約解除が認められた事例 |
||
| 440 | S43.2.22 |
取得時効の成否は、境界確定の訴えにおける境界確定とは関係がないとした事例 |
||
| 441 | S43.2.16 |
抵当権の設定契約が無効であるときは、抵当権が実行され不動産が競落されても、競落人は不動産の所有権を取得することができないとした事例 |
||
| 442 | S43.2.1 |
「推認」の語は、証拠によって認定された間接事実を総合し、経験則を適用して主要事実を認定する場合に用いられる用語法であって、証明度において劣る趣旨を示すものではないとした事例 |
||
| 443 | S43.1.30 |
甲所有不動産につき、売買予約に基づく乙の所有権移転仮登記がされた後、所有権が乙へ、さらに丙へ移転したが、丙に対し売買予約の権利譲渡を原因として、仮登記につき所有権移転請求権移転の附記登記がされた場合、丙が甲に対して仮登記の附記登記に基づく所有権移転登記手続を請求することは許されないとした事例 |
||
| 444 | S43.1.25 |
賃貸借を5年とする店舗の賃貸借契約が、一時使用のための賃貸借と認められた事例 |
||
| 445 | S43.1.25 |
賃貸借契約書記載の「入居後の大小修繕は賃借人がする」旨の条項は、単に賃貸人が民法606条1項所定の修繕義務を負わないとの趣旨にすぎず、賃借人が家屋の使用中に生ずる一切の汚損、破損個所を賃借人の費用で修繕し、家屋を賃借当初と同一状態で維持すべき義務がある趣旨ではないとした事例 |
||
| 446 | S42.12.26 |
隣接土地所有者間に境界についての合意が成立したことのみによって、合意のとおりの境界を確定することは許されないとされた事例 |
||
| 447 | S42.12.14 |
賃貸家屋の所有権および未払賃料債権の譲受人が所有権の取得登記前にした賃料の支払の催告について、賃貸借契約の解除の前提としての催告の効力を認めた事例 |
||
| 448 | S42.12.8 |
土地の賃貸借において、土地44.7坪のうち23.7坪を無断転貸した賃借人の行為は賃貸人に対する背信行為であるとして、賃貸土地全部につき契約解除を認めた事例 |
||
| 449 | S42.12.5 |
ゴルフ練習場としての使用を目的とする土地の賃貸借につき、借地人が当初から土地上にゴルフ練習場経営に必要な事務所用等の建物を築造・所有することを計画していたとしても、特段の事情がない限りその土地の賃貸借は、借地法第1条にいう「建物の所有を目的とする」賃貸借に該当しないとした事例 |
||
| 450 | S42.11.24 |
借主(子)が建物を所有して会社を経営し、そこから得る収益により貸主(親)を扶養する等の内容を目的とした、親子間の期間の定めのない土地の使用貸借において、借主が貸主の扶養をやめるなどの当事者間の信頼関係の破壊があったとして、民法第597条第2項但書の類推適用により、貸主の使用貸借契約の解約を認めた事例 |
||
| 451 | S42.11.17 |
調停にて建物の収去土地明渡しに合意した土地賃借人が、借地法上は無効の賃貸借期間を5年とした定めにつき法律上有効と思った錯誤があるとして、調停の無効を主張した事案において、当該錯誤は調停の合意の縁由についての誤りにすぎず、要素の錯誤にあたらないとして調停は有効とされた事例 |
||
| 452 | S42.11.10 |
農地法第3条または第5条にもとづく知事の許可は、農地法の立法目的に照らして、所有権の移転等につきその権利の取得者が農地法上の適格性を有するか否かの点のみを判断して決定すべきであり、私法上の効力やそれによる犯罪の成否等についてまで判断をなすべきものではないとされた事例 |
||
| 453 | S42.11.2 |
板塀で囲み上部をトタン板で覆った土地につき、所有者の黙認のもと、建築資材置場として使用していた者が、台風による囲いの倒壊後、所有者が工事中止の申し入れにもかかわらず、土地にブロツク塀を構築し、その上をトタン板で覆い、建築資材などを置く倉庫として使用した行為は、不動産侵奪罪に該当するとした事例 |
||
| 454 | S42.11.1 |
不法行為による慰謝料請求権は、財産上の損害賠償請求権と同様単純な金銭債権であり、被害者が生前に請求の意思を表明しなくても相続の対象となるとされた事例 |
||
| 455 | S42.10.31 |
甲が乙に不動産を仮装譲渡し、丙が善意で乙からこれを譲り受けた場合であっても、丙が所有権取得登記をする前に、甲からの譲受人丁が乙を債務者とし不動産について処分禁止の仮処分登記を経ていたときは、丙はその所有権取得を丁に対抗することができないとした事例 |
||
| 456 | S42.10.31 |
乙ほか5名共有の土地が一方甲に譲渡され、他方丙を経て乙に譲渡された場合、乙が所有権取得登記を経由しても、甲は登記なくして乙に対し土地の所有権取得を対抗することができるとした事例 |
||
| 457 | S42.10.31 |
土地区画整理による仮換地の指定により、従前の土地上の建物を仮換地上に移転する場合において、移転が可能であるときは、移転費用に相当金額を要するのに対し建物が朽廃に近く残存価値が少ない等特段の事情のないかぎり、従前の建物の賃貸人は賃借人に対し、建物を移転し賃貸借を継続する義務を負うとした事例 |
||
| 458 | S42.10.27 |
農地を目的とする売買契約締結後に、売主が目的物上に土盛りをし、その上に建物が建築され、そのため農地が恒久的に宅地となった等買主の責に帰すべからざる事情により農地でなくなった場合には、売買契約は知事の許可なしに効力を生ずるとした事例 |
||
| 459 | S42.10.27 |
・他人の債務のため自己の所有物をいわゆる弱い譲渡担保に供した者は、右債務の消滅時効を援用することができるとされた事例 |
||
| 460 | S42.10.24 |
貸主が家屋の賃貸借契約の解約を申入れした後に、貸主が正当事由を具備しその後6月を経過したときは、当該6月の経過により賃貸借契約は終了したとされた事例 |
||
| 461 | S42.9.29 |
・借地権及び建物の譲受人が、土地賃貸人の借地権譲受の承諾が得られぬまま、建物に増築等を行ったときは、譲受当時の原状に回復した上でなければ、買取請求権を行使できないとされた事例 |
||
| 462 | S42.9.21 |
無断増改築禁止特約に違反し、借地上の居宅(実測15.5坪)中9.5坪をバー店舗に改築した場合に、土地賃貸借関係の継続を著しく困難にする不信行為として、借地契約を即時解除することができるとした事例 |
||
| 463 | S42.9.21 |
借地上の建物に通常の修繕の域をこえた大修繕がされた場合に、借地契約が修繕前の建物が朽廃すべかりし時期に終了するものとされた事例 |
||
| 464 | S42.9.19 |
地上権の譲受人は、地上権について登記を有しなくても、地上建物について所有権移転登記を経由した以上、建物保護に関する法律第1条第1項により、地上権の承継を土地所有者に対抗できるとした事例 |
||
| 465 | S42.9.1 |
抵当権者から委任をうけた者の過誤による申請によって、抵当権設定登記が抹消された場合、抵当権の対抗力は消滅するとした事例 |
||
| 466 | S42.8.25 |
売主の支払停止前になされた農地の売買について、知事の許可がなかったため、買主は支払停止後破産申立前に所有権移転請求権保全の仮登記を経たが、破産宣告が仮登記後1年を超えてなされたときは、仮登記についてもはや破産法第74条第1項による否認をしえなくなり、買主は仮登記に基づき破産管財人に対し、知事の許可を条件とする本登記を求めることができるとした事例 |
||
| 467 | S42.8.25 |
使用貸借契約の終了を原因とする家屋明渡請求権は、性質上の不可分給付を求める権利と解すべきであって、貸主が数名あるときは、各貸主は総貸主のため家屋全部の明渡を請求することができるとした事例 |
||
| 468 | S42.8.25 |
共有物分割の結果、不動産の一部について単独所有権を取得した場合には、分筆登記を経由したうえで、権利の一部移転の登記手続をすべきとした事例 |
||
| 469 | S42.8.24 |
建物所有を目的とする借地権の設定後、地上建物の保存登記前にその土地の所有権移転請求権保全の仮登記がされた場合、借地権者は仮登記に基づいて本登記をした者に対し借地権を対抗することができないとした事例 |
||
| 470 | S42.7.21 |
不動産の取得時効完成前に原所有者から所有権を取得し時効完成後に移転登記を経由した者に対し、時効取得者は、登記なくして所有権を対抗することができるとした事例 |
||
| 471 | S42.7.21 |
耕地整理施行中の未登記の残地を買い受けた者が、耕地整理組合について調査することなく、売主の所有地であるとの言を信じてその占有を始めたとしても、売主が真の所有者の実父でこれを管理していた等の事実の下においては、買主がその所有権を取得したと信じたことにつき過失がないとされた事例 |
||
| 472 | S42.7.21 |
所有権に基づいて不動産を占有する者についても、民法162条(取得時効)の適用があるとした事例 |
||
| 473 | S42.7.20 |
借地法10条による建物買取請求権の消滅時効の期間が10年と解された事例 |
||
| 474 | S42.7.13 |
土地賃借人の賃料債務の履行の提供ないし供託が、約定の範囲を越えた土地の賃貸を履行の受領により招来させるためのもので債務の本旨に従ったものではないとして、履行の提供に当たらないとされた事例 |
||
| 475 | S42.7.6 |
建物とともに敷地の賃借権が転々譲渡され、賃借権の各譲渡について賃貸人の承諾のない場合であっても、賃借権存続期間中に譲りうけた最後の譲受人は、建物買取請求権を有するとした事例 |
||
| 476 | S42.6.30 |
被用者が重大な過失により失火したときは、使用者は、被用者の選任または監督について重大な過失がなくても、民法第715条第1項によって賠償責任を負うとした事例 |
||
| 477 | S42.6.29 |
民法第94条第2項(通謀虚偽表示)にいわゆる第三者とは、虚偽の意思表示の当事者またはその一般承継人以外の者であって、その表示の目的につき法律上利害関係を有するに至った者をいうとした事例 |
||
| 478 | S42.6.29 |
従前の宅地の所有者は仮換地自体について、その本換地として確定する以前にこれを使用収益しうべき旨の地上権を設定することはできないとした事例 |
||
| 479 | S42.6.22 |
火災により、賃借建物の屋根等がほとんど焼け落ち、倒壊の危険もあり、完全修復には多額の費用を要し、建物全部を取り壊して新築する方が経済的である等の事実関係のもとにおいて、当該建物は火災により滅失し建物賃貸借契約は終了したとされた事例 |
||
| 480 | S42.6.20 |
津波によって土地が流出した後に住宅適地造成組合によって造成された土地の所有権の取得時効につき、相続による占有者が土地登記簿を調査しなかったことをもって占有のはじめに過失があったとはいえないとした事例 |
||
| 481 | S42.6.6 |
不動産の所有権が順次甲、乙、丙と譲渡された場合に、甲が乙に対し所有権移転登記をする意思で、登記申請書類を交付していたときは、丙が同書類を利用して甲から丙に直接所有権移転登記をしても同登記は無効になるものではないとした事例 |
||
| 482 | S42.6.2 |
建物の一部であっても、障壁等によって他の部分と区画され、独占的排他的支配が可能な構造・規模を有するものは、借家法第1条にいう「建物」にあたるとした事例 |
||
| 483 | S42.5.30 |
法人の代表者は、現実に被用者の選任・監督を担当していた場合に限り、民法715条2項の代理監督者に当たるとされた事例 |
||
| 484 | S42.5.2 |
甲から乙へ家屋の所有権が譲渡移転された後、甲から家屋を賃借して引渡を受けた丙は、その後に所有権移転登記を受けた乙に対し、賃借権をもって対抗することができるとした事例 |
||
| 485 | S42.4.28 |
家屋賃借人が死亡し、唯一の相続人も行先不明で生死も判然とない場合において、家屋賃借人の内縁の夫が家屋賃借人の賃借権の援用により家屋に居住できるとした事例 |
||
| 486 | S42.4.20 |
代理人が自己または第三者の利益をはかるため権限内の行為をしたときは、相手方が代理人の意図を知りまたは知りうべきであった場合にかぎり、民法93条(心裡留保)但書の規定を類推適用し本人はその行為についての責を負わないとされた事例 |
||
| 487 | S42.4.7 |
甲が、共同相続により持分を取得した不動産につき、単独相続したとして所有権登記を経由し、乙と不動産について抵当権設定契約を締結し登記を経由したときは、甲は、乙に対し、自己の持分を超える部分について抵当権が無効であると主張しその抹消(更正)登記手続を請求することは、信義則に照らし許されないとした事例 |
||
| 488 | S42.4.6 |
宅地転用を目的とした農地の売買契約がなされた場合において、売主が知事に対する許可申請手続に必要な書類を買主に交付したのに、買主が特段の事情もなく許可申請手続をしないときには、売主はこれを理由に売買契約を解除することができるとした事例 |
||
| 489 | S42.3.31 |
借地権の無断譲渡が賃貸人に対する賃借人の背信行為となるのは、賃貸人が譲受人の賃料の支払能力、態度に不安を感じる場合に限られるものではないとして、借地上に三棟の建物を所有しうち一棟を他に譲渡した借地人に対する土地所有者の土地全部についての賃貸借契約の解除を認めた事例 |
||
| 490 | S42.3.30 |
長期にわたる賃料の不払は、それ自体賃貸借契約の継続を困難ならしめる背信行為にあたり、催告なしに契約の解除をすることができるとした事例 |
||
| 491 | S42.3.17 |
地役の性質を有する入会権が解体消滅したと認められた事例 |
||
| 492 | S42.2.24 |
贈与税課税権の消滅時効の起算日は、贈与によって財産を取得した年の翌年の3月1日であるとした事例 |
||
| 493 | S42.2.23 |
土地の一部を目的とする賃貸借について、当該契約の趣旨に適した場所が相当数あるときは、その賃借部分を特定して引き渡す賃貸人の債務は、選択債務にあたるとした事例 |
||
| 494 | S42.2.21 |
家屋賃借人の内縁の妻は、賃借人が死亡した場合には、相続人の賃借権を援用して賃貸人に対し当該家屋に居住する権利を主張することができるが、相続人とともに共同賃借人となるものではないとした事例 |
||
| 495 | S42.1.20 |
県知事の許可がないかぎり、農地の買戻は効力を発生しないから、売戻人の目的物の明渡義務も発生しないとした事例 |
||
| 496 | S42.1.20 |
相続人が、相続の放棄をした場合には相続開始時にさかのぼって相続開始がなかったと同じ地位に立ち、当該相続放棄の効力は、登記等の有無を問わず、何人に対してもその効力を生ずるとされた事例 |
||
| 497 | S42.1.20 |
建物賃借人は、建物賃貸借契約解除後占有中の当該建物を修繕しても、その修繕費償還請求権をもって当該建物につき留置権を行使することはできないとした事例 |
||
| 498 | S42.1.17 |
土地の賃貸人が調停の合意により賃借権の譲渡承諾義務を負う場合において、賃借人が承諾を求める手続をしたとき、賃貸人の現実の承諾がなくても、賃借権譲受人は賃借権の譲受をもって賃貸人に対抗することができるとされた事例 |
||
| 499 | S41.12.23 |
甲の所有地上に乙が家屋を建て、当該家屋を乙が一年間使用したら甲に所有権を移転し、以後甲・乙間で相当賃料で賃貸する契約をしたところ、家屋が完成直後に火事で焼失し乙が火災保険金を受取った事案において、代償請求として、甲の乙に対する乙の受取った火災保険金の引渡請求が認められた事例 |
||
| 500 | S41.12.22 |
第三者が民法94条2項(通謀虚偽表示)の保護をうけるためには、自己が善意であつたことを立証しなければならないとした事例 |
||
| 501 | S41.12.1 |
賃料の催告と、賃料不払による賃貸借契約解除の意思表示との間に約14年の隔たりがあっても、相手方において催告に基づく解除権の行使はないと信ずべき正当な事由が生じたといえない事情のもとでは、意思表示のときまで解除権は有効に存続しているとした事例 |
||
| 502 | S41.11.24 |
家賃が26倍に値上げされた場合であっても、当該値上額が第一審判決によって正当と判断された後、賃借人が値上額の家賃の支払催告に応じなかったときは、それを理由とする賃貸人の契約解除は有効であるとした事例 |
||
| 503 | S41.11.22 |
不動産の時効取得者は、取得時効の進行中に原権利者から当該不動産の譲渡を受けその旨の移転登記を経由した者に対しては、登記がなくても、時効による所有権の取得を主張することができるとした事例 |
||
| 504 | S41.11.18 |
・登記申請行為自体には、表見代理に関する民法の規定の適用はないとされた事例 |
||
| 505 | S41.11.10 |
・建物の賃貸人が賃貸借契約の解約申入に基づく建物の明渡請求訴訟を継続しているときは、解約申入の意思表示が黙示的・継続的にされているものと解されるとした事例 |
||
| 506 | S41.10.27 |
建物の借主が当該建物を含む貸主所有の不動産に賦課された固定資産税等の公租公課の支払を負担する等の事実があるとしても、その負担が建物の使用収益に対する対価の意味を持つと認める特段の事情のないかぎり、当該貸借関係は使用貸借であるとされた事例 |
||
| 507 | S41.10.27 |
「近い将来賃貸人が本件家屋から通勤しうる地に転勤してくるまで」との意味で期間を二年と定め、その後「更新」が続けられ結局解約申入まで約六年半以上を経過した家屋の賃貸借について、一時使用のための賃貸借と認められた事例 |
||
| 508 | S41.10.21 |
賃貸借契約が解除されていない場合でも、賃貸人は、賃借人から賃料の支払を受けた等特別の事情のないかぎり、賃借権の無断譲受人たる目的物の占有者に対し賃料相当の損害賠償請求ができるとした事例 |
||
| 509 | S41.10.7 |
15才位に達した者は、特段の事情のないかぎり、不動産について、所有権の取得時効の要件である自主占有をすることができるとした事例 |
||
| 510 | S41.10.7 |
書面によらない農地の贈与契約は、農地法第3条第1項による知事の許可を受けるまでは、農地の引渡があった後でも、取り消すことができるとした事例 |
||
| 511 | S41.9.22 |
町が付近住民の要望により、私道に所有者の承諾を得ることなく埋設した排水管について、私道所有者が当該排水管の撤去を求めた事案において、当該排水管撤去請求は、権利の濫用として許されないとした事例 |
||
| 512 | S41.9.8 |
他人の権利を目的とする売買の売主が、当該権利を取得してこれを買主に移転することができない場合、買主は売主に対し、民法第561条但書により担保責任の損害賠償の請求ができないときでも、なお債務不履行一般の規定に従って損害賠償を請求することができるとした事例 |
||
| 513 | S41.7.15 |
借地権付建物を会社名義で買受け、賃貸人との土地賃貸借契約を会社の代表者個人名義で締結したことが背信行為にあたるとして、賃貸人が賃貸借契約の解除を求めた事案において、賃貸人に対する背信行為にあたらない特別の事由があるとしてその請求を棄却した事例 |
||
| 514 | S41.7.14 |
遺留分権利者の減殺請求権は形成権であるとされた事例 |
||
| 515 | S41.7.1 |
賃貸借契約中の賃借人のする転貸等については賃貸人の書面による承諾を要する旨の特約は、合理的な目的をもってされた法律行為の方式の制限についてのものとして、有効であるとした事例 |
||
| 516 | S41.6.9 |
民法第192条(即時取得)により動産の上に行使する権利を取得したことを主張する占有者は、同条にいう「過失なき」ことを立証する責任を負わないとした事例 |
||
| 517 | S41.6.2 |
不動産の買主甲が売主乙に対し、所有権移転登記手続履行の請求訴訟を起こし勝訴判決得た場合において、乙から同一不動産の二重譲渡を受けた丙が、訴の事実審の口頭弁論終結後にその所有権移転登記を経たとしても、丙は前示確定判決について、民訴法第201条第1項の承継人にあたらないとした事例 |
||
| 518 | S41.5.31 |
農地法第4条第1項違反の罪は、宅地化の目的でなされる場合、家屋の建築工事に着手し、あるいは完全に宅地としての外観を整えるまでに至らなくとも、農地の肥培管理を不能もしくは著しく困難にして、耕作の目的に供される土地とはいいがたい状態にしたときに成立し、その時から時効が進行するとした事例 |
||
| 519 | S41.5.27 |
債務者が、被担保債権額以下の実価を有する抵当不動産を相当な価格で売却し、その代金を当該債務の弁済に充てて抵当権の消滅をはかる場合には、同不動産売却行為は詐害行為にはあたらないとした事例 |
||
| 520 | S41.5.19 |
共有物の持分の価格が過半数をこえる者は、共有物を単独で占有する他の共有者に対し、当然には、その占有する共有物の明渡を請求することができないとした事例 |
||
| 521 | S41.5.19 |
賃料不払による土地賃貸借契約解除に基づく建物収去土地明渡の訴の係属中成立した判示裁判上の和解において、賃貸借契約の合意解約がなされた等判示のような特別の事情があるときは、土地賃貸人は、当該合意解約をもって同土地上の建物の賃借人に対抗することができるとした事例 |
||
| 522 | S41.4.27 |
土地賃借人は、土地上に自己と同居する未成年の長男名義で保存登記をした建物を所有していても、その後当該土地の所有権を取得した第三者に対し、「建物保護ニ関スル法律」第1条により、土地の賃借権をもって対抗することができないとした事例 |
||
| 523 | S41.4.26 |
甲が乙の無権代理人として乙所有の不動産を丙に売り渡す契約を締結した後、甲が乙から不動産の譲渡を受けその所有権を取得するに至った場合において、丙が民法第117条にいう履行を選択したときは、前記売買契約は甲と丙との間に成立したと同様の効果を生ずるとした事例 |
||
| 524 | S41.4.22 |
借地権者が従前土地上に登記ある建物を所有している場合でも、借地権の申告に基づいて施行者が仮換地上に使用収益部分の指定をしなければ、仮換地上に使用収益権は生じないとした事例 |
||
| 525 | S41.4.22 |
民法109条の代理権授与表示者が、代理行為の相手方の悪意または過失を主張・立証した場合には、同条所定の責任を免れることができるとした事例 |
||
| 526 | S41.4.21 |
借地契約において増改築禁止特約に反し土地賃借人が増改築を行った場合において、当該増改築が借地人の土地の通常の利用上相当であり、土地賃貸人に対する信頼関係を破壊する恐れが認められないときは、土地賃貸人は建物の増改築を理由とする解除権を行使することはできないとされた事例 |
||
| 527 | S41.4.20 |
・消滅時効完成後に債務の承認をした場合において、そのことのみによって、同承認はその時効が完成したことを知ってしたものであると推定することはできないとされた事例 |
||
| 528 | S41.4.15 |
民法第162条第2項にいう平穏の占有とは、占有の取得・保持について、暴行強迫などの違法な行為を用いていない占有をいい、不動産所有者その他占有の不法を主張する者から異議をうけ、不動産の返還、占有者名義の所有権移転登記の抹消請求があっても、その占有が平穏でなくなるものではないとした事例 |
||
| 529 | S41.4.14 |
住宅建築を目的とした土地売買において、土地の8割にあたる部分が十数年前に公示された都市計画街路内に存することが、民法570条の売買の目的物に隠れたる瑕疵にあたるとした、買主の契約解除が認められた事例 |
||
| 530 | S41.4.12 |
仲介業者に情報提供をした事実はあるが、その仲介行為と成立した売買契約との間に因果関係がないとして、仲介業者の買主に対する報酬請求を棄却した事例 |
||
| 531 | S41.3.29 |
履行遅滞にある債務者がした弁済提供、供託につき、不足はあるがその額が僅少である場合には、債権者がその不足に名をかりて債務の本旨に従つた履行がないものとしてその受領を拒絶することは信義則上許されないとした事例 |
||
| 532 | S41.3.22 |
双務契約の当事者の一方が自己の債務の履行をしない意思を明確にした場合には、相手方が自己の債務の弁済の提供をしなくても、当事者の一方は、自己の債務不履行について、同時履行の抗弁権を主張することはできないとした事例 |
||
| 533 | S41.3.18 |
未登記の建物の所有者甲が、所有権を移転する意思がないのに、建物について、乙の承諾を得て乙名義の所有権保存登記を経由したときは、民法第94条第2項を類推適用して、甲は、乙が建物の所有権を有していないことをもって善意の第三者に対抗することができないとした事例 |
||
| 534 | S41.3.3 |
建物の売買契約解除後、不法に建物を占有する買主が、同建物につき必要費有益費を支出したとしても、買主は民法第295条第2項の類推適用により、当該費用の償還請求権に基づく建物の留置権は主張できないとした事例 |
||
| 535 | S41.3.3 |
共有物に対する不法行為による損害賠償請求権は、各共有者が自己の持分に応じてのみこれを行使しうるとした事例 |
||
| 536 | S41.3.1 |
抵当権の設定登記後に当該不動産について所有権移転請求権保全の仮登記を経由した者は、その後に登記された抵当権の実行による競落人に対し、その権利を対抗することができないとされた事例 |
||
| 537 | S41.2.8 |
技術士国家試験の合格、不合格の判定は、司法審査の対象とならないとした事例 |
||
| 538 | S41.1.27 |
賃借地の無断転貸を賃貸人に対する背信行為と認めるに足りないとする特段の事情は、その存在を賃借人において主張・立証すべきであるとした事例 |
||
| 539 | S41.1.21 |
所有権移転請求権保全の仮登記のなされた土地の仮換地の上に存する土地所有者の所有建物について抵当権が設定された場合には、建物の競落人は、法定地上権を取得するが、仮登記に基づいて所有権移転の本登記を経た者に対しては、法定地上権をもって対抗することができないとした事例 |
||
| 540 | S41.1.21 |
履行期の約定がある場合であっても、当事者が債務の履行期前には履行に着手しない旨合意している等格別の事情のないかぎり、履行期前に民法557条1項にいう履行の着手が生じ得ないものではないとした事例 |
||
| 541 | S41.1.20 |
同一所有者に属する土地およびその地上建物のうち、建物のみが譲渡された事案において、使用借権とする敷地の使用権設定があったと判断された事例 |
||
| 542 | S41.1.13 |
不動産の贈与を予定して、登記権利者たる受贈者の関与なく不動産の所有権取得登記がなされた場合でも、後日不動産の贈与が行われたときは、受贈者は不動産所有権の取得をもって第三者に対抗することができるとした事例 |
RETIO : (一財)不動産適正取引推進機構 機関誌