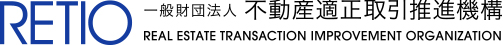意思表示等に関する判例 - 意思能力/法人・社団
該当件数 件
※判 決 日 クリックにより年月日順の並び替えができます。
| No. | 判決日 | 概要 | 事件番号 | RETIO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | H28.3.1 |
線路に立ち入り列車と衝突して鉄道会社に損害を与えた認知症の者の妻と長男の民法714条1項(責任無能力者の監督義務者等の責任)に基づく損害賠償責任が否定された事例 |
||
| 2 | H27.12.8 |
特例財団法人は、所定の手続を経て、その同一性を失わせるような根本的事項の変更に当たるか否かにかかわらず、その定款の定めを変更することができるとした事例 |
||
| 3 | H26.3.14 |
時効の期間の満了前6箇月以内の間に精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者に法定代理人がない場合において、少なくとも、時効の期間の満了前の申立てに基づき後見開始の審判がされたときは、民法158条1項の類推適用により、法定代理人が就職した時から6箇月を経過するまでの間は、その者に対して時効は完成しないとされた事例 |
||
| 4 | H26.2.27 |
権利能力のない社団は、構成員全員に総有的に帰属する不動産について、その所有権の登記名義人に対し、当該社団の代表者の個人名義に所有権移転登記手続をすることを求める訴訟の原告適格を有するとされた事例 |
||
| 5 | H23.2.15 |
マンション共用部分の無断改造工事に対する原状回復や使用料などの請求について、マンション管理組合(権利能力のない社団)は各訴えについて原告適格を有するとされた事例 |
||
| 6 | H23.2.9 |
権利能力のない社団を債務者とする金銭債権を有する債権者が、当該社団の構成員全員に総有的に帰属し、当該社団のために第三者がその登記名義人とされている不動産に対して仮差押えをする場合における申立ての方法について判断された事例 |
||
| 7 | H22.6.29 |
権利能力のない社団を債務者とする債務名義を有する債権者が、第三者が登記名義人となっている構成員の総有不動産に対して強制執行をする場合においては、強制執行の申立書に社団を債務者とする執行文の付された債務名義のほか、不動産が社団の構成員全員の総有に属する確認の確定判決その他これに準ずる文書を添付して当該社団を債務者とする強制執行の申立てをすべきとした事例 |
||
| 8 | H18.7.14 |
意思無能力者に代わって相続税を申告し納付した者による事務管理に基づく費用償還請求につき、意思無能力者には相続税申告書の提出義務がなく税務署長による税額の決定がされることもないことを前提として、事務管理に基づく費用償還請求を棄却した原審の判断には違法があるとされた事例 |
||
| 9 | H17.4.26 |
いわゆる強制加入団体でもなく、その規約において会員の退会を制限する規定を設けていない、権利能力のない社団である県営住宅の自治会の会員は、いつでも当該自治会に対する一方的意思表示によりこれを退会することができるとされた事例 |
||
| 10 | H7.11.9 |
禁治産者の後見人が、その就職前にした無権代理による訴えの提起及び弁護士に対する訴訟委任の行為の効力を再審の訴えにおいて否定することが、信義則に反するものではないとされた事例 |
||
| 11 | H7.1.24 |
責任を弁識する能力のない未成年者の行為により火災が発生した場合においては、未成年者の監督義務者が火災による損害を賠償すべき義務を負うが、監督義務者に未成年者の監督について重大な過失がなかったときは、これを免れるとした事例 |
||
| 12 | H6.9.13 |
禁治産者の後見人がその就職前に無権代理人によって締結された契約の追認を拒絶することが信義則に反するか否かを判断するにつき考慮すべき要素について示された事例 |
||
| 13 | H6.5.31 |
入会権者である村落住民が入会団体を形成し、それが権利能力のない社団に当たる場合には、右入会団体は、構成員全員の総有に属する不動産についての総有権確認請求訴訟の原告適格を有するとされた事例 |
||
| 14 | H6.4.19 |
社会福祉法人の理事が、その退任登記後に法人の代表者として第三者とした取引は、客観的な障害のため第三者が登記簿を閲覧することが不可能ないし著しく困難であるような特段の事情がない限り、民法112条の規定は適用されないとされた事例 |
||
| 15 | H4.12.10 |
・親権者が子を代理する権限を濫用して法律行為をした場合において、その行為の相手方が権限濫用の事実を知り又は知り得べかりしときは、民法93条但書の規定の類推適用により、その行為の効果は子には及ばないとした事例 |
||
| 16 | H1.12.22 |
民法187条1項(占有の承継)は、権利能力なき社団等の占有する不動産を、法人格を取得した以後当該法人が引き継いで占有している場合にも適用されるとした事例 |
||
| 17 | S60.11.29 |
・水産業協同組合法45条準用の民法54条にいう「善意」とは、理事の代表権に制限を加える定款の規定又は総会の決議の存在を知らないことをいうとされた事例 |
||
| 18 | S57.11.18 |
民法826条1項(利益相反行為)の規定に基づいて選任された特別代理人と、未成年者との利益が相反する行為については、特別代理人は、選任の審判によって付与された権限を行使することができないとされた事例 |
||
| 19 | S55.9.11 |
登記申請権者の申請に基づかないで不実の商業登記がされた場合には、登記を登記申請権者の申請に基づく登記と同視するのを相当とするような特段の事情がない限り、商法14条は適用されないとされた事例 |
||
| 20 | S51.4.23 |
財団法人が寄附行為の目的の範囲外の事業を行うためにした不動産の売却につき、本件売買の時から7年10か月余を経た後に訴を提起し、売買の無効を主張して売買物件の返還又は返還に代わる損害賠償を請求することは、信義則上許されないとした事例 |
||
| 21 | S49.12.20 |
準禁治産者である権利者が保佐人の同意を得られないため訴を提起できない場合でも、その権利についての消滅時効の進行は妨げられないとされた事例 |
||
| 22 | S49.11.14 |
特定の事項について共同代表取締役の意思が合致した場合において、代表取締役のある者が他の代表取締役に意思を外部に表示することにつき代表権の行使を委任することは、共同代表の定めに反しないとされた事例 |
||
| 23 | S48.10.9 |
権利能力のない社団の代表者が社団の名においてした取引上の債務は、社団の構成員全員に一個の義務として総有的に帰属し、社団の総有財産だけがその責任財産となり、構成員各自は、取引の相手方に対し個人的債務ないし責任を負わないとされた事例 |
||
| 24 | S48.10.5 |
入会部落の総有に属する土地の譲渡を受けた同部落の構成員は、譲渡前にこれを時効取得した者に対する関係において、民法177条にいう第三者にあたるとされた事例 |
||
| 25 | S47.6.2 |
権利能力なき社団の資産たる不動産については、社団の代表者が、社団の構成員全員の受託者たる地位において、個人の名義で所有権の登記をすることができるにすぎず、社団を権利者とする登記をし、または、社団の代表者である旨の肩書を付した代表者個人名義の登記をすることはできないとされた事例 |
||
| 26 | S47.2.18 |
未成年者の無権代理人が後見人となった場合において、先になされた無権代理行為の効果が未成年者に及ぶとされた事例 |
||
| 27 | S45.12.15 |
民法109条、商法262条は、会社を訴訟上代表する権限を有する者を定めるにあたっては適用されないとした事例 |
||
| 28 | S45.5.22 |
後見人が未成年者を代理して、後見人の内縁の夫に対し未成年者所有の土地を無償譲渡する行為は、旧民法915条4号にいう「後見人と被後見人との利益相反する行為」にあたるとした事例 |
||
| 29 | S44.11.21 |
被用者の取引行為を職務権限内の行為と信じた相手方に重大な過失がないとされた事例 |
||
| 30 | S44.9.11 |
会社の代表取締役が不動産を買い受けた場合において、これが代表取締役個人のためにした売買契約であるとした事実認定に経験則違背の違法があるとされた事例 |
||
| 31 | S44.6.26 |
・法人格のない財団として設立中の財団法人に訴訟上の当事者能力が認められた事例 |
||
| 32 | S41.10.7 |
15才位に達した者は、特段の事情のないかぎり、不動産について、所有権の取得時効の要件である自主占有をすることができるとした事例 |
||
| 33 | S39.10.15 |
・法人に非ざる社団が成立するためには、団体としての組織をそなえ、多数決の原則が行なわれ、構成員の変更にかかわらず団体が存続し、その組織において代表の方法、総会の運営、財産の管理等団体としての主要な点が確定していることを要するとした事例 |
||
| 34 | S38.9.5 |
株式会社の代表取締役が自己の利益のため会社の代表者名義でなした法律行為は、相手方が代表取締役の真意を知り、または、知りうべきものであったときは、その効力を生じないとした事例 |
||
| 35 | S37.10.2 |
親権者が自己の借入金債務につき、未成年の子の所有不動産に抵当権を設定する行為は、借入金を未成年の子の養育費にする意図であっても、民法第826条にいう「利益が相反する行為」にあたるとした事例 |
||
| 36 | S37.7.20 |
・建物所有を目的とし、民法602条所定の存続期間をこえる土地の賃貸借契約は、宗教法人令11条にいう不動産の処分にあたるとした事例 |
||
| 37 | S32.11.14 |
権利能力のない労働組合よりの脱退組合員は、その脱退が組合分裂に基づく場合であっても、当然には組合に対し財産分割請求権を有しないとした事例 |
||
| 38 | S32.6.7 |
賃借建物を転貸していた会社について、設立無効の判決が確定しても、これにより将来に向って賃貸借および転貸借関係が当然に失効するものではないとした事例 |
||
| 39 | S30.10.28 |
・他人の借地契約上の債務について連帯保証契約をすることは、特段の反証のない限り会社の目的の範囲内の行為であるとされた事例。 |
||
| 40 | S27.2.15 |
・会社の行為がその目的遂行に必要であるかどうかは、定款記載の目的自体から観察して、客観的に抽象的に必要であり得るかどうかの基準に従って決すべきであるとした事例 |
||
| 41 | S13.2.4 |
・未成年者が法定代理人の同意を得ずした債務の承認は取り消すことができるとした事例 |
昭12(オ)1810号(大審院) |
RETIO : (一財)不動産適正取引推進機構 機関誌