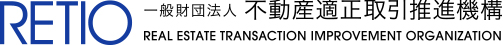その他 - 相続・贈与
該当件数 件
※判 決 日 クリックにより年月日順の並び替えができます。
| No. | 判決日 | 概要 | 事件番号 | RETIO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R1.8.27 |
相続の開始後認知によって相続人となった者が遺産の分割を請求しようとする場合において、他の共同相続人が既に当該遺産の分割をしていたときは、民法910条に基づき支払われるべき価額の算定の基礎となる遺産の価額は、当該分割の対象とされた積極財産の価額であるとされた事例 |
||
| 2 | R1.8.9 |
民法916条にいう「その者の相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、相続の承認又は放棄をしないで死亡した者の相続人が、当該死亡した者からの相続により、当該死亡した者が承認又は放棄をしなかった相続における相続人としての地位を、自己が承継した事実を知った時をいうとした事例 |
||
| 3 | H28.4.28 |
破産手続開始前に成立した第三者のためにする生命保険契約に基づき破産者である死亡保険金受取人が有する死亡保険金請求権は、破産法34条2項にいう「破産者が破産手続開始前に生じた原因に基づいて行うことがある将来の請求権」に該当するものとして、死亡保険金受取人の破産財団に属するとした事例 |
||
| 4 | H28.2.26 |
・相続の開始後認知によって相続人となった者が、他の共同相続人に対して民法910条に基づき価額の支払を請求する場合における遺産の価額算定の基準時は、価額の支払を請求した時であるとした事例 |
||
| 5 | H26.12.12 |
共同相続された委託者指図型投資信託の受益権につき、相続開始後に元本償還金又は収益分配金が発生し預り金として上記受益権の販売会社における被相続人名義の口座に入金された場合に、共同相続人の1人が自己の相続分に相当する金員の支払を請求することはできないとした事例 |
||
| 6 | H26.2.25 |
・共同相続された委託者指図型投資信託の受益権は、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはないとした事例 |
||
| 7 | H26.2.14 |
共同相続人のうち自己の相続分の全部を譲渡した者は、遺産確認の訴えの当事者適格を有しないとした事例 |
||
| 8 | H26.1.14 |
認知者は、民法786条に規定する利害関係人に当たり、自らした認知の無効を主張することができ、この理は、認知者が血縁上の父子関係がないことを知りながら認知をした場合においても異ならないとした事例 |
||
| 9 | H25.11.29 |
共有物について、遺産分割前の遺産共有持分と他の共有持分とが併存する場合、共有者が遺産共有持分と他の共有持分との間の共有関係の解消を求める裁判上の手続は民法258条に基づく共有物分割訴訟であり、共有物分割の判決によって遺産共有持分権者に分与された財産は遺産分割の対象となり、共有関係の解消については同法907条に基づく遺産分割によるべきとされた事例 |
||
| 10 | H25.9.4 |
民法900条4号ただし書前段の規定(非嫡出子の法定相続分の規定)は、遅くとも平成13年7月当時において、憲法14条1項に違反していたとした事例 |
||
| 11 | H22.3.16 |
遺言を偽造した相続人に対して、相続欠格事由に該当し、相続人の資格を有しないことの確認を求める訴訟は、固有必要的共同訴訟であって、相続人全員を当事者として提起されるべきであるとされた事例 |
||
| 12 | H21.12.10 |
国税の滞納者を含む共同相続人の間で成立した遺産分割協議は、滞納者である相続人にその相続分に満たない財産を取得させ、他の相続人にその相続分を超える財産を取得させるものであるときは、国税徴収法39条にいう第三者に利益を与える処分に当たるとされた事例 |
||
| 13 | H17.10.11 |
相続が開始して遺産分割未了の間に第二次の相続が開始した場合において、第二次被相続人から特別受益を受けた者があるときは、その持戻しをして各共同相続人の具体的相続分を算定しなければならないとされた事例 |
||
| 14 | H17.9.8 |
共同相続された不動産から生ずる賃料債権は、各共同相続人の持分に応じて分割単独債権として帰属し、その帰属は遺産分割の結果による影響を受けないとされた事例 |
||
| 15 | H16.7.6 |
共同相続人が、他の共同相続人に対し、その者が被相続人の遺産につき相続人の地位を有しないことの確認を求める訴えにつき、固有必要的共同訴訟であるとした事例 |
||
| 16 | H16.4.20 |
相続財産である可分債権につき共同相続人の一人がその相続分を超えて債権を行使した場合、他の共同相続人は不法行為に基づく損害賠償または不当利得の返還を求めることができるとされた事例 |
||
| 17 | H14.7.12 |
遺言執行者が推定相続人の廃除を求める審判手続において、廃除を求められていない推定相続人が利害関係人として審判手続に参加した場合に、参加人は廃除の申立てを却下する審判に対して即時抗告をすることができないとされた事例 |
||
| 18 | H13.7.10 |
共同相続人間においてされた相続分の譲渡に伴って生ずる農地の権利移転については、農地法3条1項の許可を要しないとされた事例 |
||
| 19 | H12.3.10 |
内縁の夫婦の一方の死亡により内縁関係が解消した場合に、民法768条(財産分与)の規定を類推適用することはできないとした事例 |
||
| 20 | H12.2.24 |
民法903条1項により算定されるいわゆる具体的相続分の価額又はその価額の遺産の総額に対する割合の確認を求める訴えは、確認の利益を欠くものとして不適法であるとした事例 |
||
| 21 | H12.1.27 |
渉外親子関係の成立の判断は、まず嫡出親子関係の成立についてその準拠法を適用し、嫡出親子関係が否定された場合には、嫡出以外の親子関係の成立についてその準拠法を適用して行うとされた事例 |
||
| 22 | H12.1.27 |
共同相続された不動産につき、被相続人から相続人以外の第三者に直接所有権移転登記が経由された場合につき、共同相続人の1人が自己の持分の登記名義を回復するには、更正登記手続によることはできす、真正な登記名義の回復の手続によるべきものとされた事例 |
||
| 23 | H11.7.19 |
共同相続人相互の間で一部の者が他の者を共同相続人でないとしてその相続権を侵害している場合において、相続回復請求権の消滅時効を援用しようとする者は、真正共同相続人の相続権を侵害している共同相続人が、当該相続権侵害の開始時点において、他に共同相続人がいることを知らず、かつ、これを知らなかったことに合理的な事由があったことを立証しなければならないとした事例 |
||
| 24 | H11.6.11 |
共同相続人の間で成立した遺産分割協議は、詐害行為取消権行使の対象となり得るとした事例 |
||
| 25 | H11.3.9 |
・被相続人の生存中になされた相続人への売買を原因とする所有権移転登記は、被相続人の死亡後に、相続を原因とするものに更正することはできないとした事例 |
||
| 26 | H11.1.21 |
相続債権者は、被相続人から抵当権の設定を受けていても、被相続人の死亡前に仮登記がされていた場合を除き、相続財産人に対して抵当権設定登記手続を請求することができず、限定承認がされた場合における限定承認者に対する設定登記手続請求も、これと同様であるとした事例 |
||
| 27 | H10.7.17 |
本人が無権代理行為の追認を拒絶した場合には、その後無権代理人が本人を相続したとしても、無権代理行為が有効になるものではないとされた事例 |
||
| 28 | H10.2.27 |
いわゆる全面価格賠償の方法により共有物を分割することの許される特段の事情の存否について、審理判断することなく競売による分割をすべきものとした原審の判断に違法があるとされた事例 |
||
| 29 | H9.9.12 |
遺言者に相続人は存在しないが相続財産全部の包括受遺者が存在する場合は、民法951条にいう「相続人のあることが明かでないとき」に当たらないとされた事例 |
||
| 30 | H9.3.14 |
共同相続人甲、乙、丙のうち甲と乙間において、ある土地につき甲の所有権確認請求を棄却する判決が確定し、確定判決の既判力により、甲が乙に対して相続による土地の共有持分取得を主張し得なくなった場合であっても、甲は土地につき遺産確認の訴えを提起することができるとした事例 |
||
| 31 | H9.3.14 |
所有権確認請求訴訟で敗訴した原告が後訴において共有持分の取得を主張することが、前訴の確定判決の既判力に抵触して許されないとされた事例 |
||
| 32 | H8.12.17 |
共同相続人の一人が相続開始前から被相続人の許諾を得て、遺産である建物に被相続人と同居してきたときは、特段の事情のない限り、被相続人と同相続人との間において、同建物について、相続開始時を始期とし、遺産分割時を終期とする使用貸借契約が成立していたものと推認されるとした事例 |
||
| 33 | H6.7.18 |
保険契約において保険契約者が死亡保険金の受取人を被保険者の「相続人」と指定した場合は、特段の事情のない限り、右指定には相続人が保険金を受け取るべき権利の割合を相続分の割合によるとする旨の指定も含まれ、各保険金受取人の有する権利の割合は相続分の割合になるとされた事例 |
||
| 34 | H6.1.25 |
固有必要的共同訴訟における共同被告の一部に対する訴えの取下げは、効力を生じないとされた事例 |
||
| 35 | H5.7.19 |
遺言により法定相続分を下回る相続分を指定された共同相続人の一人が、不動産に法定相続分に応じた共同相続登記がなされたことを利用して、その共有持分権を第三者に譲渡し、法定相続分の持分の移転登記をしたとしても、第三者はその相続人の指定相続分に応じた持分を取得するにとどまるとした事例 |
||
| 36 | H5.1.21 |
無権代理人が本人を他の相続人と共に共同相続した場合においては、共同相続人全員が共同して無権代理行為を追認しない限り、無権代理行為が有効となるものではないとした事例 |
||
| 37 | H5.1.21 |
無権代理人が本人を共同相続した場合には、共同相続人全員が共同して無権代理行為を追認しない限り、無権代理人の相続分に相当する部分においても、無権代理行為が当然に有効となるものではないとされた事例 |
||
| 38 | H4.4.10 |
相続人は、遺産の分割までの間は、相続開始時に存した金銭を相続財産として保管している他の相続人に対して、自己の相続分に相当する金銭の支払を求めることはできないとされた事例 |
||
| 39 | H4.3.13 |
保険金受取人の死亡時以後保険金の支払理由が発生するまでに受取人の変更がないときは、受取人は死亡した受取人の死亡時の法定相続人に変更されたものとするとの定めは、死亡した保険金受取人の法定相続人で保険金の支払理由が発生した当時の生存者を受取人とすることにあるとした事例 |
||
| 40 | H2.9.27 |
共同相続人は、既に成立している遺産分割協議につき、その全部又は一部を全員の合意により解除した上、改めて分割協議を成立させることができるとした事例 |
||
| 41 | H1.11.24 |
共有者の一人が死亡し、相続人の不存在が確定し、相続債権者や受遺者に対する清算手続が終了したときは、その共有持分は他の相続財産とともに特別縁故者に対する財産分与の対象となり、その財産分与がされず、当該共有持分が承継すべき者のないまま相続財産として残存することが確定したときにはじめて、民法255条により他の共有者に帰属することになるとした事例 |
||
| 42 | H1.3.28 |
共同相続人間における遺産確認の訴えは、固有必要的共同訴訟と解すべきとされた事例 |
||
| 43 | H1.2.9 |
遺産分割協議が成立した場合、相続人の一人が同協議による負担債務を履行しないときであっても、その債権を有する相続人は、民法541条(履行遅滞等による解除権)による同協議の解除はできないとされた事例 |
||
| 44 | S63.3.1 |
無権代理人を本人とともに相続した者が、その後更に本人を相続した場合においては、本人が自ら法律行為をしたと同様の法律上の地位ないし効果を生ずるとされた事例 |
||
| 45 | S62.10.8 |
運筆について他人の添え手による補助を受けてされた自筆証書遺言と民法968条1項にいう「自書」の要件について示された事例 |
||
| 46 | S62.9.4 |
遺産相続により相続人の共有となつた財産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家事審判法の定めるところに従い、家庭裁判所が審判によつてこれを定めるべきものであり、通常裁判所が判決手続で判定すべきものではないとした事例 |
||
| 47 | S61.11.20 |
不倫な関係にある女性に対する包括遺贈が公序良俗に反しないとされた事例 |
||
| 48 | S61.3.20 |
民法921条3号にいう相続財産には相続債務も含まれるとした事例 |
||
| 49 | S60.11.29 |
甲から不動産を取得した乙がこれを丙に贈与した場合において、乙が、司法書士に依頼し甲に差し出した、不動産を丙に譲渡したので甲から直接丙に所有権移転登記をするよう求める旨の内容証明郵便が、民法550条にいう書面に当たるとされた事例 |
||
| 50 | S59.1.19 |
不動産について、贈与を登記原因とした所有権移転登記の抹消手続を求める前訴を提起して敗訴した者が、贈与の不履行を理由に贈与契約を解除したとして、所有権移転登記手続を求める後訴を提起した場合において、後訴の提起は信義則に反するものではないとした事例 |
||
| 51 | S58.1.24 |
土地の死因贈与につき、事実関係のもとでは取消ができないとされた事例 |
||
| 52 | S57.4.30 |
負担の履行期が贈与者の生前と定められた負担付死因贈与の受贈者が負担の全部又はこれに類する程度の履行をした場合、特段の事情がない限り、民法1022条、1023条の規定は準用されないとされた事例 |
||
| 53 | S56.10.8 |
書面によらない土地の贈与者が受贈者に土地の占有及び登記名義を移転することができない場合において、事実関係により贈与の履行が終了したものとして民法550条に基づく取消の効力が否定された事例 |
||
| 54 | S56.10.1 |
農地の受贈者の贈与者に対して有する知事に対する所有権移転許可申請協力請求権は、民法167条1項の債権にあたり、請求権は贈与契約成立の日から10年の経過により時効によって消滅するとした事例 |
||
| 55 | S56.9.11 |
・遺言無効確認訴訟における確認の利益の存否判断にあたっては、原則として、原告の相続分が被相続人から受けた生前贈与等によりなくなるか否かを考慮すべきものではないとされた事例 |
||
| 56 | S56.4.3 |
被相続人の遺言書又はこれになされている訂正が方式を欠き無効である場合に、相続人が方式を具備させ有効な遺言書又はその訂正としての外形を作出する行為は、遺言書の偽造又は変造(民法891条5号)にあたるが、それが遺言者の意思実現のため、その法形式を整える趣旨でされたにすぎないときは、同相続人は相続欠格者にあたらないとされた事例 |
||
| 57 | S55.12.4 |
盲人は、公正証書遺言に立ち会う証人としての適格を有するとした事例 |
||
| 58 | S55.7.1 |
相続税法34条1項の規定による連帯納付義務は、相続人又は受遺者の固有の相続税の納税義務の確定という事実に照応して法律上当然に確定するとされた事例 |
||
| 59 | S54.12.14 |
被相続人が生存中に無権代理にて不動産を第三者に譲渡した共同相続人が、違産分割の結果当該不動産を取得しないこととなった場合について、民法909条但書の適用がなく、第三者は同共同相続人の法定相続分に応じた共有持分権を取得しないとした事例 |
||
| 60 | S54.9.27 |
未登記建物につき書面によらないで贈与契約がされた場合に、贈与者の意思に基づき直接受贈者名義に保存登記がされたときには、贈与契約の履行が終ったものとして、贈与契約を取り消すことはできないとされた事例 |
||
| 61 | S53.12.20 |
共同相続人の一人によって相続権を侵害された共同相続人のその侵害の排除を求める請求には民法884条の適用があるとされた事例 |
||
| 62 | S53.2.24 |
共同相続人の一人が他の共同相続人の全部又は一部の者の後見をしている場合において、後見人が被後見人全員を代理してする相続の放棄は、後見人みずからが相続の放棄をしたのちにされたか、又はこれと同時にされたときは利益相反行為にあたらないとされた事例 |
||
| 63 | S52.6.14 |
遺言者が、公正証書による遺言をするにあたり、公証人があらかじめ筆記した遺言内容を読み聞かせたのに対し、遺言者が単にうなづくのみであって、立会証人の一人が遺言者の真意を十分に確認することができなかったときは、民法969条2号にいう口授があったものとはいえないとされた事例 |
||
| 64 | S51.8.30 |
遺留分権利者が受贈者又は受遺者に対し民法1041条1項の価額弁償を請求する訴訟における贈与又は遺贈の目的物の価額算定の基準時は、訴訟の事実審口頭弁論終結の時であるとされた事例 |
||
| 65 | S51.7.19 |
相続人が遺言の執行としてされた遺贈による所有権移転登記の抹消登記手続を求める訴については、遺言執行者がある場合でも、受遺者が被告となるとされた事例 |
||
| 66 | S51.3.18 |
相続人が被相続人から贈与された金銭を、いわゆる特別受益として遺留分算定の基礎となる財産の価額に加える場合には、贈与の時の金額を相続開始の時の貨幣価値に換算した価額をもって評価すべきとされた事例 |
||
| 67 | S50.5.27 |
財産分与としてされた不動産の譲渡は、譲渡所得課税の対象となるとされた事例 |
||
| 68 | S50.4.8 |
養子とする意図で他人の子を嫡出子として出生届をしても、出生届をもって養子縁組届とみなし、有効に養子縁組が成立したものとすることはできないとされた事例 |
||
| 69 | S50.3.6 |
土地の売主の共同相続人の一部の者が登記手続義務の履行を拒絶しているため、買主が代金支払いを拒絶している場合に、他の相続人は履行を拒絶している相続人に対し、買主に代位して買主の所有権移転登記手続請求権を行使することができるとした事例 |
||
| 70 | S49.9.20 |
相続の放棄は、民法424条の詐害行為取消権行使の対象とならないとした事例 |
||
| 71 | S49.9.4 |
他人の権利の売主が死亡し、その権利者において売主を相続した場合、権利者は相続により売主の売買契約上の義務ないし地位を承継するが、相続前と同様その権利の移転につき諾否の自由を保有し、特別の事情のないかぎり、売買契約上の売主としての履行義務を拒否することができるとした事例 |
||
| 72 | S49.2.7 |
不動産につき贈与を原因とする所有権移転仮登記が経由されているにとどまるときは、これにより仮登記権利者の所有権取得又は仮登記の当事者間における贈与契約の成立を推定することはできないとされた事例 |
||
| 73 | S48.4.24 |
親権者が共同相続人である数人の子を代理してした遺産分割の協議は、民法826条2項の利益相反行為に当たるとして、追認のない限り無効であるとした事例 |
||
| 74 | S47.11.9 |
民法936条1項の規定により相続財産管理人が選任された場合において、相続財産に関する訴訟については、相続人が当事者適格を有し、相続財産管理人は、相続人全員の法定代理人として訴訟に関与するものであって、相続財産管理人としての資格では当事者適格を有しないとされた事例 |
||
| 75 | S47.7.18 |
・生前相続による不動産所有権の取得は、登記を経なければ第三者に対抗できないとされた事例 |
||
| 76 | S47.5.25 |
民法974条3号(証人及び立会人の欠格事由)にいう「配偶者」には、推定相続人の配偶者も含まれるとされた事例 |
||
| 77 | S47.5.25 |
死因贈与の取消については、民法1022条(遺言の撤回)がその方式に関する部分を除いて準用されるとされた事例 |
||
| 78 | S46.11.16 |
被相続人が、生前不動産をある相続人に贈与するとともに、他の相続人にもこれを遺贈した後、相続の開始があった場合、贈与および遺贈による物権変動の優劣は、対抗要件たる登記の具備の有無をもって決するとされた事例 |
||
| 79 | S46.10.28 |
不法の原因により既登記建物を贈与した場合、その引渡しをしただけでは、民法708条にいう不法原因給付があったとはいえないとされた事例 |
||
| 80 | S45.10.21 |
不法の原因により未登記建物を贈与した場合、1)その引渡は民法708条にいう給付にあたる、2)贈与者は所有権を理由とする建物返還請求はすることができない、3)贈与者が給付物の返還請求ができない反射的効果として、建物所有権は受贈者に帰属する、4)建物所有権が受贈者に帰属した場合、贈与者が建物の所有権保存登記を経由しても、受贈者は贈与者に対し同保存登記につき抹消登記手続を請求できる、とした事例 |
||
| 81 | S44.10.30 |
土地を占有していた被相続人が死亡し相続が開始した場合には、特別の事情のないかぎり、被相続人の土地に対する占有は相続人によつて相続されるとした事例 |
||
| 82 | S44.4.17 |
不動産について、被相続人との間に締結された契約上の義務の履行として、所有権移転登記手続を求める訴訟は、その相続人が数人いるときでも、必要的共同訴訟ではないとした事例 |
||
| 83 | S44.1.31 |
他人の財産権を贈与の目的物とする贈与契約も有効に成立するとした事例 |
||
| 84 | S43.7.16 |
一筆の土地を賃借し二棟の建物を所有する借地人が、各一棟を養女とその夫にそれぞれ贈与しその後死亡した事情のもとでの、土地賃貸人の借地権無断譲渡を理由とする各建物を受贈した養女およびその夫それぞれに対する土地明渡し請求は権利濫用に当たるとした事例 |
||
| 85 | S42.11.1 |
不法行為による慰謝料請求権は、財産上の損害賠償請求権と同様単純な金銭債権であり、被害者が生前に請求の意思を表明しなくても相続の対象となるとされた事例 |
||
| 86 | S42.4.28 |
家屋賃借人が死亡し、唯一の相続人も行先不明で生死も判然とない場合において、家屋賃借人の内縁の夫が家屋賃借人の賃借権の援用により家屋に居住できるとした事例 |
||
| 87 | S42.2.21 |
家屋賃借人の内縁の妻は、賃借人が死亡した場合には、相続人の賃借権を援用して賃貸人に対し当該家屋に居住する権利を主張することができるが、相続人とともに共同賃借人となるものではないとした事例 |
||
| 88 | S42.1.20 |
相続人が、相続の放棄をした場合には相続開始時にさかのぼって相続開始がなかったと同じ地位に立ち、当該相続放棄の効力は、登記等の有無を問わず、何人に対してもその効力を生ずるとされた事例 |
||
| 89 | S41.10.7 |
書面によらない農地の贈与契約は、農地法第3条第1項による知事の許可を受けるまでは、農地の引渡があった後でも、取り消すことができるとした事例 |
||
| 90 | S41.1.13 |
不動産の贈与を予定して、登記権利者たる受贈者の関与なく不動産の所有権取得登記がなされた場合でも、後日不動産の贈与が行われたときは、受贈者は不動産所有権の取得をもって第三者に対抗することができるとした事例 |
||
| 91 | S40.6.18 |
無権代理人が本人を相続し、本人と代理人との資格が同一人に帰した場合には、本人がみずから法律行為をしたのと同様な法律上の地位を生じたものと解されるとした事例 |
||
| 92 | S40.5.27 |
相続放棄につき民法95条(錯誤)の適用があるとした事例 |
||
| 93 | S40.3.26 |
不動産の贈与契約に基づいて、不動産の所有権移転登記がなされたときは、その引渡しの有無をとわず、民法550条にいう贈与の履行が終ったものと解されるとした事例 |
||
| 94 | S39.10.23 |
家屋賃借人の内緑の妻が賃借人死亡後も賃借権を有するとされ、選定家督相続人には右賃借権が相続されないと判断された事例 |
||
| 95 | S39.10.13 |
内縁の夫死亡後その所有家屋に居住する寡婦に対して、亡夫の相続人のした家屋明渡請求が権利の濫用にあたるとされた事例 |
||
| 96 | S39.5.26 |
入院中の内縁の夫が、同棲に使用していたその所有家屋を妻に贈与するに際して、自己の実印を家屋を買受けたときの契約書とともに妻に交付した事案において、簡易の引渡による家屋の占有移転があったとして、これにより贈与の履行が終ったものとされた事例 |
||
| 97 | S39.2.27 |
甲の相続権を乙が侵害している場合、甲の相続人丙の乙に対する相続回復請求権の消滅時効の期間20年の起算点は、丙の相続開始の時ではなく、甲の相続開始の時とであるとした事例 |
||
| 98 | S39.1.30 |
甲乙両名が共同相続した不動産につき、乙が勝手に単独所有権取得の登記をし、さらに第三取得者丙が乙から移転登記をうけた場合、甲は乙丙に対し自己の持分を登記なくして対抗できるとした事例 |
||
| 99 | S38.12.27 |
売主およびその相続人の共有不動産が売買の目的とされた場合、当該相続人は当該売買契約における売主の義務の履行を拒むことはできないとした事例 |
||
| 100 | S38.10.4 |
共同相続した不動産につき、共同相続人の一人が勝手に単独の所有権登記を行い、この者から第三者が移転登記を受けた場合、他の共同相続人は第三者に対し自己の持分を登記なくして対抗できるとし事例 |
||
| 101 | S38.2.22 |
・相続財産に属する不動産につき単独所有権移転の登記をした共同相続人及び同人から単独所有権移転の登記をうけた第三取得者に対し、他の共同相続人は自己の持分を登記なくとも対抗できるとした事例 |
||
| 102 | S36.12.22 |
借主が死亡しその相続人が複数いる場合、貸主からの契約解除には相続人全員に対して解除の意思を表示することを要するとした事例 |
||
| 103 | S36.11.28 |
連帯債務者の一人が死亡し、その相続人が数人ある場合に、相続人らは、被相続人の債務の分割されたものを承継し、各自その承継した範囲において、本来の債務者とともに連帯債務者となると解された事例 |
||
| 104 | S33.10.14 |
被相続人が不動産の譲渡をした場合、その相続人から同一不動産の譲渡を受けた者は、民法第177条にいう第三者に該当するとした事例 |
||
| 105 | S32.5.21 |
農地の贈与契約について、知事の許可により所有権の移転を生ずべき停止条件附贈与契約は有効であるとした事例 |
||
| 106 | S31.1.27 |
書面によらない不動産の贈与において、所有権の移転があっただけでは履行を終ったものとすることは出来ず、その占有の移転があったときに履行を終ったものと解すべきであるとした事例 |
||
| 107 | S30.9.9 |
農地の贈与についての知事の許可は、贈与の成立前になされることを要せず、許可のあったときから贈与は効力を生ずるものであり、許可当時贈与者が既に死亡していても、その効力の発生を妨げないとした事例 |
||
| 108 | S30.5.31 |
相続財産の共有は、民法249条以下に規定する「共有」とその性質を異にするものではないとした事例 |
||
| 109 | S29.9.10 |
民法951条の法人たる相続財産は、被相続人が生前になした不動産の贈与につき、登記の欠缺を主張できないとした事例 |
||
| 110 | S2.3.22 |
本人が無権代理行為の追認または追認の拒絶を行わず死亡し、無権代理人が本人を相続したときは、本人自ら法律行為としたのと同一の地位を有するものとする。 |
大15(オ)1073号(大審院) |
|
| 111 | M40.5.6 |
民法第550条は贈与の意思の明確を期するとともに、軽忽な贈与を予防しようとする趣旨の規定であり、当事者双方の意思表示につき書面の作成を命じたものではないとされた事例 |
明39(オ)260号(大審院) |
RETIO : (一財)不動産適正取引推進機構 機関誌