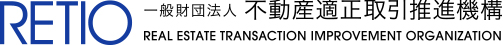| 制作:国土交通省 |
| 運営:不動産適正取引推進機構 |
| 1 本システムは、これまでに発生した不動産取引をめぐる他のトラブル事例をもとに、消費者の皆様が、トラブルの未然防止や万一トラブルに発展した場合に円滑な解決が図れるよう、情報を提供するものです。 2 掲載内容は、①裁判事例、②国土交通省各地方整備局や各都道府県で宅建業者に対して行った行政処分、③(一財)不動産適正取引推進機構で調整した特定紛争処理案件の中から基礎的で有用と思われる事例を抽出し、項目ごとに整理したうえ、事案の概要や紛争の結末等について要約して記載しています。 |
最新の情報については、
「RETIO判例検索システム」
「特定紛争案件検索システム」
「ネガティブ情報等検索サイト」(国土交通省)
「不動産のQ&A」
をご活用ください。
検索ボタンをクリックして頂くと、該当する事例の一覧が表示されます。
| トラブル事例大項目:土地建物の賃貸借契約に関するもの (原状回復を除く) |
トラブル事例中項目:賃料等 | トラブル事例小項目: |
タイトル:裁判事例短期間で2度の賃料減額請求
東京地裁判決 平成13年2月26日
(判例タイムズ 1072号 149頁)
《要旨》
賃料減額請求の和解後、借主が5か月後に再度貸主に賃料減額請求をすることは、当事者の信義則(しんぎそく)
権利の行使および義務の履行は、信義に従い
誠実に行なわなければならないとする原則をいう。に反し、権利の濫用(けんりのらんよう)
一見権利の行使とみられるが、具体的な情況や
実際の結果に照らしてそれを認めることができ
ないと判断されることをいう。例えば、加害を
目的でのみなされた権利行使は一般的に濫用とされる。というべきであるとされた事例
(1) 事案の概要
賃借人Xは、平成9年1月、賃貸人Yとの間で建物の一室を賃料月額100万円で、中華料理店経営とする賃貸借契約を締結した。
Xは、同年10月頃、Yに対し賃料減額の調停申立てをし、不調に終わった後、平成10年2月、賃料が近隣相場の約2倍であること等を理由に賃料減額請求を提起した。裁判所は平成11年8月、賃料を「平成9年9月1日から1か月61万9千円余」と判決したが、Yはこれを不服とし控訴した。また、Yは、Xが平成9年8月の賃料より、Xが適正と考えた賃料である47万5千円しか支払わなかったので、平成10年4月本件建物の明渡訴訟を提起し、裁判所はこれを認容したが、Xが控訴した。
これら各訴訟の第一審判決を受けて、平成11年12月、XとYとの間で、賃料を平成9年9月分から1か月80万円とする、未払賃料の差額分はXがYに分割して支払う等との合意がなされ、和解が成立した。
ところが、Xは、平成12年2月に再び賃料減額の調停申立てをし、調停不成立後、同年4月、平成12年4月以降の賃料は月額49万5千円余であるとの確認を求めた賃料減額請求訴訟を再度提起した。
(2) 判決の要旨
(ア)訴訟上の和解は、訴訟当事者双方が合意により、実体関係について互譲をすることにより、訴訟を終了させるものである。和解した訴訟当事者には、信義則(しんぎそく)
権利の行使および義務の履行は、信義に従い
誠実に行なわなければならないとする原則をいう。上、和解の内容に抵触する方向で何らかの法的に意味のある行動に出ることが制約されることがある。賃貸借契約は契約当事者間の信頼関係を基礎とする継続的なもので、契約当事者間において信義則(しんぎそく)
権利の行使および義務の履行は、信義に従い
誠実に行なわなければならないとする原則をいう。が働く場面は、他の契約類型と比較して多くなるものといわなければならない。
(イ)本件賃料額について、本件和解から相当の期間経過後であれば、経済状態や市場動向の変化により賃料増減額を求めることは許容されてしかるべきであるが、本件和解と再度の訴えは時間的に近接しており、和解をもって紛争を終了させたという趣旨を没却するもので、訴訟当事者間の信義則(しんぎそく)
権利の行使および義務の履行は、信義に従い
誠実に行なわなければならないとする原則をいう。に反するものと評価せざるを得ない。
(ウ)したがって、本件賃料減額請求は、当事者間の信義則(しんぎそく)
権利の行使および義務の履行は、信義に従い
誠実に行なわなければならないとする原則をいう。に反し、権利濫用というべきでその請求を棄却する。
(3) まとめ
本件のように訴訟上の和解の趣旨に反して、短期間のうちに訴訟を再提起する事例は少ないと思われるが、継続的な信頼関係を基礎とする賃貸借契約関係において、大きな経済状態や市場動向の変化がなければ、このような賃借人の行為は、当事者間の信義則(しんぎそく)
権利の行使および義務の履行は、信義に従い
誠実に行なわなければならないとする原則をいう。に違反し、また、権利濫用であるとした本判決は実務上においても妥当と思われる。
| 本システムの掲載情報の正確性については万全を期しておりますが、利用者が本システムの情報を用いて行う行為については本システムの制作者、運営者は何ら責任を負うものではありません。また、同種の事案について、必ず同様の結果が得られるものではありませんのでご承知おきください。なお、個別に発生したトラブル等については、管轄の行政庁等の相談窓口等にお問い合わせください。 |