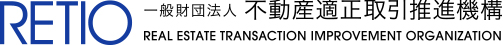| 制作:国土交通省 |
| 運営:不動産適正取引推進機構 |
| 1 本システムは、これまでに発生した不動産取引をめぐる他のトラブル事例をもとに、消費者の皆様が、トラブルの未然防止や万一トラブルに発展した場合に円滑な解決が図れるよう、情報を提供するものです。 2 掲載内容は、①裁判事例、②国土交通省各地方整備局や各都道府県で宅建業者に対して行った行政処分、③(一財)不動産適正取引推進機構で調整した特定紛争処理案件の中から基礎的で有用と思われる事例を抽出し、項目ごとに整理したうえ、事案の概要や紛争の結末等について要約して記載しています。 |
最新の情報については、
「RETIO判例検索システム」
「特定紛争案件検索システム」
「ネガティブ情報等検索サイト」(国土交通省)
「不動産のQ&A」
をご活用ください。
検索ボタンをクリックして頂くと、該当する事例の一覧が表示されます。
| トラブル事例大項目:その他 | トラブル事例中項目:その他 | トラブル事例小項目: |
タイトル:裁判事例司法書士の本人確認義務と賠償責任
東京地裁判決 平成16年8月6日
(判例タイムズ 1196号 120頁)
《要旨》
登記済証及び印鑑登録証明書等が偽造文書であったことを看過して、本人確認を怠った司法書士の責任が認められた事例
(1) 事案の概要
ブローカーAは、Xに対し、約1千坪の土地を譲渡担保(じょうとたんぽ)
債権保全のため、債務者の所有する物を債権者
に譲渡し、債務が完済されるとその所有権が債
務者に復帰するという制度。にして、3億5千万円を借りたいとするC(実は「D」)がいるとし、検討を申し入れた。Xは、A及びAに話を持ってきたブローカーBと現地に行き、役所も調査し、2億5千万円以上の価値があると判断した。
平成13年12月10日、A、B、CことD、X及び司法書士Yは喫茶店に会した。その際、Dは、名はCと記載されDの顔写真の貼られた自動車運転免許証を示したので、Xは、DがCであると判断した。Xは、DをCとして紹介した上、Yに、登記手続きに関する書類の確認と、不足部分の書類の指示を依頼した。
Yは、Dから関係書類の一部を預かった。14日、X及びDは公証人役場(こうしょうにんやくば)
公証人(公正証書の作成、確定日付の付与
などの公証事務を行なうために、法務大臣
が任命する公務員のこと)が執務する事務
所のこと。を訪れ、公正証書個人や法人からの嘱託により、公証人が
公証役場で作成する契約書・合意書などのこと。を作成したが、公証人は本件印鑑登録証明書が偽造であることに気付かず、DをCであると判断した。17日、X、D及びYは登記申請書等の確認を行ったが、その際、Yは実印や印影と印鑑登録証明書の印影の照合を行い、印鑑証明書等を裏返し変形菱形の影があることを確認し、透かしが施されていると判断した。運転免許書の写真とDが同一人物であることを確認した。同日、登記申請がなされ、Xは、Dに対して2億2,289万円余を支払った。しかし、登記済権利書、印鑑登録証明書等が偽造文書であったため、登記申請は却下された。
Xは、D等を詐欺(さぎ)
他人を騙すことにより、その者に誤った動機を抱かせること。罪で告訴し、Yに対し、Yが売主の本人確認を怠った過失により、売買代金を売主に騙取されたと主張して、債務不履行(さいむふりこう)
売買契約において、代金を支払ったにもかかわらず、
売主が物件を引き渡さない場合など、
債務が履行されない状態のこと。ないし不法行為(ふほうこうい)
他人の権利・利益を違法に侵害したことによって
損害を与える行為をいう。
このような行為によって生じた損害については、
加害者が被害者に賠償する責任を負わなければならない。に基づく損害賠償の支払を求めた。
(2) 判決の要旨
(ア)一般的に、他人から委任を受けた者には、委任した者が本人か否かを確認すべき義務がある。登記申請に携わった司法書士は、業務に関する法令及び実務に精通すべきであって、本件で問題になっているのは権利義務関係に直結する極めて重要な事務であることに鑑みると、書類を精査して、それが偽造に係るものか否かを確認すべき義務があると解するべきである。
(イ)Yが、印鑑証明書を光源にかざすことなく、裏面を見て透かしを確認したのみで透かしが施されていると判断したことは、本件印鑑証明書等の確認を怠った過失があると解さざるを得ない。
(ウ)経緯・内容が不自然な契約であること等一切の事情を考慮すると、その損害の大部分はXが負担すべきであるといえ、8割5分の過失相殺(そうさい)
2人の者が互いに相手に対して同種の債権を
持っているとき、相手方への意思表示によって
その債務を対当額で消滅させることをいう。(かしつそうさい)
損害賠償額から過失相当分を差し引いて
損害を負担することをいう。賠償を受ける
者にも過失がある場合に、負担を公平に
行なうために適用される。をするのが相当である。
(3) まとめ
本判決では、印鑑登録証明書等の書類の精査・確認方法等についても詳述されている。参考になる事例と思われる
| 本システムの掲載情報の正確性については万全を期しておりますが、利用者が本システムの情報を用いて行う行為については本システムの制作者、運営者は何ら責任を負うものではありません。また、同種の事案について、必ず同様の結果が得られるものではありませんのでご承知おきください。なお、個別に発生したトラブル等については、管轄の行政庁等の相談窓口等にお問い合わせください。 |