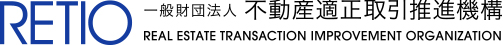昭和51年~昭和64年
該当件数 件
※判 決 日 クリックにより年月日順の並び替えができます。
| No. | 判決日 | 概要 | 事件番号 | RETIO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | S63.12.1 |
先に登記を経由した抵当権者に対抗することができないために競売手続において抹消された所有権に関する仮登記の権利者は、仮登記の後に登記を経由した抵当権者に対して、不当利得を理由として、その者が交付を受けた代価の返還を請求することはできないとした事例 |
||
| 2 | S63.11.25 |
不動産売買契約が解除された場合の損害賠償額の予定に関する約定は、賠償額算定の争いを避けるためにされたものであり、解除の有無によって買主の請求しうる額に差異がない等判示の事情のもとにおいては、買主が契約を解除することなく本来の給付に代わる填補賠償を請求する場合にも適用されるとした事例 |
RETIO 12-022
|
|
| 3 | S63.11.17 |
土地改良法53条1項2号の照応関係は、土地改良事業の目的に照らし、従前の土地に所有権及び地役権以外の権利又は処分の制限がある場合でない限り、同一所有者に対する従前の土地全体と換地全体とを総合的にみて、その間に認められれば足りるとされた事例 |
||
| 4 | S63.10.6 |
民事執行法による不動産競売事件における引渡命令は、公開の法廷における口頭弁論を経ないで引渡命令及びこれに対する執行抗告を棄却する決定をしても、これをもって憲法32条又は82条に違反するものではないとした事例 |
||
| 5 | S63.9.8 |
土地賃貸人の借地権無断譲渡を理由とした借地契約の解除請求に対し、借地人が買主との売買契約は、借地権譲渡について土地所有者の承諾が得られることを停止条件としており借地権譲渡の効力は生じていないと主張した事案において、本件契約と同時に買主に建物が引き渡されているなどの事情などから、売買契約と同時に借地権譲渡がなされたものと判断された事例 |
||
| 6 | S63.7.19 |
抵当権の設定されている不動産について当該抵当権者以外の者との間にされた代物弁済予約及び譲渡担保契約が詐害行為に該当する場合において、不動産が不可分のものであり、詐害行為の後に弁済等によって抵当権設定登記が抹消されたときは、その取消による原状回復は、不動産の価額から抵当権の被担保債権額を控除した残額の限度で価格賠償の方法によるとされた事例 |
||
| 7 | S63.7.1 |
借地上の建物の賃借人は、その敷地の地代の弁済について法律上の利害関係を有するとして、借地人の地代不払い前になした建物賃借人の土地所有者に対する地代弁済の提供を有効と認めた事例 |
||
| 8 | S63.7.1 |
債権者が第三者所有の不動産の上に設定を受けた抵当権が不存在であるにもかかわらず、抵当権の実行により第三者が不動産の所有権を喪失したときは、第三者は、売却代金から弁済金の交付を受けた債権者に対し不当利得返還請求権を有するとした事例 |
||
| 9 | S63.7.1 |
被用者と第三者との共同不法行為により他人に損害を加えた場合において、第三者が自己と被用者との過失割合に従って定められるべき自己の負担部分を超えて被害者に損害を賠償したときは、第三者は、被用者の負担部分について使用者に対し求償することができるとした事例 |
||
| 10 | S63.5.20 |
共有者の一部の者から共有物を占有使用することを承認された第三者に対して、その余の共有者は、当然には、共有物の明渡しを請求することはできないとされた事例 |
||
| 11 | S63.4.8 |
物上保証人からされた被担保債権の将来の弁済を原因とする抵当権設定登記又はいわゆる仮登記担保権の仮登記の抹消登記手続を求める請求は、将来物上保証人が被担保債権を弁済することを条件としても、認容することができるとした事例 |
||
| 12 | S63.3.31 |
共有者の一人が共有物を他に賃貸して得る収益につきその持分割合を超える部分の不当利得返還を求める他の共有者の請求のうち事実審の口頭弁論終結時後に係る請求部分は、将来の給付の訴えを提起することのできる請求としての適格を有しないとされた事例 |
||
| 13 | S63.3.1 |
無権代理人を本人とともに相続した者が、その後更に本人を相続した場合においては、本人が自ら法律行為をしたと同様の法律上の地位ないし効果を生ずるとされた事例 |
||
| 14 | S63.2.25 |
不動産の引渡命令の発付を受けた買受人が当該不動産を第三者に譲渡したとしても、引渡命令の相手方は、買受人に対して提起する引渡命令に対する請求異議の訴えにおいて、譲渡の事実をもって異議の事由とすることはできないとされた事例 |
||
| 15 | S63.1.21 |
河川改修工事による収容ないし占用許可の取消しに関し、輪中堤(堤防)の文化財的価値が損失補償の対象になるかがあらそわれた事例において、同輪中堤は歴史的、社会的、学術的価値を内包するが、それ以上に不動産としての市場価値を有するものではないとして、損失補償の対象とはならないとされた事例 |
||
| 16 | S63.1.18 |
共有の性質を有しない入会地上の天然の樹木の所有権について、事実関係の判断により、土地の所有者にあるとされた事例 |
||
| 17 | S62.12.18 |
不動産競売手続における配当金が同一担保権者の有する数個の被担保債権のすべてを消滅させるに足りない場合には、弁済充当の指定に関する特約があっても、その配当金は、民法489条ないし491条の規定に従って数個の債権に充当されるとした事例 |
||
| 18 | S62.11.26 |
請負人が破産宣告を受けた場合には、当該請負契約の目的である仕事が請負人以外の者において完成することのできない性質のものでない限り、当該請負契約について破産法59条が適用されるとした事例 |
||
| 19 | S62.11.24 |
里道の用途廃止により生活に著しい支障が生ずるという特段の事情は認められないとして、近くに居住する者の里道の用途廃止処分取消しの訴えにつき原告適格を有しないとされた事例 |
||
| 20 | S62.11.13 |
未登記建物を買い受けた者が、所有権を証する書面として、同人を建物の建築主とする真実と符合しない記載内容の建築工事完了引渡証明書を添付し建物の表示の登記の申請をした場合には、その登記申請は、不動産登記法49条8号、10号により却下されるとされた事例 |
||
| 21 | S62.11.12 |
不動産が譲渡担保の目的とされ、設定者甲から譲渡担保権者乙への所有権移転登記が経由された場合において、被担保債務の弁済等により譲渡担保権が消滅した後に乙から目的不動産を譲り受けた丙は、民法177条にいう第三者に当たるとした事例 |
||
| 22 | S62.10.8 |
運筆について他人の添え手による補助を受けてされた自筆証書遺言と民法968条1項にいう「自書」の要件について示された事例 |
||
| 23 | S62.10.8 |
無断転貸を理由とする土地賃貸借契約の解除権の消滅時効は、転借人が転貸借契約に基づき当該土地の使用収益を開始した時から進行し、債権に準ずるものとして民法167条1項により10年を経過したときに消滅するととした事例 |
||
| 24 | S62.9.4 |
遺産相続により相続人の共有となつた財産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家事審判法の定めるところに従い、家庭裁判所が審判によつてこれを定めるべきものであり、通常裁判所が判決手続で判定すべきものではないとした事例 |
||
| 25 | S62.9.3 |
物上保証人が債権者に対し被担保債権の存在を承認しても、右承認によっては、債権者と物上保証人との相対的関係においても、被担保債権について時効中断の効力は生じないとされた事例 |
||
| 26 | S62.7.17 |
・区分所有建物の暴力団関係者の使用につき、契約解除及び専有部分の引渡し請求が認められた事例 |
||
| 27 | S62.7.9 |
土地区画整理法77条に基づき従前地上の建物を仮換地上に移築するため解体した場合、同解体は不動産登記法(昭和58年法律第51号による改正前のもの)93条ノ6第1項にいう建物の「滅失」に当たるとされた事例 |
||
| 28 | S62.7.7 |
・民法117条2項(無権代理人の責任)にいう「過失」は、重大な過失に限定されるものではないとした事例 |
||
| 29 | S62.6.5 |
無権限者から土地を賃借し、平穏公然に土地を継続使用し賃料を支払ってきた土地の賃借人について、使用開始後20年の経過により、土地所有者に対する土地の賃借権の取得時効が成立したとされた事例 |
||
| 30 | S62.4.23 |
・不動産の受遺者は、遺言執行者があるときでも、所有権に基づき、不動産に対する無効な抵当権に基づく競売手続の排除を求めることができるとした事例 |
||
| 31 | S62.4.22 |
・森林法186条は憲法29条2項に違反するとした事例 |
||
| 32 | S62.4.17 |
土地改良事業により土地改良区から換地処分を受けた者が、換地処分は照応の原則に違反し無効であると主張しこれを争おうとするときは、換地処分の無効確認を求める訴えを提起することができるとした事例 |
||
| 33 | S62.3.24 |
土地の無断転貸がなされるも背信行為と認めるに足りない事情があり、賃貸人が賃貸借契約を解除できない場合において、当該契約が合意解除されたとしても、それが賃料不払い等による法定解除権の行使が許されるものである等の事情のない限り、賃貸人は賃借人(転貸人)との合意解除の効果をもって転借人に対抗できないとされた事例 |
||
| 34 | S62.2.26 |
土地区画整理事業において、公簿地積を基準地積としてなされた換地処分は、特に希望する者に限り実測地積により得る途が開いてあれば、憲法29条に違反しないとされた事例 |
||
| 35 | S62.2.13 |
売買代金債務を目的とする準消費貸借契約が締結された場合であつても、売主が自己の所有権移転登記手続債務につき売買契約に基づいて有していた同時履行の抗弁権を失わないとされた事例 |
||
| 36 | S62.2.13 |
公営住宅の建替事業に伴い、公営住宅法(昭和55年法律第27号による改正前のもの)23条の6に基づき入居者に対して明渡請求をする場合には、借家法1条の2所定の要件を具備することを要しないとした事例 |
||
| 37 | S62.2.12 |
帰属清算型の譲渡担保において、債権者の支払うべき清算金の有無及びその額は、債権者が債務者に対し清算金の支払若しくはその提供をした時若しくは目的不動産の適正評価額が債務額を上回らない旨の通知をした時、又は債権者において目的不動産を第三者に売却等をした時を基準として確定されるとした事例 |
||
| 38 | S62.1.22 |
相続土地の共有持分の取得が相続人らにおいて第一回遺産分割協議を合意解除し改めて第二回遺産分割協議をしたことに伴うものである場合には、右取得は地方税法73条の7第1号にいう「相続に因る不動産の取得」に該当するとされた事例 |
||
| 39 | S61.12.16 |
海は、いわゆる公共用物であって、国の直接の公法的支配管理に服し、特定人による排他的支配の許されないものであり、過去において国が一定範囲を区画してこれを私人の所有に帰属させた場合を除き、所有権の客体たる土地に当たらないとした事例 |
||
| 40 | S61.12.11 |
固定資産評価基準(昭和38年12月25日自治省告示第158号)は、前年中に取得された償却資産の評価については、いわゆる半年分償却法のみを認め、いわゆる月割償却法はこれを認めない趣旨と解するとした事例 |
||
| 41 | S61.12.5 |
農地の売買契約締結後、農地法3条許可前に相続となった場合の課税財産は、売買契約に基づき買主が売主に対して取得した所有権移転請求権等の債権的権利であり、その課税評価額は当該農地の取得価額に相当するとされた事例 |
||
| 42 | S61.11.20 |
クラブのホステスが顧客の飲食代金債務についてした保証契約が公序良俗に反するものとはいえないとされた事例 |
||
| 43 | S61.11.20 |
不倫な関係にある女性に対する包括遺贈が公序良俗に反しないとされた事例 |
||
| 44 | S61.11.20 |
融資の担保の目的で、債務者が自己の第三債務者に対する請負代金債権の代理受領を債権者に委任し、第三債務者が債権者に委任契約の内容を了承し、請負代金を直接支払うことを約束しながら、これを債務者に支払ったときは、債権者は第三債務者に対し、代理受領による貸金の回収という財産上の利益が害されたことを損害として、不法行為に基づく損害賠償請求権を行使することができるとした事例 |
||
| 45 | S61.11.18 |
登記上の所有者を真実の所有者と信じて抵当権を設定し、その後競売にて自ら競落したXが、真実の所有者Aより建物を賃借していたYに対し賃借権の不存在等を求めた事案において、Xが建物の真実の所有者がAであること及びA・Y間の賃貸借契約締結の事実を知らなかったとしても、Yは賃借権をもってXに対抗することができ、Yに対する関係で民法94条2項を適用ないし類推適用する余地はないとした事例 |
||
| 46 | S61.9.11 |
農地法19条(農地又は採草放牧地の賃貸借の存続期間) は、地上権に適用又は準用されないとした事例 |
||
| 47 | S61.7.17 |
従前の土地の所有者は、仮換地の不法占拠者に対し、将来の賃料相当損害金の請求を認容する確定判決を得た場合においても、その事実審口頭弁論終結後に、公租公課の増大、土地の価格の高騰等により、認容額が不相当となったときは、新訴により、認容額と適正賃料額との差額に相当する損害金の支払を求めることができるとした事例 |
||
| 48 | S61.7.15 |
譲渡担保権者が設定された先順位の抵当権又は根抵当権の被担保債権を代位弁済したことにより取得する求償債権は、譲渡担保設定契約に特段の定めのない限り、譲渡担保権によって担保されるべき債権の範囲に含まれないとされた事例 |
||
| 49 | S61.7.10 |
区分所有建物の保存改修工事により共用部分である部屋の壁面に設置された出窓風の飾り物が、専有部分の所有権を侵害しているとして、専有部分の所有者が管理組合等に対し撤去等を求めた事案において、管理組合は被告適格を有するとしたが、事実関係のもとにおいては管理組合等に撤去義務はないとして、専有部分所有者の請求を棄却した事例 |
||
| 50 | S61.6.19 |
建築基準法46条1項に基づく壁面線の指定は、特定の街区を対象として行う対物的な処分であり、特定の個人又は団体を名あて人として行うものではないから、その指定については行政不服審査法57条1項の適用はない(利害関係人は、同条2項により教示を求めることができるものとされている)とされた事例 |
||
| 51 | S61.5.29 |
町村の境界を確定するに当たっては、まず、江戸時代における関係町村の当該係争地域に対する支配・管理・利用等の状況を調べ、そのおおよその区分線を知り得る場合には、これを基準として境界を確定すべきとした事例(筑波山山頂付近における隣接両町の境界を確定した事例) |
||
| 52 | S61.4.25 |
区分所有建物における共用設備のある倉庫が、建物の専有部分として区分所有権の目的となるとされた事例 |
||
| 53 | S61.4.11 |
仮登記担保権者は、仮登記担保契約に関する法律2条1項所定の債務者又は第三者に対する通知をし、その到達の日から2月の清算期間を経過したのちであっても、同法5条1項所定の通知をしていない後順位担保権者に対しては仮登記に基づく本登記の承諾請求をすることはできないとした事例 |
||
| 54 | S61.4.11 |
債務の弁済と当該債務の担保のために経由された仮登記担保権設定の仮登記の抹消登記手続ないし抹消登記手続に代わる移転登記手続とは、前者が後者に対し先履行の関係にあるものであって、同時履行の関係に立つものではないとした事例 |
||
| 55 | S61.3.20 |
民法921条3号にいう相続財産には相続債務も含まれるとした事例 |
||
| 56 | S61.3.17 |
・時効による債権消滅の効果は、時効期間の経過とともに確定的に生ずるものではなく、時効が援用されたときにはじめて確定的に生ずるとした事例 |
||
| 57 | S61.2.27 |
一筆の土地が現地においてA部分とB部分とに明確に区分され、A部分は甲に、B部分は乙にそれぞれ賃貸された後において、甲が売買の目的物を一筆の土地と表示して契約を締結したとしても、B部分を含める旨の明示的な合意がされている等の特段の事情のない限り、一筆の土地全部が売買の対象とされたものと認めることは経験則に反するとされた事例 |
||
| 58 | S60.12.20 |
債務者が代物弁済に供した不動産をその登記未了の間に第三者に譲渡したがその後代物弁済契約が遡って失効した場合において、債権者に対する不法行為責任がないとされた事例 |
||
| 59 | S60.12.17 |
宅地建物取引業法47条1号に違反した宅建業者の代表取締役について、同法84条により、同法80条の罪の行為者として処罰されるとした事例 |
||
| 60 | S60.12.17 |
将来換地となることが予想される土地に対して換地計画を定めないでした仮換地指定処分が、土地区画整理法98条1項前段にいう工事のため必要がある場合に当たるとして、適法とされた事例 |
||
| 61 | S60.11.29 |
・障害物の除去時期が確定できないため、使用収益開始の日を追って定める旨通知してなされた仮換地指定につき違法とはいえないとされた事例 |
||
| 62 | S60.11.29 |
・水産業協同組合法45条準用の民法54条にいう「善意」とは、理事の代表権に制限を加える定款の規定又は総会の決議の存在を知らないことをいうとされた事例 |
||
| 63 | S60.11.29 |
甲から不動産を取得した乙がこれを丙に贈与した場合において、乙が、司法書士に依頼し甲に差し出した、不動産を丙に譲渡したので甲から直接丙に所有権移転登記をするよう求める旨の内容証明郵便が、民法550条にいう書面に当たるとされた事例 |
||
| 64 | S60.11.26 |
仮登記担保権が設定された不動産の譲渡を受けた第三者は、当該仮登記担保権の被担保債権の消滅時効を援用することができるとした事例 |
||
| 65 | S60.11.14 |
建築基準法48条1項但書により、特定行政庁が第一種低層住居専用地域における良好な住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した建築物につき、当該敷地の隣接居住者が当該許可の取消しを求める原告適格を有しないとされた事例 |
||
| 66 | S60.7.16 |
建築主と付近住民との紛争につき建築主に行政指導が行われていることのみを理由として建築確認申請に対する処分を留保することは、国家賠償法一条一項所定の違法な行為となるとされた事例 |
||
| 67 | S60.5.17 |
請負契約が請負人の責に帰すべき事由により中途で終了した場合において、注文者が残工事の施工に要した費用として請負人に賠償請求できるのは、残工事に要した費用のうち、未施工部分に相当する請負代金額を超える部分に限られるとされた事例 |
||
| 68 | S60.3.28 |
残代金を約定期限までに支払わないときは契約は当然に解除されたものとする旨の解除条件が付された土地の売買契約において、代金の一部を支払わなかった買主が、契約時より民法162条の自主占有があったとした20年の取得時効の主張が認められた事例 |
||
| 69 | S60.3.26 |
宅地建物取引業法49条にいう「帳簿」とは、本人の意思、形式、記載内容、保管状況から判断して、宅地建物取引業者がその業務に関し同条所定の事項を記載することを予定して備え付けたと認められる帳簿をいうとされた事例 |
RETIO 02-008
|
|
| 70 | S59.12.21 |
新築されたマンションに隣接する家屋の所有者の、現在は発生していないが将来ビル風による被害が生ずる恐れがあるとしてその予防に要した工事費用は、特段の事情のない限り民法717条の損害には該当しないとした事例 |
||
| 71 | S59.12.20 |
他人名義で根抵当権設定登記を有する債権者は、抵当不動産の譲渡後に開始された不動産競売事件において配当を受けることはできないとされた事例 |
||
| 72 | S59.12.13 |
公営住宅の入居者が、公営住宅法22条1項所定の明渡請求事由に該当する行為をした場合であっても、賃貸人である事業主体との間の信頼関係を破壊するとは認め難い特段の事情があるときは、事業主体の長がした明渡請求は効力を生じないとした事例 |
||
| 73 | S59.12.7 |
新築の家屋は、一連の新築工事が完了した時に、固定資産税の課税客体となるとした事例 |
||
| 74 | S59.11.22 |
借主及びその家族の居住を目的とする建物の使用貸借契約について、建物の占用使用開始より約32年4か月の長年月の経過により、目的に従い使用収益をなすに足るべき期間は既に経過しているとして、使用貸借契約の解除を認めた事例 |
||
| 75 | S59.11.6 |
路線の認定及び道路区域の決定の手続を経ずに行われた道路用地の任意取得は、違法ではないとされた事例 |
||
| 76 | S59.10.26 |
建築基準法6条1項による確認を受けた建築物の建築等の工事が完了したときは、確認の取消を求める訴えの利益は失われるとした事例 |
||
| 77 | S59.9.20 |
売買に基づく所有権移転登記手続請求権を被保全権利とする処分禁止の仮処分が、その後完成した取得時効に基づく所有権移転登記手続請求権について効力を有するとされた事例 |
||
| 78 | S59.9.18 |
買受希望者の希望により設計変更等を行ったが、買受希望者の一方的事情により売買が不成立になったとした、マンション売主の買受希望者に対する契約準備段階における信義則上の注意義務違反を理由とした損害賠償請求が認められた事例 |
||
| 79 | S59.9.6 |
施行者が仮換地を指定するに際し、あらかじめ土地区画整理審議会の意見を聞く手続をとらなかったとしても、それだけで仮換地の指定が当然に無効となるものではないとした事例 |
||
| 80 | S59.5.25 |
農地の譲受人が、当該譲渡について必要な農地調整法(昭和24年法律第215号による改正前のもの)4条1項所定の知事の許可を受けていないときは、特段の事情のない限り、農地を占有するに当たってこれを自己の所有と信じても、無過失であったとはいえないとされた事例 |
||
| 81 | S59.5.17 |
建物収去土地明渡請求及び賃料相当損害金請求訴訟の係属中に借主が破産宣告を受けた場合において、破産宣告日前日までの賃料相当損害金の請求に係る訴訟は、破産法246条の破産債権の確定を求める訴訟となるべきであり、その受継は同法246条、244条2項、247条によりすることを要するとされた事例 |
||
| 82 | S59.4.24 |
動産執行による金銭債権の消滅時効中断の効力は、債権者が執行官に対しその執行の申立をした時に生ずるとされた事例 |
||
| 83 | S59.4.24 |
共有不動産につき、共有者の一部の者が勝手に自己名義で所有権移転登記又は所有権移転請求権仮登記をした場合に、他の共有者がその共有持分に対する妨害排除として登記名義人に対し請求することができるのは、自己の持分についてのみの一部抹消(更正)登記手続に限られるとした事例 |
||
| 84 | S59.4.20 |
建物の所有を目的とする土地の賃貸借において、契約期間満了にあたり調停で決定した更新料を賃借人が支払わなかったことを理由とする賃貸人の賃貸借契約の解除が認められた事例 |
||
| 85 | S59.4.5 |
建物所有を目的とする地上権設定登記は、借地法7条による地上権の存続期間が延長された場合においても、これを表示するものとして効力を有するとした事例 |
||
| 86 | S59.3.9 |
不動産の仮差押による時効中断の効力は、第三者の申立による強制競売により不動産が競落されて仮差押の登記が抹消されても失われず、その抹消の時まで中断事由が存続したとされた事例 |
||
| 87 | S59.3.6 |
不動産競売についての予納金及び登録免許税の納付による支出は、所得税法上の必要経費にあたらないとされた事例 |
||
| 88 | S59.2.16 |
公簿上相隣接する二筆の土地の中間に第三者所有の土地が介在する場合、二筆の土地の所有名義人間の境界確定を訴えにより求めることはできないとした事例 |
||
| 89 | S59.2.14 |
順位を異にする複数の抵当権が設定されている不動産について後順位の抵当権の実行がされた場合において、最先順位の抵当権設定後、後順位抵当権設定前に不動産を賃借した者は、最先順位の抵当権設定当時存在していた賃借権が競売手続中に消滅したときであっても、賃借権をもって不動産の競落人に対抗することができないとした事例 |
||
| 90 | S59.1.31 |
数人が共同して行う土地改良事業の認可の申請に同意した者は、既に換地を行うことが予定されているのを了知して同意をしたときであっても、換地計画に同意する義務を負うものではないとした事例 |
||
| 91 | S59.1.27 |
借地人所有の建物の壁面に取り付けられた第三者所有の広告用看板について、同看板の所有をもって当該建物の壁面についての客観的外部的な事実支配があるとは認められないとして、建物収去土地明渡請求事件の判決に基づきなされた敷地明渡しの強制執行の効力は、同看板にも及ぶとされた事例 |
||
| 92 | S59.1.19 |
不動産について、贈与を登記原因とした所有権移転登記の抹消手続を求める前訴を提起して敗訴した者が、贈与の不履行を理由に贈与契約を解除したとして、所有権移転登記手続を求める後訴を提起した場合において、後訴の提起は信義則に反するものではないとした事例 |
||
| 93 | S58.12.8 |
旧日本住宅公団と賃借人との間の公団住宅賃貸借契約については、借家法7条1項の規定の適用があるとして、旧日本住宅公団の家賃改定を容認した事例 |
||
| 94 | S58.12.6 |
市の道路用地買収において、市が買収済の特定の残地を他に優先者のない限り払い下げる旨の説明を受け買収に応じた道路買収協力者の、当該残地が払い下げられたことを理由とする市に対する不法行為に基づく損害賠償請求が棄却された事例 |
||
| 95 | S58.11.15 |
農地の賃貸借について、農地法による知事の許可なく賃貸借契約が合意解除された後、宅地造成が行われ宅地化された場合において、農地の賃貸借契約の合意解除が知事の許可なしに効力を生じたとされた事例 |
||
| 96 | S58.10.28 |
土地区画整理法100条の2の規定により、施行者が管理する土地について、第三者が権原なく同土地を不法に占有する場合には、施行者はこれに対し物権的支配権に基づき土地の明渡を求めることができるとした事例 |
||
| 97 | S58.10.20 |
予見可能性の有無はその公務員の通常有すべき知識経験を基準として判定すべきであるとした事例 |
||
| 98 | S58.10.18 |
隣接する甲乙両地各所有者間の境界確定訴訟において、甲地のうち境界の一部に接続する部分につき乙地所有者の時効取得が認められても、甲地の所有者はその境界部分についても境界確定を求めることができるとした事例 |
||
| 99 | S58.9.20 |
委任契約たる税理士顧問契約は、受任者の利益をも目的として締結された場合でない限り、委任者がいつでも、かつ、なんらその理由を告知せずに、解除することができるとした事例 |
||
| 100 | S58.9.9 |
自動車学校建築のため木造家屋の敷地に使用する目的でされた土地の賃貸借について、契約当事者は単に自動車運転教習コースのみならず、自動車学校経営に必要な建物所有をも主たる目的として本件賃貸借契約を締結したことが明らかであるなどとして、土地全体について借地法の適用を認めた事例 |
||
| 101 | S58.9.8 |
土地収用法133条1項所定の期間経過後に損失の補償に関する訴えが予備的に追加された場合において、事実関係等より主位的請求が損失補償額自体を争う趣旨を含むとみることはできないとして、予備的請求の訴えを出訴期間を徒過して提起されたものとして棄却した事例 |
||
| 102 | S58.9.6 |
農地法五条所定の許可がされた農地に隣接する農地の所有者が当該許可の取消しを求める原告適格を有しないとされた事例 |
||
| 103 | S58.7.5 |
第一売買の買主より不動産を購入し中間省略登記によって仮登記を受けた第二売買の買主に対して、第一売買の売主が、第一売買の合意解除による仮登記の抹消を請求した事案において、第二売買の買主は民法545条1項但書にいう「第三者」に該当しないとしてその請求が認められた事例 |
||
| 104 | S58.6.30 |
敷金返還請求権に質権が設定された事案において、指名債権に対する質権設定を第三者に対抗しうる要件としての第三債務者に対する通知又はその承諾は、具体的に特定された者に対する質権設定についてされることを要するとされた事例 |
||
| 105 | S58.4.19 |
土地の売却交渉において、売買条件の全てを諒承し、売買契約公正証書の作成の日まで取り決めながら、契約締結に応じないで土地を他に売却した売主につき、契約締結上の過失に基づく債務不履行責任を認めた事例 |
||
| 106 | S58.4.14 |
建物の登記名義人が不実である場合、真実の建物所有者がその登記名義人の共同相続人であるとしても、同登記をもって建物保護に関する法律1条による法定地上権の対抗力は得られないとした事例 |
||
| 107 | S58.4.8 |
ビラ貼りのための建物立入りが建造物侵入罪にあたるとされた例 |
||
| 108 | S58.4.1 |
自転車に乗っていた7歳の児童が、飼主の手を離れ道路に走り出してきた犬を避けようとして、誤って道路から転落し負傷した事故について、犬の飼主に民法718条の責任を認め、足のとどかない自転車に乗っていた児童の治療費について90パーセントの過失相殺を認めた事例 |
||
| 109 | S58.3.31 |
代物弁済予約のなされた不動産につき、清算金の支払いがなされないまま第三者が仮登記担保権者から不動産の所有権を取得した場合、債務者は第三者からの不動産の明渡請求に対し、仮登記担保権者に対する清算金支払請求権を被担保債権とする留置権の抗弁権を主張することができるとした事例 |
||
| 110 | S58.3.25 |
民法576条但書の「売主が相当の担保を供したとき」とは、売主が買主との合意に基づいて担保物権を設定したか、又は保証契約を締結したなどの場合をいい、担保の提供について買主の承諾を伴わない場合はこれにあたらないとした事例 |
||
| 111 | S58.3.24 |
民法186条1項の所有の意思の推定は、占有者がその性質上所有の意思のないものとされる権原に基づき占有を取得した事実が証明されるか、又は、占有中真の所有者であれば通常はとらない態度を示し、若しくは所有者であれば当然とるべき行動に出なかつたなど、外形的客観的に占有者が他人の所有権を排斥して占有する意思を有していなかったと解される事情が証明されるときは、覆されるとされた事例 |
||
| 112 | S58.3.24 |
朽廃に近い建物を取得した土地転借権の無断譲受人が、土地の賃借人兼転貸人の承諾を得ず、また異議の申し入れ、裁判所の仮処分決定を無視して、建物の大改造の工事を行い完成させた場合において、無断譲受人が借地法10条に基づく建物の買取請求権を行使することは、信義則に反し許されないとした事例 |
||
| 113 | S58.3.18 |
遺言の解釈にあたっては、遺言書の文言を形式的に判断するだけでなく、遺言者の真意を探究すべきものであり、遺言書の特定条項の解釈においても、当該条項と遺言書の全記載との関連、遺言書作成当時の事情及び遺言者の置かれていた状況などを考慮して当該条項の趣旨を確定すべきであるとされた事例 |
||
| 114 | S58.2.18 |
道路法70条1項(道路の新設又は改築に伴う損失の補償)による補償の対象は、道路工事施工による土地の形状変更を直接の原因として生じた障害除去のため、やむを得ず行った工事に起因する損失に限られ、警察規制等による法規制上の障害に基づく損失は含まれないとした事例 |
||
| 115 | S58.2.8 |
入会団体に個別的に加入を認められたと主張する者が入会権者に対し入会権を有することの確認を請求する場合には、主張者が各自単独で訴えを提起することができるとした事例 |
||
| 116 | S58.1.24 |
土地の死因贈与につき、事実関係のもとでは取消ができないとされた事例 |
||
| 117 | S58.1.20 |
建物所有を目的とする借地契約の更新拒絶に正当の事由があるかどうかを判断するにあたっては、借地契約が当初から建物賃借人の存在を容認したものであるか又は実質上建物賃借人と借地人とを同一視することができるなどの特段の事情の存在する場合のほかは、建物賃借人の事情を借地人側の事情として斟酌することは許されないとした事例 |
||
| 118 | S57.12.17 |
連帯債務者の一人が弁済その他の免責の行為をするに先立ち、他の連帯債務者に対し民法443条1項の通知をすることを怠った場合は、既に弁済その他により共同の免責を得ていた他の連帯債務者に対し、同条2項の規定により自己の免責行為を有効であるとみなすことはできないとされた事例 |
||
| 119 | S57.12.2 |
所有権に基づく土地明渡訴訟の係争中に提起された境界の確定を求める訴えは、境界の確定が土地所有権に基づく土地明渡訴訟の先決関係に立つ法律関係にあたるものと解することはできないことから、中間確認の訴えとしては不適法であるとされた事例 |
||
| 120 | S57.11.18 |
民法826条1項(利益相反行為)の規定に基づいて選任された特別代理人と、未成年者との利益が相反する行為については、特別代理人は、選任の審判によって付与された権限を行使することができないとされた事例 |
||
| 121 | S57.10.19 |
民法724条(不法行為による損害賠償請求権の期間の制限)所定の3年の時効期間の計算においては、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時が午前零時でない限り、時効期間の初日を算入すべきではないとされた事例 |
||
| 122 | S57.10.19 |
土地所有者が、土地賃借人との土地賃貸借契約を合意解除し、不法占有となった者の所有する地上建物を自力救済により違法に取り壊した場合において、土地所有者は土地の不法占有を理由とする建物所有者に対する損害賠償請求ができるとされた事例 |
||
| 123 | S57.9.28 |
土地所有者の建物収去土地明渡請求に対し、建物所有者が「土地所有者は、譲渡担保設定による所有権移転登記により、明渡請求の基礎となる土地所有権を喪失した」と主張した事案において、土地所有者の譲渡担保設定における所有権移転の効力は、債権担保の目的を達するのに必要な範囲内に限られるとして、その主張を否定した事例 |
||
| 124 | S57.9.9 |
宅地建物取引業法13条における名義貸しとは、自己の名義をもつて他人に宅地建物取引業を営ませる行為につき、その相手方が宅地建物取引業を営む免許を受けていると否とにかかわりなく、一律にこれを禁止、処罰する趣旨であるとした事例 |
||
| 125 | S57.9.7 |
闘犬の襲撃による幼児の死亡事故につき、飼主に飼育場所を提供しかつ日常飼育に協力していた者に対して、闘犬の保管において危険発生を防止すべき高度の注意義務があり民法709条の不法行為責任を負うとされた事例 |
||
| 126 | S57.7.15 |
約束手形の裏書人が振出人の手形金支払義務の時効による消滅に伴い、自己の所持人に対する償還義務も消滅したとしてその履行を免れようとすることが信義則に反し許されないとされた事例 |
||
| 127 | S57.7.1 |
・入会部落の構成員が有する使用収益権の確認又はこれに基づく妨害排除の請求については、構成員各自に当事者適格があるとされた事例 |
||
| 128 | S57.7.1 |
競売手続中の他人所有の不動産を目的物とする売買につき、買主が売主の履行遅滞による売買契約の解除及び損害賠償の請求を求めた事案において、売主の履行遅滞は競落許可決定に対し即時抗告の申立がされたこと等の売主の責に帰することのできない事由によるものとして、その請求を棄却した事例 |
||
| 129 | S57.6.17 |
公有水面を埋め立てるため投入された土砂は、その投入によって直ちに公有水面の地盤に附合して国の所有となることはなく、原則として、埋立工事の竣功認可の時に埋立権者の取得する埋立地に附合するものであって、その時までは、独立した動産としての存在を失わないとした事例 |
||
| 130 | S57.6.17 |
・一筆の土地の一部分の売買契約において、対象土地部分が具体的に特定していないとされた事例 |
||
| 131 | S57.6.17 |
農地の売買において、買主が約定の履行期後売主に対し再三にわたり売買契約の履行を催告し、その間常に残代金の支払の準備をし、農地法3条所定の認可がされ次第残代金の支払いができる状態にあったときは、現実に残代金を提供しなくても、民法557条1項の「契約の履行に着手」したものと認められた事例 |
||
| 132 | S57.6.8 |
土地の仮装譲受人が土地上に建物を建築してこれを他人に賃貸した場合、建物賃借人は、仮装譲渡された土地については法律上の利害関係を有するものとは認められないから、民法94条2項所定の第三者にはあたらないとして、土地所有者(仮想譲渡人)の建物賃借人に対する建物明渡請求が認められた事例 |
||
| 133 | S57.6.4 |
不動産を目的とする代物弁済契約の意思表示がされたときは、これにより当該不動産の所有権移転の効果が生ずるとした事例 |
||
| 134 | S57.4.30 |
負担の履行期が贈与者の生前と定められた負担付死因贈与の受贈者が負担の全部又はこれに類する程度の履行をした場合、特段の事情がない限り、民法1022条、1023条の規定は準用されないとされた事例 |
||
| 135 | S57.4.22 |
都市計画区域内における高度地区指定の決定は、抗告訴訟の対象にならないとされた事例 |
||
| 136 | S57.4.22 |
都市計画法8条1項1号の規定に基づく工業地域指定の決定は、抗告訴訟の対象にならないとした事例 |
||
| 137 | S57.4.9 |
後順位担保権者の申し立てによる不動産競売手続が開始されている場合において、仮登記担保権者によって提起された仮登記に基づく本登記手続の承諾請求及び本登記を条件とする不動産の明渡請求が認められた事例 |
||
| 138 | S57.3.30 |
占有補助者による占有の侵奪を否定した判断に、民法200条(占有回収の訴え)違背の違法があるとされた事例 |
||
| 139 | S57.3.25 |
所有権移転請求権保全の仮登記の名義人は、登記上利害関係を有する第三者の承諾書等がないため、仮登記とは無関係に所有権移転登記を経由した場合であっても、特段の事情のない限り、仮登記義務者に対して仮登記の本登記手続を請求する権利を失わず、右仮登記の本登記を承諾すべき第三者の義務も消滅しないとした事例 |
||
| 140 | S57.3.12 |
工場抵当法2条の規定により工場に属する土地又は建物とともに抵当権の目的とされた動産が、抵当権者の同意を得ないで、備え付けられた工場から搬出された場合、第三者において即時取得をしない限りは、抵当権者は搬出された目的動産をもとの備付場所である工場に戻すことを求めることができるとした事例 |
||
| 141 | S57.3.9 |
・共有物分割の訴えは、分割方法を具体的指定の必要はなく、単に共有物の分割を求める旨の申し立てで足りるとした事例 |
||
| 142 | S57.2.18 |
未登記不動産にも民法177条の適用があり、時効取得者は登記を備えなければ、時効完成後に不動産を取得し登記を備えた第三者に対し対抗できないとした事例 |
||
| 143 | S57.2.5 |
鉱業権設定後、採掘予定の鉱区内に学校が建設されたため、その周囲50mの範囲で採掘ができなくなったとして、鉱業者が学校の建設者に損害賠償を請求した事案において、鉱業法64条の規定により鉱業権の行使が制限されても、その損失につき憲法29条3項を根拠としてその補償を請求することはできないとした事例 |
||
| 144 | S57.2.4 |
借地期間が20年に1日足りない非堅固建物の所有を目的とする借地契約については、その形式、文言にかかわらず、借地権の存続期間を20年と定める趣旨のものと認めるのが相当とした事例 |
||
| 145 | S57.1.29 |
執行力のある債務名義又は終局判決を有しない破産債権者の届出債権に対する債権調査期日における破産管財人又は他の債権者の異議は、破産債権届出の時効中断の効力に影響を及ぼすものではないとされた事例 |
||
| 146 | S57.1.22 |
山林原野が村有財産として管理処分され、部落による共同体的統制の存在が認められない場合において、共有の性質を有する入会権及び共有の性質を有しない入会権ともに認められないとされた事例 |
||
| 147 | S57.1.22 |
譲渡担保を設定した債務者の受戻の請求において、債務の弁済と弁済に伴う目的不動産の返還請求権とを合体して、一個の形成権たる受戻権であるとの法律構成をする余地はなく、これに民法167条2項(消滅時効)の規定を適用することはできないとした事例 |
||
| 148 | S57.1.21 |
土地の売買契約において、土地の面積が表示された場合でも、その表示が代金額決定の基礎とされたにとどまり契約の目的を達成する上で特段の意味を持つものでないときは、当該土地が表示どおりの面積を有したとすれば買主が得たであろう利益について、売主は損害賠償責任を負わないとした事例 |
||
| 149 | S57.1.19 |
固定資産の土地名寄帳及び家屋名寄帳は、市町村が固定資産税の課税上の必要に基づき作成する資料であり、その記載が固定資産税の納税義務者の権利義務に影響を及ぼすものではないから、固定資産の所有者であっても、法律上市町村に対し名寄帳の閲覧を請求する権利はないとした事例 |
||
| 150 | S57.1.19 |
抵当債務は、抵当権設定登記の抹消登記手続より先に履行すべきもので、後者とは同時履行の関係に立たないとした事例 |
||
| 151 | S56.12.18 |
自筆証書遺言における証書の記載自体からみて明らかな誤記の訂正については、民法968条2項所定の方式の違背があっても、その違背は遺言の効力に影響を及ぼさないとされた事例 |
||
| 152 | S56.12.17 |
譲渡担保権者は、特段の事情がないかぎり、譲渡担保権者たる地位に基づいて目的物件に対し譲渡担保権設定者の一般債権者がした強制執行の排除を求めることができるとした事例 |
||
| 153 | S56.12.4 |
仮換地について、賃借権の目的となるべき土地の指定を受けていない賃借人に対する、賃貸人の明渡請求が権利の濫用にあたるとされた事例 |
||
| 154 | S56.11.24 |
不動産につき取得時効が完成したときは、同不動産についての取得時効期間の進行中に締結され、所有権移転請求権仮登記により保全された売買予約上の買主の地位は消滅し、時効取得者は、その所有権の取得を登記なくして仮登記権利者に対抗することができるとした事例 |
||
| 155 | S56.11.5 |
檻から出した飼犬が公道に飛び出し、進行中の原動機付自転車に接触して転倒させ、運転者を負傷させた事故について、犬の飼主に民法718条(動物の占有者等の責任)による損害賠償責任を認めた事例 |
||
| 156 | S56.10.30 |
共有不動産につき、単独相続したとして登記を得て売買した売主が、当該不動産につき自己が取得した持分をこえる部分の所有権が無効であると主張して、買主および買主よりの転取得者に対し、所有権移転の無効及び抹消(更正)登記手続を請求することは信義則に照らして許されないとした事例 |
||
| 157 | S56.10.30 |
将来発生する求償債権を既発生の貸金債権と表示してされた抵当権設定仮登記について、その効力が認められた事例 |
||
| 158 | S56.10.16 |
日本国内に営業所を有する外国法人に対する損害賠償請求訴訟については、右法人にわが国の裁判権が及ぶものと解するのが相当とされた事例 |
||
| 159 | S56.10.13 |
民法467条1項所定の通知又は承諾は、債権の譲受人が債務者に対して債権を行使するための積極的な要件ではなく、債務者において通知又は承諾の欠けていることを主張して譲受人の債権行使を阻止することができるにすぎないとして、貸主の地位を承継した建物賃貸人の、賃借人に対する前貸主との未払賃料、損害金等の請求を容認した事例 |
||
| 160 | S56.10.8 |
書面によらない土地の贈与者が受贈者に土地の占有及び登記名義を移転することができない場合において、事実関係により贈与の履行が終了したものとして民法550条に基づく取消の効力が否定された事例 |
||
| 161 | S56.10.1 |
農地の受贈者の贈与者に対して有する知事に対する所有権移転許可申請協力請求権は、民法167条1項の債権にあたり、請求権は贈与契約成立の日から10年の経過により時効によって消滅するとした事例 |
||
| 162 | S56.9.18 |
庭園等に使用する各種花木を幼木から栽培している土地が、農地法2条1項にいう農地にあたらないとはいえないとされた事例 |
||
| 163 | S56.9.11 |
・遺言無効確認訴訟における確認の利益の存否判断にあたっては、原則として、原告の相続分が被相続人から受けた生前贈与等によりなくなるか否かを考慮すべきものではないとされた事例 |
||
| 164 | S56.9.8 |
宅地造成を目的とした山林の売買において、保安林指定があったことにつき、売主の瑕疵担保責任を認めた事例 |
||
| 165 | S56.7.17 |
共用設備が設置されている車庫について、認定した事実により、建物の区分所有等に関する法律にいう専有部分にあたるとされた事例 |
||
| 166 | S56.7.16 |
給水装置新設工事申込の受理の事実上の拒絶につき、建築基準法違反の状態にある建物の状況を是正し建築確認を受けたうえ申込をするよう一応の勧告をしたものにすぎないとして、不法行為による損害賠償責任を否定した事例 |
||
| 167 | S56.7.3 |
・所有権に基づく登記請求を認容した確定判決は、その理由において所有権の存否を確認している場合であっても、所有権の存否について既判力を有しないとした事例 |
||
| 168 | S56.7.3 |
土地区画整理法103条の規定に基づく換地処分について被処分者がする審査請求の請求期間の起算日は、同人が換地処分の通知を受けてその処分があったことを知った日の翌日であるとした事例 |
||
| 169 | S56.6.26 |
負担付贈与がされた場合における贈与税の課税価格は、贈与に係る財産の時価から当該負担額を控除した価格であるとされた事例 |
||
| 170 | S56.6.18 |
共用設備が設置されている倉庫について、共用設備の利用管理によって倉庫の排他的使用に格別の制限ないし障害を生じないときは、倉庫は建物の区分所有等に関する法律にいう専有部分にあたるとされた事例 |
||
| 171 | S56.6.18 |
建物の区分所有等に関する法律1条にいう構造上区分された建物部分とは、建物の構成部分である隔壁、階層等により独立した物的支配に適する程度に他の部分と遮断されており、その範囲が明確な建物部分をいい、必ずしも周囲すべてが完全に遮蔽されていることを要しないとした事例 |
||
| 172 | S56.6.16 |
土地の売買予約契約の成立後、売主買主双方が予想せずその責に帰することのできない事情により価額が高騰した後になされた、買主の予約完結権の行使が信義則に反しないとされた事例 |
||
| 173 | S56.6.16 |
長期間継続した地代不払を一括して一個の解除原因とする賃貸借契約の解除権の消滅時効は、最後の地代の支払期日が経過した時から進行するとした事例 |
||
| 174 | S56.6.16 |
建物所有を目的とする土地賃貸借契約の更新拒絶に正当事由があるかどうかを判断する場合において、第三者である建物賃借人の事情は斟酌すべき事情とはならないとした事例 |
||
| 175 | S56.6.4 |
・一区画の仮換地の一部を所有の意思をもって所要の期間継続して占有した者は、従前の土地につき当該占有部分に対応する部分が特定されていないときは、時効により従前の土地に対する共有持分権を取得するとともに、当該占有部分につき、共有持分権者の一人が現に排他的な使用収益権能を取得している場合と同様の使用収益権能を取得するとした事例 |
||
| 176 | S56.4.20 |
借地契約において、将来の賃料は当事者が協議して定める旨の約定がされた場合でも、当事者が賃料増減の意思表示前にあらかじめ協議を経ず、また、意思表示後の協議が当事者相互の事情により進まないため更にその協議を尽くさなかったからといって、賃料増減の意思表示が無効となるものではないとした事例 |
||
| 177 | S56.4.14 |
いわゆる政令指定都市の区長が弁護士法23条の2に基づく照会に応じて前科及び犯罪経歴を報告したことが過失による公権力の違法な行使にあたるとされた事例 |
||
| 178 | S56.4.3 |
被相続人の遺言書又はこれになされている訂正が方式を欠き無効である場合に、相続人が方式を具備させ有効な遺言書又はその訂正としての外形を作出する行為は、遺言書の偽造又は変造(民法891条5号)にあたるが、それが遺言者の意思実現のため、その法形式を整える趣旨でされたにすぎないときは、同相続人は相続欠格者にあたらないとされた事例 |
||
| 179 | S56.3.20 |
土地所有者が地代の受領を拒絶し又はこれを受領しない意思が明確であるため地上権者において提供をするまでもなく債務不履行の責を免れる事情にある場合、土地所有者は自己の受領遅滞を解消させる措置を講じたのちでなければ、地上権消滅請求の意思表示をすることができないとした事例 |
||
| 180 | S56.3.13 |
土地の賃貸借契約の期間満了を理由とする土地明渡請求訴訟において、期間満了の時期が賃貸人の主張する時期より後であった場合でも、それが訴訟の係属中であるときは、異議は期間満了後の土地使用継続に対しても黙示的に述べられていると解されるとした事例 |
||
| 181 | S56.2.24 |
債務者が甲であるのに、誤って債務者が乙であるとして、乙所有の不動産になされた抵当権設定登記の効力があらそわれた事案において、債務者の表示の不一致は更正登記により訂正することができ、抵当権設定登記は有効であるされた事例 |
||
| 182 | S56.2.17 |
建物等の工事が未完成の間に、注文者が請負人の債務不履行により契約を解除する場合において、工事内容が可分であり、しかも当事者が既施工部分の給付に関し利益を有するときは、特段の事情のない限り、未施工部分についての契約の一部解除はできるが、既施工部分についての契約解除はできないとされた事例 |
||
| 183 | S56.2.5 |
別荘地の買主と分譲業者との間の土地管理契約について、同契約に基づかなければ分譲業者の水道等の諸施設の利用できず、分譲業者も管理費により別荘地の維持、管理の経費をまかなっている等の事実関係のもとにおいては、受託者である分譲業者から一方的に管理契約を解約することができないとされた事例 |
||
| 184 | S56.1.30 |
土地付分譲マンション付属の駐車場専用使用権分譲特約が、公序良俗違反として無効とはいえないとされた事例 |
||
| 185 | S56.1.27 |
土地の買主が売買契約に基づいて目的土地の占有を取得した場合には、他人物売買であるため土地の所有権を直ちに取得するものでないことを買主が知っているときであっても、特段の事情のない限り、買主の占有は所有の意思をもってするものとすべきであるとされた事例 |
||
| 186 | S56.1.19 | 建物管理契約において、委任者が委任契約の解除権自体を放棄したものとは解されない事情がある場合は、委任者はやむをえない事由がなくても、民法651条により契約を解除することができるとされた事例 |
||
| 187 | S55.12.11 |
賃借権の譲渡を承諾しない賃貸人は、無断譲渡を理由とする賃貸借契約の解除権が時効消滅した場合であっても、所有権に基づき、賃借権の無断譲受人に対し目的物の明渡を求めることができるとした事例 |
||
| 188 | S55.12.4 |
盲人は、公正証書遺言に立ち会う証人としての適格を有するとした事例 |
||
| 189 | S55.10.28 |
建物賃借人は、その賃借権を保全するために、債権者代位権に基づき建物賃貸人に代位して、借地法10条の建物買取請求権を行使することは許されないとした事例 |
||
| 190 | S55.10.23 |
売買を請求原因とする所有権確認訴訟において、当事者が詐欺による取消権を行使できたのに行使せず判決が確定したのちは、後訴において詐欺による取消権を行使して所有権の存否を争うことは許されないとした事例 |
||
| 191 | S55.9.30 |
土地の一部を目的物とする売買契約において、分筆の催告に売主が応じなかったため、買主が測量により目的物を定め売主に通知した事案において、民法406条以下の規定により売買の範囲が特定し、その所有権が売買契約の効力発生時に遡って買主に帰属したとされた事例 |
||
| 192 | S55.9.11 |
登記申請権者の申請に基づかないで不実の商業登記がされた場合には、登記を登記申請権者の申請に基づく登記と同視するのを相当とするような特段の事情がない限り、商法14条は適用されないとされた事例 |
||
| 193 | S55.9.11 |
民法94条2項所定の第3者の善意の存否は、同条項の適用の対象となるべき法律関係ごとに当該法律関係につき第三者が利害関係を有するに至った時期を基準として決すべきであるとした事例 |
||
| 194 | S55.7.15 |
建築基準法6条1項に基づく確認申請の審査の対象には、当該建築計画の民法234条1項の規定への適合性(隣地より50cm)は含まれないとされた事例 |
||
| 195 | S55.7.10 |
土地区画整理組合が、原則として公簿地積を基準地積とし例外的に実測地積による方法で土地区画整理事業を施行する場合において、定款には単に原則的な基準のみを記載し、例外的な措置の詳細については、別に定款の委任により執行機関の制定する執行細則等における定めにこれを委ねることも許されるとした事例 |
||
| 196 | S55.7.1 |
相続税法34条1項の規定による連帯納付義務は、相続人又は受遺者の固有の相続税の納税義務の確定という事実に照応して法律上当然に確定するとされた事例 |
||
| 197 | S55.6.5 |
宅地造成を目的とする山林の売買において、登記簿上に保安林の表示がなく現地にも保安林の標識がなかったとしても、媒介を行う宅地建物取引業者には、目的たる山林について保安林指定の有無を調査すべき注意義務があるとされた事例 |
||
| 198 | S55.5.30 |
約束手形の所持人と裏書人との間において裏書人の手形上の債務につき支払猶予の特約がされた場合には、所持人の裏書人に対する手形上の請求権の消滅時効は、同猶予期間が満了した時から進行するとされた事例 |
||
| 199 | S55.5.30 |
日本住宅公団法施行規則15条1項にいう「特別の必要がある場合」において、日本住宅公団は賃貸住宅を他に譲渡し、これに伴って賃貸人の地位をその譲受人に承継させてはならない義務を賃借人に対して負うものではないとした事例 |
||
| 200 | S55.4.18 |
土地収用法旧71条及び74条(昭和42年法律第74号による改正前のもの)のもとにおいて、当該事業の施行が残地の価格に及ぼす影響のうち利益と損失とを明確に区別することができない場合に、それらを総合的に勘案することは、同法90条の相殺禁止規定に抵触しないとされた事例 |
||
| 201 | S55.3.6 |
土地区画整理事業施行地内の土地の売買につき、従前地につきそれが別の特定の土地に換地されることを前提として締結された売買契約は、換地処分等に無効などの瑕疵があるとしても、予定通りの換地がされないことが確定しない限り効力を有するとした事例 |
||
| 202 | S55.3.6 |
土地賃借権の譲渡の承諾に付帯して約された、土地の一部の土地賃貸人への返却を、借地権譲受人が履行しなかったことを理由とする、土地賃貸人の土地全体についての土地賃貸借契約の解除が認められた事例 |
||
| 203 | S55.2.29 |
農地の売買における買主の売主に対する許可申請協力請求権の消滅時効は、売主が他人から当該農地の所有権を取得した時から進行し、10年の経過により消滅するとした事例 |
||
| 204 | S55.1.25 |
宅地建物取引業法65条2項に基づきなされた業務停止処分の取消しを求める訴えにおいて、原告が主張する「法律生活上の利益」は、行政事件訴訟法9条にいう「処分の取消しによって回復すべき法律上の利益」にはあたらないとされた事例 |
||
| 205 | S55.1.24 |
不動産物権の譲渡行為が債権者の債権成立前にされた場合には、その登記が債権成立後に経由されたときであつても、詐害行為取消権は成立しないとされた事例 |
||
| 206 | S55.1.22 |
市街化区域内農地の宅地並み課税により固定資産税等が著しく上昇したとしても、小作料の最高額の統制を定める農地法改正法(昭和45年法律第56号)附則8項は、財産権を保障する憲法29条に違反するものではないとした事例 |
||
| 207 | S54.12.14 |
被相続人が生存中に無権代理にて不動産を第三者に譲渡した共同相続人が、違産分割の結果当該不動産を取得しないこととなった場合について、民法909条但書の適用がなく、第三者は同共同相続人の法定相続分に応じた共有持分権を取得しないとした事例 |
||
| 208 | S54.12.14 |
無権代理行為の追認には、取り消しうべき行為についての法定追認を定めた民法125条は類推適用されないとした事例 |
||
| 209 | S54.11.30 |
建物明渡の確定判決がなされたが建物の明渡に応じなかった医療法人の建物の不法占拠につき、医療法人の理事らに対する不法行為による損害賠償責任を認めた事例 |
||
| 210 | S54.11.16 |
控訴審において全部勝訴の判決を得た当事者は、第1審において自己の請求の一部を棄却され、控訴審においてこれに対する控訴も附帯控訴もしないまま相手方の控訴棄却判決がなされた場合に、第1審判決にて棄却された請求の認容を求める目的であっても、附帯上告を提起することは許されないとされた事例 |
||
| 211 | S54.11.1 |
土地の所有権が被告にないとする確認の訴は、隣接地を所有する原告が同土地を道路として使用することを所有権を主張する被告によって妨げられており、かつ、被告が同土地を時効取得することを防止するため必要があると主張するだけでは、確認の利益があるとはいえないとした事例 |
||
| 212 | S54.9.27 |
未登記建物につき書面によらないで贈与契約がされた場合に、贈与者の意思に基づき直接受贈者名義に保存登記がされたときには、贈与契約の履行が終ったものとして、贈与契約を取り消すことはできないとされた事例 |
||
| 213 | S54.9.21 |
借地法10条による建物買取請求権について、当該土地明渡請求訴訟における訴状送達の時から10年の経過により時効消滅しているとされた事例 |
||
| 214 | S54.9.11 |
所有権移転仮登記に後れて目的物件につき権原を取得し占有を開始した第三者は、仮登記権利者あるいは仮登記に基づき本登記を行った所有権者に対し、本登記がなされる以前の物件占有について、不法占有者としての損害賠償責任は負わないとした事例 |
||
| 215 | S54.9.7 |
土地改良法に基づく農用地の交換分合の前後を通じ、特定の所有者の失うべき土地と取得すべき土地とについて自主占有が継続しているときは、取得時効の成否に関しては両土地の占有期間を通算することができるとされた事例 |
||
| 216 | S54.9.6 |
手形の裏書人が金額1500万円の手形を、金額150万円の手形と誤信し同金額の手形債務を負担する意思のもとに裏書をした場合に、悪意の取得者に対して錯誤を理由に償還義務の履行を拒むことができるのは、同手形金のうち150万円を超える部分についてだけであって、その全部についてではないとされた事例 |
||
| 217 | S54.9.6 |
違約手付金の約定が契約関係を清算する趣旨でなされた場合、手付金の受領者は、相手方に違約があったときは、契約解除の手続を経ることなく手付金流しとしてこれを自己に帰属させることができるとともに、相手方に対しその旨を告知したときは、これによって契約関係も当然に終了するとした事例 |
||
| 218 | S54.7.31 |
占有者の占有が自主占有にあたらないことを理由に取得時効の成立を争う者は、占有が他主占有にあたることについての立証責任を負うとした事例 |
||
| 219 | S54.5.31 |
自筆遺言証書の日付として「昭和四拾壱年七月吉日」と記載された証書は、民法968条1項にいう日付の記載を欠くものとして無効であるとした事例 |
||
| 220 | S54.5.29 |
借地上の数棟の建物のうち一部の建物の譲渡にともなう借地の一部無断転貸を理由として土地賃貸借契約全体が解除された場合には、そのほかの建物について所有者である借地人は建物買取請求権を有しないとした事例 |
||
| 221 | S54.3.20 |
仕事の目的物に瑕疵がある場合には、注文者は、瑕疵の修補が可能なときであっても、修補を請求することなく直ちに修補に代る損害賠償を請求することができるとした事例 |
||
| 222 | S54.3.15 |
土地地積更正登記につき、当該土地の隣接地の所有者は、その取消を求める法律上の利益を有しないとした事例 |
||
| 223 | S54.3.1 |
土地区画整理事業の施行区域内の特定土地につき、所有権その他権利を有する者全員が他の土地の換地に影響を及ぼさない限度内において、特定土地に対する換地の位置、範囲に関し合意し、換地を求める申し出があったときは、事業施行者は、公益に反せず事業施行上支障を生じない限り、土地区画整理法89条1項所定の基準によることなく、合意に従って各土地の換地を定めることができるとした事例 |
||
| 224 | S54.2.22 |
仮登記担保関係において、債権者が履行遅滞を理由に目的不動産につき、予め交付を受けていた登記手続に必要な書類を利用して所有権移転登記を完了したとしても、仮登記担保権行使による所有権の取得に清算金の支払いが必要な場合においては、債権者が債務者に対し清算金の提供をするまでは、債務者は債務を弁済して仮登記担保関係を消滅させることができるとした事例 |
||
| 225 | S54.2.22 |
共同相続人全員の合意によって遺産分割前に遺産を構成する特定不動産を売却した場合の売却代金は、特別の事情のない限り、相続財産には加えられず、共同相続人が各持分に応じて個々にこれを分割取得するとした事例 |
||
| 226 | S54.2.20 |
請負人が第三者に損害を与えた場合において、注文者に注文又は指図について過失があるとした事例 |
||
| 227 | S54.2.2 |
請負契約の目的物の瑕疵修補に代わる損害賠償請求をした場合の損害額の算定時点は、請求時を基準として行われるとし、後に物価の高騰により修補費用が増加したとしても、注文主は請負人に対しその増加額を求めることはできないとした事例 |
||
| 228 | S54.1.30 |
所有権保存登記抹消登記手続請求訴訟において勝訴の確定判決を得た原告が、被告の口頭弁論終結後の承継人に対し真正な登記名義の回復のための所有権移転登記手続を求める訴は、前訴の判決の存在によって当然に訴えの利益を欠くことにはならないとした事例 |
||
| 229 | S54.1.25 |
譲渡担保契約が抵当権者への詐害行為に該当する場合において、譲渡担保権者が当該抵当権者以外の債権者であり、土地の価額から抵当権の被担保債権の額を控除した額が詐害行為取消権の債権額を下回っているときは、譲渡担保契約の全部を取り消し土地自体の原状回復をすることが認められるとした事例 |
||
| 230 | S54.1.25 |
建築途中の未だ独立の不動産に至らない建前に第三者が材料を供して工事を施し、独立の不動産である建物に仕上げた場合における建物所有権の帰属は、民法243条の規定によるのではなく、同法246条2項の規定に基づいて決定すべきとした事例 |
||
| 231 | S54.1.25 |
破産宣告当時、破産者所有の不動産につき対抗力ある賃借権の負担が存在する場合において、破産宣告後に不動産が転貸されたとしても、特段の事情のない限り、転借人の転借権取得は破産法54条1項所定の破産者の法律行為によらない権利の取得には該当しないとした事例 |
||
| 232 | S54.1.19 |
賃借人が複数の共同賃借人であるときにおいて、賃貸人が借地法12条に基づく賃料増額の請求をする場合は、賃借人全員に対し増額の意思表示をする必要があり、その意思表示が賃借人の一部に対してされたにすぎないときは、これを受けた者との関係においてもその効力を生じないとされた事例 |
||
| 233 | S53.12.22 |
土地賃借権が賃貸人の承諾を得て旧賃借人から新賃借人に移転された場合であっても、敷金に関する敷金交付者の権利義務関係は、特段の事情のない限り、新賃借人に承継されないとした事例 |
||
| 234 | S53.12.22 |
債務の弁済供託により譲渡担保権が消滅した場合にも、民法496条2項が類推適用され、譲渡担保権が被担保債権の弁済供託により消滅した場合は、弁済者は供託物を取り戻すことができず、また、供託物を取り戻したときであっても譲渡担保権は復活しないとした事例 |
||
| 235 | S53.12.20 |
共同相続人の一人によって相続権を侵害された共同相続人のその侵害の排除を求める請求には民法884条の適用があるとされた事例 |
||
| 236 | S53.12.14 |
土地賃借権の無断譲受人による土地の使用が賃借意思に基づくものではないとして、賃借権の時効取得が否定された事例 |
||
| 237 | S53.12.5 |
土地の賃貸人が、一括して賃貸した土地の一部につき賃貸借契約を解除し、賃借人に対し同部分については損害金として残余の部分については賃料として金員の支払を求め、賃借人が土地の全部につき全額を賃料として弁済のため供託した場合には、その供託は賃料部分に関しては有効な弁済供託であるとした事例 |
||
| 238 | S53.11.30 |
注文者の請負人に対する目的物の瑕疵修補に代わる損害賠償債権を自働債権とし請負人の注文者に対する工事代金債権を受働債権とする相殺が当事者間の特約により許されないとされた事例 |
||
| 239 | S53.10.5 |
不動産の引渡請求権者は、目的不動産についてされた債務者の処分行為を詐害行為として取り消す場合に、直接自己に対する所有権移転登記手続を請求することはできないとされた事例 |
||
| 240 | S53.9.29 |
土地及びその地上建物の所有者が建物につき抵当権を設定したときは、土地の所有権移転登記を経由していなくても、法定地上権の成立を妨げないとした事例 |
||
| 241 | S53.9.21 |
請負人の注文者に対する報酬債権と注文者の請負人に対する目的物の瑕疵修補に代わる損害賠償債権とは、両債権額が異なる場合であっても相殺できるとされた事例 |
||
| 242 | S53.9.7 |
第三者が賃借土地の上に存する建物の所有権を取得した場合において、賃貸借契約が賃借権の無断譲渡を理由として解除されたときは、その後に賃料相当損害金の不払が生じても、借地法10条に基づく建物買取請求権は消滅しないとした事例 |
||
| 243 | S53.9.7 |
農地につき売買契約が二重に締結され、各買主が所有権移転の仮登記を経由した後、第二買主が農地法の手続を行い売買契約の効力を発生させた上農地を宅地としたときは、売主と第一の買主間の売買契約はその効力を生じ、第一の買主は第二の買主に対し仮登記に基づく本登記の承諾を求めることができるとした事例 |
||
| 244 | S53.7.17 |
相殺の計算をするにあたっては、民法506条の規定に則り、双方の債権が相殺適状となった時期を標準として双方の債権額を定め、その対当額において差引計算をすべきであるとされた事例 |
||
| 245 | S53.7.17 |
建物の社会的残存耐用年数が約10年、建物価格が702万円余の鑑定評価書がある場合において、特段の理由なく建物を取引上無価値と認め、借地法10条の建物買取請求権の成立を否定するのは違法であるとされた事例 |
||
| 246 | S53.7.13 |
共同相続人の1人が遺産を構成する特定の不動産について、同人の有する共有持分権を第三者に譲り渡した場合については、民法905条の規定を適用又は類推適用することはできないとされた事例 |
||
| 247 | S53.7.10 |
登記権利者及び登記義務者双方から登記手続の委託を受けた司法書士が登記義務者から登記手続に必要な書類の返還を求められた場合でも、登記権利者に対する関係ではその返還を拒むべき委任契約上の義務があるとした事例 |
||
| 248 | S53.7.4 |
債務者所有の不動産と物上保証人所有の不動産とを共同抵当の目的として順位を異にする数個の抵当権が設定されている場合において、物上保証人所有の不動産について先に競売がされ、その競落代金の交付により一番抵当権者が弁済を受けたときは、後順位抵当権者は、物上保証人に移転した債務者所有の不動産に対する一番抵当権から優先して弁済を受けることができるとされた事例 |
||
| 249 | S53.7.4 |
営造物の通常の用法に即しない行動の結果事故が生じた場合において、その営造物として本来具有すべき安全性に欠けるところがなく、右行動が設置管理者において通常予測することのできないものであるときは、右事故が営造物の設置又は管理の瑕疵によるものであるということはできないとされた事例 |
||
| 250 | S53.6.29 |
賃貸中の不動産に対する競売開始決定の差押の効力発生後賃貸人のした賃借権譲渡の承諾は、特段の事情のない限り、右差押の効力によつて禁止される処分行為にあたらず、譲受人は、賃借権の取得をもって競落人に対抗することができるとされた事例 |
||
| 251 | S53.5.25 |
自称代理人が目的不動産の登記済権利証、所有者の白紙委任状、印鑑証明書等を所持し行った譲渡担保契約の締結及び金銭の借入につき、その取引の相手方が、自称代理人の代理権の有無について直接所有者に問い合わせるなどの調査をせず代理権限があると信じたことが、民法110条の「正当な理由」に該当しないとされた事例 |
||
| 252 | S53.4.11 |
共有不動産の分割により他の共有者の有していた持分を取得することは、地方税法73条の2第1項にいう「不動産の取得」にあたり、不動産取得税の課税対象となるとした事例 |
||
| 253 | S53.3.6 |
不動産の占有主体に変更があって承継された二個以上の占有が併せて主張された場合、民法162条2項にいう占有者の善意・無過失は、その主張にかかる最初の占有者につきその占有開始の時点において判定すれば足りるとされた事例 |
||
| 254 | S53.2.24 |
共同相続人の一人が他の共同相続人の全部又は一部の者の後見をしている場合において、後見人が被後見人全員を代理してする相続の放棄は、後見人みずからが相続の放棄をしたのちにされたか、又はこれと同時にされたときは利益相反行為にあたらないとされた事例 |
||
| 255 | S53.2.24 |
・賃料増額請求が争われた場合における増額分の賃料は、原則として、その債権の存在を認める裁判が確定した日の属する年分の所得の計算上、収入金額に算入されるとした事例 |
||
| 256 | S53.2.16 |
農地法の不在地主による小作地の所有禁止の規定は、憲法29条に違反しないとされた事例 |
||
| 257 | S53.2.16 |
夫婦の一方の特有財産である資産を財産分与として他方に譲渡することは、所得税法33条1項にいう「資産の譲渡」にあたり、譲渡所得を生ずるとした事例 |
||
| 258 | S52.12.23 |
整地請負契約の解除の認定において、一部解除の認定は相当でなく、契約全部を解除する旨の意思表示をしたと認定するのが相当であるとされた事例 |
||
| 259 | S52.12.23 |
建物収去土地明渡の確定判決の基礎となった事実審口頭弁論の終結後に債務者から建物の所有権を取得した者は、その終結前に経由していた所有権移転仮登記に基づく本登記を経由した場合であっても、仮登記時にさかのぼって被告適格を承継するものではなく、口頭弁論終結後の承継人にあたるとした事例 |
||
| 260 | S52.12.19 |
建物所有目的の土地の賃貸借契約において、賃借人が借地期間の経過と同時に地上建物を賃貸人に贈与する旨の特約は、同特約によって賃借人が受ける不利益が補償される特段の事情がないときは、借地法11条により無効であるとされた事例 |
||
| 261 | S52.12.8 |
民法上の組合所有の不動産を理事名義に登記することを承諾した組合員が、組合から不動産を譲り受けた後も理事名義のままにしていたが、その後理事より第三者が譲渡を受け所有権移転登記を経由した場合、組合員は理事の所有権取得の無効をもって善意無過失の第三者に対抗することができないとされた事例 |
||
| 262 | S52.10.11 |
土地及びその地上の非堅固建物の所有者が土地につき抵当権を設定したのち地上建物を取り壊して堅固建物を建築した場合に、堅固建物の所有を目的とする法定地上権が成立するとされた事例 |
||
| 263 | S52.9.29 |
土地の管理権を与えられ他に賃貸する権限を有していると称する者との間で締結された賃貸借契約に基づき、賃借人が平穏公然に土地の継続的な用益をしていた事案において、賃借人の土地賃借権の時効取得を認めた事例 |
||
| 264 | S52.9.27 |
土地の賃借人は、所有建物につき債権担保のため債権者名義に所有権移転登記をした場合、その後に土地の所有権を譲り受けた第三者に対し、建物保護に関する法律第1条による土地賃借権を対抗することができないとした事例 |
||
| 265 | S52.6.20 |
借地上の建物の譲受人は、地主から提起された建物収去土地明渡請求訴訟の事実審口頭弁論終結後においても、建物買取請求権を行使することができるとされた事例 |
||
| 266 | S52.6.14 |
遺言者が、公正証書による遺言をするにあたり、公証人があらかじめ筆記した遺言内容を読み聞かせたのに対し、遺言者が単にうなづくのみであって、立会証人の一人が遺言者の真意を十分に確認することができなかったときは、民法969条2号にいう口授があったものとはいえないとされた事例 |
||
| 267 | S52.5.2 |
建物賃貸において賃貸人が受領した保証金のうち、特約により返還を要しないとした部分は、賃貸人の受領した年の不動産所得の収入金額であるとされた事例 |
昭52(行ツ)18号(裁判所HP未登載) |
|
| 268 | S52.4.28 |
道路について、黙示的に公用が廃止されたものとして取得時効の成立が認められた事例 |
||
| 269 | S52.4.15 |
書証の成立の真正についての自白は裁判所を拘束しないとされた事例 |
||
| 270 | S52.4.4 |
農地の売買契約について、知事の許可を受ける前であつても、買主が残代金全額を支払いのため提供したときは、契約の履行の着手があったと解されるとした事例 |
||
| 271 | S52.3.31 |
履行不能における債務者の責に帰すべからざる事由とは、債務者に故意・過失がないか、又は債務者に債務不履行の責任を負わせることが信義則上酷に失すると認められるような事由をいうとされた事案 |
||
| 272 | S52.3.15 |
賃貸人が地上の建物の不存在を理由に、借地人の借地法4条1項に基づく借地権の更新請求権がないと主張することが信義則上許されないとされた事例 |
||
| 273 | S52.3.11 |
土地の賃借人が地上に所有する建物に抵当権を設定しその登記を経たのちに賃貸人の承諾を得て賃借人から土地の賃借権のみを譲り受けた者は、抵当権の実行により競落人が建物の所有権とともに土地の賃借権を取得したときに競落人との関係において賃借権を失い、競落人が右賃借権の取得につき賃貸人の承諾を得たときに賃貸人との関係においても賃借人の地位を失うとした事例 |
||
| 274 | S52.3.3 |
農地の賃借人が所有者から農地を買い受けたときは、農地調整法4条所定の都道府県知事の許可又は市町村農地委員会の承認を得なかったとしても、買主は、売買契約が締結されその代金が支払われた時に、民法185条にいう新権原により所有の意思をもって農地の占有を始めたものというべきであるとされた事例 |
||
| 275 | S52.2.22 |
請負契約において仕事が完成しない間に注文者の責に帰すべき事由によりその完成が不能となった場合には、請負人は自己の残債務を免れるが、民法536条2項により、注文者に請負代金全額を請求することができ、ただ、自己の債務を免れたことにより得た利益を注文者に償還すべきであるとされた事例 |
||
| 276 | S52.2.17 |
農地を目的とする売買契約締結後に買主が農地を宅地化した事案において、売買契約が知事の許可なしに効力を生ずるとされた事例 |
||
| 277 | S52.1.20 |
土地区画整理法による換地処分がされた場合、従前の土地に存在した未登記賃借権は、これについて同法85条のいわゆる権利申告がされていないときでも、換地上に移行して存続するとした事例 |
||
| 278 | S51.12.24 |
公共用財産が、長年事実上公の目的に供用されることなく放置され、公共用財産としての形態、機能を全く喪失した場合には、公共用財産について黙示的に公用が廃止されたものとして、その物を平穏かつ公然に占有した者の取得時効の成立を認めた事例 |
||
| 279 | S51.12.20 |
仲介人に売主への本件土地建物の引渡し等の催告を依頼し、また所有権移転登記手続請求の訴訟を提起するとともに、売主に代金の受け取りを求めたこと等により、買主の契約の履行の著手を認めた事例 |
||
| 280 | S51.12.20 |
農地の買主が農地法5条の許可申請手続に協力しない場合でも、売買代金が完済されているときは、特段の事情のない限り、売主は買主が協力をしないことを理由に売買契約を解除することはできない |
||
| 281 | S51.12.17 |
賃借人が賃料の支払を1か月分でも怠ったときは建物賃貸借契約は当然解除となる旨の訴訟上の和解条項に基づき、賃貸人が賃借人の賃料1か月分の賃料延滞により契約解除を求めた事案において、延滞事情の考慮等から信頼関係が賃貸借契約の当然解除を相当とする程度にまで破壊されたといえないとして、その請求を棄却した事例 |
||
| 282 | S51.12.14 |
賃貸人が賃料延滞を理由として土地賃貸借契約を解除するには、賃借人に対して催告すれば足り、地上建物の借家人に対して延滞賃料の支払の機会を与えなければならないものではないとした事例 |
||
| 283 | S51.12.2 |
所有者の無権代理人から農地を買い受けた小作人が、新権原による自主占有を開始したものとされ占有の始め過失がないとされた事例 |
||
| 284 | S51.12.2 |
双務契約の当事者の一方が、相手方の債務と同時履行の関係にある自らの反対給付の提供をすることなしに、相手方の履行遅滞を理由としてした契約解除は、相手方の履行遅滞があれば催告を要することなく契約を解除しうる旨の特約がある場合においても、その効力を生じないとされた事例 |
||
| 285 | S51.11.5 |
不動産の譲渡による所有権移転登記請求権は、譲渡によって生じた所有権移転の事実が存する限り独立して消滅時効にかからないとした事例 |
||
| 286 | S51.10.12 |
不動産取得税の5年の消滅時効の起算日は、登記又は申告等の日を基準とすべきでなく、実際に取得した日であるとした事例 |
||
| 287 | S51.10.8 |
民法388条により抵当権設定者が法定地上権を設定したとみなされるためには、抵当権設定当時に土地とその地上建物が同一の所有者に属することを要し、これらが別個の所有者に属するときには法定地上権を設定したとみなすことはできず、この理は両所有者の間に親子・夫婦の関係があるときでも同様であるとした事例 |
||
| 288 | S51.10.1 |
借地契約の法定更新に際し、賃貸人の請求があれば当然に賃貸人に対する賃借人の更新料支払義務が生ずる旨の商慣習又は事実たる慣習は存在しないとした事例 |
||
| 289 | S51.9.21 |
譲渡担保の目的不動産に先順位根抵当権が設定された場合には、特別の事情がない限り、目的不動産の適正な評価額から根抵当権の極度額を控除した残余価額と当該譲渡担保の被担保債権額とを比較して、清算金債務の有無及び数額を確定すべきとされた事例 |
||
| 290 | S51.9.21 |
譲渡担保の目的とされた借地上の建物を債権者が帰属清算の方法により取得する場合において、土地賃借権の譲渡につき賃貸人の承諾が不可能又は著しく困難と認められるときは、債権者は建物買取請求権を行使する場合の対価をもって、当該建物の適正評価額として清算金額を算定することができるとした事例 |
||
| 291 | S51.9.7 |
共有にかかる土地が不法に占有されたことを理由として、共有者の全員又はその一部の者から不法占有者に対してその損害賠償を求める場合には、共有者は、それぞれその共有持分の割合に応じて請求をすべきものであり、その割合を超えて請求をすることは許されないとした事例 |
||
| 292 | S51.8.30 |
遺留分権利者が受贈者又は受遺者に対し民法1041条1項の価額弁償を請求する訴訟における贈与又は遺贈の目的物の価額算定の基準時は、訴訟の事実審口頭弁論終結の時であるとされた事例 |
||
| 293 | S51.8.30 |
山林「a」の仮換地「A」について仮換地自体に着目して売買契約が締結されたのち、仮換地の指定の変更により、山林「a」の一部である山林「a’」につき仮換地「A」と同一性のある仮換地「A’」が、山林「a」の残部である山林「b」につき仮換地「B」が各指定され、次いで仮換地がそのまま換地「A”」、換地「B’」と定められた場合には、買主は換地「A”」の所有権を取得するにすぎず換地「B’」の所有権を取得するものではないとされた事例 |
||
| 294 | S51.7.19 |
相続人が遺言の執行としてされた遺贈による所有権移転登記の抹消登記手続を求める訴については、遺言執行者がある場合でも、受遺者が被告となるとされた事例 |
||
| 295 | S51.7.8 |
使用者がその事業の執行につき、被用者の惹起した自動車事故により損害を被った場合において、信義則上被用者に対し、右損害の一部についてのみ賠償及び求償の請求が許されるにすぎないとされた事例 |
||
| 296 | S51.6.25 |
電気器具の販売会社が継続的商取引上の債権担保のため、保証人本人の実印の押してある本人名義の契約書と本人の印鑑証明書とを持参した代理人との間で連帯根保証契約を締結した場合に、民法110条の正当理由があるとはいえないとされた事例 |
||
| 297 | S51.6.21 |
転貸借の目的となっている土地の賃借権の譲渡を受けた者は、賃借権の譲渡人から転借人に対する譲渡の通知又は譲渡についての転借人の承諾がない以上、転借人に対し、その転貸人としての地位を主張することができないとされた事例 |
||
| 298 | S51.6.17 |
農地買収・売渡処分が買収計画取消判決の確定により失効した場合、被売渡人から土地を買い受けた者が、土地返還請求訴訟提起後に買収処分の無効に帰すべきことを疑わずに有益費を支出したとしても、有益費償還請求権に基づく土地留置権を行使することはできないとした事例 |
||
| 299 | S51.6.3 |
増改築禁止の特約がある建物所有を目的とする土地賃貸借契約において、建物の増改築を理由とする解除権の行使が信義則上許されないとされた事例 |
||
| 300 | S51.5.25 |
消滅時効の援用が権利濫用にあたるとされた事例 |
||
| 301 | S51.4.23 |
財団法人が寄附行為の目的の範囲外の事業を行うためにした不動産の売却につき、本件売買の時から7年10か月余を経た後に訴を提起し、売買の無効を主張して売買物件の返還又は返還に代わる損害賠償を請求することは、信義則上許されないとした事例 |
||
| 302 | S51.4.9 |
復代理人が委任事務を処理するにあたり受領した物を代理人に引き渡したときは、特別の事情がない限り、復代理人の本人に対する受領物引渡義務は消滅するとされた事例 |
||
| 303 | S51.4.8 |
先順位受附の登記申請人が、後順位受附の登記申請に基づき不動産登記法48条に違反してされた登記につき、同条違反だけを理由にその抹消登記手続を求めることは許されないとされた事例 |
||
| 304 | S51.3.26 |
不動産取得税の納税者が同税の賦課処分の取消訴訟において、固定資産課税台帳に登録された当該不動産の価格が客観的に適正な価格と異なると主張して課税標準たる価格を争うことはできないとされた事例 |
||
| 305 | S51.3.19 |
同一不動産を目的とする後順位仮登記担保権者は、債務者のために先順位仮登記担保権者の被担保債権を弁済するにつき民法500条(法定代位)にいう「正当の利益」を有するとされた事例 |
||
| 306 | S51.3.18 |
相続人が被相続人から贈与された金銭を、いわゆる特別受益として遺留分算定の基礎となる財産の価額に加える場合には、贈与の時の金額を相続開始の時の貨幣価値に換算した価額をもって評価すべきとされた事例 |
||
| 307 | S51.3.4 |
建造物侵入罪の客体となるいわゆる囲繞地にあたるとされた事例 |
||
| 308 | S51.3.4 |
建物の貸室の賃貸借契約に際し賃借人から建物所有者である賃貸人に差し入れられた保証金がいわゆる建設協力金であり、他に敷金も差し入れられているなどの判示の事実関係のもとでは、建物の所有権を譲り受けた新賃貸人は、旧賃貸人の保証金返還債務を承継しないとした事例 |
||
| 309 | S51.2.27 |
土地に対する抵当権設定当時、その地上に建物が存在しなかったときは、たとえ抵当権者において建物の築造をあらかじめ承認した事実があっても、民法388条(法定地上権)の適用がないとされた事例 |
||
| 310 | S51.2.17 |
不動産の強制競売において、競落許可決定が確定して競落人がその代金を全額支払い競落不動産の所有権を取得したときは、その後、執行債権が消滅したことを理由に強制競売手続開始決定が取り消され、競売申立が却下されても、競落の効果に影響を及ぼさないとされた事例 |
||
| 311 | S51.2.13 |
売買契約に基づき目的物の引渡を受けていた買主は、民法561条(他人の権利の売買における売主の担保責任)により契約を解除した場合でも、原状回復義務の内容として、解除までの間目的物を使用したことによる利益を売主に返還しなければならないとされた事例 |
||
| 312 | S51.2.6 |
借地契約上の借主の権利を被保全権利とする処分禁止仮処分命令に違反してされた貸主の処分行為による第三者の権利取得は、借主との関係において全面的に否定されるものではなく、第三者は権利取得を理由として、借主の契約上の権利の実現を妨げることが許されないものにすぎないとした事例 |
RETIO : (一財)不動産適正取引推進機構 機関誌