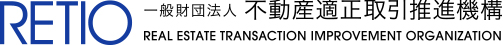その他 - その他
該当件数 件
※判 決 日 クリックにより年月日順の並び替えができます。
| No. | 判決日 | 概要 | 事件番号 | RETIO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R4.12.12 |
賃貸住宅に係る賃料債務等の保証委託及び連帯保証に関する契約書中の、「賃料等の不払があるときに連帯保証人が無催告にて賃貸借契約を解除することができる旨を定める条項、賃料等の不払等の事情が存するときに連帯保証人が賃貸住宅の明渡しがあったものとみなすことができる旨を定める条項」の消費者契約法10条に規定する消費者契約の条項該当性について判断された事例 |
||
| 2 | R4.7.19 |
宮古島市水道事業給水条例16条3項は、水道事業者である市が水道法15条2項ただし書により水道の使用者に対し給水義務を負わない場合において、使用者との関係で給水義務の不履行に基づく損害賠償責任を負うものではないことを確認した規定にすぎないとされた事例 |
||
| 3 | R4.4.19 |
相続税の課税価格に算入される不動産の価額を財産評価基本通達の定める方法により評価した価額を上回る価額によるものとすることが租税法上の一般原則としての平等原則に違反しないとされた事例 |
||
| 4 | R4.3.22 |
不動産取得税の課税に関し、複数の不動産を一括して分割の対象とする共有物の分割により不動産を取得した場合における持分超過部分の有無及び額については、分割の対象とされた個々の不動産ごとに、分割前の持分の割合に相当する価格と分割後に所有することとなった不動産の価格とを比較して判断すべきとした事例 |
||
| 5 | R2.9.18 |
不動産競売手続において区分所有法所定の先取特権を有する債権者の配当要求により、配当要求債権に消滅時効の中断の効力が生ずるためには、民事執行法181条1項各号に掲げる文書により債権者が先取特権を有することが不動産競売手続において証明されれば足りるとされた事例 |
||
| 6 | R2.9.11 |
請負契約に基づく請負代金債権と同契約の目的物の瑕疵修補に代わる損害賠償債権の一方を本訴請求債権とし、他方を反訴請求債権とする本訴及び反訴の係属中における、本訴請求債権を自働債権とし反訴請求債権を受働債権とする相殺の抗弁を主張することは許されるとされた事例 |
||
| 7 | R2.9.8 |
請負人である破産者の支払の停止の前に締結された請負契約に基づく注文者の破産者に対する違約金債権の取得が、破産法72条2項2号にいう「前に生じた原因」に基づく場合に当たり,違約金債権を自働債権とする相殺が許されるとされた事例 |
||
| 8 | R2.3.24 |
家屋の評価の誤りに基づき固定資産税等の税額が過大に決定されたことによる損害賠償請求権に係る民法724条後段所定の除斥期間は、当該年度の固定資産税等に係る賦課決定がされ所有者に納税通知書が交付された時から進行するとされた事例 |
||
| 9 | R2.3.19 |
固定資産評価基準により隣接する2筆以上の宅地を一画地として認定して画地計算法を適用する場合において、各筆の宅地の評点数は、画地計算法の適用により算出された当該画地の単位地積当たりの評点数に、各筆の宅地の地積を乗ずることによって算出されるとした事例 |
||
| 10 | R2.3.6 |
不動産の所有権移転登記の申請の委任を受けた司法書士に当該申請の委任者以外の者との関係において注意義務違反があるとした原審の判断に違法があるとされた事例 |
||
| 11 | R1.8.27 |
相続の開始後認知によって相続人となった者が遺産の分割を請求しようとする場合において、他の共同相続人が既に当該遺産の分割をしていたときは、民法910条に基づき支払われるべき価額の算定の基礎となる遺産の価額は、当該分割の対象とされた積極財産の価額であるとされた事例 |
||
| 12 | R1.8.9 |
民法916条にいう「その者の相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、相続の承認又は放棄をしないで死亡した者の相続人が、当該死亡した者からの相続により、当該死亡した者が承認又は放棄をしなかった相続における相続人としての地位を、自己が承継した事実を知った時をいうとした事例 |
||
| 13 | R1.7.18 |
土地改良区が河川法23条の許可に基づいて取水した水が流れる水路への第三者の排水により当該水路の流水についての当該土地改良区の排他的管理権が侵害されたとした原審の判断に違法があるとされた事例 |
||
| 14 | R1.7.18 |
都市計画区域内にある公園について、湖南市地域ふれあい公園条例(平成17年湖南市条例第35号)に基づく公告がされたことをもって、都市公園法2条の2に基づく公告がされたとはいえないとされた事例 |
||
| 15 | R1.7.16 |
固定資産課税台帳に登録された価格を不服として固定資産評価審査委員会に審査の申出をした者は、同委員会による審査の際に主張しなかった事由であっても、当該申出に対する同委員会の決定の取消訴訟において、その違法性を基礎付ける事由として、これを主張することが許されるとした事例 |
||
| 16 | H31.4.9 |
固定資産課税台帳に登録された土地の価格について、当該土地が調整池の用に供されその機能を保持することが商業施設に係る開発行為の許可条件になっていることを理由に地目を宅地と認定するなどして算出された上記価格が固定資産評価基準によって決定される価格を上回るものではないとした原審の判断に違法があるとされた事例 |
||
| 17 | H31.3.18 |
相続財産についての情報が被相続人に関するものとしてその生前に個人情報保護法2条1項にいう「個人に関する情報」に当たるものであったとしても、そのことから直ちに、当該情報が当該相続財産を取得した相続人又は受遺者に関するものとして上記「個人に関する情報」に当たるということはできないとされた事例 |
||
| 18 | H31.1.23 |
性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律3条1項4号は、憲法13条、14条1項に違反しないとされた事例 |
||
| 19 | H30.12.21 |
弁護士法23条の2第2項に基づく照会をした弁護士会が、その相手方に対し、当該照会に対する報告をする義務があることの確認を求める訴えは、確認の利益を欠くものとして不適法であるとされた事例 |
||
| 20 | H30.7.17 |
固定資産課税台帳の土地の登録価格について、接面道路が建築基準法42条1項3号の要件を満たすか不明にもかかわらず、同道路に該当する旨の市長の判定がされていること等を理由に、接面道路が同道路に該当することを前提とする価格の決定は適法とした原審の判断に違法があるとされた事例 |
||
| 21 | H30.2.23 |
抵当権の被担保債権が免責許可の決定の効力を受ける場合における当該抵当権自体の消滅時効は、民法167条2項所定の20年の消滅時効にかかるとされた事例 |
||
| 22 | H29.10.23 |
個人情報の漏えいを理由とする損害賠償請求訴訟における損害に関する原審の判断に審理不尽の違法があるとされた事例 |
||
| 23 | H29.2.28 |
私道の用に供されている宅地の相続税に係る財産の評価における減額の要否及び程度は、私道としての利用に関する建築基準法等の法令上の制約の有無のみならず、当該宅地の位置関係、形状等や道路としての利用状況、これらを踏まえた道路以外の用途への転用の難易等に照らし、当該宅地の客観的交換価値に低下が認められるか否か、また、その低下がどの程度かを考慮して決定する必要があるとされた事例 |
||
| 24 | H28.12.19 |
地方税法施行令附則6条の17第2項にいう「居住の用に供するために独立的に区画された部分が100以上ある共同住宅等」に当たるか否かは、1棟の共同住宅等ごとに判断すべきであるとした事例 |
||
| 25 | H28.10.18 |
弁護士法23条の2第2項に基づく照会に対する報告を拒絶する行為が、同照会をした弁護士会の法律上保護される利益を侵害するものとして当該弁護士会に対する不法行為を構成することはないとした事例 |
||
| 26 | H28.6.27 |
認定司法書士が代理した債務整理につき、当該債務整理の対象となる個別の債権価額が司法書士法3条1項7号規定の額を超え、裁判外の和解について代理することができないとして、受領した報酬につき不法行為による損害賠償として報酬相当額の支払義務を負うとされた事例 |
||
| 27 | H28.6.27 |
市が土地開発公社の取得した土地をその簿価に基づき正常価格の約1.35倍の価格で買い取る売買契約を締結した市長の判断が裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用するものとして違法となるとはいえないとした事例 |
||
| 28 | H28.6.3 |
いわゆる花押を書くことは、自筆証書遺言の押印の要件を満たさないとされた事例 |
||
| 29 | H28.5.25 |
ガス抜き配管内で結露水が滞留してメタンガスが漏出したことによって生じた温泉施設の爆発事故について,設計担当者に結露水の水抜き作業に係る情報を確実に説明すべき業務上の注意義務があったとされた事例 |
||
| 30 | H28.4.28 |
破産手続開始前に成立した第三者のためにする生命保険契約に基づき破産者である死亡保険金受取人が有する死亡保険金請求権は、破産法34条2項にいう「破産者が破産手続開始前に生じた原因に基づいて行うことがある将来の請求権」に該当するものとして、死亡保険金受取人の破産財団に属するとした事例 |
||
| 31 | H28.3.31 |
宅建業法30条1項前段所定の取戻事由が発生した場合において、取戻公告がされなかったときは、宅建業者の営業保証金の取戻請求権の消滅時効は、当該事由が発生した時から10年を経過した時から進行するとされた事例(破棄自判・RETIO101-118の上告審) |
RETIO 123-063
|
|
| 32 | H28.3.29 |
信託契約の受託者が所有する複数の不動産の固定資産税に係る滞納処分としてされた、信託財産である土地とその上の家屋に係る賃料債権に対する差押えが適法とされた事例 |
||
| 33 | H28.2.26 |
・相続の開始後認知によって相続人となった者が、他の共同相続人に対して民法910条に基づき価額の支払を請求する場合における遺産の価額算定の基準時は、価額の支払を請求した時であるとした事例 |
||
| 34 | H28.1.12 |
信用保証協会と金融機関との間で保証契約が締結され融資が実行された後に主債務者が反社会的勢力であることが判明した場合において、信用保証協会の保証契約の意思表示に要素の錯誤がないとされた事例 |
||
| 35 | H28.1.12 |
信用保証協会と金融機関との間で保証契約が締結され融資が実行された後に主債務者が反社会的勢力であることが判明した場合において、信用保証協会の保証契約の意思表示に要素の錯誤がないとされた事例 |
||
| 36 | H28.1.12 |
信用保証協会と金融機関との間で保証契約が締結されて融資が実行された後に主債務者が反社会的勢力であることが判明した場合において、信用保証協会の保証契約の意思表示に要素の錯誤がないとされた事例 |
||
| 37 | H27.12.14 |
市街化調整区域内にある土地を開発区域とする開発許可に関する工事が完了し、当該工事の検査済証が交付された後においても、当該開発許可の取消しを求める訴えの利益は失われないとされた事例 |
||
| 38 | H27.11.20 |
遺言者が自筆証書である遺言書の文面全体に故意に斜線を引く行為が、民法1024条前段所定の「故意に遺言書を破棄したとき」に該当し遺言を撤回したものとみなされた事例 |
||
| 39 | H27.11.19 |
保証人が主たる債務者に対して取得した求償権の消滅時効の中断事由がある場合であっても、共同保証人間の求償権について消滅時効の中断の効力は生じないとされた事例 |
||
| 40 | H27.7.17 |
登記簿の表題部の所有者欄に「大字西」などと記載されている土地につき、地方税法343条2項後段の類推適用により、当該土地の所在する地区の住民により組織されている自治会又は町会が固定資産税の納税義務者に当たるとした原審の判断に違法があるとされた事例 |
||
| 41 | H27.3.27 |
市営住宅条例で入居者が暴力団員であることが判明した場合に明渡請求できる定めは憲法に違反しないとされた事例 |
RETIO 124-131
|
|
| 42 | H27.2.17 |
事前求償権を被保全債権とする仮差押えは、事後求償権の消滅時効をも中断する効力を有するとした事例 |
||
| 43 | H26.12.12 |
相続税につき減額更正がされた後に増額更正がされた場合において,上記増額更正により新たに納付すべきこととなった税額に係る部分について上記相続税の法定納期限の翌日からその新たに納付すべきこととなった税額の納期限までの期間に係る延滞税が発生しないとされた事例 |
||
| 44 | H26.12.12 |
共同相続された委託者指図型投資信託の受益権につき、相続開始後に元本償還金又は収益分配金が発生し預り金として上記受益権の販売会社における被相続人名義の口座に入金された場合に、共同相続人の1人が自己の相続分に相当する金員の支払を請求することはできないとした事例 |
||
| 45 | H26.10.9 |
労働大臣が石綿製品の製造等を行う工場又は作業場における石綿関連疾患の発生防止のために労働基準法に基づく省令制定権限を行使しなかったことが国家賠償法1条1項の適用上違法であるとはいえないとした原審の判断に違法があるとされた事例 |
||
| 46 | H26.9.25 |
土地又は家屋につき、賦課期日の時点において登記簿又は土地補充課税台帳若しくは家屋補充課税台帳に登記又は登録がされていない場合において、賦課決定処分時までに賦課期日現在の所有者として登記又は登録されている者は、当該賦課期日に係る年度における固定資産税の納税義務を負うとした事例 |
||
| 47 | H26.4.7 |
約款で暴力団員からの貯金の新規預入申込みを拒絶する旨定めている銀行の担当者に暴力団員であるのに暴力団員でないことを表明、確約して口座開設等を申し込み通帳等の交付を受けた行為が、詐欺罪に当たるとされた事例 |
||
| 48 | H26.3.28 |
暴力団関係者の利用を拒絶しているゴルフ場において暴力団関係者であることを申告せずに施設利用を申し込む行為が、詐欺罪にいう人を欺く行為に当たらないとされた事例 |
||
| 49 | H26.3.28 |
入会の際に暴力団関係者を同伴しない旨誓約したゴルフ倶楽部会員において、同伴者が暴力団関係者であることを申告せずに同人に関するゴルフ場の施設利用を申し込み、施設を利用させた行為が、詐欺罪に当たるとされた事例 |
||
| 50 | H26.3.28 |
暴力団関係者の利用を拒絶しているゴルフ場において暴力団関係者であることを申告せずに施設利用を申し込む行為が、詐欺罪にいう人を欺く行為に当たらないとされた事例 |
||
| 51 | H26.3.14 |
時効の期間の満了前6箇月以内の間に精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者に法定代理人がない場合において、少なくとも、時効の期間の満了前の申立てに基づき後見開始の審判がされたときは、民法158条1項の類推適用により、法定代理人が就職した時から6箇月を経過するまでの間は、その者に対して時効は完成しないとされた事例 |
||
| 52 | H26.2.25 |
・共同相続された委託者指図型投資信託の受益権は、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはないとした事例 |
||
| 53 | H26.2.14 |
共同相続人のうち自己の相続分の全部を譲渡した者は、遺産確認の訴えの当事者適格を有しないとした事例 |
||
| 54 | H26.1.14 |
認知者は、民法786条に規定する利害関係人に当たり、自らした認知の無効を主張することができ、この理は、認知者が血縁上の父子関係がないことを知りながら認知をした場合においても異ならないとした事例 |
||
| 55 | H25.11.29 |
共有物について、遺産分割前の遺産共有持分と他の共有持分とが併存する場合、共有者が遺産共有持分と他の共有持分との間の共有関係の解消を求める裁判上の手続は民法258条に基づく共有物分割訴訟であり、共有物分割の判決によって遺産共有持分権者に分与された財産は遺産分割の対象となり、共有関係の解消については同法907条に基づく遺産分割によるべきとされた事例 |
||
| 56 | H25.10.25 |
土地収用法94条7項又は8項の規定による収用委員会の裁決の判断内容が損失の補償に関する事項に限られている場合であっても、その名宛人は、上記裁決の取消訴訟を提起することができるとした事例 |
||
| 57 | H25.9.13 |
保証人が主たる債務を相続したことを知りながら保証債務の弁済をした場合、当該弁済は、特段の事情のない限り、主たる債務者による承認として当該主たる債務の消滅時効を中断する効力を有するとした事例 |
||
| 58 | H25.9.4 |
民法900条4号ただし書前段の規定(非嫡出子の法定相続分の規定)は、遅くとも平成13年7月当時において、憲法14条1項に違反していたとした事例 |
||
| 59 | H25.7.12 |
原審が,壁面に吹き付けられた石綿が露出している建物が通常有すべき安全性を欠くと評価されるようになった時点を明らかにしないまま、同建物の設置又は保存の瑕疵の有無について判断したことに審理不尽の違法があるとされた事例 |
||
| 60 | H25.7.12 |
滞納者と他の者との共有に係る不動産につき、滞納者の持分が国税徴収法47条1項に基づいて差し押さえられた場合における他の共有者は、その差押処分の取消訴訟の原告適格を有するとした事例 |
||
| 61 | H25.7.12 |
固定資産税評価額について、土地の基準年度に係る賦課期日における登録価格が評価基準によって決定される価格を上回る場合には、同期日における当該土地の客観的な交換価値としての適正な時価を上回るか否かにかかわらず、その登録価格の決定は違法となるとされた事例。 |
||
| 62 | H25.6.6 |
・いわゆる明示的一部請求の訴えに係る訴訟において、債権の一部消滅の抗弁に理由があると判断され判決にて債権の総額の認定がされた場合、残部についての消滅時効の中断の効力は生じないとされた事例 |
||
| 63 | H25.4.16 |
債務整理に係る法律事務を受任した弁護士が、特定の債権者の債権につき消滅時効の完成を待つ方針を採る場合において、上記方針に伴う不利益等や他の選択肢を説明すべき委任契約上の義務を負うとされた事例 |
||
| 64 | H25.3.26 |
一級建築士により構造計算書に偽装が行われていた建築物の計画についての建築主事による建築確認が、国家賠償法1条1項の適用上違法となるとはいえないとされた事例 |
||
| 65 | H25.3.22 |
土地区画整理事業の施行地区内の土地について、売買当時、賦課金を課される可能性が存在していたことをもって、民法570 条にいう瑕疵があるとはいえないとされた事例 |
RETIO 117-090
|
|
| 66 | H25.2.28 |
・既に弁済期にある自働債権と弁済期の定めのある受働債権とが相殺適状にあるというためには、受働債権につき、期限の利益を放棄することができるというだけではなく、期限の利益の放棄又は喪失等により、その弁済期が現実に到来していることを要するとされた事例 |
||
| 67 | H24.12.21 |
共有者の1人が共有物を第三者に賃貸して得る収益につき、その持分割合を超える部分の不当利得返還を求める他の共有者の請求のうち、事実審の口頭弁論終結の日の翌日以降の分は、その性質上、将来の給付の訴えを提起することのできる請求としての適格を有しないとされた事例 |
||
| 68 | H24.11.20 |
収用委員会の裁決につき審査請求をすることができる場合に、審査請求がされたときにおける収用委員会の裁決の取消訴訟の出訴期間は、土地収用法133条1項ではなく行政事件訴訟法14条3項の適用により、その審査請求に対する裁決があったことを知った日から6か月以内かつ当該裁決の日から1年以内となるとした事例 |
||
| 69 | H24.4.23 |
住民訴訟の係属中にされたその請求に係る市の損害賠償請求権を放棄する旨の市議会の議決が違法であるとした原審の判断に違法があるとされた事例 |
||
| 70 | H24.3.16 |
取得時効完成後、所有権移転登記前に第三者により設定された抵当権は、特段の事情がない限り、再度の取得時効により消滅するとされた事例 |
RETIO 86-096
|
|
| 71 | H24.2.16 |
従前の宅地が整形で、北側と南側で道路に接していたのに対し、仮換地の形状が一部不整形で、北側と東側で道路に接することとなったマンションの敷地の仮換地指定が、照応の原則を定める土地区画整理法89条1項に違反しないとした事例 |
||
| 72 | H23.12.16 |
建築基準法等の法令の規定に適合しない建物の建築を目的とする請負契約を締結した請負人と注文者が、互いに工事代金支払、損害賠償等を求めて争った事案において、違法建物建築の本工事の請負契約が公序良俗に反し無効とされ、本工事施工開始後に施工された追加変更工事の施工の合意が公序良俗に反せず有効とされた事例 |
RETIO 86-102
|
|
| 73 | H23.11.17 |
公有地に係る土地信託契約において、受益者に対する費用補償請求権を定めた旧信託法(平成18年法律第109号による改正前のもの)36条2項本文の適用を排除する旨の合意が成立していたとはいえないとされた事例 |
||
| 74 | H23.9.30 |
長期譲渡所得に係る損益通算を認めないこととした平成16年法律第14号による改正後の租税特別措置法31条の規定をその施行日より前に個人が行う土地等又は建物等の譲渡について適用するものとしている平成16年法律第14号附則27条1項の規定は、憲法84条の趣旨に反しないとした事例 |
||
| 75 | H23.9.22 |
長期譲渡所得に係る損益通算を認めないこととした平成16年法律第14号による改正後の租税特別措置法31条の規定をその施行日より前に個人が行う土地等又は建物等の譲渡について適用するものとしている平成16年法律第14号附則27条1項の規定は、憲法84条の趣旨に反しないとした事例 |
||
| 76 | H23.7.21 |
建物としての基本的な安全性を損なう瑕疵には、放置するといずれは居住者等の生命、身体又は財産に対する危険が現実化することになる瑕疵も含まれるとされた事例 【H19.7.6最高裁差戻、H23.7.21最高裁差戻、H25.1.29最高裁上告棄却】 |
RETIO 84-101
|
|
| 77 | H23.7.15 |
賃貸借契約書に一義的かつ具体的に記載された更新料条項は、更新料の額が賃料の額、賃貸借契約が更新される期間等に照らし高額に過ぎるなどの特段の事情がない限り、消費者契約法10条により無効ということはできないとされた事例 |
RETIO 115-083
|
|
| 78 | H23.7.12 |
消費者契約である居住用建物の賃貸借契約に付されたいわゆる敷引特約(敷引金の額は月額賃料の3.5倍程度)が、消費者契約法10条により無効ということはできないとされた事例 |
RETIO 83-140
|
|
| 79 | H23.6.7 |
公にされている処分基準の適用関係を示さずにされた建築士法10条1項2号及び3号に基づく一級建築士免許取消処分が、行政手続法14条1項本文の定める理由提示の要件を欠き違法であるとされた事例 |
||
| 80 | H23.6.3 |
土地を時効取得したと主張する者が、当該土地は所有者が不明であるから国庫に帰属していたとして、国に対し当該土地の所有権を有することの確認を求める訴えにつき、確認の利益を欠くとされた事例 |
||
| 81 | H23.4.22 |
契約の一方当事者が当該契約の締結に先立ち,信義則上の説明義務に違反して、当該契約を締結するか否かに関する判断に影響を及ぼすべき情報を相手方に提供しなかった場合には、上記一方当事者は、相手方が当該契約を締結したことにより被った損害につき、不法行為による賠償責任を負うことがあるのは格別、当該契約上の債務の不履行による賠償責任を負うことはないとした事例 |
RETIO 83-124
|
|
| 82 | H23.3.25 |
家屋の建替えにより、固定資産税等の賦課期日に旧居住用家屋が取り壊され存しなかったが、居住用家屋の建築工事が現に進行中であることが客観的に見て取れる状況にあった土地について、当該年度の固定資産税及び都市計画税につき、住宅用地に対する課税標準の特例の適用があるとされた事例 |
||
| 83 | H23.3.24 |
・居住用建物の賃貸借契約に付された敷引特約は、敷引金の額が高額に過ぎると評価されるものは、特段の事情のない限り、消費者契約法10条により無効とされるとした事例 |
RETIO 82-150
|
|
| 84 | H23.2.22 |
「相続させる」旨の遺言は、推定相続人が遺言者の死亡以前に死亡した場合には、特段の事情のない限り、その効力を生じないとして代襲者の上告を棄却した事例 |
RETIO 84-134
|
|
| 85 | H23.2.9 |
権利能力のない社団を債務者とする金銭債権を有する債権者が、当該社団の構成員全員に総有的に帰属し、当該社団のために第三者がその登記名義人とされている不動産に対して仮差押えをする場合における申立ての方法について判断された事例 |
||
| 86 | H23.1.21 |
抵当権設定登記後に賃借権の時効取得に必要な期間、当該不動産を継続的に用益したとしても、賃借人は公売による買受人に対し賃借権の時効取得を主張できないとした事例 |
RETIO 82-182
|
|
| 87 | H22.12.16 |
不動産の所有権が、元の所有者から中間者、現在の所有者に、順次移転したにもかかわらず、登記名義が元の所有者に残っている場合において、現在の所有者が元の所有者に対して直接、真正な登記名義の回復を原因とする所有権移転登記手続を請求することは許されないとした事例 |
RETIO 81-070
|
|
| 88 | H22.10.15 |
被相続人が生前に提起して相続人が承継していた所得税更正処分等の取消訴訟において同処分等の取消判決が確定した場合、被相続人が同処分等に基づき納付していた所得税等に係る過納金の還付請求権は、被相続人の相続財産を構成し相続税の課税財産となるとした事例 |
||
| 89 | H22.10.14 |
数社を介し順次発注された工事の最終の受注者と、最終受注者への発注者との間の請負契約において、発注者が代金の支払を受けた後に最終受注者に代金を支払う旨の合意は、発注者が代金の支払を受けることを停止条件とする旨とはいえず、発注者が代金支払を受けた時点又はその見込みがなくなった時点で支払期限が到来する旨とした事例 |
||
| 90 | H22.9.9 |
土地の賃貸人及び転貸人が、転借人所有の地上建物の根抵当権者に対し、借地権が消滅するおそれが生じたときはその事実を通知をする旨の条項を含む念書を差し入れた場合において、同通知の不履行を理由とした損害賠償請求が認められた事例 |
RETIO 80-146
|
|
| 91 | H22.7.20 |
弁護士資格等がない者らが、ビルの所有者から委託を受け賃借人らと立退交渉を行い、賃貸借契約を合意解除した上で各室を明け渡させた行為について、弁護士法72条違反にあたるとされた事例 |
RETIO 81-102
|
|
| 92 | H22.6.17 |
新築建物を購入した買主らが、当該建物には構造耐力上の安全性を欠くなどの瑕疵があると主張して、その設計、工事の施工等を行った業者らに対し、不法行為に基づく損害賠償等を求めた事案において、購入した新築建物自体が社会経済的価値を有しない場合には、買主から工事施工者等に対する建替え費用相当額の損害賠償請求においてその居住利益を損害額から控除することはできないとされた事例(控訴審 H21.6.4 名古屋高裁 RETIO78-106) |
RETIO 114-074
|
|
| 93 | H22.6.3 |
固定資産税等の税額の過大な決定よって損害を被った納税者は、地方税法432条1項本文に基づく審査の申出及び同法434条1項に基づく取消訴訟等の手続を経るまでもなく、国家賠償請求を行い得るとした事例 |
||
| 94 | H22.4.20 |
共有不動産につき、持分を有しない者がこれを有するものとして共有名義の所有権保存登記がされている場合、共有者の1人は、その持分に対する妨害排除として、登記を実体的権利に合致させるため、持分を有しない登記名義人に対し、自己の持分についての更正登記手続を求めることができるにとどまり、他の共有者の持分についての更正登記手続までを求めることはできないとした事例 |
||
| 95 | H22.4.20 |
市の土地買収につき租税特別措置法所定の特別控除額の特例適用がある旨の市の職員の誤った教示等に従い所得税の申告をし、過少申告加算税の賦課決定等を受けた者への市の損害賠償責任を認め、損害の有無及び額並びに過失相殺の可否について更に審理を尽くさせるため原審に差し戻した事例 |
||
| 96 | H22.4.13 |
都市計画法56条1項の規定に基づく土地の買取りが収用の実質を有しないとして、土地を売却した納税者に対する租税特別措置法上の譲渡所得の特例措置の適用を否定した事例 |
||
| 97 | H22.3.30 |
道路買収により買収地上の建物移転補償金を受けた個人が、当該建物を他に譲渡して曳行移転させた場合において、取壊工事費に相当する補償金部分等のうち、曳行移転費用に充てられた部分は所得税法44条の適用を受け、それ以外の部分についても同条又は措置法33条1項の適用を受ける部分がありうるとした事例 |
||
| 98 | H22.3.16 |
遺言を偽造した相続人に対して、相続欠格事由に該当し、相続人の資格を有しないことの確認を求める訴訟は、固有必要的共同訴訟であって、相続人全員を当事者として提起されるべきであるとされた事例 |
||
| 99 | H22.1.19 |
共有者の1人が共有不動産の賃料収入を全額自己の不動産所得として計算し、所得税等を過大に支払ったとしても、過大に納付した分を含め所得税等の申告納付は自己の事務であり、他人のために事務を管理したということはできず、事務管理は成立しないとして、事務管理に基づく費用償還請求を棄却した事例 |
||
| 100 | H21.12.18 |
遺留分権利者から遺留分減殺請求を受けた受遺者等が、価額弁償の意思表示をしたが、遺留分権利者から目的物の現物返還請求も価額弁償請求もされていない場合において、弁償額につき当事者間に争いがあり、受遺者等が判決により確定されたときは速やかに支払う意思を表明して、弁償額の確定を求める訴えを提起したときは、訴えには確認の利益があるとした事例 |
||
| 101 | H21.12.17 |
市が土地開発公社に対し土地の先行取得を委託する契約の有効性等が争われた事例において、同委託契約は私法上無効とはいえず、また、市が公社の取得した土地を委託契約に基づき売買契約を締結したことが違法ともいえないとした事例 |
||
| 102 | H21.12.17 |
都建築安全条例4条3項に基づく安全認定が行われた上で建築確認がされている場合、建築確認の取消訴訟において安全認定が違法であるために同条1項所定の接道義務の違反があると主張することは安全認定が取り消されていなくても許されるとした事例 |
||
| 103 | H21.12.10 |
国税の滞納者を含む共同相続人の間で成立した遺産分割協議は、滞納者である相続人にその相続分に満たない財産を取得させ、他の相続人にその相続分を超える財産を取得させるものであるときは、国税徴収法39条にいう第三者に利益を与える処分に当たるとされた事例 |
||
| 104 | H21.11.30 |
分譲マンション各住戸のドアポストに政党の活動報告等を記載したビラを投函する目的で、マンション管理組合の意思に反してマンションに立ち入った行為が、刑法130条前段の罪(住居侵入罪)が成立するとされた事例 |
||
| 105 | H21.11.9 |
民法704条(悪意の受益者の返還義務等)後段の損害賠償責任の規定は、悪意の受益者が不法行為の要件を充足する限りにおいて、不法行為責任を負うことを注意的に規定したものにすぎず、悪意の受益者に対して不法行為責任とは異なる特別の責任を負わせたものではないとした事例 |
||
| 106 | H21.9.4 |
貸金業者の借主に対する貸金の支払請求、弁済を受ける行為が不法行為となるのは、貸金業者が当該債権が事実的、法律的根拠を欠くことを知りながら、又は通常の貸金業者であれば容易にそのことを知り得たのにあえて請求をしたなど、社会通念に照らし著しく相当性を欠く場合に限られ、この理は当該貸金業者が過払金の受領につき民法704条所定の悪意の受益者に推定されるときであっても異ならないとした事例 |
||
| 107 | H21.9.4 |
借主の利息制限法1条1項所定の制限を超えた利息の継続支払により過払金が発生した場合における、悪意の受益者の民法704条による利息の支払いは、金銭消費貸借が継続的に借入れと弁済が繰り返される基本契約に基づくもので、過払金が発生した当時他の借入金債務がなければ過払金をその後に発生する新たな借入金債務に充当する旨の合意を含むものであった場合でも、異ならないとした事例 |
||
| 108 | H21.7.16 |
相手方らの立入禁止等と記載した看板を被告人方建物に取り付けようとする行為に対して、被告人らの上記建物の共有持分権、賃借権等や業務、名誉に対する急迫不正の侵害への防衛として行った、被告人が相手方の胸部等を両手で突いた暴行が、刑法36条1項にいう「やむを得ずにした行為」に当たるとされた事例 |
RETIO 78-122
|
|
| 109 | H21.7.13 |
警察署庁舎建物の利用のために供されている高さ約2.4mの塀は、刑法130条にいう「建造物」の一部を構成するものとして建造物侵入罪の客体に当たり、中庭に駐車された捜査車両を確認する目的で本件塀の上部に上がった行為は、建造物侵入罪を構成するとした事例 |
||
| 110 | H21.7.10 |
「期限の利益喪失特約の下での制限超過部分の支払いは原則として貸金業法43条1項にいう、債務者が利息として任意に支払ったものということはできない。」とした、最高裁平成18年1月13日判決以前の期限の利益喪失特約下の支払について、これを受領したことのみを理由として当該貸金業者を悪意の受益者であると推定することはできないとした事例 |
||
| 111 | H21.6.5 |
市街化が進んでいない場合の市街化区域農地等の固定資産評価において、固定資産評価基準所定の評価方法等により算定された価格は、当該土地の適正な時価を上回るとした原審の判断に違法があるとした事例 |
||
| 112 | H21.3.27 |
債権の譲渡禁止の特約は、債務者の利益保護のために付されるものと解され、譲渡禁止の特約に反して債権を譲渡した債権者が同特約の存在を理由に譲渡の無効を主張することは、債務者にその無効を主張する意思があることが明らかであるなどの特段の事情がない限り許されないとした事例 |
||
| 113 | H21.3.26 |
他人所有の建物を預かり保管していた者が、金銭的利益を得ようとして、同建物の電磁的記録である登記記録に不実の抵当権設定仮登記を了したことにつき、電磁的公正証書原本不実記録罪及び同供用罪とともに横領罪が成立するとされた事例 |
||
| 114 | H21.3.24 |
相続人のうちの1人に対して財産全部を相続させる旨の遺言がされた場合においては、特段の事情のない限り、当該相続人に相続債務も全て相続させる旨の意思表示と解され、これにより相続人間においては、当該相続人が指定相続分の割合に応じて相続債務を全て承継することになるとされた事例 |
||
| 115 | H21.1.22 |
過払金充当合意を含む基本契約に基づく継続的な金銭消費貸借取引において、同取引により発生した過払金返還請求権の消滅時効は、特段の事情がない限り、同取引が終了した時点から進行するとされた事例 |
||
| 116 | H21.1.22 |
・金融機関は、預金契約に基づき、預金者の求めに応じて預金口座の取引経過を開示すべき義務を負うとした事例 |
||
| 117 | H20.12.16 |
いわゆるフルペイアウト方式によるファイナンス・リース契約中の、ユーザーについて民事再生手続開始の申立てがあったことを契約の解除事由とする旨の特約は、無効であるとされた事例 |
||
| 118 | H20.12.11 |
相続人が遺産取得の代償として自己所有建物を他の相続人に譲渡する条項がある遺産分割調停調書を添付してされた所有権移転登記申請につき、登記原因証明情報の提供を欠くことを理由に却下した処分が違法とされた事例 |
RETIO 75-064
|
|
| 119 | H20.10.10 |
窃盗グループにより法律関係のない振込みが普通預金口座へ行われ、当該口座より窃盗グループへ預金の払い戻しが行われた事件において、法律関係のない振込みの不当利得返還義務の負担を理由とした当該口座所有者の金融機関の過失を原因とした金融機関への預金払い戻し請求は、権利の濫用には当たらないとされた事例 |
||
| 120 | H20.9.10 |
市町村の施行に係る土地区画整理事業の事業計画の決定は,抗告訴訟の対象となる行政処分に当たるとした事例 |
||
| 121 | H20.7.17 |
土地が入会地か否かの争いにおいて、訴えの提起に同調しない一部構成員がいるため、入会集団の構成員全員で訴えを提起することができないときは、訴えの提起に同調しない構成員も被告に加え、入会集団の構成員全員が当該土地について入会権を有することの確認を求める訴えを提起することが許され、構成員全員による訴えの提起ではないことを理由に当事者適格を否定されることはないとした事例 |
||
| 122 | H20.7.4 |
コンビニエンス・ストアのフランチャイズ・チェーンの加盟店基本契約において、運営者提供の発注システムによる商品仕入れにおいて運営者が加盟店に代わり支払う仕入代金につき、その内容に関する加盟店への報告に関する定めがない場合において、当該支払い内容の報告を加盟店経営者から請求があった場合には、準委任の性質を有する本件委託について、民法656条、645条規定の受任者の報告義務を負うとされた事例 |
||
| 123 | H20.6.10 |
いわゆるヤミ金融業者の著しく高利の貸付けに対する借主の不法行為に基づく損害賠償請求に関し、借主がこの借入れにより得た貸付金に相当する利益を、貸主が損益相殺等の対象としてその損害額から控除請求することは民法708条の趣旨に反し許されないとした事例 |
||
| 124 | H20.4.14 |
共有の性質を有する入会権に関する各地方の慣習の効力は、入会権の処分についても及び、入会集団の構成員全員の同意を要件としないで同処分を認める慣習であっても、公序良俗に反するなどその効力を否定すべき特段の事情が認められない限り、有効であるとした事例 |
||
| 125 | H20.4.11 |
公務員宿舎である集合住宅の1階出入口から各室玄関前までの部分及び門塀等の囲障を設置したその敷地が刑法130条(邸宅侵入罪)の客体に当たり、各室玄関ドアの新聞受けに政治ビラを投函する目的で立入った行為を同条の罪に問うことができ、そのことは憲法21条(表現の自由)に違反しないとされた事例 |
RETIO 75-066
|
|
| 126 | H20.3.27 |
業務上の過重負荷と基礎疾患とが共に原因となって従業員が死亡した場合において、使用者の不法行為を理由とする損害賠償の額を定めるに当たり、使用者による過失相殺の主張が訴訟上の信義則に反するとして民法722条2項の規定を類推適用しなかった原審の判断に違法があるとされた事例 |
||
| 127 | H20.1.24 |
遺留分権利者が受遺者に対して価額弁償を請求する権利を行使する旨の意思表示をした場合には、当該遺留分権利者は、遺留分減殺によって取得した目的物の所有権及び所有権に基づく現物返還請求権をさかのぼって失い、これに代わる価額弁償請求権を確定的に取得するとした事例 |
||
| 128 | H19.7.6 |
建物の設計・施工者等が、瑕疵により生命、身体又は財産を侵害された者に対し、不法行為責任を負うとされた事例 【H19.7.6最高裁差戻、H23.7.21最高裁差戻、H25.1.29最高裁上告棄却】 |
RETIO 121-099
|
|
| 129 | H19.3.20 |
建造物に取り付けられた物が建造物損壊罪の客体に当たるか否かは、当該物と建造物との接合の程度のほか、当該物の建造物における機能上の重要性を総合考慮して決すべきものであるが、住居の玄関ドアは、外壁と接続し、外界との遮断、防犯等の重要な役割を果たしているから、建造物損壊罪の客体に当たるとした事例 |
||
| 130 | H19.2.13 |
継続的貸付に関する基本契約の締結がない場合において、第一の貸付の各弁済金のうち利息制限法1条1項所定の利息の制限額を超えて利息として支払われた部分を元本に充当すると過払金が発生し、その後第二の貸付に係る債務が発生したときは、第一の貸付に係る過払金は、第一の貸付に係る債務の各弁済が第二の貸付の前にされたものであるか否かにかかわらず第二の貸付に係る債務には充当されないとした事例 |
||
| 131 | H19.1.23 |
被相続人の居住の用に供されていたが、土地区画整理事業における仮換地の指定に伴い相続開始の直前に更地となっていた土地の相続税の課税価格については、本件仮換地を居住の用に供する予定がなかったと認めるに足りる特段の事情のない限り、租税特別措置法69条の3(小規模宅地等の特例)の適用があるとされた事例 |
||
| 132 | H19.1.19 |
無道路地であっても実際に利用している通路が同一の所有者に帰属する場合、固定資産税台帳に登録すべき価格を決定するに当たり、通路開設補正を適用しないとする取扱は同基準に違反せず地方税法403条1項に違反しないとされた事例 |
||
| 133 | H18.11.27 |
大学入学試験の合格者が、入学金および授業料等を納付した後に入学を辞退した事案において、入学金については、消費者契約法9条1号の「平均的な損害」を超えるものではないとして有効とされ、授業料等については、入学辞退が入学日よりも前に行われた場合は原則として返還義務を負い、入学日以降に行われた場合は返還義務を負う理由はないとされた事例 |
||
| 134 | H18.11.14 |
代位弁済をした保証人が、原債権及びその担保権を代位行使し、担保不動産の差押債権者の地位承継を執行裁判所に申し出た場合には、承継申出の主債務者への通知がなくても求償権の消滅時効が不動産競売手続完了までの間中断するとされた事例 |
||
| 135 | H18.9.14 |
賃借人から建物明渡しに関する交渉の依頼を受けた弁護士が、賃貸人から受け取った造作買取代金、追加金を依頼者に報告しなかったことが弁護士法所定の「品位を失うべき非行」に該当するとされた事例 |
||
| 136 | H18.9.4 |
下請業者が施工業者との間で下請契約を締結する前に、施主の了承を得て下請の仕事の準備作業を開始したが、施主が下請業者の支出費用の補填など代償的措置を講ずることなく施工計画を中止した場合においては、これにより生じた下請け業者の損害につき、施主に不法行為による賠償責任が生じるとした事例 |
||
| 137 | H18.9.4 |
建設大臣が都市計画公園とする決定に、隣接する国有地でなく民有地を区域に定めた行為が裁量権の範囲を逸脱・濫用に当たらないとした判断に違法性があるとされ差し戻された事例 |
RETIO 67-080
|
|
| 138 | H18.7.14 |
意思無能力者に代わって相続税を申告し納付した者による事務管理に基づく費用償還請求につき、意思無能力者には相続税申告書の提出義務がなく税務署長による税額の決定がされることもないことを前提として、事務管理に基づく費用償還請求を棄却した原審の判断には違法があるとされた事例 |
||
| 139 | H18.7.7 |
固定資産税の課税標準である土地の「適正な時価」とは、正常な条件の下に成立する当該土地の取引価格、すなわち、客観的な交換価値をいうものであり、これを当該土地から得ることのできる収益を基準に資本還元して導き出される価格をいうものと解することはできず、また、一般に土地の取引価格は、上記の価格以下にとどまるものでなければ正常な条件の下に成立したものとはいえないということもできないとした事例 |
||
| 140 | H18.6.12 |
建築後に土地の一部を売却すると、容積率制限を越える違法建築物となり、また当該土地購入者も敷地の二重使用となり建築確認申請の支障となる敷地について、その一部売却が困難である点を説明しなかった建築会社に説明義務違反があるとされ、銀行にも説明すべき信義則上の義務を肯認する余地があるとされた事例 |
RETIO 65-074
|
|
| 141 | H18.4.20 |
資産の譲渡に当たって支出された費用が所得税法33条3項所定の譲渡費用に当たるかどうかは、現実に行われた資産の譲渡を前提として、客観的に見てその譲渡を実現するために当該費用が必要であったかどうかによって判断すべきであるとされた事例 |
||
| 142 | H18.3.17 |
入会部落の慣習に基づく入会集団の会則のうち、入会権者の資格を原則として男子孫に限定し同入会部落の部落民以外の男性と婚姻した女子孫は離婚して旧姓に復しない限り入会権者の資格を認めないとする部分につき民法90条の規定により無効とされた事例 |
||
| 143 | H18.2.23 |
不実の所有権移転登記がされたことにつき、所有者が当該移転登記の抹消を請求した事案において、不動産の権利証を預け、売買の意思がないのに売買契約書に署名押印するなど所有者にも重い帰責性があるとして、民法94条2項、110条を類推適用すべきものとされた事例(控訴審 H15.3.28 福岡高裁 RETIO61-74) |
RETIO 66-040
|
|
| 144 | H18.1.19 |
登記に表示された所在地番及び床面積が実際と異なる建物が、借地借家法10条1項の「登記された建物」に当たるかが争われた事案において、所在地番の相違が登記官の過誤によるものであり、床面積の相違は建物の同一性を否定するものでないとして、同建物は、「登記された建物」に当たるとされた事例 |
RETIO 66-052
|
|
| 145 | H18.1.19 |
債務者が利息制限法所定の制限を超える約定利息の支払を遅滞したときには当然に期限の利益を喪失する旨の特約の効力は、制限超過部分の支払を怠った場合に期限の利益を喪失するとする部分につき無効であるとした事例 |
||
| 146 | H18.1.17 |
通路部分の時効取得の成否が争われた事案について、不動産の取得時効完成後に当該不動産の譲渡を受けて所有権移転登記を了した者が背信的悪意者に当たるためには、時効取得者が多年にわたり当該不動産を占有している事実を認識することが必要であるとされた事例 |
RETIO 65-050
|
|
| 147 | H17.12.16 |
公有水面埋立法に基づく埋立免許を受けて埋立工事が完成した後竣工認可がされていない埋立地につき、黙示的に公用が廃止されたものとして取得時効の成立が認められるとされた事例 |
||
| 148 | H17.12.15 |
相続を原因として共同相続人の1人に対してなされた所有権移転登記が実体関係に符合しないとした他の相続人が是正を求める方法として、更正登記手続の方法によることはできないが、当該登記の全部抹消登記手続を求めることはできるとした事例 |
||
| 149 | H17.11.1 |
昭和13年に決定された都市計画に係る計画道路の区域内にその一部が含まれる土地に建築物の建築の制限が課せられることによる損失について、憲法29条3項に基づく補償請求をすることができないとされた事例 |
||
| 150 | H17.10.11 |
相続が開始して遺産分割未了の間に第二次の相続が開始した場合において、第二次被相続人から特別受益を受けた者があるときは、その持戻しをして各共同相続人の具体的相続分を算定しなければならないとされた事例 |
||
| 151 | H17.9.8 |
共同相続された不動産から生ずる賃料債権は、各共同相続人の持分に応じて分割単独債権として帰属し、その帰属は遺産分割の結果による影響を受けないとされた事例 |
||
| 152 | H17.7.11 |
土地課税台帳等に登録の基準年度の土地価格についての審査決定の取消訴訟において、固定資産評価審査委員会の認定価格が、裁判所が認定した適正な時価等を上回っていることを理由として、審査決定を取り消す場合には、当該審査決定のうちその適正な時価等を超える部分に限り取り消せば足りるとした事例 |
||
| 153 | H17.6.24 |
指定確認検査機関による建築基準法6条の2第1項の確認に係る建築物について、同法6条1項の確認をする権限を有する建築主事が置かれた地方公共団体は、指定確認検査機関の当該確認につき行政事件訴訟法21条1項所定の「当該処分又は裁決に係る事務の帰属する国又は公共団体」に当たると判示した事例 |
RETIO 63-032
|
|
| 154 | H17.6.14 |
損害賠償額の算定に当たり、被害者の将来の逸失利益を現在価額に換算するために控除すべき中間利息の割合は、民事法定利率によらなければならないとされた事例 |
||
| 155 | H17.4.26 |
いわゆる強制加入団体でもなく、その規約において会員の退会を制限する規定を設けていない、権利能力のない社団である県営住宅の自治会の会員は、いつでも当該自治会に対する一方的意思表示によりこれを退会することができるとされた事例 |
||
| 156 | H17.3.29 |
同一の敷地にあって一つのリゾートホテルを構成している複数の建物の固定資産課税台帳の登録価格についてされた審査申出の棄却決定の取消しを求める各請求が互いに行政事件訴訟法13条6号所定の関連請求に当たるとされた事例 |
||
| 157 | H16.10.29 |
別荘地の不動産取得税につき、賦課決定の基礎となった固定資産税課税台帳登録価格が、急傾斜地である土地の現況を無視した評価であるとして、原審判決を破棄し差し戻した事例 |
||
| 158 | H16.10.29 |
土地を造成し宅地分譲を行うに当たり、地方公共団体から都市計画法上の同意権を背景として開発区域外の排水路の改修工事を行うよう指導された場合において、その費用の見積金額を「当該事業年度の収益に係る売上原価」の額として損金算入することができるとされた事例 |
||
| 159 | H16.7.13 |
農地所有者が、その土地を耕作して占有する者に行った明渡し請求に対し、占有者が、本件土地は先代が賃借権を時効取得したものを相続したものであるとした事案において、農地の賃借権の時効取得については、農地法3条の規定の適用はなく、知事等の許可がなくても時効取得が認められるとされた事例 |
RETIO 61-072
|
|
| 160 | H16.7.7 |
根抵当権放棄の対価が、根抵当権者が相当と認めた金額であっても、当該支払いは根抵当権目的不動産の第三者への正規売却に伴うものとの誤信がなければ、根抵当権の放棄に応じなかったにもかかわらず、根抵当権設定者が、真実は自己の支配会社への売却であることを秘し、根抵当権者を欺き誤信させ、根抵当権を放棄させてその抹消登記を了した場合には、刑法246条2項の詐欺罪が成立するとした事例 |
||
| 161 | H16.7.6 |
共同相続人が、他の共同相続人に対し、その者が被相続人の遺産につき相続人の地位を有しないことの確認を求める訴えにつき、固有必要的共同訴訟であるとした事例 |
||
| 162 | H16.6.8 |
土地売買契約の当事者双方から所有権移転登記手続についての代理を嘱託された司法書士が、本件土地について実体的所有関係を確定することができない等と述べて嘱託を拒んだことにつき、正当な事由がないとして、土地売主の司法書士に対する損害賠償請求が一部容認された事例 |
RETIO 61-070
|
|
| 163 | H16.4.27 |
身体への蓄積により人の健康を害する物質による損害など、不法行為により発生する損害の性質上、加害行為終了後相当の期間を経て損害が発生する場合には、「不法行為の時」と規定される損害賠償請求権の除斥期間の起算点は、当該損害の全部又は一部が発生した時が除斥期間の起算点となるとされた事例 |
||
| 164 | H16.4.23 |
マンション管理組合が組合員である区分所有者に対して前所有者の延滞していた管理費及び特別修繕費を請求したのに対し、管理費等に係る債権が5年間の短期消滅時効を定める民法169条所定の定期給付債権に当たり、5年を経過した部分は時効により消滅しているとの区分所有者の主張が認容された事例(控訴審 H13.10.31 東京高裁 RETIO53-86) |
RETIO 59-054
|
|
| 165 | H16.4.20 |
相続財産である可分債権につき共同相続人の一人がその相続分を超えて債権を行使した場合、他の共同相続人は不法行為に基づく損害賠償または不当利得の返還を求めることができるとされた事例 |
||
| 166 | H15.12.9 |
地震保険加入の意思決定は、生命、身体等の人格的利益に関するものではなく、財産的利益に関するものであることに鑑みると、特段の事情が存しない限り、火災保険契約締結に際して、火災保険会社は保険契約者に対し地震保険の内容等に関する情報提供をすべき信義則上の義務はないとした事例 |
||
| 167 | H15.11.14 |
建築確認申請書に自己が工事監理を行う旨の実体に沿わない記載をした一級建築士が建築主に工事監理者の変更の届出をさせる等の適切な措置を執らずに放置した行為が、当該建築主から瑕疵のある建物を購入した者に対する不法行為になるとされた事例 |
RETIO 58-054
|
|
| 168 | H15.11.7 |
金融機関の従業員が顧客に対し融資を受けて宅地を購入するように勧誘する際に、当該宅地が接道要件を具備していないことを説明しなかったことが、当該宅地を購入した顧客に対する不法行為を構成するとはいえないとされた事例 |
RETIO 59-052
|
|
| 169 | H15.10.31 |
不動産の時効取得を原因とする所有権移転登記前に、前所有者によって設定された抵当権に対抗するため、起算点を後にずらして抵当権設定登記後の時効取得を主張・援用することができないとされた事例 |
||
| 170 | H15.10.10 |
耐震性の高い建物とするため主柱に特に太い鉄骨を使用することが重要な内容である建物建築工事の請負契約において、建物請負業者が注文主に無断で約定の太さの鉄骨を使用しなかったことは、使用された鉄骨が、構造計算上居住用建物としての安全性を備えていたとしても、当該主柱工事は瑕疵にあたるとされた事例 |
RETIO 58-052
|
|
| 171 | H15.7.18 |
評価基準に従い決定した固定資産課税台帳登録の家屋の価格は、評価基準が定める評価方法によっては再建築費を適切に算定することができない特別の事情又は評価基準が定める減点補正を超える減価を要する特別の事情の存しない限り、その適正な時価であると推認するのが相当であるとし、登録価格が適正な時価を超えるとした原審の判断に違法があったとした事例 |
||
| 172 | H15.7.11 |
不動産の共有者の1人は、共有不動産について実体上の権利を有しないのに持分移転登記を経由している者に対し、単独でその持分移転登記の抹消登記手続を請求することができるとされた事例 |
RETIO 58-050
|
|
| 173 | H15.6.26 |
土地課税台帳等に登録された土地の価格が、賦課期日における当該土地の客観的な交換価値を上回れば、当該価格の決定は違法となるとして、賦課期日における宅地の価格の決定に適正な時価を超える違法があるとされた事例 |
||
| 174 | H15.6.13 |
不動産の所有者から交付を受けた登記済証、白紙委任状等を利用して不実の所有権移転登記がされた場合において、所有者が虚偽の外観の作出に関与しておらず、放置していたとも言えないとして、所有者に対し所有権が移転したことを善意無過失の第三者が対抗し得ないとされた事例 |
RETIO 57-134
|
|
| 175 | H15.4.23 |
委託を受けて他人の不動産を占有する者がほしいままに売却等による所有権移転行為を行った場合に、先行の抵当権設定行為が存在することは、後行の所有権移転行為について横領罪が成立することを妨げないとされた事例 |
||
| 176 | H15.4.18 |
法律行為が公序に反することを目的とするものであるとして無効になるかどうかは、法律行為がされた時点の公序に照らして判断すべきとされた事例 |
||
| 177 | H15.4.11 |
入会地の売却代金債権が、入会権者らに総有的に帰属するとし、各入会権者が同代金債権について持分に応じた分割債権を取得したということはできないとされた事例 |
||
| 178 | H15.3.14 |
破産終結決定がされて法人格が消滅した会社を主債務者とする保証人は、主債務についての消滅時効が会社の法人格の消滅後に完成したことを主張してこれを援用することはできないとした事例 |
||
| 179 | H14.10.25 |
民事訴訟法113条の類推適用により、競売開始決定の公示送達による送達が、被担保債権の時効中断事由である差押えの通知としての効力を有するとされた事例 |
||
| 180 | H14.9.24 |
建物の建築請負工事に基づいて建築された建物に重大な瑕疵があるために、これを建替えざるを得ないとして、請負人に対して建物の建替えに要する費用相当額の損害賠償を命じた事例 |
RETIO 57-138
|
|
| 181 | H14.9.24 |
ワープロを操作して秘密証書遺言の遺言書の表題及び本文を入力し印字した者が民法970条1項3号にいう筆者であるとされた事例 |
||
| 182 | H14.7.12 |
遺言執行者が推定相続人の廃除を求める審判手続において、廃除を求められていない推定相続人が利害関係人として審判手続に参加した場合に、参加人は廃除の申立てを却下する審判に対して即時抗告をすることができないとされた事例 |
||
| 183 | H14.7.11 |
特定の商品代金の立替払契約がいわゆる空クレジット契約である場合において、保証人の意思表示には法律行為の要素に錯誤があるとされた事例 |
||
| 184 | H14.7.9 |
地方公共団体が建築工事の中止命令の名あて人に対して同工事を続行してはならない旨の裁判を求める訴えが不適法とされた事例 |
||
| 185 | H14.6.11 |
土地収用法71条は憲法29条3項に違反するものではないとされた事例 |
||
| 186 | H14.6.10 |
特定の遺産を「相続させる」旨の遺言により特定の不動産を取得した者は、登記なしにその取得を他の相続人及び他の相続人から当該不動産に関する権利の移転・設定を受けた第三者に対抗できるとされた事例 |
||
| 187 | H14.4.5 |
土石の捨場として使用されていた農地の売主が、その後買主によって行われた同土地の非農地への造成、転用を完成させる行為に共同正犯として関与したときは、農地法4条1項違反の罪と同法5条1項違反の罪の双方が成立するとした事例 |
||
| 188 | H14.3.28 |
・総合設計許可に係る建築物により、日照を阻害される周辺の他の建築物に居住する者は、同許可の取消訴訟の原告適格を有するとした事例 |
||
| 189 | H14.2.28 |
不活動仮眠時間であっても、労働からの解放が保証されていない場合は労基法上の労働時間に該当するとされた事例 |
||
| 190 | H14.1.22 |
他人の権利を譲り受けて訴訟等の手段によってその権利の実行をすることを業とする行為であっても、みだりに訴訟を誘発するなど国民の法律生活上の利益に対する弊害が生ずるおそれがなく、社会的経済的に正当な業務の範囲内にあると認められる場合には、弁護士法73条に違反するものではないとされた事例 |
||
| 191 | H14.1.22 |
総合設計許可に係る建築物の倒壊、炎上等により直接的な被害を受けることが予想される範囲の地域に存する建築物に居住し又はこれを所有する者は、総合設計許可の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者として、その取消訴訟における原告適格を有するとした事例 |
||
| 192 | H13.11.27 |
弁済供託における供託金取戻請求権の消滅時効は、供託者が免責の効果を受ける必要が消滅した時から進行するとして、賃料債務についてされた弁済供託につき、賃料債務の弁済期の翌日から民法169条(定期給付債権の短期消滅時効)所定の5年間の時効期間が経過した時、さらにそれから10年が経過することによって消滅時効が完成すると判示した事例 |
RETIO 52-057
|
|
| 193 | H13.11.27 |
購入土地の一部について道路位置指定がなされていたことは瑕疵にあたるとして、買主が売主に対し損害賠償を請求した事案において、瑕疵担保による損害賠償請求権の消滅時効は買主が売買の目的物の引渡しを受けた時から進行するとして、10年経過による消滅時効により買主の請求を棄却した事例 |
RETIO 52-018
|
|
| 194 | H13.11.22 |
遺留分減殺請求権は、遺留分権利者が、これを第三者に譲渡するなど、権利行使の確定的意思を有することを外部に表明したと認められる特段の事情がある場合を除き、債権者代位の目的とすることができないとされた事例 |
||
| 195 | H13.10.26 |
農地転用許可を停止条件とする土地売買につき、転用許可手続未了であっても、代金を支払い、引渡しを受けた時点で自主占有が開始されたものとした事例 |
||
| 196 | H13.7.19 |
請負人が欺罔手段を用い請負代金を不当に早く受領したことをもって刑法246条1項の詐欺罪が成立するというためには、欺罔手段を用いなかった場合に得られたであろう請負代金の支払とは社会通念上別個の支払に当たるといい得る程度の期間支払時期を早めたものであることを要するとした事例 |
||
| 197 | H13.7.10 |
被相続人の占有により取得時効が完成した場合において、その共同相続人の1人は、自己の相続分の限度においてのみ取得時効を援用することができるとした事例 |
||
| 198 | H13.7.10 |
共同相続人間においてされた相続分の譲渡に伴って生ずる農地の権利移転については、農地法3条1項の許可を要しないとされた事例 |
||
| 199 | H13.3.28 |
宅地並み課税の税負担は、値上がり益を享受している農地所有者が資産維持の経費として担うべきと解され、小作料は農地の使用収益の対価であることから、小作地において固定資産税等の宅地並み課税を理由とする小作料の増額請求をすることはできないとされた事例 |
||
| 200 | H13.3.27 |
遺言公正証書の作成に当たり、当該遺言の証人の欠格事由に該当する者が同席していたとしても、この者によって遺言の内容が左右されたり、遺言者が自己の真意に基づいて遺言をすることを妨げられたりするなど特段の事情のない限り、同遺言が無効となるものではないとされた事例 |
||
| 201 | H13.3.13 |
遺言者の住所のみをもって表示された不動産の遺贈の解釈として、同所の建物のみの遺贈と解すべきではなく、土地及び建物一体の遺贈と解されるとされた事例 |
||
| 202 | H13.2.22 |
民法564条規定の、売主の担保責任の除斥期間の起算点である「事実を知った時」とは、買主が売主に対し民法563条又は565条規定の担保責任を追及し得る程度に確実な事実関係を認識した時をいうとした事例 |
RETIO 50-080
|
|
| 203 | H12.12.15 |
使用貸借における用法違反が、土地所有者の意思に反して占有の態様を質的に変化させ、その占有を新たに排除したとして不動産侵奪罪の成立が認められた事例 |
||
| 204 | H12.12.15 |
都職員の警告を無視して都公園予定地の一部に無権原で簡易建物を構築し、相当期間撤去にも応じなかった行為が不動産の侵奪に当たるとされた事例 |
||
| 205 | H12.10.20 |
A社とその関連会社B社の代表を兼ねる取締役が、B社救済の目的で同社所有不動産を不当に高額でA社に購入させ損害を与えたとして、A社の株主が株主代表訴訟を提起した事案において、取締役に商法266条1項4号の責任のほか、同法266条1項5号の責任をも負うとした事例 |
||
| 206 | H12.7.12 |
相手方の同意を得ないで相手方との会話を録音したテープの証拠能力が認められた事例 |
||
| 207 | H12.7.11 |
受贈者又は受遺者は、遺留分減殺の対象とされた贈与又は遺贈の目的である各個の財産について、民法1041条1項に基づき価額を弁償して、その返還義務を免れることができるとした事例 |
||
| 208 | H12.5.30 |
共同相続人の一部の者が、遺留分減殺請求権の行使により受贈者から取得すべき持分を超える持分を有償で受贈者から取得した場合において、その持分取得に係る登記は相続登記の更正登記の手続により行うことはできないとされた事例 |
||
| 209 | H12.4.7 |
共有地を一部の共有者が他の共有者を排除して占有している場合において、排除された共有者は、当該一部の共有者に対し明渡請求をすることはできないが、共有持分に応じた地代相当額の不当利得返還請求又は損害賠償請求ができるとされた事例 |
||
| 210 | H12.3.24 |
長時間にわたる残業を恒常的に伴う業務に従事していた従業員がうつ病にり患し、衝動的、突発的に自殺した事案において、使用者に民法715条に基づく損害賠償責任が認められた事例 |
||
| 211 | H12.3.10 |
内縁の夫婦の一方の死亡により内縁関係が解消した場合に、民法768条(財産分与)の規定を類推適用することはできないとした事例 |
||
| 212 | H12.2.24 |
民法903条1項により算定されるいわゆる具体的相続分の価額又はその価額の遺産の総額に対する割合の確認を求める訴えは、確認の利益を欠くものとして不適法であるとした事例 |
||
| 213 | H12.1.27 |
渉外親子関係の成立の判断は、まず嫡出親子関係の成立についてその準拠法を適用し、嫡出親子関係が否定された場合には、嫡出以外の親子関係の成立についてその準拠法を適用して行うとされた事例 |
||
| 214 | H12.1.27 |
共同相続された不動産につき、被相続人から相続人以外の第三者に直接所有権移転登記が経由された場合につき、共同相続人の1人が自己の持分の登記名義を回復するには、更正登記手続によることはできす、真正な登記名義の回復の手続によるべきものとされた事例 |
||
| 215 | H11.12.16 |
いわゆる「相続させる」遺言について、特定の不動産の所有権移転登記を指定された相続人に取得されることが、遺言執行人の職務権限に属するとされた事例 |
||
| 216 | H11.12.9 |
建物賃借人が土地に産業廃棄物を大量に廃棄・堆積した行為が、土地所有者に対する不動産侵奪罪を構成するとされた事例 |
||
| 217 | H11.11.25 |
建築請負人からの注文者に対する請負契約に係る建物の所有権保存登記抹消登記手続請求訴訟の提起は、請負代金債権の消滅時効中断事由である裁判上の請求に準ずるものとはいえず、訴訟の係属中の請負代金について催告が継続していたということもできないとした事例 |
||
| 218 | H11.11.25 |
都市計画法に基づく環状六号線道路拡幅事業の認可処分及び首都高速道路公団に対する中央環状新宿線建設事業の承認処分の取消訴訟において、事業地の周辺地域に居住し、又は通勤、通学しているが事業地内の不動産につき権利を有しない者は、処分の取消しを求める原告適格を有しないとした事例 |
||
| 219 | H11.11.24 |
抵当権者が権利の目的である建物の所有者の不法占有者に対する妨害排除請求権を代位行使して、直接抵当権者に建物を明け渡すよう求めることができるとされた事例 |
RETIO 45-043
|
|
| 220 | H11.11.9 |
主債務者である破産者が免責決定を受けた場合に、免責決定の効力の及ぶ債務の保証人は、その債権についての消滅時効を援用することができないとされた事例 |
||
| 221 | H11.11.9 |
土地の共有者のうちに境界確定の訴えを提起することに同調しない者がいる場合には、その余の共有者は、隣接する土地の所有者と訴えを提起することに同調しない者とを被告にして訴えを提起することができるとした事例 |
||
| 222 | H11.10.26 |
開発行為に関する工事が完了し検査済証が交付された時点においては、予定建物の建築確認がされていないとしても開発許可の取消しを求める訴えはできないとした事例 |
||
| 223 | H11.10.21 |
後順位抵当権者は、先順位抵当権の被担保債権の消滅時効を援用することはできないとされた事例 |
||
| 224 | H11.9.9 |
・極度額を超える金額の被担保債権を請求債権とする根抵当権の実行がされた場合、被担保債権の消滅時効中断の効力は、当該極度額の範囲にとどまらず、請求債権として表示された当該被担保債権の全部について生じるとした事例 |
||
| 225 | H11.7.19 |
共同相続人相互の間で一部の者が他の者を共同相続人でないとしてその相続権を侵害している場合において、相続回復請求権の消滅時効を援用しようとする者は、真正共同相続人の相続権を侵害している共同相続人が、当該相続権侵害の開始時点において、他に共同相続人がいることを知らず、かつ、これを知らなかったことに合理的な事由があったことを立証しなければならないとした事例 |
||
| 226 | H11.6.24 |
遺留分減殺の対象としての要件を満たす贈与を受けた者が、取得時効を援用したとしても、贈与に対する減殺請求による遺留分権利者への目的物についての権利の帰属は妨げられないとした事例 |
||
| 227 | H11.6.11 |
遺言者の生存中に推定相続人が提起した遺贈を内容とする遺言の無効確認の訴えは、遺言者が心神喪失の常況にあって、遺言者による当該遺言の取消し又は変更の可能性が事実上ないとしても、不適法であるとした事例 |
||
| 228 | H11.6.11 |
共同相続人の間で成立した遺産分割協議は、詐害行為取消権行使の対象となり得るとした事例 |
||
| 229 | H11.6.10 |
相続財産に属する特定の財産を計算の基礎としない相続税の期限内申告書が提出された場合において、納税者が当該財産が相続財産に属さないか又は属する可能性が小さいことを客観的に裏付けるに足りる事実を認識して期限内申告書を提出したときは、国税通則法65条4項にいう「正当な理由」があるとされた事例 |
||
| 230 | H11.4.27 |
不動産競売手続きにおいて債務名義の正本を有する債権者がする配当要求は、配当要求に係る債権の消滅時効を中断する効力があるとされた事例 |
||
| 231 | H11.4.22 |
共有に係る土地及び借地権につき、全面的価格賠償方式による分割を認めた事例 |
||
| 232 | H11.3.10 |
廃棄物処理法における「不要物」とは、自ら利用し又は他人に有償で譲渡することができないために事業者にとって不要となった物をいい、これに該当するか否かは、その物の性状、排出の状況、通常の取扱い形態、取引価値の有無及び事業者の意思等を総合的に勘案して決するとした事例 |
||
| 233 | H11.3.9 |
・被相続人の生存中になされた相続人への売買を原因とする所有権移転登記は、被相続人の死亡後に、相続を原因とするものに更正することはできないとした事例 |
||
| 234 | H11.2.26 |
譲渡担保権者から被担保債権の弁済期後に譲渡担保権の目的物を譲り受けた第三者は、譲渡担保権設定者が譲渡担保権者に対して有する清算金支払請求権につき、消滅時効を援用することができるとした事例 |
||
| 235 | H11.2.23 |
やむを得ない事由があっても任意の脱退を許さない旨の組合契約における約定は、無効であるとした事例 |
||
| 236 | H11.1.22 |
都市計画法43条1項6号ロにいう「市街化調整区域に関する都市計画が決定され…た際すでに宅地であった土地」とは、市街化調整区域指定時に宅地であり、かつ、それ以降継続して宅地であることを要するとされた事例 |
平10(行ツ)114号(裁判所HP未登載) |
RETIO 45-069
|
| 237 | H11.1.21 |
水道事業者である町が水道水の需要の増加を抑制するため、マンション分譲業者との給水契約の締結を拒否したことに、水道法15条1項にいう「正当の理由」があるとされた事例 |
||
| 238 | H11.1.21 |
相続債権者は、被相続人から抵当権の設定を受けていても、被相続人の死亡前に仮登記がされていた場合を除き、相続財産人に対して抵当権設定登記手続を請求することができず、限定承認がされた場合における限定承認者に対する設定登記手続請求も、これと同様であるとした事例 |
||
| 239 | H10.12.17 |
不法行為に基づく損害賠償請求訴訟の係属によって不当利得返還請求権の消滅時効が中断するとされた事例 |
||
| 240 | H10.12.17 |
パチンコ屋の近隣住民が、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律3条1項に基づいてなされた営業許可が違法であるとしてその取消しを求めた事案において、近隣住民らに当該営業の許可処分の取消しを求める訴えの原告適格を有しないとした事例 |
||
| 241 | H10.11.25 |
相互銀行の役員らが、土地の購入資金及び開発資金等の融資をするにあたり、担保が大幅に不足し、回収困難に陥るおそれが明らかであり、当該融資の必要性、緊急性が認められず、第三者の利益を図る目的があったとして、特別背任罪の成立を認めた事例 |
RETIO 43-091
|
|
| 242 | H10.11.24 |
・仮差押えによる時効中断の効力は、仮差押えの執行保全の効力が存続する間は継続するとした事例 |
||
| 243 | H10.11.12 |
市がその施行する土地区画整理事業において、取得した保留地を随意契約の方法により売却する行為は、「財産の処分」及び「契約の締結」に当たり、住民訴訟の対象となるとした事例 |
||
| 244 | H10.7.17 |
本人が無権代理行為の追認を拒絶した場合には、その後無権代理人が本人を相続したとしても、無権代理行為が有効になるものではないとされた事例 |
||
| 245 | H10.6.30 |
一個の債権の一部についてのみ判決を求める旨を明示して訴えを提起している場合において、当該債権の残部を自働債権として他の訴訟において相殺の抗弁を主張することは、債権の分割行使をすることが訴訟上の権利の濫用に当たるなど特段の事情の存しない限り、許されるとされた事例 |
||
| 246 | H10.6.22 |
詐害行為の受益者は、詐害行為取消権を行使する債権者の債権の消滅時効を援用することができるとした事例 |
||
| 247 | H10.6.11 |
被相続人の全財産が相続人の一部の者に遺贈された場合において、遺留分減殺請求権を有する相続人が、遺贈の効力を争うことなく、遺産分割協議の申入れをしたときは、特段の事情のない限り、その申入れには遺留分減殺の意思表示が含まれているとした事例 |
||
| 248 | H10.4.24 |
土地の売買において買主の仮登記が付されたが、売買から20年以上経過した後に、売主が買主の仮登記を抹消した上で第三者に売却したため、買主が売主に対し債務不履行による損害賠償を求め、売主が消滅時効を主張し争った事案において、契約に基づく債務不履行による損害賠償請求権の消滅時効は、売買契約締結時から進行するとされた事例 |
||
| 249 | H10.3.24 |
民法903条1項の定める相続人に対する贈与は、相続開始よりも相当以前にされたものであって、その後の時の経過に伴う社会経済事情や相続人など関係人の個人的事情の変化をも考慮するとき、減殺請求を認めることが相続人に酷であるなどの特段の事情のない限り、民法1030条の定める要件を満たさないものであっても、遺留分減殺の対象となるとされた事例 |
||
| 250 | H10.3.24 |
共有者の一部が、他の共有者の同意を得ず共有物に変更を加えた場合において、他の共有者は、各自の共有持分権に基づき、同行為の全部禁止を求めることだけでなく、原状に復することが不能であるなどの特段の事情を除き、共有物を原状に復させることを求めることもできるとした事例 |
||
| 251 | H10.3.13 |
民法969条に従い公正証書による遺言がされる場合において、証人は、遺言者が同条4号所定の署名及び押印をするに際しても、これに立ち会うことを要するとされた事例 |
||
| 252 | H10.3.10 |
遺留分権利者が減殺請求権を行使するよりも前に、減殺を受けるべき受遺者が遺贈の目的を他人に譲り渡した場合において、遺留分権利者に対して価額弁償すべき額は、譲渡の価額がその当時において客観的に相当と認められるものであったときは、その価額を基準として算定すべきとされた事例 |
||
| 253 | H10.2.27 |
いわゆる全面価格賠償の方法により共有物を分割することの許される特段の事情の存否について、審理判断することなく競売による分割をすべきものとした原審の判断に違法があるとされた事例 |
||
| 254 | H10.2.27 |
遺言により特定の相続人に相続させるものとされた特定の不動産についての賃借権確認請求訴訟の被告適格を有する者は、遺言執行者があるときであっても、特段の事情のない限り、遺言執行者ではなく、右相続人であるとされた事例 |
||
| 255 | H10.2.26 |
共有の不動産を居住または共同事業のために共同で使用してきた内縁の夫婦の一方が死亡した場合において、両者の間では特段の事情がない限り、その一方が死亡したときは他方が当該不動産を単独で使用する旨の合意が成立していたものと推認されるとした事例 |
||
| 256 | H10.2.26 |
相続人に対する遺贈が遺留分減殺の対象となる場合においては、遺贈の目的の価額のうち受遺者の遺留分額を超える部分のみが、民法1034条にいう目的の価額に当たるとした事例 |
||
| 257 | H10.2.24 |
登録免許税法25条に基づいて登記官の行う登録免許税額の納付の事実の確認は、抗告訴訟の対象となる行政処分に当たらないとされた事例 |
||
| 258 | H10.2.13 |
不動産の死因贈与の受贈者が贈与者の相続人である場合において、限定承認がされたときは、死因贈与に基づく限定承認者への所有権移転登記が相続債権者による差押登記よりも先にされたとしても、信義則に照らし、限定承認者は相続債権者に対して不動産の所有権取得を対抗することができないとした事例 |
||
| 259 | H9.12.18 |
担保権の設定された物件が弁済までの間に共同相続により共有となった場合、民法501条5号にいう「頭数」は、弁済の時における物件の共有持分権者をそれぞれ一名として頭数を数えるべきものと解されるとした事例 |
||
| 260 | H9.11.13 |
遺言者が遺言を撤回する遺言を更に別の遺言をもって撤回した場合において、遺言書の記載に照らし、遺言者の意思が当初の遺言の復活を希望するものであることが明らかなときは、当初の遺言の効力が復活するとされた事例 |
||
| 261 | H9.11.13 |
期間の定めのある建物の賃貸借において、賃借人のために保証人が賃貸人との間で保証契約を締結した場合には、特段の事情のない限り更新後の賃貸借から生ずる賃借人の債務についても保証の責めを免れないとされた事例 |
RETIO 126-077
|
|
| 262 | H9.11.11 |
賭博により生じた債権が譲渡された場合において、債務者が異議をとどめず債権譲渡を承諾したときであっても、債務者に信義則違反などの特段の事情のない限り、債務者は債権の譲受人に対して債権の発生に係る契約の公序良俗違反による無効を主張してその履行を拒むことができるとした事例 |
||
| 263 | H9.9.12 |
遺言者に相続人は存在しないが相続財産全部の包括受遺者が存在する場合は、民法951条にいう「相続人のあることが明かでないとき」に当たらないとされた事例 |
||
| 264 | H9.7.15 |
請負人の報酬債権に対し、注文者がこれと同時履行の関係にある目的物の瑕疵修補に代わる損害賠償債権を自働債権とする相殺の意思表示をした場合、注文者は、請負人に対する相殺後の報酬残債務について、相殺の意思表示をした日の翌日から履行遅滞による責任を負うとした事例 |
||
| 265 | H9.6.5 |
一個の不動産の全体を目的とする抵当権が設定されている場合において、抵当不動産の共有持分を取得した第三者が抵当権の滌除をすることは許されないとした事例 |
||
| 266 | H9.3.14 |
共同相続人甲、乙、丙のうち甲と乙間において、ある土地につき甲の所有権確認請求を棄却する判決が確定し、確定判決の既判力により、甲が乙に対して相続による土地の共有持分取得を主張し得なくなった場合であっても、甲は土地につき遺産確認の訴えを提起することができるとした事例 |
||
| 267 | H9.3.14 |
所有権確認請求訴訟で敗訴した原告が後訴において共有持分の取得を主張することが、前訴の確定判決の既判力に抵触して許されないとされた事例 |
||
| 268 | H9.2.14 |
請負契約の目的物に瑕疵がある場合においては、注文者は請負人から瑕疵の修補に代わる損害の賠償を受けるまでは、瑕疵の程度や各契約当事者の交渉態度等に鑑み信義則に反する場合を除き、報酬全額の支払を拒むことができ、これにつき履行遅滞の責任も負わないとした事例 |
||
| 269 | H9.1.28 |
土地収用法133条所定の損失補償に関する訴訟において、裁判所は、収用委員会の補償に関する認定判断に裁量権の逸脱濫用があるかどうかを審理判断するのではなく、裁決時点における正当な補償額を客観的に認定し裁決に定められた補償額が認定額と異なるときは、これを違法とし、正当な補償額を確定すべきであるとされた事例 |
||
| 270 | H9.1.28 |
相続人が相続に関する被相続人の遺言書を破棄又は隠匿した場合において、相続人の同行為が相続に関して不当な利益を目的とするものでなかったときは、同相続人は、民法891条5号所定の相続欠格者に当たらないとされた事例 |
||
| 271 | H9.1.28 |
開発区域内の土地が、がけ崩れのおそれが多い土地等に当たる場合には、がけ崩れ等による直接的な被害を受けることが予想される範囲の地域に居住する者は、開発許可の取消訴訟における原告適格を有するとした事例 |
||
| 272 | H8.12.17 |
共同相続人の一人が相続開始前から被相続人の許諾を得て、遺産である建物に被相続人と同居してきたときは、特段の事情のない限り、被相続人と同相続人との間において、同建物について、相続開始時を始期とし、遺産分割時を終期とする使用貸借契約が成立していたものと推認されるとした事例 |
||
| 273 | H8.11.26 |
被相続人が相続開始時に債務を有していた場合における遺留分の侵害額は、被相続人が相続開始時に有していた財産の価額にその贈与した財産の価額を加え、その中から債務の全額を控除して遺留分算定の基礎となる財産額を確定し、それに法定の遺留分の割合を乗じるなどして算定した遺留分の額から遺留分権利者が相続によって得た財産の額を控除し、同人が負担すべき相続債務の額を加算して算定するとされた事例 |
||
| 274 | H8.11.12 |
他主占有者の相続人が独自の占有に基づく取得時効の成立を主張する場合において、占有が所有の意思に基づくものであるといい得るためには、占有者である当該相続人において、その事実的支配が外形的客観的にみて独自の所有の意思に基づくものと解される事情を自ら証明する必要があるとした事例 |
||
| 275 | H8.10.31 |
いわゆる全面的価格賠償の方法により共有物を分割することの許される特段の事情の存否について、審理判断することなく競売による分割をすべきものとした原審の判断に違法があるとされた事例 |
||
| 276 | H8.10.31 |
いわゆる全面的価格賠償の方法により共有物を分割することが許されるとされた事例 |
||
| 277 | H8.10.31 |
共有物を取得させるべき者に賠償金の支払能力があることを確定しないで、いわゆる全面的価格賠償の方法により共有物を分割した原審の判断に違法があるとされた事例 |
||
| 278 | H8.10.29 |
所有者甲から乙が不動産を買い受け、その登記が未了の間に、甲から丙が当該不動産を二重に買い受け、更に丙から転得者丁が買い受けて登記を完了した場合に、丙が背信的悪意者に当たるとしても、丁は、乙に対する関係で丁自身が背信的悪意者と評価されるのでない限り、当該不動産の所有権取得をもって乙に対抗することができるとした事例 |
||
| 279 | H8.9.27 |
連帯保証債務の物上保証人に対する抵当権の実行は、主債務の消滅時効の中断にならないとした事例 (控訴審H7.5.31 東京高裁 RETIO32-30) |
RETIO 36-046
|
|
| 280 | H8.7.12 |
物上保証人に対する不動産競売において、被担保債権の時効中断の効力は、競売開始決定正本が債務者に送達された時に生ずるとされた事例 |
||
| 281 | H8.6.18 |
敷金の返還請求権を目的とする質権設定に関し、第三債務者が敷金から控除される金額の割合を定めた特約が存在することにつき錯誤し異議をとどめない承諾をした場合において、同錯誤は要素の錯誤に当たるとされた事例 |
||
| 282 | H8.6.4 |
代金手取額のほか売主に課される譲渡所得税相当分を買主が負担する条件にて不動産売買契約を締結し、買主が用意した譲渡所得税相当分の金額を売主が信用金庫に預金したが、買主がその預金をすぐ引き出したため、売主が買主及び信用金庫等に対し損害賠償を請求した事案について、売買代金額は譲渡所得税相当額を含めた額で、払戻請求権は特段の事情のない限り売主に帰属するとされた事例 |
平7(オ)21号(裁判所HP未登載) |
RETIO 38-051
|
| 283 | H8.5.28 |
違法な申立てにより仮差押え登記を行った債権者の、当該差し押さえにより締結していた転売契約が違約解除となった売主に対する損害賠償について、債権者が知っていた売主の転売利益のほか、同契約の解除に伴う買主への違約金支払い額も予見することができたとして認められた事例 |
||
| 284 | H8.4.26 |
振込依頼人から受取人の銀行の普通預金口座に振込みがあったときは、両者の間に振込みの原因となる法律関係が存在するか否かにかかわらず、受取人と銀行との間に振込金額相当の普通預金契約が成立するとした事例 |
||
| 285 | H8.3.28 |
不動産競売手続きにおいて、抵当権者が債権の一部に対する配当を受けたことをもって、残額について時効の中断の効力を有するものではないとされた事例 |
||
| 286 | H8.1.26 |
遺言者の財産全部の包括遺贈に対して遺留分権利者が減殺請求権を行使した場合に遺留分権利者に帰属する権利は、遺産分割の対象となる相続財産としての性質を有しないとされた事例 |
||
| 287 | H7.12.15 |
登記簿上の所有名義人に対して所有権移転登記手続を求めないなどの土地占有者の態度が他主占有と解される事情として十分であるとはいえないとされた事例 |
||
| 288 | H7.12.5 |
単独名義で相続登記した共同相続人の一人から不動産を譲り受けた者は、その譲渡人が本来の相続持分を超える部分が他の共同相続人に属することを知っていた等の事由により、他の共同相続人に対して相続回復請求権の消滅時効を援用することができない場合には、その譲受人も消滅時効を援用できないとされた事例 |
||
| 289 | H7.9.19 |
建物借主より請け負って修繕工事をした者が、借主の無資力を理由に建物所有者に対し不当利得返還請求をする場合には、建物所有者が対価関係なしに修繕工事の利益を受けたときに限られるとした事例 |
||
| 290 | H7.9.5 |
預託金会員制ゴルフクラブの施設利用権の消滅時効は、会員が施設の利用をしない状態が継続したことのみによっては進行せず、ゴルフ場経営会社が、会員に対してその資格を否定して施設の利用を拒絶し、あるいは会員の利用を不可能な状態としたような時から進行し、同利用権が時効により消滅したときは、ゴルフ会員権は、包括的権利としては存続し得ないとされた事例 |
||
| 291 | H7.9.5 |
物上保証人に対する不動産競売において、開始決定の債務者への送達が付郵便送達によりされた場合、決定正本が郵便に付して発送されたことによっては被担保債権の消滅時効の中断の効力を生ぜず、正本の到達によって初めて時効中断の効力を生ずるとした事例 |
||
| 292 | H7.7.7 |
住宅ローンの名義貸しを銀行の貸付担当者が知っていたときは、消費貸借契約上の貸主としての保護を受けるに値せず、民法93条但書の類推適用により、その返還を求めることができないとされた事例 |
平7(オ)362号(裁判所HP未登載) |
RETIO 33-047
|
| 293 | H7.6.23 |
債権者が物上保証人に対して担保保存義務免除特約の効力を主張することが信義則に違反せず権利の濫用にも当たらないとされた事例 |
||
| 294 | H7.6.9 |
遺留分権利者が減殺請求により取得した不動産の所有権又は共有持分権に基づく登記請求権は、時効によって消滅することはないとされた事例 |
||
| 295 | H7.3.23 |
・主たる債務者の破産手続の債権調査期日終了後に、債権全額を弁済した保証人が債権の届出名義の変更の申出をした場合、保証人が取得した求償権の消滅時効は、求償権の全部について届出名義の変更の時から破産手続の終了に至るまで中断するとされた事例 |
||
| 296 | H7.3.10 |
物上保証人が債務者の承認により被担保債権について生じた消滅時効中断の効力を否定することは、担保権の付従性に抵触し、民法396条の趣旨に反し許されないとされた事例 |
||
| 297 | H7.3.7 |
公簿上特定の地番により表示される甲乙両地が相隣接する場合に、乙地の所有者が甲地のうち境界の全部に接続する部分を時効取得したとしても、甲乙両地の各所有者は、境界確定の訴えの当事者適格を失わないとした事例 |
||
| 298 | H7.1.24 |
甲が被相続人の遺言により、相続にて不動産の所有権を取得した場合には、甲は単独でその旨の所有権移転登記手続をすることができ、遺言執行者は、遺言の執行としてその登記手続をする義務を負わないとした事例 |
||
| 299 | H7.1.24 |
責任を弁識する能力のない未成年者の行為により火災が発生した場合においては、未成年者の監督義務者が火災による損害を賠償すべき義務を負うが、監督義務者に未成年者の監督について重大な過失がなかったときは、これを免れるとした事例 |
||
| 300 | H7.1.19 |
甲がその所有する一棟の建物のうち構造上区分され独立して住居等の用途に供することができる建物部分のみについて、乙に対し賃借権を設定したが、甲乙間の合意に基づき一棟の建物全部について乙の賃借権設定の登記がされている場合において、甲が乙に対して登記の抹消登記手続を請求したときは、その請求はその建物部分を除く残余の部分に関する限度において認容されるとした事例 |
||
| 301 | H6.12.20 |
地上建物の共有者の一人にすぎない土地共有者の債務を担保するため土地共有者の全員が各持分に共同して抵当権を設定した場合に法定地上権が成立しないとされた事例 |
||
| 302 | H6.12.16 |
民法891条5号にいう遺言書の隠匿に当たらないとされた事例 |
||
| 303 | H6.12.16 |
要役地の所有者が、自己所有地を提供したり費用を負担したりして、道路の拡幅、維持管理を行うとともに、通路として使用していたときには、要役地の所有者によって通路が開設されたものと認められるとし、その後20年以上通路として使用していたことにより通行地役権の時効取得が認められるとした事例 |
||
| 304 | H6.11.24 |
民法719条所定の共同不法行為が負担する損害賠償債務は、いわゆる不真正連帯債務であつて連帯債務ではないから、その損害賠償債務については連帯債務に関する同法437条の規定は適用されないとされた事例 |
||
| 305 | H6.10.11 |
建物借主の失火により建物が全焼してその敷地の使用貸借権を喪失した賃貸人は、焼失時の建物の価格と本件土地使用に係る経済的利益に相当する額との合計額を、本件建物の焼失による損害として請求することができるとした事例 |
||
| 306 | H6.9.27 |
甲の乙に対する売買契約に基づく所有権移転登記手続請求訴訟において、丙が、乙に対して所有権移転請求権保全の仮登記に基づく本登記手続を、甲に対して本登記手続の承諾を求めてした参加の申出は、(旧)民訴法71条による参加の申出に当たらないとされた事例 |
||
| 307 | H6.9.13 |
遺産分割協議により、他の相続人に代償金を交付して単独で相続した不動産を売却した場合の譲渡所得の計算において、相続財産の取得費に、交付した代償金及び代償金支払いのための銀行借入金の利息相当額は、算入することはできないとされた事例 |
||
| 308 | H6.9.8 |
地方公共団体が、買主として、使用目的を定めないで農地の売買契約を締結した後に、当該農地を学校の敷地に供することを確定したときは、その時点において、売買は農地法所定の都道府県知事の許可を経ないで効力を生ずると解された事例 |
||
| 309 | H6.7.18 |
保険契約において保険契約者が死亡保険金の受取人を被保険者の「相続人」と指定した場合は、特段の事情のない限り、右指定には相続人が保険金を受け取るべき権利の割合を相続分の割合によるとする旨の指定も含まれ、各保険金受取人の有する権利の割合は相続分の割合になるとされた事例 |
||
| 310 | H6.6.24 |
押印のない自筆証書遺言の有効性が争われた事案において、遺言書本文の入れられた封筒の封じ目にされた押印をもって民法968条1項の押印の要件に欠けるところはないとして、同遺言書の有効性を認めた原判決を是認した事例 |
||
| 311 | H6.6.21 |
仮差押えによる時効中断の効力は、仮差押解放金の供託により仮差押えの執行が取り消された場合においても、なお継続するとされた事例 |
||
| 312 | H6.5.31 |
条件の成就によって利益を受ける当事者が故意に条件を成就させたときは、民法130条の類推適用により、相手方は条件が成就していないものとみなすことができるとされた事例 |
||
| 313 | H6.5.31 |
入会権者である村落住民が入会団体を形成し、それが権利能力のない社団に当たる場合には、右入会団体は、構成員全員の総有に属する不動産についての総有権確認請求訴訟の原告適格を有するとされた事例 |
||
| 314 | H6.5.12 |
甲建物について滅失の事実がないのに滅失登記がされ、別の乙建物として表示登記及び所有権保存登記がされた場合、甲建物の根抵当権者は、乙建物の所有名義人に対し乙建物の表示登記及び所有権保存登記の抹消登記手続を、甲建物の所有名義人であった者に対し甲建物の滅失の登記の抹消登記手続を請求できるとした事例 |
||
| 315 | H6.4.22 |
都市計画法14条の4の規定に基づく地区計画の決定については抗告訴訟の対象とならないとしてその請求を棄却した事例 |
||
| 316 | H6.4.21 |
当事者が損害賠償の額を予定した場合においても、債務不履行に関し債権者に過失があったときは、特段の事情のない限り、裁判所は、損害賠償の責任及びその金額を定めるにつき、これを斟酌すべきであるとした事例 |
||
| 317 | H6.4.21 |
地方税法73条の21第1項ただし書にいう「当該固定資産の価格により難いとき」とは、当該不動産につき、固定資産税の賦課期日後に増築、改築、損壊、地目の変換その他特別の事情が生じ、その結果、登録価格が当該不動産の適正な時価を示しているものということができないため、登録価格を不動産取得税の課税標準としての不動産の価格とすることが適当でなくなった場合をいうとした事例 |
||
| 318 | H6.4.7 |
土地及び建物が甲・乙の共有に属する場合において、土地についての甲の持分が強制競売により売却され、丙がその持分を取得しても、民事執行法81条の規定による法定地上権は成立しないとした事例 |
||
| 319 | H6.2.22 |
雇用者の安全配慮義務違反によりじん肺にかかったことを理由とする損害賠償請求権の消滅時効は、じん肺法所定の管理区分についての最終の行政上の決定を受けた時から進行するとされた事例 |
||
| 320 | H6.2.8 |
他人の土地上の建物の所有権を取得した者が自らの意思に基づいて所有権取得の登記を経由した場合には、たとい建物を他に譲渡したとしても、引き続き登記名義を保有する限り、土地所有者に対し、譲渡による建物所有権の喪失を主張して建物収去・土地明渡しの義務を免れることはできないとした事例 |
||
| 321 | H6.1.25 |
固有必要的共同訴訟における共同被告の一部に対する訴えの取下げは、効力を生じないとされた事例 |
||
| 322 | H5.12.16 |
特定の土地の分割方法を定めた遺言の存在を知らずになされた遺産分割協議の意思表示について、要素の錯誤がないとはいえないとされた事例 |
||
| 323 | H5.11.25 |
ホテル火災において、ホテルを経営する会社の代表取締役に業務上過失致死傷罪が成立するとされた事例 |
||
| 324 | H5.10.19 |
建物建築工事の注文者と元請負人との間に、請負契約が中途で解除された際の出来形部分の所有権は注文者に帰属する旨の約定がある場合には、元請負人から一括して当該工事を請け負った下請負人が自ら材料を提供して出来形部分を築造したとしても、注文者と下請負人との間に格別の合意があるなど特段の事情のない限り、契約が中途で解除された際の出来形部分の所有権は注文者に帰属するとした事例 |
||
| 325 | H5.10.19 |
・カーボン複写の方法で記載された自筆の遺言は、民法968条1項の自書の要件に欠けるものではなく有効とされた事例 |
||
| 326 | H5.9.24 |
隣接地に下水管を敷設する工事の承諾及び当該工事の妨害禁止請求が、建築基準法に違反する建物建築の場合においては権利の濫用にあたるとされた事例 |
||
| 327 | H5.9.10 |
宅地開発の隣接地の住民らが、開発行為の許可の取消し等を求めた事案において、開発行為に関する工事が完了し、当該工事の検査済証の交付がされた後においては、開発許可の取消しを求める訴えの利益は失われるとした事例 |
||
| 328 | H5.7.19 |
遺言により法定相続分を下回る相続分を指定された共同相続人の一人が、不動産に法定相続分に応じた共同相続登記がなされたことを利用して、その共有持分権を第三者に譲渡し、法定相続分の持分の移転登記をしたとしても、第三者はその相続人の指定相続分に応じた持分を取得するにとどまるとした事例 |
||
| 329 | H5.5.28 |
相続税法55条本文にいう「相続分」には、共同相続人間の譲渡に係る相続分が含まれるとされた事例 |
||
| 330 | H5.3.30 |
幼児が公の営造物を設置管理者の通常予測し得ない異常な方法で使用して生じた事故につき、設置管理者が損害賠償責任を負わないとされた事例 |
||
| 331 | H5.3.30 |
火災保険の目的である建物の譲渡につき、保険者に対する通知義務を怠ったときには保険金の支払が免責される旨の普通保険約款の条項は、譲渡後遅滞なく通知を怠っている間に保険事故が発生した場合に保険者が免責されることを定めたものであるとして、建物譲渡2日後の火災事故による被災において、当特約により保険者が免責されるものではないとした事例 |
||
| 332 | H5.2.26 |
・譲渡担保権者及び譲渡担保設定者は、いずれも譲渡担保の目的不動産について被保険利益を有するとした事例 |
||
| 333 | H5.2.18 |
マンション事業者に対し市が建築指導要綱に基づき教育施設負担金の寄付を求めた行為が、違法な公権力の行使に当たるとされた事例 |
||
| 334 | H5.1.21 |
無権代理人が本人を他の相続人と共に共同相続した場合においては、共同相続人全員が共同して無権代理行為を追認しない限り、無権代理行為が有効となるものではないとした事例 |
||
| 335 | H5.1.21 |
無権代理人が本人を共同相続した場合には、共同相続人全員が共同して無権代理行為を追認しない限り、無権代理人の相続分に相当する部分においても、無権代理行為が当然に有効となるものではないとされた事例 |
||
| 336 | H5.1.19 |
受遺者の選定を遺言執行者に委託する旨の遺言は、遺産の利用目的が公益目的に限定されているため、目的を達成することができる被選定者の範囲が国又は地方公共団体等に限定されているものと解されるときは、有効であるとされた事例 |
||
| 337 | H4.12.10 |
・親権者が子を代理する権限を濫用して法律行為をした場合において、その行為の相手方が権限濫用の事実を知り又は知り得べかりしときは、民法93条但書の規定の類推適用により、その行為の効果は子には及ばないとした事例 |
||
| 338 | H4.11.26 |
都市再開発法51条1項、54条1項に基づき地方公共団体により定められ公告された第二種市街地再開発事業の事業計画の決定は、抗告訴訟の対象となる行政処分に当たるとされた事例 |
||
| 339 | H4.11.16 |
法人に対する土地の遺贈について、遺留分権利者による減殺の請求がされた場合であっても、これに対して民法1041条1項の価額による弁償が行われたときは、その遺贈は所得税法59条1項1号の遺贈に当たるとされた事例 |
||
| 340 | H4.10.20 |
・民法566条3項にいう一年の期間は、除斥期間であるとした事例 |
RETIO 128-114
|
|
| 341 | H4.4.10 |
相続人は、遺産の分割までの間は、相続開始時に存した金銭を相続財産として保管している他の相続人に対して、自己の相続分に相当する金銭の支払を求めることはできないとされた事例 |
||
| 342 | H4.3.19 |
売買予約に基づく所有権移転請求権保全の仮登記のされた不動産の第三取得者は、予約完結権の消滅によって直接利益を受ける者に当たり、その消滅時効を援用することができるとした事例 |
||
| 343 | H4.3.13 |
保険金受取人の死亡時以後保険金の支払理由が発生するまでに受取人の変更がないときは、受取人は死亡した受取人の死亡時の法定相続人に変更されたものとするとの定めは、死亡した保険金受取人の法定相続人で保険金の支払理由が発生した当時の生存者を受取人とすることにあるとした事例 |
||
| 344 | H4.1.24 |
町営の土地改良事業の工事等が完了して原状回復が社会通念上不可能となった場合であっても、右事業の施行の認可の取消しを求める訴えの利益は消滅しないとされた事例 |
||
| 345 | H4.1.24 |
民法258条による共有不動産の分割請求において、請求者が多数である場合においては、被請求者の持分の限度で現物を分割し、その余は請求物らの共有として残す方法によることも許されるとされた事例 |
||
| 346 | H3.11.14 |
デパートの火災事故につき、防火管理上の注意義務を負うのは一般には会社の業務執行権限を有する代表取締役であるとして、会社の取締役人事部長及び建物防火管理責任者には業務上過失致死傷罪が成立しないとされた事例 |
||
| 347 | H3.10.17 |
建物賃貸人の失火による火災で焼失した、衣料品類販売業を営む賃借人の衣料等の損害について、賃貸人の債務不履行による損害賠償責任を認めた事例 |
||
| 348 | H3.7.18 |
同一の建物に二重の表示登記がされた場合において、先行の表示登記に基づく所有権保存登記の名義人等が、その地位に基づいて、後行の表示登記ないしその登記に基づく所有権保存登記の抹消を求めることはできないとされた事例 |
||
| 349 | H3.7.16 |
宅地造成工事の請負人は、造成工事の完了した宅地部分を注文者に引き渡した場合でも、特段の事情がない限り、債権の全部の弁済を受けるまでは残余の土地について留置権を行使することができるとされた事例 |
||
| 350 | H3.5.10 |
連帯債務者の一部の者に対する債権が転付命令によって第三者に移転したとしても、その余の連帯債務者に対する債権は移転しないとした事例 |
||
| 351 | H3.4.19 |
特定の遺産を特定の相続人に「相続させる」趣旨の遺言は、遺言書の記載から、その趣旨が遺贈であることが明らかであるか又は遺贈と解すべき特段の事情のない限り、当該遺産を当該相続人をして単独で相続させる遺産分割の方法が指定されたものと解されるとされた事例 |
||
| 352 | H2.11.29 |
デパート火災事故において、デパートの管理課長、及びビル内のキャバレーの代表取締役、支配人に、業務上過失致死傷罪が成立するとされた事例 |
||
| 353 | H2.11.16 |
ホテルの火災事故において、ホテルの経営者に業務上過失致死傷罪が成立するとされた事例 |
||
| 354 | H2.9.27 |
共同相続人は、既に成立している遺産分割協議につき、その全部又は一部を全員の合意により解除した上、改めて分割協議を成立させることができるとした事例 |
||
| 355 | H2.6.5 |
売買予約に基づく所有権移転請求権保全仮登記の経由された不動産につき抵当権の設定を受け、その登記を経由した者は、予約完結権の消滅によって直接利益を受ける者に当たり、その消滅時効を援用することができるとした事例 |
||
| 356 | H2.1.18 |
固定資産評価審査委員会が土地の登録価格の不服審査を口頭審理手続きによって行う場合において審査申出人に対し評価の根拠等として知らせる措置を講ずべき事項の範囲 |
||
| 357 | H1.12.22 |
民法187条1項(占有の承継)は、権利能力なき社団等の占有する不動産を、法人格を取得した以後当該法人が引き継いで占有している場合にも適用されるとした事例 |
||
| 358 | H1.11.24 |
共有者の一人が死亡し、相続人の不存在が確定し、相続債権者や受遺者に対する清算手続が終了したときは、その共有持分は他の相続財産とともに特別縁故者に対する財産分与の対象となり、その財産分与がされず、当該共有持分が承継すべき者のないまま相続財産として残存することが確定したときにはじめて、民法255条により他の共有者に帰属することになるとした事例 |
||
| 359 | H1.11.8 |
市の宅地開発指導要綱を順守させるための圧力手段として、水道事業者の給水の権限を用い給水契約の締結を拒むことは許されないとされた事例 |
||
| 360 | H1.10.13 |
不動産強制競売手続において催告を受けた抵当権者がする債権の届出は、その届出に係る債権に関する裁判上の請求、破産手続参加又はこれらに準ずる時効中断事由に該当しないとされた事例 |
||
| 361 | H1.9.21 |
・商法266条ノ3第1項前段所定の損害賠償債務は、履行の請求を受けた時に履行遅滞となるとした事例 |
||
| 362 | H1.9.19 |
境界線より50cmの距離を置かないで建物建築を始めた隣地所有者に対して、境界線50cm以内に存する建物の収去を求めた事案において、建築基準法65条所定の建築物の建築には民法234条1項は適用されないとしてその請求が棄却された事例 |
RETIO 14-029
|
|
| 363 | H1.9.14 |
協議離婚に伴う財産分与としての土地建物の譲渡において、譲渡人に多額の譲渡所得税が課税されることを知らなかった錯誤があり無効であるとして、譲受人に所有権移転登記の抹消登記手続を求めた事案において、本件財産分与契約において、譲渡人は自己に課税されないという動機を黙示的に表示していたとして、動機の表示がないことを理由に錯誤の主張を排斥した原判決を破棄し差し戻した事例 |
||
| 364 | H1.7.4 |
土地所有者による、河川管理者が当該土地が河川法にいう河川区域でないこと等の確認を求める訴えにおいて、同法75条に基づく監督処分等をまってこれに関する訴訟等を事後的に争ったのでは回復しがたい重大な損害を被るおそれがある等の特段の事情がないとして、訴えの利益を欠き不適法であるとした事例 |
||
| 365 | H1.6.23 |
自筆遺言証書における押印は、指印をもって足りるとした事例 |
||
| 366 | H1.6.20 |
民法968条の自筆証書遺言における押印としては、遺言者が印章に代えて拇指その他の指頭に墨、朱肉等をつけて押捺すること(指印)をもって足りるとした事例 |
||
| 367 | H1.3.28 |
共同相続人間における遺産確認の訴えは、固有必要的共同訴訟と解すべきとされた事例 |
||
| 368 | H1.3.28 |
消防署職員の消火活動が不十分なため再燃して火災が発生した場合において、失火ノ責任ニ関スル法律を適用し同職員の責任を否定した事例 |
||
| 369 | H1.3.28 |
乙の土地所有権に基づく甲が占有する部分の明渡し請求が境界確定訴訟と併合審理されており、判決において、甲占有部分の乙の所有権が否定され、甲に対する明渡請求が棄却されたときは、たとえ、これと同時に乙主張とおりの土地の境界が確定されたとしても、占有部分については所有権に関する取得時効中断の効力は生じないとされた事例 |
||
| 370 | H1.3.28 |
居住していた家屋より転居した後、相続によりその家屋の所有者となり譲渡をした場合、租税特別措置法35条の居住用財産を譲渡した場合の特別控除の特例を受けるための適用要件に該当しないとされた事例 |
||
| 371 | H1.2.16 |
自筆遺言証書における押印は、指印をもって足りるとした事例 |
||
| 372 | H1.2.9 |
遺産分割協議が成立した場合、相続人の一人が同協議による負担債務を履行しないときであっても、その債権を有する相続人は、民法541条(履行遅滞等による解除権)による同協議の解除はできないとされた事例 |
||
| 373 | S63.11.17 |
土地改良法53条1項2号の照応関係は、土地改良事業の目的に照らし、従前の土地に所有権及び地役権以外の権利又は処分の制限がある場合でない限り、同一所有者に対する従前の土地全体と換地全体とを総合的にみて、その間に認められれば足りるとされた事例 |
||
| 374 | S63.7.1 |
被用者と第三者との共同不法行為により他人に損害を加えた場合において、第三者が自己と被用者との過失割合に従って定められるべき自己の負担部分を超えて被害者に損害を賠償したときは、第三者は、被用者の負担部分について使用者に対し求償することができるとした事例 |
||
| 375 | S63.5.20 |
共有者の一部の者から共有物を占有使用することを承認された第三者に対して、その余の共有者は、当然には、共有物の明渡しを請求することはできないとされた事例 |
||
| 376 | S63.3.31 |
共有者の一人が共有物を他に賃貸して得る収益につきその持分割合を超える部分の不当利得返還を求める他の共有者の請求のうち事実審の口頭弁論終結時後に係る請求部分は、将来の給付の訴えを提起することのできる請求としての適格を有しないとされた事例 |
||
| 377 | S63.3.1 |
無権代理人を本人とともに相続した者が、その後更に本人を相続した場合においては、本人が自ら法律行為をしたと同様の法律上の地位ないし効果を生ずるとされた事例 |
||
| 378 | S63.1.21 |
河川改修工事による収容ないし占用許可の取消しに関し、輪中堤(堤防)の文化財的価値が損失補償の対象になるかがあらそわれた事例において、同輪中堤は歴史的、社会的、学術的価値を内包するが、それ以上に不動産としての市場価値を有するものではないとして、損失補償の対象とはならないとされた事例 |
||
| 379 | S63.1.18 |
共有の性質を有しない入会地上の天然の樹木の所有権について、事実関係の判断により、土地の所有者にあるとされた事例 |
||
| 380 | S62.11.26 |
請負人が破産宣告を受けた場合には、当該請負契約の目的である仕事が請負人以外の者において完成することのできない性質のものでない限り、当該請負契約について破産法59条が適用されるとした事例 |
||
| 381 | S62.11.13 |
未登記建物を買い受けた者が、所有権を証する書面として、同人を建物の建築主とする真実と符合しない記載内容の建築工事完了引渡証明書を添付し建物の表示の登記の申請をした場合には、その登記申請は、不動産登記法49条8号、10号により却下されるとされた事例 |
||
| 382 | S62.11.12 |
不動産が譲渡担保の目的とされ、設定者甲から譲渡担保権者乙への所有権移転登記が経由された場合において、被担保債務の弁済等により譲渡担保権が消滅した後に乙から目的不動産を譲り受けた丙は、民法177条にいう第三者に当たるとした事例 |
||
| 383 | S62.10.8 |
運筆について他人の添え手による補助を受けてされた自筆証書遺言と民法968条1項にいう「自書」の要件について示された事例 |
||
| 384 | S62.10.8 |
無断転貸を理由とする土地賃貸借契約の解除権の消滅時効は、転借人が転貸借契約に基づき当該土地の使用収益を開始した時から進行し、債権に準ずるものとして民法167条1項により10年を経過したときに消滅するととした事例 |
||
| 385 | S62.9.4 |
遺産相続により相続人の共有となつた財産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家事審判法の定めるところに従い、家庭裁判所が審判によつてこれを定めるべきものであり、通常裁判所が判決手続で判定すべきものではないとした事例 |
||
| 386 | S62.9.3 |
物上保証人が債権者に対し被担保債権の存在を承認しても、右承認によっては、債権者と物上保証人との相対的関係においても、被担保債権について時効中断の効力は生じないとされた事例 |
||
| 387 | S62.7.17 |
・区分所有建物の暴力団関係者の使用につき、契約解除及び専有部分の引渡し請求が認められた事例 |
||
| 388 | S62.7.9 |
土地区画整理法77条に基づき従前地上の建物を仮換地上に移築するため解体した場合、同解体は不動産登記法(昭和58年法律第51号による改正前のもの)93条ノ6第1項にいう建物の「滅失」に当たるとされた事例 |
||
| 389 | S62.6.5 |
無権限者から土地を賃借し、平穏公然に土地を継続使用し賃料を支払ってきた土地の賃借人について、使用開始後20年の経過により、土地所有者に対する土地の賃借権の取得時効が成立したとされた事例 |
||
| 390 | S62.4.23 |
・不動産の受遺者は、遺言執行者があるときでも、所有権に基づき、不動産に対する無効な抵当権に基づく競売手続の排除を求めることができるとした事例 |
||
| 391 | S62.4.22 |
・森林法186条は憲法29条2項に違反するとした事例 |
||
| 392 | S62.4.17 |
土地改良事業により土地改良区から換地処分を受けた者が、換地処分は照応の原則に違反し無効であると主張しこれを争おうとするときは、換地処分の無効確認を求める訴えを提起することができるとした事例 |
||
| 393 | S62.2.26 |
土地区画整理事業において、公簿地積を基準地積としてなされた換地処分は、特に希望する者に限り実測地積により得る途が開いてあれば、憲法29条に違反しないとされた事例 |
||
| 394 | S62.2.13 |
売買代金債務を目的とする準消費貸借契約が締結された場合であつても、売主が自己の所有権移転登記手続債務につき売買契約に基づいて有していた同時履行の抗弁権を失わないとされた事例 |
||
| 395 | S62.1.22 |
相続土地の共有持分の取得が相続人らにおいて第一回遺産分割協議を合意解除し改めて第二回遺産分割協議をしたことに伴うものである場合には、右取得は地方税法73条の7第1号にいう「相続に因る不動産の取得」に該当するとされた事例 |
||
| 396 | S61.12.16 |
海は、いわゆる公共用物であって、国の直接の公法的支配管理に服し、特定人による排他的支配の許されないものであり、過去において国が一定範囲を区画してこれを私人の所有に帰属させた場合を除き、所有権の客体たる土地に当たらないとした事例 |
||
| 397 | S61.12.11 |
固定資産評価基準(昭和38年12月25日自治省告示第158号)は、前年中に取得された償却資産の評価については、いわゆる半年分償却法のみを認め、いわゆる月割償却法はこれを認めない趣旨と解するとした事例 |
||
| 398 | S61.12.5 |
農地の売買契約締結後、農地法3条許可前に相続となった場合の課税財産は、売買契約に基づき買主が売主に対して取得した所有権移転請求権等の債権的権利であり、その課税評価額は当該農地の取得価額に相当するとされた事例 |
||
| 399 | S61.11.20 |
クラブのホステスが顧客の飲食代金債務についてした保証契約が公序良俗に反するものとはいえないとされた事例 |
||
| 400 | S61.11.20 |
不倫な関係にある女性に対する包括遺贈が公序良俗に反しないとされた事例 |
||
| 401 | S61.11.20 |
融資の担保の目的で、債務者が自己の第三債務者に対する請負代金債権の代理受領を債権者に委任し、第三債務者が債権者に委任契約の内容を了承し、請負代金を直接支払うことを約束しながら、これを債務者に支払ったときは、債権者は第三債務者に対し、代理受領による貸金の回収という財産上の利益が害されたことを損害として、不法行為に基づく損害賠償請求権を行使することができるとした事例 |
||
| 402 | S61.11.18 |
登記上の所有者を真実の所有者と信じて抵当権を設定し、その後競売にて自ら競落したXが、真実の所有者Aより建物を賃借していたYに対し賃借権の不存在等を求めた事案において、Xが建物の真実の所有者がAであること及びA・Y間の賃貸借契約締結の事実を知らなかったとしても、Yは賃借権をもってXに対抗することができ、Yに対する関係で民法94条2項を適用ないし類推適用する余地はないとした事例 |
||
| 403 | S61.9.11 |
農地法19条(農地又は採草放牧地の賃貸借の存続期間) は、地上権に適用又は準用されないとした事例 |
||
| 404 | S61.7.17 |
従前の土地の所有者は、仮換地の不法占拠者に対し、将来の賃料相当損害金の請求を認容する確定判決を得た場合においても、その事実審口頭弁論終結後に、公租公課の増大、土地の価格の高騰等により、認容額が不相当となったときは、新訴により、認容額と適正賃料額との差額に相当する損害金の支払を求めることができるとした事例 |
||
| 405 | S61.6.19 |
建築基準法46条1項に基づく壁面線の指定は、特定の街区を対象として行う対物的な処分であり、特定の個人又は団体を名あて人として行うものではないから、その指定については行政不服審査法57条1項の適用はない(利害関係人は、同条2項により教示を求めることができるものとされている)とされた事例 |
||
| 406 | S61.3.20 |
民法921条3号にいう相続財産には相続債務も含まれるとした事例 |
||
| 407 | S61.3.17 |
・時効による債権消滅の効果は、時効期間の経過とともに確定的に生ずるものではなく、時効が援用されたときにはじめて確定的に生ずるとした事例 |
||
| 408 | S60.12.17 |
将来換地となることが予想される土地に対して換地計画を定めないでした仮換地指定処分が、土地区画整理法98条1項前段にいう工事のため必要がある場合に当たるとして、適法とされた事例 |
||
| 409 | S60.11.29 |
・障害物の除去時期が確定できないため、使用収益開始の日を追って定める旨通知してなされた仮換地指定につき違法とはいえないとされた事例 |
||
| 410 | S60.11.29 |
甲から不動産を取得した乙がこれを丙に贈与した場合において、乙が、司法書士に依頼し甲に差し出した、不動産を丙に譲渡したので甲から直接丙に所有権移転登記をするよう求める旨の内容証明郵便が、民法550条にいう書面に当たるとされた事例 |
||
| 411 | S60.11.26 |
仮登記担保権が設定された不動産の譲渡を受けた第三者は、当該仮登記担保権の被担保債権の消滅時効を援用することができるとした事例 |
||
| 412 | S60.11.14 |
建築基準法48条1項但書により、特定行政庁が第一種低層住居専用地域における良好な住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した建築物につき、当該敷地の隣接居住者が当該許可の取消しを求める原告適格を有しないとされた事例 |
||
| 413 | S60.7.16 |
建築主と付近住民との紛争につき建築主に行政指導が行われていることのみを理由として建築確認申請に対する処分を留保することは、国家賠償法一条一項所定の違法な行為となるとされた事例 |
||
| 414 | S60.5.17 |
請負契約が請負人の責に帰すべき事由により中途で終了した場合において、注文者が残工事の施工に要した費用として請負人に賠償請求できるのは、残工事に要した費用のうち、未施工部分に相当する請負代金額を超える部分に限られるとされた事例 |
||
| 415 | S60.3.28 |
残代金を約定期限までに支払わないときは契約は当然に解除されたものとする旨の解除条件が付された土地の売買契約において、代金の一部を支払わなかった買主が、契約時より民法162条の自主占有があったとした20年の取得時効の主張が認められた事例 |
||
| 416 | S59.12.20 |
他人名義で根抵当権設定登記を有する債権者は、抵当不動産の譲渡後に開始された不動産競売事件において配当を受けることはできないとされた事例 |
||
| 417 | S59.12.7 |
新築の家屋は、一連の新築工事が完了した時に、固定資産税の課税客体となるとした事例 |
||
| 418 | S59.10.26 |
建築基準法6条1項による確認を受けた建築物の建築等の工事が完了したときは、確認の取消を求める訴えの利益は失われるとした事例 |
||
| 419 | S59.9.20 |
売買に基づく所有権移転登記手続請求権を被保全権利とする処分禁止の仮処分が、その後完成した取得時効に基づく所有権移転登記手続請求権について効力を有するとされた事例 |
||
| 420 | S59.9.6 |
施行者が仮換地を指定するに際し、あらかじめ土地区画整理審議会の意見を聞く手続をとらなかったとしても、それだけで仮換地の指定が当然に無効となるものではないとした事例 |
||
| 421 | S59.5.25 |
農地の譲受人が、当該譲渡について必要な農地調整法(昭和24年法律第215号による改正前のもの)4条1項所定の知事の許可を受けていないときは、特段の事情のない限り、農地を占有するに当たってこれを自己の所有と信じても、無過失であったとはいえないとされた事例 |
||
| 422 | S59.4.24 |
動産執行による金銭債権の消滅時効中断の効力は、債権者が執行官に対しその執行の申立をした時に生ずるとされた事例 |
||
| 423 | S59.4.24 |
共有不動産につき、共有者の一部の者が勝手に自己名義で所有権移転登記又は所有権移転請求権仮登記をした場合に、他の共有者がその共有持分に対する妨害排除として登記名義人に対し請求することができるのは、自己の持分についてのみの一部抹消(更正)登記手続に限られるとした事例 |
||
| 424 | S59.4.5 |
建物所有を目的とする地上権設定登記は、借地法7条による地上権の存続期間が延長された場合においても、これを表示するものとして効力を有するとした事例 |
||
| 425 | S59.3.9 |
不動産の仮差押による時効中断の効力は、第三者の申立による強制競売により不動産が競落されて仮差押の登記が抹消されても失われず、その抹消の時まで中断事由が存続したとされた事例 |
||
| 426 | S59.3.6 |
不動産競売についての予納金及び登録免許税の納付による支出は、所得税法上の必要経費にあたらないとされた事例 |
||
| 427 | S59.1.31 |
数人が共同して行う土地改良事業の認可の申請に同意した者は、既に換地を行うことが予定されているのを了知して同意をしたときであっても、換地計画に同意する義務を負うものではないとした事例 |
||
| 428 | S59.1.19 |
不動産について、贈与を登記原因とした所有権移転登記の抹消手続を求める前訴を提起して敗訴した者が、贈与の不履行を理由に贈与契約を解除したとして、所有権移転登記手続を求める後訴を提起した場合において、後訴の提起は信義則に反するものではないとした事例 |
||
| 429 | S58.12.6 |
市の道路用地買収において、市が買収済の特定の残地を他に優先者のない限り払い下げる旨の説明を受け買収に応じた道路買収協力者の、当該残地が払い下げられたことを理由とする市に対する不法行為に基づく損害賠償請求が棄却された事例 |
||
| 430 | S58.11.15 |
農地の賃貸借について、農地法による知事の許可なく賃貸借契約が合意解除された後、宅地造成が行われ宅地化された場合において、農地の賃貸借契約の合意解除が知事の許可なしに効力を生じたとされた事例 |
||
| 431 | S58.10.28 |
土地区画整理法100条の2の規定により、施行者が管理する土地について、第三者が権原なく同土地を不法に占有する場合には、施行者はこれに対し物権的支配権に基づき土地の明渡を求めることができるとした事例 |
||
| 432 | S58.10.20 |
予見可能性の有無はその公務員の通常有すべき知識経験を基準として判定すべきであるとした事例 |
||
| 433 | S58.9.20 |
委任契約たる税理士顧問契約は、受任者の利益をも目的として締結された場合でない限り、委任者がいつでも、かつ、なんらその理由を告知せずに、解除することができるとした事例 |
||
| 434 | S58.9.8 |
土地収用法133条1項所定の期間経過後に損失の補償に関する訴えが予備的に追加された場合において、事実関係等より主位的請求が損失補償額自体を争う趣旨を含むとみることはできないとして、予備的請求の訴えを出訴期間を徒過して提起されたものとして棄却した事例 |
||
| 435 | S58.9.6 |
農地法五条所定の許可がされた農地に隣接する農地の所有者が当該許可の取消しを求める原告適格を有しないとされた事例 |
||
| 436 | S58.7.5 |
第一売買の買主より不動産を購入し中間省略登記によって仮登記を受けた第二売買の買主に対して、第一売買の売主が、第一売買の合意解除による仮登記の抹消を請求した事案において、第二売買の買主は民法545条1項但書にいう「第三者」に該当しないとしてその請求が認められた事例 |
||
| 437 | S58.4.14 |
建物の登記名義人が不実である場合、真実の建物所有者がその登記名義人の共同相続人であるとしても、同登記をもって建物保護に関する法律1条による法定地上権の対抗力は得られないとした事例 |
||
| 438 | S58.4.8 |
ビラ貼りのための建物立入りが建造物侵入罪にあたるとされた例 |
||
| 439 | S58.3.24 |
民法186条1項の所有の意思の推定は、占有者がその性質上所有の意思のないものとされる権原に基づき占有を取得した事実が証明されるか、又は、占有中真の所有者であれば通常はとらない態度を示し、若しくは所有者であれば当然とるべき行動に出なかつたなど、外形的客観的に占有者が他人の所有権を排斥して占有する意思を有していなかったと解される事情が証明されるときは、覆されるとされた事例 |
||
| 440 | S58.3.18 |
遺言の解釈にあたっては、遺言書の文言を形式的に判断するだけでなく、遺言者の真意を探究すべきものであり、遺言書の特定条項の解釈においても、当該条項と遺言書の全記載との関連、遺言書作成当時の事情及び遺言者の置かれていた状況などを考慮して当該条項の趣旨を確定すべきであるとされた事例 |
||
| 441 | S58.2.18 |
道路法70条1項(道路の新設又は改築に伴う損失の補償)による補償の対象は、道路工事施工による土地の形状変更を直接の原因として生じた障害除去のため、やむを得ず行った工事に起因する損失に限られ、警察規制等による法規制上の障害に基づく損失は含まれないとした事例 |
||
| 442 | S58.2.8 |
入会団体に個別的に加入を認められたと主張する者が入会権者に対し入会権を有することの確認を請求する場合には、主張者が各自単独で訴えを提起することができるとした事例 |
||
| 443 | S58.1.24 |
土地の死因贈与につき、事実関係のもとでは取消ができないとされた事例 |
||
| 444 | S57.12.17 |
連帯債務者の一人が弁済その他の免責の行為をするに先立ち、他の連帯債務者に対し民法443条1項の通知をすることを怠った場合は、既に弁済その他により共同の免責を得ていた他の連帯債務者に対し、同条2項の規定により自己の免責行為を有効であるとみなすことはできないとされた事例 |
||
| 445 | S57.11.18 |
民法826条1項(利益相反行為)の規定に基づいて選任された特別代理人と、未成年者との利益が相反する行為については、特別代理人は、選任の審判によって付与された権限を行使することができないとされた事例 |
||
| 446 | S57.10.19 |
民法724条(不法行為による損害賠償請求権の期間の制限)所定の3年の時効期間の計算においては、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時が午前零時でない限り、時効期間の初日を算入すべきではないとされた事例 |
||
| 447 | S57.10.19 |
土地所有者が、土地賃借人との土地賃貸借契約を合意解除し、不法占有となった者の所有する地上建物を自力救済により違法に取り壊した場合において、土地所有者は土地の不法占有を理由とする建物所有者に対する損害賠償請求ができるとされた事例 |
||
| 448 | S57.7.15 |
約束手形の裏書人が振出人の手形金支払義務の時効による消滅に伴い、自己の所持人に対する償還義務も消滅したとしてその履行を免れようとすることが信義則に反し許されないとされた事例 |
||
| 449 | S57.7.1 |
・入会部落の構成員が有する使用収益権の確認又はこれに基づく妨害排除の請求については、構成員各自に当事者適格があるとされた事例 |
||
| 450 | S57.6.17 |
・一筆の土地の一部分の売買契約において、対象土地部分が具体的に特定していないとされた事例 |
||
| 451 | S57.6.17 |
農地の売買において、買主が約定の履行期後売主に対し再三にわたり売買契約の履行を催告し、その間常に残代金の支払の準備をし、農地法3条所定の認可がされ次第残代金の支払いができる状態にあったときは、現実に残代金を提供しなくても、民法557条1項の「契約の履行に着手」したものと認められた事例 |
||
| 452 | S57.4.30 |
負担の履行期が贈与者の生前と定められた負担付死因贈与の受贈者が負担の全部又はこれに類する程度の履行をした場合、特段の事情がない限り、民法1022条、1023条の規定は準用されないとされた事例 |
||
| 453 | S57.4.22 |
都市計画区域内における高度地区指定の決定は、抗告訴訟の対象にならないとされた事例 |
||
| 454 | S57.4.22 |
都市計画法8条1項1号の規定に基づく工業地域指定の決定は、抗告訴訟の対象にならないとした事例 |
||
| 455 | S57.3.25 |
所有権移転請求権保全の仮登記の名義人は、登記上利害関係を有する第三者の承諾書等がないため、仮登記とは無関係に所有権移転登記を経由した場合であっても、特段の事情のない限り、仮登記義務者に対して仮登記の本登記手続を請求する権利を失わず、右仮登記の本登記を承諾すべき第三者の義務も消滅しないとした事例 |
||
| 456 | S57.3.9 |
・共有物分割の訴えは、分割方法を具体的指定の必要はなく、単に共有物の分割を求める旨の申し立てで足りるとした事例 |
||
| 457 | S57.2.18 |
未登記不動産にも民法177条の適用があり、時効取得者は登記を備えなければ、時効完成後に不動産を取得し登記を備えた第三者に対し対抗できないとした事例 |
||
| 458 | S57.1.29 |
執行力のある債務名義又は終局判決を有しない破産債権者の届出債権に対する債権調査期日における破産管財人又は他の債権者の異議は、破産債権届出の時効中断の効力に影響を及ぼすものではないとされた事例 |
||
| 459 | S57.1.22 |
山林原野が村有財産として管理処分され、部落による共同体的統制の存在が認められない場合において、共有の性質を有する入会権及び共有の性質を有しない入会権ともに認められないとされた事例 |
||
| 460 | S57.1.22 |
譲渡担保を設定した債務者の受戻の請求において、債務の弁済と弁済に伴う目的不動産の返還請求権とを合体して、一個の形成権たる受戻権であるとの法律構成をする余地はなく、これに民法167条2項(消滅時効)の規定を適用することはできないとした事例 |
||
| 461 | S57.1.19 |
固定資産の土地名寄帳及び家屋名寄帳は、市町村が固定資産税の課税上の必要に基づき作成する資料であり、その記載が固定資産税の納税義務者の権利義務に影響を及ぼすものではないから、固定資産の所有者であっても、法律上市町村に対し名寄帳の閲覧を請求する権利はないとした事例 |
||
| 462 | S56.12.18 |
自筆証書遺言における証書の記載自体からみて明らかな誤記の訂正については、民法968条2項所定の方式の違背があっても、その違背は遺言の効力に影響を及ぼさないとされた事例 |
||
| 463 | S56.12.4 |
仮換地について、賃借権の目的となるべき土地の指定を受けていない賃借人に対する、賃貸人の明渡請求が権利の濫用にあたるとされた事例 |
||
| 464 | S56.11.24 |
不動産につき取得時効が完成したときは、同不動産についての取得時効期間の進行中に締結され、所有権移転請求権仮登記により保全された売買予約上の買主の地位は消滅し、時効取得者は、その所有権の取得を登記なくして仮登記権利者に対抗することができるとした事例 |
||
| 465 | S56.10.30 |
共有不動産につき、単独相続したとして登記を得て売買した売主が、当該不動産につき自己が取得した持分をこえる部分の所有権が無効であると主張して、買主および買主よりの転取得者に対し、所有権移転の無効及び抹消(更正)登記手続を請求することは信義則に照らして許されないとした事例 |
||
| 466 | S56.10.16 |
日本国内に営業所を有する外国法人に対する損害賠償請求訴訟については、右法人にわが国の裁判権が及ぶものと解するのが相当とされた事例 |
||
| 467 | S56.10.8 |
書面によらない土地の贈与者が受贈者に土地の占有及び登記名義を移転することができない場合において、事実関係により贈与の履行が終了したものとして民法550条に基づく取消の効力が否定された事例 |
||
| 468 | S56.10.1 |
農地の受贈者の贈与者に対して有する知事に対する所有権移転許可申請協力請求権は、民法167条1項の債権にあたり、請求権は贈与契約成立の日から10年の経過により時効によって消滅するとした事例 |
||
| 469 | S56.9.18 |
庭園等に使用する各種花木を幼木から栽培している土地が、農地法2条1項にいう農地にあたらないとはいえないとされた事例 |
||
| 470 | S56.9.11 |
・遺言無効確認訴訟における確認の利益の存否判断にあたっては、原則として、原告の相続分が被相続人から受けた生前贈与等によりなくなるか否かを考慮すべきものではないとされた事例 |
||
| 471 | S56.7.16 |
給水装置新設工事申込の受理の事実上の拒絶につき、建築基準法違反の状態にある建物の状況を是正し建築確認を受けたうえ申込をするよう一応の勧告をしたものにすぎないとして、不法行為による損害賠償責任を否定した事例 |
||
| 472 | S56.7.3 |
・所有権に基づく登記請求を認容した確定判決は、その理由において所有権の存否を確認している場合であっても、所有権の存否について既判力を有しないとした事例 |
||
| 473 | S56.7.3 |
土地区画整理法103条の規定に基づく換地処分について被処分者がする審査請求の請求期間の起算日は、同人が換地処分の通知を受けてその処分があったことを知った日の翌日であるとした事例 |
||
| 474 | S56.6.26 |
負担付贈与がされた場合における贈与税の課税価格は、贈与に係る財産の時価から当該負担額を控除した価格であるとされた事例 |
||
| 475 | S56.6.16 |
長期間継続した地代不払を一括して一個の解除原因とする賃貸借契約の解除権の消滅時効は、最後の地代の支払期日が経過した時から進行するとした事例 |
||
| 476 | S56.6.4 |
・一区画の仮換地の一部を所有の意思をもって所要の期間継続して占有した者は、従前の土地につき当該占有部分に対応する部分が特定されていないときは、時効により従前の土地に対する共有持分権を取得するとともに、当該占有部分につき、共有持分権者の一人が現に排他的な使用収益権能を取得している場合と同様の使用収益権能を取得するとした事例 |
||
| 477 | S56.4.14 |
いわゆる政令指定都市の区長が弁護士法23条の2に基づく照会に応じて前科及び犯罪経歴を報告したことが過失による公権力の違法な行使にあたるとされた事例 |
||
| 478 | S56.4.3 |
被相続人の遺言書又はこれになされている訂正が方式を欠き無効である場合に、相続人が方式を具備させ有効な遺言書又はその訂正としての外形を作出する行為は、遺言書の偽造又は変造(民法891条5号)にあたるが、それが遺言者の意思実現のため、その法形式を整える趣旨でされたにすぎないときは、同相続人は相続欠格者にあたらないとされた事例 |
||
| 479 | S56.2.24 |
債務者が甲であるのに、誤って債務者が乙であるとして、乙所有の不動産になされた抵当権設定登記の効力があらそわれた事案において、債務者の表示の不一致は更正登記により訂正することができ、抵当権設定登記は有効であるされた事例 |
||
| 480 | S56.2.17 |
建物等の工事が未完成の間に、注文者が請負人の債務不履行により契約を解除する場合において、工事内容が可分であり、しかも当事者が既施工部分の給付に関し利益を有するときは、特段の事情のない限り、未施工部分についての契約の一部解除はできるが、既施工部分についての契約解除はできないとされた事例 |
||
| 481 | S56.2.5 |
別荘地の買主と分譲業者との間の土地管理契約について、同契約に基づかなければ分譲業者の水道等の諸施設の利用できず、分譲業者も管理費により別荘地の維持、管理の経費をまかなっている等の事実関係のもとにおいては、受託者である分譲業者から一方的に管理契約を解約することができないとされた事例 |
||
| 482 | S56.1.27 |
土地の買主が売買契約に基づいて目的土地の占有を取得した場合には、他人物売買であるため土地の所有権を直ちに取得するものでないことを買主が知っているときであっても、特段の事情のない限り、買主の占有は所有の意思をもってするものとすべきであるとされた事例 |
||
| 483 | S56.1.19 | 建物管理契約において、委任者が委任契約の解除権自体を放棄したものとは解されない事情がある場合は、委任者はやむをえない事由がなくても、民法651条により契約を解除することができるとされた事例 |
||
| 484 | S55.12.11 |
賃借権の譲渡を承諾しない賃貸人は、無断譲渡を理由とする賃貸借契約の解除権が時効消滅した場合であっても、所有権に基づき、賃借権の無断譲受人に対し目的物の明渡を求めることができるとした事例 |
||
| 485 | S55.12.4 |
盲人は、公正証書遺言に立ち会う証人としての適格を有するとした事例 |
||
| 486 | S55.9.11 |
登記申請権者の申請に基づかないで不実の商業登記がされた場合には、登記を登記申請権者の申請に基づく登記と同視するのを相当とするような特段の事情がない限り、商法14条は適用されないとされた事例 |
||
| 487 | S55.7.15 |
建築基準法6条1項に基づく確認申請の審査の対象には、当該建築計画の民法234条1項の規定への適合性(隣地より50cm)は含まれないとされた事例 |
||
| 488 | S55.7.10 |
土地区画整理組合が、原則として公簿地積を基準地積とし例外的に実測地積による方法で土地区画整理事業を施行する場合において、定款には単に原則的な基準のみを記載し、例外的な措置の詳細については、別に定款の委任により執行機関の制定する執行細則等における定めにこれを委ねることも許されるとした事例 |
||
| 489 | S55.7.1 |
相続税法34条1項の規定による連帯納付義務は、相続人又は受遺者の固有の相続税の納税義務の確定という事実に照応して法律上当然に確定するとされた事例 |
||
| 490 | S55.5.30 |
約束手形の所持人と裏書人との間において裏書人の手形上の債務につき支払猶予の特約がされた場合には、所持人の裏書人に対する手形上の請求権の消滅時効は、同猶予期間が満了した時から進行するとされた事例 |
||
| 491 | S55.4.18 |
土地収用法旧71条及び74条(昭和42年法律第74号による改正前のもの)のもとにおいて、当該事業の施行が残地の価格に及ぼす影響のうち利益と損失とを明確に区別することができない場合に、それらを総合的に勘案することは、同法90条の相殺禁止規定に抵触しないとされた事例 |
||
| 492 | S55.3.6 |
土地区画整理事業施行地内の土地の売買につき、従前地につきそれが別の特定の土地に換地されることを前提として締結された売買契約は、換地処分等に無効などの瑕疵があるとしても、予定通りの換地がされないことが確定しない限り効力を有するとした事例 |
||
| 493 | S55.2.29 |
農地の売買における買主の売主に対する許可申請協力請求権の消滅時効は、売主が他人から当該農地の所有権を取得した時から進行し、10年の経過により消滅するとした事例 |
||
| 494 | S55.1.22 |
市街化区域内農地の宅地並み課税により固定資産税等が著しく上昇したとしても、小作料の最高額の統制を定める農地法改正法(昭和45年法律第56号)附則8項は、財産権を保障する憲法29条に違反するものではないとした事例 |
||
| 495 | S54.12.14 |
被相続人が生存中に無権代理にて不動産を第三者に譲渡した共同相続人が、違産分割の結果当該不動産を取得しないこととなった場合について、民法909条但書の適用がなく、第三者は同共同相続人の法定相続分に応じた共有持分権を取得しないとした事例 |
||
| 496 | S54.12.14 |
無権代理行為の追認には、取り消しうべき行為についての法定追認を定めた民法125条は類推適用されないとした事例 |
||
| 497 | S54.11.30 |
建物明渡の確定判決がなされたが建物の明渡に応じなかった医療法人の建物の不法占拠につき、医療法人の理事らに対する不法行為による損害賠償責任を認めた事例 |
||
| 498 | S54.9.27 |
未登記建物につき書面によらないで贈与契約がされた場合に、贈与者の意思に基づき直接受贈者名義に保存登記がされたときには、贈与契約の履行が終ったものとして、贈与契約を取り消すことはできないとされた事例 |
||
| 499 | S54.9.21 |
借地法10条による建物買取請求権について、当該土地明渡請求訴訟における訴状送達の時から10年の経過により時効消滅しているとされた事例 |
||
| 500 | S54.9.11 |
所有権移転仮登記に後れて目的物件につき権原を取得し占有を開始した第三者は、仮登記権利者あるいは仮登記に基づき本登記を行った所有権者に対し、本登記がなされる以前の物件占有について、不法占有者としての損害賠償責任は負わないとした事例 |
||
| 501 | S54.9.7 |
土地改良法に基づく農用地の交換分合の前後を通じ、特定の所有者の失うべき土地と取得すべき土地とについて自主占有が継続しているときは、取得時効の成否に関しては両土地の占有期間を通算することができるとされた事例 |
||
| 502 | S54.7.31 |
占有者の占有が自主占有にあたらないことを理由に取得時効の成立を争う者は、占有が他主占有にあたることについての立証責任を負うとした事例 |
||
| 503 | S54.5.31 |
自筆遺言証書の日付として「昭和四拾壱年七月吉日」と記載された証書は、民法968条1項にいう日付の記載を欠くものとして無効であるとした事例 |
||
| 504 | S54.3.20 |
仕事の目的物に瑕疵がある場合には、注文者は、瑕疵の修補が可能なときであっても、修補を請求することなく直ちに修補に代る損害賠償を請求することができるとした事例 |
||
| 505 | S54.3.15 |
土地地積更正登記につき、当該土地の隣接地の所有者は、その取消を求める法律上の利益を有しないとした事例 |
||
| 506 | S54.3.1 |
土地区画整理事業の施行区域内の特定土地につき、所有権その他権利を有する者全員が他の土地の換地に影響を及ぼさない限度内において、特定土地に対する換地の位置、範囲に関し合意し、換地を求める申し出があったときは、事業施行者は、公益に反せず事業施行上支障を生じない限り、土地区画整理法89条1項所定の基準によることなく、合意に従って各土地の換地を定めることができるとした事例 |
||
| 507 | S54.2.22 |
共同相続人全員の合意によって遺産分割前に遺産を構成する特定不動産を売却した場合の売却代金は、特別の事情のない限り、相続財産には加えられず、共同相続人が各持分に応じて個々にこれを分割取得するとした事例 |
||
| 508 | S54.2.20 |
請負人が第三者に損害を与えた場合において、注文者に注文又は指図について過失があるとした事例 |
||
| 509 | S54.2.2 |
請負契約の目的物の瑕疵修補に代わる損害賠償請求をした場合の損害額の算定時点は、請求時を基準として行われるとし、後に物価の高騰により修補費用が増加したとしても、注文主は請負人に対しその増加額を求めることはできないとした事例 |
||
| 510 | S54.1.30 |
所有権保存登記抹消登記手続請求訴訟において勝訴の確定判決を得た原告が、被告の口頭弁論終結後の承継人に対し真正な登記名義の回復のための所有権移転登記手続を求める訴は、前訴の判決の存在によって当然に訴えの利益を欠くことにはならないとした事例 |
||
| 511 | S54.1.25 |
建築途中の未だ独立の不動産に至らない建前に第三者が材料を供して工事を施し、独立の不動産である建物に仕上げた場合における建物所有権の帰属は、民法243条の規定によるのではなく、同法246条2項の規定に基づいて決定すべきとした事例 |
||
| 512 | S54.1.19 |
賃借人が複数の共同賃借人であるときにおいて、賃貸人が借地法12条に基づく賃料増額の請求をする場合は、賃借人全員に対し増額の意思表示をする必要があり、その意思表示が賃借人の一部に対してされたにすぎないときは、これを受けた者との関係においてもその効力を生じないとされた事例 |
||
| 513 | S53.12.20 |
共同相続人の一人によって相続権を侵害された共同相続人のその侵害の排除を求める請求には民法884条の適用があるとされた事例 |
||
| 514 | S53.12.14 |
土地賃借権の無断譲受人による土地の使用が賃借意思に基づくものではないとして、賃借権の時効取得が否定された事例 |
||
| 515 | S53.11.30 |
注文者の請負人に対する目的物の瑕疵修補に代わる損害賠償債権を自働債権とし請負人の注文者に対する工事代金債権を受働債権とする相殺が当事者間の特約により許されないとされた事例 |
||
| 516 | S53.10.5 |
不動産の引渡請求権者は、目的不動産についてされた債務者の処分行為を詐害行為として取り消す場合に、直接自己に対する所有権移転登記手続を請求することはできないとされた事例 |
||
| 517 | S53.9.21 |
請負人の注文者に対する報酬債権と注文者の請負人に対する目的物の瑕疵修補に代わる損害賠償債権とは、両債権額が異なる場合であっても相殺できるとされた事例 |
||
| 518 | S53.9.7 |
農地につき売買契約が二重に締結され、各買主が所有権移転の仮登記を経由した後、第二買主が農地法の手続を行い売買契約の効力を発生させた上農地を宅地としたときは、売主と第一の買主間の売買契約はその効力を生じ、第一の買主は第二の買主に対し仮登記に基づく本登記の承諾を求めることができるとした事例 |
||
| 519 | S53.7.17 |
相殺の計算をするにあたっては、民法506条の規定に則り、双方の債権が相殺適状となった時期を標準として双方の債権額を定め、その対当額において差引計算をすべきであるとされた事例 |
||
| 520 | S53.7.13 |
共同相続人の1人が遺産を構成する特定の不動産について、同人の有する共有持分権を第三者に譲り渡した場合については、民法905条の規定を適用又は類推適用することはできないとされた事例 |
||
| 521 | S53.7.10 |
登記権利者及び登記義務者双方から登記手続の委託を受けた司法書士が登記義務者から登記手続に必要な書類の返還を求められた場合でも、登記権利者に対する関係ではその返還を拒むべき委任契約上の義務があるとした事例 |
||
| 522 | S53.7.4 |
営造物の通常の用法に即しない行動の結果事故が生じた場合において、その営造物として本来具有すべき安全性に欠けるところがなく、右行動が設置管理者において通常予測することのできないものであるときは、右事故が営造物の設置又は管理の瑕疵によるものであるということはできないとされた事例 |
||
| 523 | S53.4.11 |
共有不動産の分割により他の共有者の有していた持分を取得することは、地方税法73条の2第1項にいう「不動産の取得」にあたり、不動産取得税の課税対象となるとした事例 |
||
| 524 | S53.3.6 |
不動産の占有主体に変更があって承継された二個以上の占有が併せて主張された場合、民法162条2項にいう占有者の善意・無過失は、その主張にかかる最初の占有者につきその占有開始の時点において判定すれば足りるとされた事例 |
||
| 525 | S53.2.24 |
共同相続人の一人が他の共同相続人の全部又は一部の者の後見をしている場合において、後見人が被後見人全員を代理してする相続の放棄は、後見人みずからが相続の放棄をしたのちにされたか、又はこれと同時にされたときは利益相反行為にあたらないとされた事例 |
||
| 526 | S53.2.24 |
・賃料増額請求が争われた場合における増額分の賃料は、原則として、その債権の存在を認める裁判が確定した日の属する年分の所得の計算上、収入金額に算入されるとした事例 |
||
| 527 | S53.2.16 |
農地法の不在地主による小作地の所有禁止の規定は、憲法29条に違反しないとされた事例 |
||
| 528 | S53.2.16 |
夫婦の一方の特有財産である資産を財産分与として他方に譲渡することは、所得税法33条1項にいう「資産の譲渡」にあたり、譲渡所得を生ずるとした事例 |
||
| 529 | S52.12.23 |
整地請負契約の解除の認定において、一部解除の認定は相当でなく、契約全部を解除する旨の意思表示をしたと認定するのが相当であるとされた事例 |
||
| 530 | S52.12.8 |
民法上の組合所有の不動産を理事名義に登記することを承諾した組合員が、組合から不動産を譲り受けた後も理事名義のままにしていたが、その後理事より第三者が譲渡を受け所有権移転登記を経由した場合、組合員は理事の所有権取得の無効をもって善意無過失の第三者に対抗することができないとされた事例 |
||
| 531 | S52.9.29 |
土地の管理権を与えられ他に賃貸する権限を有していると称する者との間で締結された賃貸借契約に基づき、賃借人が平穏公然に土地の継続的な用益をしていた事案において、賃借人の土地賃借権の時効取得を認めた事例 |
||
| 532 | S52.6.14 |
遺言者が、公正証書による遺言をするにあたり、公証人があらかじめ筆記した遺言内容を読み聞かせたのに対し、遺言者が単にうなづくのみであって、立会証人の一人が遺言者の真意を十分に確認することができなかったときは、民法969条2号にいう口授があったものとはいえないとされた事例 |
||
| 533 | S52.5.2 |
建物賃貸において賃貸人が受領した保証金のうち、特約により返還を要しないとした部分は、賃貸人の受領した年の不動産所得の収入金額であるとされた事例 |
昭52(行ツ)18号(裁判所HP未登載) |
|
| 534 | S52.4.28 |
道路について、黙示的に公用が廃止されたものとして取得時効の成立が認められた事例 |
||
| 535 | S52.4.15 |
書証の成立の真正についての自白は裁判所を拘束しないとされた事例 |
||
| 536 | S52.4.4 |
農地の売買契約について、知事の許可を受ける前であつても、買主が残代金全額を支払いのため提供したときは、契約の履行の着手があったと解されるとした事例 |
||
| 537 | S52.3.3 |
農地の賃借人が所有者から農地を買い受けたときは、農地調整法4条所定の都道府県知事の許可又は市町村農地委員会の承認を得なかったとしても、買主は、売買契約が締結されその代金が支払われた時に、民法185条にいう新権原により所有の意思をもって農地の占有を始めたものというべきであるとされた事例 |
||
| 538 | S52.2.22 |
請負契約において仕事が完成しない間に注文者の責に帰すべき事由によりその完成が不能となった場合には、請負人は自己の残債務を免れるが、民法536条2項により、注文者に請負代金全額を請求することができ、ただ、自己の債務を免れたことにより得た利益を注文者に償還すべきであるとされた事例 |
||
| 539 | S52.2.17 |
農地を目的とする売買契約締結後に買主が農地を宅地化した事案において、売買契約が知事の許可なしに効力を生ずるとされた事例 |
||
| 540 | S52.1.20 |
土地区画整理法による換地処分がされた場合、従前の土地に存在した未登記賃借権は、これについて同法85条のいわゆる権利申告がされていないときでも、換地上に移行して存続するとした事例 |
||
| 541 | S51.12.24 |
公共用財産が、長年事実上公の目的に供用されることなく放置され、公共用財産としての形態、機能を全く喪失した場合には、公共用財産について黙示的に公用が廃止されたものとして、その物を平穏かつ公然に占有した者の取得時効の成立を認めた事例 |
||
| 542 | S51.12.20 |
農地の買主が農地法5条の許可申請手続に協力しない場合でも、売買代金が完済されているときは、特段の事情のない限り、売主は買主が協力をしないことを理由に売買契約を解除することはできない |
||
| 543 | S51.12.2 |
所有者の無権代理人から農地を買い受けた小作人が、新権原による自主占有を開始したものとされ占有の始め過失がないとされた事例 |
||
| 544 | S51.11.5 |
不動産の譲渡による所有権移転登記請求権は、譲渡によって生じた所有権移転の事実が存する限り独立して消滅時効にかからないとした事例 |
||
| 545 | S51.10.12 |
不動産取得税の5年の消滅時効の起算日は、登記又は申告等の日を基準とすべきでなく、実際に取得した日であるとした事例 |
||
| 546 | S51.9.7 |
共有にかかる土地が不法に占有されたことを理由として、共有者の全員又はその一部の者から不法占有者に対してその損害賠償を求める場合には、共有者は、それぞれその共有持分の割合に応じて請求をすべきものであり、その割合を超えて請求をすることは許されないとした事例 |
||
| 547 | S51.8.30 |
遺留分権利者が受贈者又は受遺者に対し民法1041条1項の価額弁償を請求する訴訟における贈与又は遺贈の目的物の価額算定の基準時は、訴訟の事実審口頭弁論終結の時であるとされた事例 |
||
| 548 | S51.8.30 |
山林「a」の仮換地「A」について仮換地自体に着目して売買契約が締結されたのち、仮換地の指定の変更により、山林「a」の一部である山林「a’」につき仮換地「A」と同一性のある仮換地「A’」が、山林「a」の残部である山林「b」につき仮換地「B」が各指定され、次いで仮換地がそのまま換地「A”」、換地「B’」と定められた場合には、買主は換地「A”」の所有権を取得するにすぎず換地「B’」の所有権を取得するものではないとされた事例 |
||
| 549 | S51.7.19 |
相続人が遺言の執行としてされた遺贈による所有権移転登記の抹消登記手続を求める訴については、遺言執行者がある場合でも、受遺者が被告となるとされた事例 |
||
| 550 | S51.7.8 |
使用者がその事業の執行につき、被用者の惹起した自動車事故により損害を被った場合において、信義則上被用者に対し、右損害の一部についてのみ賠償及び求償の請求が許されるにすぎないとされた事例 |
||
| 551 | S51.6.25 |
電気器具の販売会社が継続的商取引上の債権担保のため、保証人本人の実印の押してある本人名義の契約書と本人の印鑑証明書とを持参した代理人との間で連帯根保証契約を締結した場合に、民法110条の正当理由があるとはいえないとされた事例 |
||
| 552 | S51.6.17 |
農地買収・売渡処分が買収計画取消判決の確定により失効した場合、被売渡人から土地を買い受けた者が、土地返還請求訴訟提起後に買収処分の無効に帰すべきことを疑わずに有益費を支出したとしても、有益費償還請求権に基づく土地留置権を行使することはできないとした事例 |
||
| 553 | S51.5.25 |
消滅時効の援用が権利濫用にあたるとされた事例 |
||
| 554 | S51.4.8 |
先順位受附の登記申請人が、後順位受附の登記申請に基づき不動産登記法48条に違反してされた登記につき、同条違反だけを理由にその抹消登記手続を求めることは許されないとされた事例 |
||
| 555 | S51.3.26 |
不動産取得税の納税者が同税の賦課処分の取消訴訟において、固定資産課税台帳に登録された当該不動産の価格が客観的に適正な価格と異なると主張して課税標準たる価格を争うことはできないとされた事例 |
||
| 556 | S51.3.18 |
相続人が被相続人から贈与された金銭を、いわゆる特別受益として遺留分算定の基礎となる財産の価額に加える場合には、贈与の時の金額を相続開始の時の貨幣価値に換算した価額をもって評価すべきとされた事例 |
||
| 557 | S51.3.4 |
建造物侵入罪の客体となるいわゆる囲繞地にあたるとされた事例 |
||
| 558 | S50.12.25 |
土地区画整理法による土地区画整理のための換地予定地を不法に占有する者がある場合、従前の土地所有者は、これに対し所有権に基づく物上請求権と同様の権利を行使することができるとされた事例 |
||
| 559 | S50.12.23 |
甲から所有権を譲り受けてその登記を経由した乙は、登記簿滅失による回復登記申請期間を徒過しても、乙の登記後甲から所有権を譲り受けた丙に対し、自己の所有権取得を対抗できるとされた事例 |
||
| 560 | S50.12.18 |
地方税法73条の21第1項にいう「固定資産課税台帳に固定資産の価格が登録されている不動産」とは、不動産を取縛した日の属する年の1月1日における当該不動産の価格が固定資産課税台帳に登録されている不動産を指すとされた事例 |
||
| 561 | S50.11.28 |
土地賃借人が建物保護に関する法律1条によりその賃借権を第三者に対抗しうるためには、賃借人が借地上に自己名義で登記した建物を所有していることが必要であり、自己の子名義で登記をした建物を所有していても、その賃借権を第三者に対抗しえないとした事例 |
||
| 562 | S50.11.28 |
仮登記担保権者が、目的不動産を自己の所有とすると意思表示をしただけで清算をせず、仮登記のまま目的不動産を第三者に譲渡し、第三者が本登記を経た場合において、本登記が債務者の意思に基づかずにされたときは、債務者は第三者に対して本登記の抹消登記手続を請求することができるとした事例 |
||
| 563 | S50.11.21 |
物上保証人に対する抵当権の実行により、競売裁判所が競売開始決定をし、これを債務者に告知した場合には、被担保債権についての消滅時効は中断するとされた事例 |
||
| 564 | S50.11.7 |
共同相続人の一部から遺産を構成する特定不動産の共有持分権を譲り受けた第三者が当該共有関係の解消のためにとるべき裁判手続は、遺産分割審判ではなく、共有物分割訴訟であるとされた事例 |
||
| 565 | S50.10.28 |
建物新築による不動産工事の先取特権保存の登記につき、建物所在地番の更正が許されないとされた事例 |
||
| 566 | S50.10.14 |
第三者の売買予約に基づく所有権移転請求権保全の仮登記が存在する建物の競落人は、後日売買予約の完結により仮登記の本登記がなされ、目的物件の所有権を喪失した場合には、当該建物の売買(競落)を解除することができるとした事例 |
||
| 567 | S50.9.25 |
時効による農地所有権の取得については、農地法三条の適用はないとされた事例 |
||
| 568 | S50.6.26 |
道路工事中であった県道の工事標識板や赤色灯が、直前に通過した車両により倒され灯りが消され状態であったために引き起こされた事故について、道路管理に瑕疵はなかったとして国賠法に基づく請求が棄却された事例 |
||
| 569 | S50.5.27 |
財産分与としてされた不動産の譲渡は、譲渡所得課税の対象となるとされた事例 |
||
| 570 | S50.5.27 |
それぞれ登記がされている隣接する二棟の建物につき、2階の隔壁の一部を除去し連絡したという事実のみで、両建物がそれぞれの建物としての独立性を失い一棟の建物になつたものと判断することはできないとした事例 |
||
| 571 | S50.4.22 |
賃借地の一部に属するものと信じて賃貸人以外の第三者所有の隣地を占有していた者が、国に物納された右賃借地の払下を受け、以後所有の意思をもって第三者の所有地を占有するに至ったというだけでは、これを自己の所有と信ずるにつき過失がなかったとはいえないとされた事例 |
||
| 572 | S50.4.11 |
農地の買主が売主に対して有する知事に対する所有権移転許可申請協力請求権の消滅時効は、10年であるとした事例 |
||
| 573 | S50.4.11 |
文化財保護法が、史跡名勝天然記念物に関する現状変更行為禁止の代償として補償規定を定めなかったことをもって、違憲無効ということはできないとした事例 |
||
| 574 | S50.4.8 |
養子とする意図で他人の子を嫡出子として出生届をしても、出生届をもって養子縁組届とみなし、有効に養子縁組が成立したものとすることはできないとされた事例 |
||
| 575 | S50.4.4 |
宅地建物取引業者が行った法律事務の取扱いについて、商法503条により商行為となるが、それが一回限りであり、かつ、反復の意思をもってなされたものでないとして、弁護士法72条に触れないとした事例 |
||
| 576 | S50.3.6 |
土地の売主の共同相続人の一部の者が登記手続義務の履行を拒絶しているため、買主が代金支払いを拒絶している場合に、他の相続人は履行を拒絶している相続人に対し、買主に代位して買主の所有権移転登記手続請求権を行使することができるとした事例 |
||
| 577 | S50.2.13 |
借地人が借地上に自己を所有者と記載した表示の登記のある建物を所有する場合は、建物保護に関する法律一条にいう登記したる建物を有するときにあたるとした事例 |
||
| 578 | S50.1.31 |
農地について締結された賃貸借契約に確定期限が付されている場合において賃借権設定許可申請手続がされないままその期限が到来したときは、賃貸人の賃借人に対する許可申請手続義務は消滅するとされた事例 |
||
| 579 | S50.1.31 |
第三者の不法行為又は債務不履行により家屋が焼失した場合、その損害につき火災保険契約に基づいて家屋所有者に給付される保険金は、第三者が負担すべき損害賠償額から損益相殺として控除されるべき利益にはあたらないとした事例 |
||
| 580 | S49.12.24 |
約1年9ヶ月前に日本に帰化した遺言者の、署名は存するが押印を欠く英文の自筆遺言証書について有効とされた事例 |
||
| 581 | S49.12.20 |
準禁治産者である権利者が保佐人の同意を得られないため訴を提起できない場合でも、その権利についての消滅時効の進行は妨げられないとされた事例 |
||
| 582 | S49.12.17 |
転用目的の農地の売主は、特別の事情がないかぎり、買主に対し、農業委員会が農地法五条の許可の判断資料として事実上提出を求めた隣接農地所有者の承諾を取得すべき義務を負うものではないとされた事例 |
||
| 583 | S49.12.17 |
商法266条の3第1項前段所定の第三者の取締役に対する損害賠償請求権の消滅時効期間は10年と解すべきとした事例 |
||
| 584 | S49.11.22 |
建物が売買により順次占有が承継され、当初建物占有者の占有開始から20年の経過により、現建物所有者につき取得時効が完成した旨の主張は、仮にその占有の間に占有承継人として別の者が介在することが証拠上認められるならば、その者の占有を取得時効の期間として主張する趣旨を含むと解されるとした事例 |
||
| 585 | S49.11.5 |
信用保証協会が債務者及び保証人と、協会の代位弁済による求償債権の損害金につき法定利息と異なる約定をしても、協会は約定を第三者に対抗することはできないとされた事例 |
||
| 586 | S49.9.26 |
甲を欺罔してその農地を買い受けた乙が、農地法五条の許可を条件とする所有権移転仮登記を得たうえ、売買契約上の権利を善意の丙に譲渡して仮登記移転の附記登記をした場合には、丙は民法96条3項にいう第三者にあたるとされた事例 |
||
| 587 | S49.9.20 |
民法216条にいう工作物の破潰又は阻塞は、それが、自然力ないしは不可抗力によって生じた場合に限らず、工作物の所有者の故意過失によって生じた場合も含むとされた事例 |
||
| 588 | S49.9.20 |
相続の放棄は、民法424条の詐害行為取消権行使の対象とならないとした事例 |
||
| 589 | S49.9.20 |
相続税の課税価格の算出上控除すべき弁済期未到来の金銭債務の評価方法 |
||
| 590 | S49.9.4 |
他人の権利の売主が死亡し、その権利者において売主を相続した場合、権利者は相続により売主の売買契約上の義務ないし地位を承継するが、相続前と同様その権利の移転につき諾否の自由を保有し、特別の事情のないかぎり、売買契約上の売主としての履行義務を拒否することができるとした事例 |
||
| 591 | S49.5.8 |
土地売却の仲介をした宅建業者が売主との契約により売却にかかる土地の再評価税を自己の負担において代納付した場合、その代納付金が当該土地の仲介手数料を得た年度の収入を得るために支出した費用であって、その金額も算定可能であったときは、代納付金は同年度の経費として計上すべきであるとした事例 |
||
| 592 | S49.4.26 |
相続財産の限度での支払を命ずる判決が確定した場合における判決の効力 |
||
| 593 | S49.3.19 |
賃貸中の宅地を譲り受けた者は、その所有権の移転につき登記を経由しないかぎり、賃貸人たる地位の取得を賃借人に対抗できないとした事例 |
||
| 594 | S49.3.8 |
雑所得として課税された金銭債権が後日貸倒れにより回収不能となった場合、当該課税処分そのものが取消又は変更されなくても、国は、同処分に基づいて先に徴収した所得税のうち貸倒額に対応する税額を不当利得として納税者に返還する義務を負うとした事例 |
||
| 595 | S49.2.7 |
不動産につき贈与を原因とする所有権移転仮登記が経由されているにとどまるときは、これにより仮登記権利者の所有権取得又は仮登記の当事者間における贈与契約の成立を推定することはできないとされた事例 |
||
| 596 | S49.2.5 |
行政財産である土地について建物所有を目的とし期間の定めなくされた使用許可が当該行政財産本来の用途又は目的上の必要に基づき将来に向って取り消されたときは、使用権者は特別の事情のないかぎり、取消による土地使用権喪失についての補償を求めることはできないとした事例 |
||
| 597 | S48.12.21 |
土地区画整理事業による換地処分確定後の換地につき、売買による所有権の移転があっても、換地に関する清算交付金請求権は、売買当事者間において清算交付金の帰属についての特段の合意がないかぎり、売買当事者の関係のみならず、整理事業施行者に対する関係でも、買主には移転しないとした事例 |
||
| 598 | S48.12.14 |
抵当不動産の譲渡を受けた第三者は、抵当権の被担保債権の消滅時効を援用することができるとした事例 |
||
| 599 | S48.12.11 |
農地の売買契約締結後、その現況が宅地となった場合には、特段の事情のないかぎり、売買契約は知事の許可なしに効力を生ずるとされた事例 |
||
| 600 | S48.12.7 |
従前地の一部の賃借人は、土地区画整理事業施行者から仮換地につき使用収益すべき部分の指定を受けなかったとしても、従前の土地所有者との間で、仮換地の特定部分について使用収益できる旨合意し、かつ、特定部分がそのまま本換地の一部となることを条件として換地処分終了後もこれを賃貸借する旨合意した場合には、従前の土地所有者との関係では特定部分について賃借権を主張することができるとした事例 |
||
| 601 | S48.11.22 |
破産者がした債務の弁済が破産管財人により否認され、その給付したものが破産財団に復帰したときは、さきにいったん消滅した連帯保証債務は、当然復活するとされた事例 |
||
| 602 | S48.11.16 |
昭和36年法律第74号による改正前の地方税法のもとにおいても、譲渡担保による不動産の取得は、同法73条の2第1項にいう「不動産の取得」にあたるとして、不動産取得税の課税が容認された事例 |
||
| 603 | S48.10.30 |
代理人がした商行為による債権につき本人が提起した債権請求訴訟の係属中に、相手方が商法504条但書に基づき債権者として代理人を選択したときは、本人の請求は、右訴訟が係属している間代理人の債権につき催告に準じた時効中断の効力を及ぼすとされた事例 |
||
| 604 | S48.10.18 |
旧都市計画法(大正8年法律第36号)16条1項に基づき土地を収用する場合、被収用者に対し土地収用法72条(昭和42年法律第74号による改正前のもの)によって補償すべき相当な価格を定めるにあたっては、当該都市計画事業のため同土地に課せられた建築制限を斟酌してはならないとした事例 |
||
| 605 | S48.10.12 |
農地売買につき、売主が買主と協力して農地法五条の許可申請をしたが手続上の不備で受理を拒まれたときは、許可申請をしたことをもって売主の買主に対する売買契約上の許可申請義務を果たしたとはいえないとされた事例 |
||
| 606 | S48.10.11 |
債権者は、金銭を目的とする債務の不履行による損害賠償として、債務者に対し弁護士費用その他の取立費用を請求できないとした事例 |
||
| 607 | S48.10.9 |
権利能力のない社団の代表者が社団の名においてした取引上の債務は、社団の構成員全員に一個の義務として総有的に帰属し、社団の総有財産だけがその責任財産となり、構成員各自は、取引の相手方に対し個人的債務ないし責任を負わないとされた事例 |
||
| 608 | S48.10.5 |
抵当権の設定されている建物の買主は、抵当権の実行により建物が他に競落されたのち、不法占有中に建物に支出した費用に関し留置権を主張することはできないとした事例 |
||
| 609 | S48.10.5 |
入会部落の総有に属する土地の譲渡を受けた同部落の構成員は、譲渡前にこれを時効取得した者に対する関係において、民法177条にいう第三者にあたるとされた事例 |
||
| 610 | S48.9.7 |
手形債務を主たる債務として手形外の連帯保証契約が締結されている場合において、連帯保証人に対し裁判上の請求がされたときは、手形債務についても消滅時効が中断するとされた事例 |
||
| 611 | S48.7.12 |
数量の不足又は一部滅失の場合における売主の瑕疵担保責任の除斥期間は、善意の買主が、売買目的物の数量不足を知ったが、その責に帰さない事由により売主を知ることができなかった場合には、売主を知った時から起算されるとした事例 |
||
| 612 | S48.6.28 |
未登記建物の所有者は、その建物が固定資産課税台帳上他人の所有名義で登録されていることを知りながら、これを明示または黙示に承認していた場合には、民法94条2項の類推適用により、名義人が所有権を有しないことを善意の第三者に対抗することができないとした事例 |
||
| 613 | S48.5.25 |
農地法20条2項各号所定の事由は、都道府県知事が同条による許可を与えるについての要件であって、農地の賃貸借の解約権の発生ないし行使の実体的要件をなすものではないとされた事例 |
||
| 614 | S48.4.26 |
甲が所有土地につき、乙の同意のないままに乙への所有権移転登記を経由し乙名義で丙に売却した等の事情のある場合において、乙に譲渡所得があるとした課税処分は無効であるとした事例 |
||
| 615 | S48.4.24 |
親権者が共同相続人である数人の子を代理してした遺産分割の協議は、民法826条2項の利益相反行為に当たるとして、追認のない限り無効であるとした事例 |
||
| 616 | S48.4.13 |
土地に対する使用貸借上の借主の権利の時効取得が成立するためには、土地の継続的な使用収益という外形的事実が存在し、かつ、その使用収益が土地の借主としての権利の行使の意思に基づくものであることが客観的に表現されていることを必要とするとした事例 |
||
| 617 | S48.3.13 |
・入会権確認訴訟において、入会権者が死亡した場合には、入会慣行に従って死亡者に代わり入会権を取得した者が、その訴訟手続を承継するとした事例 |
||
| 618 | S48.1.26 |
不動産の交換契約の当事者甲が、契約に基づき相手方乙の提供した不動産の占有を開始しても、甲が契約の締結に際し詐欺を行ない、そのため契約が乙の錯誤により無効と認められるときは、甲の占有は所有の意思をもって善意・無過失で開始されたと認めるべきではないとした事例 |
||
| 619 | S47.12.14 |
従前地の一部につき、甲の賃借権を乙が譲り受けたが、別に賃借権を主張する者があったため、土地区画整理事業施行者が紛争の経緯を考慮して、甲に対し従前地に対する換地予定地につき賃借権の目的となる部分の指定通知をしたときは、乙は同部分につき使用収益権を取得するとした事例 |
||
| 620 | S47.11.28 |
甲が、乙と相通じ、仮装の所有権移転請求権保全の仮登記手続をする意思で、乙の提示した所有権移転登記手続に必要な書類に、これを仮登記手続に必要な書類と誤解して署名押印したところ、乙がほしいままに書類を用いて所有権移転登記手続をしたときは、甲は、乙の所有権取得の無効をもって善意・無過失の第三者に対抗することができないとされた事例 |
||
| 621 | S47.11.21 |
法人における民法192条(即時取得)の善意・無過失は、その法人の代表者について決するが、代理人が取引行為をしたときは、その代理人について決すべきであるとされた事例 |
||
| 622 | S47.11.9 |
民法936条1項の規定により相続財産管理人が選任された場合において、相続財産に関する訴訟については、相続人が当事者適格を有し、相続財産管理人は、相続人全員の法定代理人として訴訟に関与するものであって、相続財産管理人としての資格では当事者適格を有しないとされた事例 |
||
| 623 | S47.11.9 |
従前の土地につき賃借権を有する者は、仮換地につき、土地区画整理事業の施行者から仮にその権利の目的となる土地またはその部分の指定を受けないかぎり、当該仮換地を使用収益することができないとされた事例 |
||
| 624 | S47.9.8 |
共同相続人の一人が相続財産につき単独所有者としての自主占有を取得したと認められた事例 |
||
| 625 | S47.7.18 |
・生前相続による不動産所有権の取得は、登記を経なければ第三者に対抗できないとされた事例 |
||
| 626 | S47.7.13 |
土地の賃借人は、借地上に妻名義で保存登記を経由した建物を所有していても、その後その土地の所有権を取得した第三者に対し、建物保護に関する法律一条により、その土地の賃借権をもって対抗することができないとされた事例 |
||
| 627 | S47.7.6 |
登記簿上後順位の抵当権者または仮登記担保権者であった者でも、先順位の仮登記担保権者から本登記手続承諾請求を受けた当時、既に他にその登記につき附記登記による権利移転の登記を経由した者は、仮登記担保権者に対して清算金を受けるべき地位にあることを主張できないとされた事例 |
||
| 628 | S47.6.22 |
土地の賃借人は、借地上に妻名義で保存登記を経由した建物を所有していても、その後その土地の所有権を取得した第三者に対し、建物保護に関する法律一条により、その土地の賃借権をもって対抗することができないとされた事例 |
||
| 629 | S47.6.2 |
権利能力なき社団の資産たる不動産については、社団の代表者が、社団の構成員全員の受託者たる地位において、個人の名義で所有権の登記をすることができるにすぎず、社団を権利者とする登記をし、または、社団の代表者である旨の肩書を付した代表者個人名義の登記をすることはできないとされた事例 |
||
| 630 | S47.5.25 |
民法974条3号(証人及び立会人の欠格事由)にいう「配偶者」には、推定相続人の配偶者も含まれるとされた事例 |
||
| 631 | S47.5.25 |
死因贈与の取消については、民法1022条(遺言の撤回)がその方式に関する部分を除いて準用されるとされた事例 |
||
| 632 | S47.4.13 |
詐害行為取消の消滅時効の進行時点である、取消権者が取消の原因を覚知した時とは、取消権者が詐害行為取消権発生の要件たる事実、すなわち、債務者が債権者を害することを知って当該法律行為をした事実を知ったことを意味し、単に取消権者が詐害の客観的事実を知っただけでは足りないとした事例 |
||
| 633 | S47.3.23 |
請負契約が請負人の債務不履行により、請負人が注文主に対し前払金返還債務を負担することを約した場合、特段の事情がない限り、保証人も約定の債務について賠償責任を負うとされた事例 |
||
| 634 | S47.3.21 |
債権者のする破産宣告の申立は、債権の消滅時効の中断事由たる裁判上の請求にあたるとした事例 |
||
| 635 | S47.3.17 |
危急時遺言の遺言書に遺言をした日附ないしその証書の作成日附を記載することは、遺言の有効要件ではなく、遺言書に作成の日として記載された日附が正確性を欠いていても、遺言は無効ではないとされた事例 |
||
| 636 | S47.2.24 |
登記簿の記載から賃借権の消滅を信頼した建物の競落人について、民法94条2項(通謀虚偽表示)の類推適用がないとされた事例 |
||
| 637 | S47.2.18 |
建物の賃借人がその責に帰すべき事由によつて賃借建物に火災を発生させ、これを焼失させた場合には、賃貸人は、特段の事情のないかぎり、催告を経ないで賃貸借契約を解除することができるとした事例 |
||
| 638 | S47.1.25 |
不動産の所有者でない者が、登記簿上その所有者として登記されているため、不動産に対する固定資産税を課せられ納付した場合には、所有名義人は真の所有者に対し、不当利得として納付税額相当額の返還を請求できるとした事例 |
||
| 639 | S46.12.21 |
建物の共有者の一人がその敷地を所有する場合において、土地に設定された抵当権が実行され、第三者がこれを競落したときは、土地につき建物共有者全員のために法定地上権が成立するとされた事例 |
||
| 640 | S46.12.9 |
隣接する土地の一方または双方が共有に属する場合の境界確定の訴えは、固有必要的共同訴訟と解すべきであるとした事例 |
||
| 641 | S46.11.30 |
・土地区画整理事業の施行者が仮換地上の建物の移転除却を怠った不作為につき、土地所有者に対する損害賠償責任が認められた事例 |
||
| 642 | S46.11.30 |
相続人が、被相続人の死亡により、相続財産の占有を承継したばかりでなく、新たに相続財産を事実上支配し、所有の意思を持って占有を開始した場合においては、被相続人の占有が所有の意思のないものであったときでも、相続人は民法185条にいう「新権原」により所有の意思をもって占有を始めたものであるとした事例 |
||
| 643 | S46.11.30 |
甲乙丙三者間において中間省略登記の合意が成立した場合においても、中間者乙は、当然には甲に対する移転登記請求権を失うものではないとした事例 |
||
| 644 | S46.11.26 |
換地予定地の指定通知が従前の土地の所有者に対してなされた後においては、当該換地予定地を占有するのでなければ、従前の土地を占有したからといって、その従前の土地の所有権地上権または賃借権を時効によつて取得することはできないとされた事例 |
||
| 645 | S46.11.26 |
地上権の時効取得が成立するためには、土地の継続的な使用という外形的事実が存在するほかに、その使用が地上権行使の意思に基づくものであることが客観的に表現されていることを要するとした事例 |
||
| 646 | S46.11.25 |
不動産の売主が売買契約の効力の発生を争うとともに仮定的にその取得時効を援用した場合に、売買契約の効力につき判断することなく、売主のため取得時効の完成を認めることを妨げないとした事例 |
||
| 647 | S46.11.25 |
土地所有権の取得時効の要件として無過失と認められた事例 |
||
| 648 | S46.11.16 |
被相続人が、生前不動産をある相続人に贈与するとともに、他の相続人にもこれを遺贈した後、相続の開始があった場合、贈与および遺贈による物権変動の優劣は、対抗要件たる登記の具備の有無をもって決するとされた事例 |
||
| 649 | S46.11.11 |
民法162条2項の10年の取得時効を主張するものは、その不動産を自己の所有と信じたことにつき無過失であったことの立証責任を負うとした事例 |
||
| 650 | S46.11.9 |
知事の許可のない使用貸借契約に基づいて引き渡された農地の返還請求が、その権利の行使において信義誠実の原則に従ったものとはいえず排斥を免れないとされた事例 |
||
| 651 | S46.11.5 |
不動産の二重譲渡において、登記未経由のまま占有していた買主が時効取得を主張する場合の起算点は、占有開始の時点であるとした事例 |
||
| 652 | S46.10.28 |
不法の原因により既登記建物を贈与した場合、その引渡しをしただけでは、民法708条にいう不法原因給付があったとはいえないとされた事例 |
||
| 653 | S46.7.14 |
弁護士法72条は、弁護士でない者が、報酬を得る目的で、業として同条本文所定の法律事務を取り扱いまたはこれらの周旋をすることを禁止する規定であるとした事例 |
||
| 654 | S46.6.18 |
不動産の共有物分割訴訟においては、共有者間に持分の譲渡があっても、その登記が存しないため、譲受人が持分の取得をもって他の共有者に対抗することができないときは、共有者全員に対する関係において、持分がなお譲渡人に帰属するものとして共有物分割を命ずべきであるとした事例 |
||
| 655 | S46.6.11 |
農地の売主と買主の地位の譲受人との間における知事の許可申請手続等に関する合意が有効とされた事例 |
||
| 656 | S46.4.23 |
工作物が本来備えるべき安全性を欠く場合には、工作物の設置又は保存に瑕疵があるものとして、民法717条(工作物責任)所定の帰責原因となるとされた事例 |
||
| 657 | S46.4.21 |
仮登記名義人が本登記を申請する場合、第三者の承諾書またはこれに対抗しうべき裁判の謄本の添付を要するとした不動産登記法105条1項は、憲法29条に違反しないとされた事例 |
||
| 658 | S46.4.20 |
第三者の金銭債務について、親権者が連帯保証をするとともに、子の代理人として、同一債務につき連帯保証をし、親権者と子が共有する不動産について抵当権を設定する行為は、民法826条の利益相反行為にあたるとした事例 |
||
| 659 | S46.4.8 |
不動産が甲から乙丙丁と順次譲渡され所有権移転登記は、甲が同意しないのに甲から直接丁に対し経由された場合において甲が登記を無効としてその抹消を求めることが許されないとされた事例 |
||
| 660 | S46.4.6 |
農地の買主が目的農地を転売した場合に、転買人が当初の売主に対して直接農地法五条所定の知事に対する許可申請手続を求めることは許されないとした事例 |
||
| 661 | S46.3.9 |
購入土地の一部につき、買受人が農業委員会作成の図面または法務局備付の図面を閲覧し、実地調査をすれば、当該土地が売買に含まないことを容易に知り得たにもかかわらず、この調査をせず自己の所有に属するとして開始した占有には、自己の所有と信じたことに過失があるとされた事例 |
||
| 662 | S46.3.5 |
請負人が材料全部を提供して建築した建物が、完成と同時に注文者の所有に帰したものと認められた事例 |
||
| 663 | S46.2.23 |
地積更正登記は土地の表示に関する登記(不動産登記法78条)であって、権利に関する登記ではないから、これについては、不動産登記法66条、56条の適用はないとした事例 |
||
| 664 | S45.12.22 |
家屋の塀における器物毀棄罪につき、被害物件の所有者の妻に告訴権を認めた事例 |
||
| 665 | S45.12.18 |
仮換地の指定後に、従前の土地を所有する意思をもって当該仮換地の占有を始めた者は、換地処分の公告の日までに民法162条所定の要件を満たしたときは、取得により従前の土地の所有権を取得するとされた事例 |
||
| 666 | S45.12.15 |
不動産の賃借人は、賃借権に基づいて、賃貸人に代位し、賃借不動産について権原なく所有権取得登記を有する第三者に対し、賃貸人の物上請求権を代位行使し、その登記の抹消手続を求めることはできないとした事例 |
||
| 667 | S45.12.15 |
寺院境内地についての土地賃借権の時効取得が認められた事例 |
||
| 668 | S45.12.15 |
無権代理人が、無権代理による契約後にその目的物の共有持分を譲り受けた場合においても、契約の相手方が民法117条にいう履行を選択した事実がないときは、持分に対する部分につき、契約が有効となるものではないとした事例 |
||
| 669 | S45.12.10 |
乙が甲から所有権移転登記を経た不動産について、甲より登記原因の無効を理由とする予告登記がなされた後、乙より丙に所有権移転登記がされ、ついで甲勝訴の判決が確定した場合において、甲の丙に対する所有権移転登記抹消請求の訴えを排訴することは、予告登記の効力により妨げられるものではないとされた事例 |
||
| 670 | S45.11.26 |
農地の売買契約において、本件土地が宅地化されるに至った原因およびその経緯に鑑み、宅地化により本件各売買契約は、農地法所定の許可を経ることなくその効力を生ずるに至ったとされた事例 |
||
| 671 | S45.11.24 |
地主の承諾を得て土地賃借権の譲渡を受け、土地上の所有建物につき登記を経由して第三者に対する対抗力を備えた者は、土地の一部についての賃借権の二重譲渡を受け、これに建物を建てその占有をなす者に対し、直接その建物の収去明渡請求をすることができるとされた事例 |
||
| 672 | S45.11.19 |
不動産の買主が、売主に対する貸金を債権とした抵当権設定登記および所有権移転請求権保全の仮登記を経た場合において、売主より不動産を買い受け所有権登記を経た善意の第三者に対して、買主は自己の登記が実体上の権利関係と相違し仮登記を経由した所有権者であると主張することはできないとした事例 |
||
| 673 | S45.11.6 |
数個の共有建物が一筆の土地上にあり外形上一団の建物とみられる場合に、民法258条により建物につき現物分割をするには、建物を一括して分割の対象とし、共有者がそれぞれ各個の建物の単独所有権を取得する方法によることも許されるとした事例 |
||
| 674 | S45.10.29 |
占有における所有の意思の有無は、占有取得の原因たる事実によって客観的に定められるべきものであるから、所有権譲受を内容とする交換契約に基づき開始した占有は、所有の意思をもってする占有であるとされた事例 |
||
| 675 | S45.10.23 |
借地権の設定に際し土地所有者が受け取る権利金は、長期の存続期間を定め、かつ、借地権の譲渡性を認める等、所有者が当該土地の使用収益権を半永久的に手離す結果となる場合に、その価額が更地価格の極めて高い割合の金額であるなど、明らかに所有権の権能の一部を譲渡した対価であるものでないかぎり、譲渡所得にはあたらないとされた事例 |
||
| 676 | S45.10.21 |
不法の原因により未登記建物を贈与した場合、1)その引渡は民法708条にいう給付にあたる、2)贈与者は所有権を理由とする建物返還請求はすることができない、3)贈与者が給付物の返還請求ができない反射的効果として、建物所有権は受贈者に帰属する、4)建物所有権が受贈者に帰属した場合、贈与者が建物の所有権保存登記を経由しても、受贈者は贈与者に対し同保存登記につき抹消登記手続を請求できる、とした事例 |
||
| 677 | S45.9.22 |
不実の所有権移転登記が所有者の承認のもとに存続せしめられていたものとして、民法94条2項を類推適用すべきものとされた事例 |
||
| 678 | S45.8.20 |
・国道への落石の事故につき道路の管理に瑕疵があると認められた事例 |
||
| 679 | S45.7.16 |
現存する建物の所有者が、その建物の所在地上に以前存在していた旧建物の所有名義人に対し、旧建物の滅失登記手続を訴求する利益はないとされた事例 |
||
| 680 | S45.7.15 |
弁済供託における供託金取戻請求権の消滅時効は、供託の基礎となった債務について紛争の解決などによってその不存在が確定するなど、供託者が免責の効果を受ける必要が消滅した時から進行し、10年をもって完成するとされた事例 |
||
| 681 | S45.6.18 |
占有における所有の意思の有無は、占有取得の原因たる事実によって外形的客観的に定められるべきものであるから、賃貸借が法律上効力を生じない場合にあっても、賃貸借により取得した占有は他主占有というべきであるとされた事例 |
||
| 682 | S45.6.2 |
甲が融資を受けるため、乙と通謀して不動産の売買を仮装して乙に所有権移転登記をし、乙がさらに丙に融資の斡旋を依頼して不動産の登記手続に必要な登記済証等を預け、丙がこれらの書類により乙よりの所有権移転登記を経たときは、甲は丙の所有権取得の無効をもって善意無過失の第三者に対抗できないとした事例 |
||
| 683 | S45.5.28 |
地上権の時効取得が成立するためには、土地の継続的な使用という外形的事実が存在するほかに、その使用が地上権行使の意思に基づくものであることが、客観的に表現されていることを要するとされた事例 |
||
| 684 | S45.5.22 |
不動産の賃借人が賃貸人の相続人に対して賃借権の確認を求める訴訟は、相続人が数人あるときでも、必要的共同訴訟ではないとした事例 |
||
| 685 | S45.5.21 |
債務者が、消滅時効の完成後に、債権者に対し当該債務を承認した場合においても、以後ふたたび時効は進行し、債務者は、再度完成した消滅時効を援用することができるとされた事例 |
||
| 686 | S45.4.21 |
証人または当事者本人として真実を陳述することに対する対価として金員を支払う旨の契約が公序良俗に反するとされた事例 |
||
| 687 | S45.4.16 |
未登記建物の所有者が、その建物につき家屋台帳上他人の所有名義で登録されていることを知りながら、これを明示または黙示に承認した場合には、その所有者は台帳上の名義人から権利の設定を受けた善意の第三者に対し、民法94条2項の類推適用により対抗することができないとされた事例 |
||
| 688 | S45.4.10 |
・仮換地の土地一部分の売買契約において、売主は所有権移転登記に関し、仮換地全体に対する目的土地の地積に応じた従前地の持分権の移転登記手続を履行する義務を負い、買主が売主に対し仮換地指定変更申請に協力しないことが、同義務に影響を及ぼすものではないとした事例 |
||
| 689 | S45.3.26 |
契約を解除した当事者が第三者の登記の欠缺を主張することが信義則上許されないとされた事例 |
||
| 690 | S45.3.26 |
建物の登記が所在地番の表示において実際と多少相違する事案において、建物保護に関スル法律1条1項の「登記したる建物を有する」に当たるとされた事例 |
||
| 691 | S45.2.24 |
登記の欠缺を主張することができない、いわゆる背信的悪意者にあたるとされた事例 |
||
| 692 | S45.2.12 |
下請負人の被用者の加害行為につき元請負人の使用者責任が認められた事例 |
||
| 693 | S45.1.23 |
不動産の二重譲渡において双方の買主がそれぞれ売主に対して処分禁止の仮処分を執行した後、第一次仮処分債権者が本案の勝訴判決に基づいて所有権移転登記を経由した場合、その買主は第二次仮処分債権者に対し自己の所有権を対抗できるとした事例 |
||
| 694 | S44.12.23 |
建物保護に関する法律1条は、登記した建物をもって土地賃借権の登記に代用する趣旨であり、当該建物の登記に所在の地番として記載されている土地についてのみ、同条による賃借権の対抗力を生ずるとした事例 |
||
| 695 | S44.12.19 |
不動産の買主が売主に対して処分禁止の仮処分をした場合に、不動産の他の買主が同一不動産について第二次の処分禁止の仮処分をすることは妨げられないが、第一次仮処分の債権者が、被保全権利の実現として、売買契約に基づく所有権移転登記を経由したときは、第二次仮処分の債権者は、自己の仮処分の効力を主張して所有権の取得を否定することはできないとした事例 |
||
| 696 | S44.12.18 |
不動産を買い受け所有権に基づいてこれを占有する買主は、売主との関係においても、自己の占有を理由として不動産につき時効による所有権の取得を主張することができるとした事例 |
||
| 697 | S44.12.11 |
所有権に基づいて不動産を占有するものについて、所有権の取得時効の適用があるとした事例 |
||
| 698 | S44.12.4 |
道路法の道路について、その後所有権を取得し登記した第三者は、道路管理者に対し対抗要件の欠缺を主張できる場合であっても、道路管理者の不法占有を理由とする損害賠償請求は許されないとされた事例 |
||
| 699 | S44.11.27 |
債務者兼抵当権設定者が債務の不存在を理由として提起した抵当権設定登記抹消登記手続請求訴訟において、債権者兼抵当権者が請求棄却の判決を求め被担保債権の存在を主張したときは、その主張は裁判上の請求に準ずるものとして、被担保債権につき消滅時効中断の効力を生ずるとした事例 |
||
| 700 | S44.11.26 |
・取締役の悪意又は重過失による任務懈怠と第三者の損害との間に相当因果関係があるかぎり、これにより会社が損害を被り、ひいて第三者に損害が生じた場合であると、直接第三者が損害を被った場合であるとを問わず、当該取締役は直接第三者に対し損害賠償責任を負うとした事例 |
||
| 701 | S44.11.18 |
住宅建設・販売事業を営む事業者の被用者との間で、土地・建物の購入契約をし代金を支払ったが、被用者にその権限がなかった事案において、権限がないことを知らなかったことに重大な過失はなかったとして、買受人の事業者に対する使用者責任に基づく損害賠償請求が認められた事例 |
||
| 702 | S44.11.13 |
土地(地番A)の賃借人が、賃借地上の所有建物を、自己所有地(地番B)上の所有建物に合併登記したところ、建物所在地が地番B番とのみ表示され、地番Aの表示がされない場合であっても、合併登記をもって賃借人は賃借地(地番A)上に建物保護法1条にいう登記した建物を所有するとされた事例 |
||
| 703 | S44.11.4 |
従前の土地の所有者の所有する仮換地上の建物が抵当権の実行により競落されたときは、従前の土地について法定地上権が成立し、競落人は、法定地上権に基づいて仮換地の使用収益が許されるとされた事例 |
||
| 704 | S44.10.31 |
農地を目的とする売買契約締結後に、買主がこれに地盛りをし売主の承諾のもと建物を建築するなどしたため、土地が完全に宅地に変じた場合には、売買契約は知事の許可なしに効力を生ずるとした事例 |
||
| 705 | S44.10.30 |
土地を占有していた被相続人が死亡し相続が開始した場合には、特別の事情のないかぎり、被相続人の土地に対する占有は相続人によつて相続されるとした事例 |
||
| 706 | S44.9.12 |
請負契約に基づき建築された建物所有権が原始的に注文者に帰属するとした事例 |
||
| 707 | S44.9.2 |
共有不動産につき、共有者の一人が単独所有権として登記を経由した場合において、他の共有者は、単独所有権の取得登記を共同所有権の取得登記に更正登記手続を求めることができるとされた事例 |
||
| 708 | S44.7.24 |
賃貸借契約終了または所有権に基づく家屋明渡請求権を共同相続した者の賃借権者または不法占有者に対する家屋明渡請求訴訟は、必要的共同訴訟ではないとされた事例 |
||
| 709 | S44.7.24 |
一筆の土地の一部の賃借人が賃借地を含む土地に対する仮換地の指定に際し賃借権の届出をしたが土地区画整理事業施行者から使用収益すべき部分の指定がない場合、賃借人は仮換地につき現実に使用収益をする権能を有しないとした事例 |
||
| 710 | S44.7.15 |
建物賃借人は、建物賃貸人による敷地所有権の取得時効を援用することはできないとされた事例 |
||
| 711 | S44.7.8 |
建物の所有者がその敷地を占有する権原のない場合に、建物の所有者を代表者とする会社がその建物を借り受け占有しているときは、同会社は敷地の所有者に対し敷地の不法占有による損害賠償責任を負うとした事例 |
||
| 712 | S44.7.8 |
他人の土地の用益がその他人の承諾のない転貸借に基づくものである場合において、土地の継続的な用益という外形的事実が存在し、かつ、その用益が賃借の意思に基づくものであることが客観的に表現されているときは、その土地の賃借権ないし転借権を時効により取得することができる |
||
| 713 | S44.6.26 |
・法人格のない財団として設立中の財団法人に訴訟上の当事者能力が認められた事例 |
||
| 714 | S44.6.24 |
所有権に基づく登記請求を認容した確定判決は、その理由において所有権の存否を確認している場合であっても、所有権の存否について既判力およびこれに類似する効力(いわゆる争点効)を有するものではないとされた事例 |
||
| 715 | S44.6.17 |
甲所有の従前地につき換地処分がされたときは、換地処分公告の翌日から従前地とみなされる換地につき甲は所有権を取得し、当該換地部分につき乙が所有権を有していたとしても、これに対しなんらの換地処分等がされないときは、公告の翌日以後は当該換地部分につき乙の所有権を認めることはできないとした事例 |
||
| 716 | S44.6.3 |
賃貸建物につき売買契約に基づく所有権移転請求権保全の仮登記が経由された後に、仮登記義務者が賃料債権を第三者に譲渡しても、賃料債権譲渡は仮登記に基づく所有権移転の本登記が経由されたことによって、その効力を否定されるものではないとされた事例 |
||
| 717 | S44.5.30 |
従来母屋に接続する簡単なバラック建付属建物であった部分を拡げて店舗に改造し、母屋との間に板壁による間仕切りをし、母屋と全く別個に使用できるようにした場合においては、柱および板壁を共通とし、建物が屋根続きで外観上は一体の建物の観を呈していても、改造部分につき区分所有権が成立するとした事例 |
||
| 718 | S44.5.29 |
共有者の一人の単独名義に所有権登記されている場合、その登記が保存登記で、かつ、第三者のための登記が存在しないときでも、他の共有者はその所有権登記につき、自己の持分についてのみ一部抹消(更正)登記手続を求めることはできるが、その全部の抹消登記手続を求めることはできないとされた事例 |
||
| 719 | S44.5.27 |
甲が乙の承諾のもとに乙名義で不動産を競落し、丙が善意で乙からこれを譲り受けた場合において、甲は丙に対し登記の欠缺を主張して不動産の所有権の取得を否定することはできないとした事例 |
||
| 720 | S44.5.27 |
農地の二重売買につき、第一の買主が売主の履行不能を理由とする損害賠償を求めた事案において、第二買主の所有権移転請求権保全の仮登記を経由をもって売主の履行不能が確定したとはいえないし、同仮登記により農地法の許可が得られない証拠もないとして、その請求を棄却した事案 |
||
| 721 | S44.5.22 |
都市計画において公園とされている市有地について、民法162条による取得時効の成立が認められた事例 |
||
| 722 | S44.5.2 |
中間省略登記が中間取得者の同意なしにされた場合においても、中間取得者でない者は、登記の無効を主張してその抹消登記手続を求めることはできないとされた事例 |
||
| 723 | S44.4.24 |
所有権移転登記申請手続が登記義務者の意思に基づいてなされたものである以上、代理人による登記申請書に適式の代理委任状その他代理権限を証する書面が添付されなかった一事によって、登記の効力が生じないと解すべきものではないとした事例 |
||
| 724 | S44.4.22 |
甲所有不動産について、乙のためにされた抵当権設定登記および所有権移転請求権保全の仮登記につき、それぞれ丙に権利移転の附記登記が経由された場合において、甲が、抵当債務の弁済、代物弁済契約の無効を理由に登記の抹消請求をするには、丙のみを被告とすれば足り、乙を被告とすることを要しないとした事例 |
||
| 725 | S44.4.22 |
従前の土地の一部の賃借人は、特段の事情のないかぎり、土地区画整理事業の施行者から、使用収益部分の指定を受けることによって、はじめてその部分について現実に使用収益をすることができるとした事例 |
||
| 726 | S44.4.17 |
不動産について、被相続人との間に締結された契約上の義務の履行として、所有権移転登記手続を求める訴訟は、その相続人が数人いるときでも、必要的共同訴訟ではないとした事例 |
||
| 727 | S44.3.27 |
共有不動産につき共有者の一人が持分権を放棄した場合、他の共有者は放棄にかかる持分権の移転登記手続を求めるべきであって、放棄者の持分権取得登記の抹消登記手続を求めることは許されないとされた事例 |
||
| 728 | S44.3.20 |
主債務の消滅時効完成後に、主債務者が当該債務を承認し、保証人が、主債務者の債務承認を知って、保証債務を承認した場合には、保証人がその後主債務の消滅時効を援用することは信義則に照らして許されないとした事例 |
||
| 729 | S44.3.4 |
所有権移転請求権保全の仮登記が登記原因たる実体上の権利を欠き無効であるとされた事例 |
||
| 730 | S44.1.31 |
他人の財産権を贈与の目的物とする贈与契約も有効に成立するとした事例 |
||
| 731 | S44.1.28 |
土地改良区の土地改良事業の施行にあたり、一時利用地の指定を受けながらこれに対応する換地を交付されなかった者は、一時利用地を他人の換地とした処分の無効確認を求める利益を有しないとされた事例 |
||
| 732 | S44.1.28 |
遺留分権利者が受遺者に対して行なう減殺請求権は形成権であり、必ずしも裁判上の請求による必要はなく、いったんその意思表示がされた以上、法律上当然に減殺の効力を生ずるとした事例 |
||
| 733 | S43.12.24 |
民法162条2項の占有者の善意・無過失とは、自己に所有権があるものと信じ、かつ、そのように信ずるにつき過失のないことをいい、占有者において、占有の目的不動産に抵当権が設定されていることを知り、または、不注意により知らなかった場合でも、善意・無過失の占有者ということを妨げないとした事例 |
||
| 734 | S43.12.24 |
仮換地の指定後、従前の土地が分割譲渡され所有者を異にする二筆以上の土地となった場合、施行者により各筆に対する仮換地を特定した変更指定処分がされないかぎり、各所有者は仮換地全体につき、従前の土地に対する各自の所有地積の割合に応じ使用収益権を共同して行使すべきいわゆる準共有関係にあるものとされた事例 |
||
| 735 | S43.12.24 |
請負人が第三者に損害を与えた場合において、注文者に注文または指図について過失があるとされた事例 |
||
| 736 | S43.12.24 |
弁護士でない者に、自己の法律事件の示談解決を依頼し、これに報酬を与えもしくは与えることを約束しても、弁護士法第72条違反の罪の教唆犯は成立しないとされた事例 |
||
| 737 | S43.12.20 |
民法1013条(遺言の執行の妨害行為の禁止)の規定が適用される場合においても、取引の安全をはかる見地から設けられた民法478条(債権の準占有者に対する弁済)の規定は排除されないとした事例 |
||
| 738 | S43.12.4 |
仮登記が仮登記権利者不知の間に不法に抹消された場合には、登記上利害の関係を有する第三者は、その善意、悪意または回復登記により受ける損害の有無、程度にかかわらず、仮登記権利者の回復登記手続に必要な承諾を与えなければならないとされた事例 |
||
| 739 | S43.11.28 |
不動産の賃貸人が特約に基づき賃借権設定登記をする義務を負っていても、賃料支払義務と同時履行の関係とする特約がなく、かつ、登記がないと契約目的を達することができないという特段の事情もない場合には、賃借人は登記義務の履行がないことを理由に賃料の支払を拒むことはできないとした事例 |
||
| 740 | S43.11.27 |
・河川附近地制限令第4条第2号、第10条は、憲法第29条第3項に違反しないとした事例 |
||
| 741 | S43.11.19 |
不動産の譲受人が登記を経ないうちに、不動産について、第三者から譲渡人を仮処分債務者とする処分禁止の仮処分が執行された場合においても、譲受人が登記なく仮処分債権者に権利取得を対抗しうる地位にあったときは、譲受人は仮処分執行後も仮処分債権者に対し所有権の取得を対抗できるとした事例 |
||
| 742 | S43.11.15 |
部落民全員が、その総有に属する土地について、入会権者として登記の必要に迫られ、単に登記の便宜から、部落民の一部の者のために売買による所有権移転登記を経由した場合には、民法94条2項の適用または類推適用がないとした事例 |
||
| 743 | S43.11.13 |
所有権に基づく登記手続請求の訴訟において、被告が自己に所有権があることを主張して請求棄却の判決を求めることは、原告のための取得時効を中断する効力を生ずるとした事例 |
||
| 744 | S43.10.31 |
賃借権の譲渡転貸許容の特約がされその旨の登記がされている土地賃貸借において、賃借権の消滅を第三者に対抗するためにはその旨の登記を経由する必要があるとした事例 |
||
| 745 | S43.10.17 |
不動産の売買予約を仮装して所有権移転請求権保全の仮登記手続をした場合において、外観上の仮登記権利者が仮登記に基づき所有権移転の本登記手続をしたときは、外観上の仮登記義務者は本登記の無効をもって善意無過失の第三者に対抗できないとした事例 |
||
| 746 | S43.10.17 |
主たる債務者の債務の短期消滅時効期間が民法174条ノ2の規定によつて10年に延長される場合には、これに応じて保証人の債務の消滅時効期間も同じく10年に変ずるものと解されるとした事例 |
||
| 747 | S43.10.8 |
土地の継続的な用益という外形的事実が存在し、かつ、それが賃借の意思に基づくことが客観的に表現されているときは、土地賃借権を時効により取得することができるとした事例 |
||
| 748 | S43.10.8 |
・抵当権の設定契約が無効のときには、その抵当権に基づく競売により、抵当物件が競落されても、競落人はその所有権を取得することができないとした事例 |
||
| 749 | S43.10.8 |
予告登記の存することの一事から、これに後行して係争不動産につき物権の得喪変更に関する法律行為をなした第三者が当該登記原因の瑕疵につき悪意と推定されるべきではないとされた事例 |
||
| 750 | S43.9.26 |
・物上保証人は、被担保債権の消滅時効を援用することができるとした事例 |
||
| 751 | S43.9.12 |
家屋の所有権を贈与により取得したとした者の、贈与者の相続人らに対する所有権移転登記請求訴訟において、裁判所が贈与の主張は死因贈与の主張を包含するものと解し、死因贈与による所有権移転を認定することは、当事者の主張しない事実を認定したものとはいえないとした事例 |
||
| 752 | S43.9.6 |
・買収農地の売渡を受けて農業用施設として占有している者は、その売渡処分が当然無効であっても、その占有の始めに善意・無過失というべきであるとした事例 |
||
| 753 | S43.8.2 |
甲から山林を購入した乙が23年間これを占有していたところ、丙がその事実を知りながら、乙の未登記に乗じて乙に高値で売却する目的で、甲から当該山林を購入し登記を経たという事情の下では、丙は、いわゆる背信的悪意者として、乙の登記がないことを主張する正当の利益を有する第三者に当たらないとされた事例 |
||
| 754 | S43.7.16 |
一筆の土地を賃借し二棟の建物を所有する借地人が、各一棟を養女とその夫にそれぞれ贈与しその後死亡した事情のもとでの、土地賃貸人の借地権無断譲渡を理由とする各建物を受贈した養女およびその夫それぞれに対する土地明渡し請求は権利濫用に当たるとした事例 |
||
| 755 | S43.6.21 |
売主および買主が連署のうえ農地法5条による許可申請書を知事あてに提出したときは、特約その他特別の事情のないかぎり、民法557条1項にいう「契約の履行に著手」したと解されるとした事例 |
||
| 756 | S43.6.13 |
建物の附合の成否について、新築部分の構造、利用方法を考察し、従前の建物に接して築造され、構造上建物としての独立性を欠き、一体となって利用され取引されるべき状態にあるときは、附合したものと解すべきであるとした事例 |
||
| 757 | S43.5.28 |
土地所有者がその所有権にもとづいて地上の建物の共同相続人を相手方として建物収去土地明渡を請求する訴訟は、いわゆる固有必要的共同訴訟ではないとされた事例 |
||
| 758 | S43.5.23 |
従前の土地の一部について賃借権を有する者は、土地区画整理事業の施行者から、権利の目的となるべき土地としての指定通知を受けないかぎり、たとえ施行者からの通知により賃借地上の建物を解体移転したとしても、当然には仮換地について現実に使用収益をすることができないとした事例 |
||
| 759 | S43.4.4 |
共有者の一人が、権限なく、共有物を自己の単独所有に属するものとして他に売り渡した場合でも、売買契約は有効に成立し、自己の持分をこえる部分については、他人の権利の売買としての法律関係を生ずるとともに、自己の持分の範囲内においては、約旨に従った履行義務を負うとした事例 |
||
| 760 | S43.3.28 |
土地の賃借人は賃借権を保全するため、賃貸人たる土地所有者に代位して土地の不法占拠者に対し建物収去及び土地明渡を請求することができ、かつその場合、直接自己に対して収去明渡をなすべきことを請求できるとした事例 |
||
| 761 | S43.3.15 |
土地の所有者がその所有権に基づいて地上の建物の所有者である共同相続人を相手方とし、建物収去土地明渡を請求する訴訟は、いわゆる固有必要的共同訴訟ではないとした事例 |
||
| 762 | S43.3.8 |
弁護士が登記申請の双方代理をしても、その弁護士の行為は、特段の事由のないかぎり、弁護士法第25条第1号に違反しないとした事例 |
||
| 763 | S43.3.1 |
相続人が登記簿に基づき実地に調査すれば、相続した土地の範囲に甲地を含まないことを容易に知ることができたにもかかわらず、この調査をしなかったために、甲地が相続した土地に含まれると信じて占有をはじめたときは、相続人は占有のはじめにおいて無過失ではないとした事例 |
||
| 764 | S43.3.1 |
一筆の従前地全部を賃借する者が適法な賃借権の届出をした場合であっても、施行者から通知がない以上、賃借人は換地予定地について使用収益権を有しないとされた事例 |
||
| 765 | S43.2.22 |
取得時効の成否は、境界確定の訴えにおける境界確定とは関係がないとした事例 |
||
| 766 | S43.2.1 |
「推認」の語は、証拠によって認定された間接事実を総合し、経験則を適用して主要事実を認定する場合に用いられる用語法であって、証明度において劣る趣旨を示すものではないとした事例 |
||
| 767 | S43.1.30 |
甲所有不動産につき、売買予約に基づく乙の所有権移転仮登記がされた後、所有権が乙へ、さらに丙へ移転したが、丙に対し売買予約の権利譲渡を原因として、仮登記につき所有権移転請求権移転の附記登記がされた場合、丙が甲に対して仮登記の附記登記に基づく所有権移転登記手続を請求することは許されないとした事例 |
||
| 768 | S42.11.10 |
農地法第3条または第5条にもとづく知事の許可は、農地法の立法目的に照らして、所有権の移転等につきその権利の取得者が農地法上の適格性を有するか否かの点のみを判断して決定すべきであり、私法上の効力やそれによる犯罪の成否等についてまで判断をなすべきものではないとされた事例 |
||
| 769 | S42.11.2 |
板塀で囲み上部をトタン板で覆った土地につき、所有者の黙認のもと、建築資材置場として使用していた者が、台風による囲いの倒壊後、所有者が工事中止の申し入れにもかかわらず、土地にブロツク塀を構築し、その上をトタン板で覆い、建築資材などを置く倉庫として使用した行為は、不動産侵奪罪に該当するとした事例 |
||
| 770 | S42.11.1 |
不法行為による慰謝料請求権は、財産上の損害賠償請求権と同様単純な金銭債権であり、被害者が生前に請求の意思を表明しなくても相続の対象となるとされた事例 |
||
| 771 | S42.10.31 |
甲が乙に不動産を仮装譲渡し、丙が善意で乙からこれを譲り受けた場合であっても、丙が所有権取得登記をする前に、甲からの譲受人丁が乙を債務者とし不動産について処分禁止の仮処分登記を経ていたときは、丙はその所有権取得を丁に対抗することができないとした事例 |
||
| 772 | S42.10.31 |
乙ほか5名共有の土地が一方甲に譲渡され、他方丙を経て乙に譲渡された場合、乙が所有権取得登記を経由しても、甲は登記なくして乙に対し土地の所有権取得を対抗することができるとした事例 |
||
| 773 | S42.10.31 |
土地区画整理による仮換地の指定により、従前の土地上の建物を仮換地上に移転する場合において、移転が可能であるときは、移転費用に相当金額を要するのに対し建物が朽廃に近く残存価値が少ない等特段の事情のないかぎり、従前の建物の賃貸人は賃借人に対し、建物を移転し賃貸借を継続する義務を負うとした事例 |
||
| 774 | S42.10.27 |
農地を目的とする売買契約締結後に、売主が目的物上に土盛りをし、その上に建物が建築され、そのため農地が恒久的に宅地となった等買主の責に帰すべからざる事情により農地でなくなった場合には、売買契約は知事の許可なしに効力を生ずるとした事例 |
||
| 775 | S42.10.27 |
・他人の債務のため自己の所有物をいわゆる弱い譲渡担保に供した者は、右債務の消滅時効を援用することができるとされた事例 |
||
| 776 | S42.9.19 |
地上権の譲受人は、地上権について登記を有しなくても、地上建物について所有権移転登記を経由した以上、建物保護に関する法律第1条第1項により、地上権の承継を土地所有者に対抗できるとした事例 |
||
| 777 | S42.9.1 |
抵当権者から委任をうけた者の過誤による申請によって、抵当権設定登記が抹消された場合、抵当権の対抗力は消滅するとした事例 |
||
| 778 | S42.8.25 |
売主の支払停止前になされた農地の売買について、知事の許可がなかったため、買主は支払停止後破産申立前に所有権移転請求権保全の仮登記を経たが、破産宣告が仮登記後1年を超えてなされたときは、仮登記についてもはや破産法第74条第1項による否認をしえなくなり、買主は仮登記に基づき破産管財人に対し、知事の許可を条件とする本登記を求めることができるとした事例 |
||
| 779 | S42.8.25 |
使用貸借契約の終了を原因とする家屋明渡請求権は、性質上の不可分給付を求める権利と解すべきであって、貸主が数名あるときは、各貸主は総貸主のため家屋全部の明渡を請求することができるとした事例 |
||
| 780 | S42.8.25 |
共有物分割の結果、不動産の一部について単独所有権を取得した場合には、分筆登記を経由したうえで、権利の一部移転の登記手続をすべきとした事例 |
||
| 781 | S42.8.24 |
建物所有を目的とする借地権の設定後、地上建物の保存登記前にその土地の所有権移転請求権保全の仮登記がされた場合、借地権者は仮登記に基づいて本登記をした者に対し借地権を対抗することができないとした事例 |
||
| 782 | S42.7.21 |
不動産の取得時効完成前に原所有者から所有権を取得し時効完成後に移転登記を経由した者に対し、時効取得者は、登記なくして所有権を対抗することができるとした事例 |
||
| 783 | S42.7.21 |
耕地整理施行中の未登記の残地を買い受けた者が、耕地整理組合について調査することなく、売主の所有地であるとの言を信じてその占有を始めたとしても、売主が真の所有者の実父でこれを管理していた等の事実の下においては、買主がその所有権を取得したと信じたことにつき過失がないとされた事例 |
||
| 784 | S42.7.21 |
所有権に基づいて不動産を占有する者についても、民法162条(取得時効)の適用があるとした事例 |
||
| 785 | S42.7.20 |
借地法10条による建物買取請求権の消滅時効の期間が10年と解された事例 |
||
| 786 | S42.6.30 |
被用者が重大な過失により失火したときは、使用者は、被用者の選任または監督について重大な過失がなくても、民法第715条第1項によって賠償責任を負うとした事例 |
||
| 787 | S42.6.29 |
従前の宅地の所有者は仮換地自体について、その本換地として確定する以前にこれを使用収益しうべき旨の地上権を設定することはできないとした事例 |
||
| 788 | S42.6.22 |
火災により、賃借建物の屋根等がほとんど焼け落ち、倒壊の危険もあり、完全修復には多額の費用を要し、建物全部を取り壊して新築する方が経済的である等の事実関係のもとにおいて、当該建物は火災により滅失し建物賃貸借契約は終了したとされた事例 |
||
| 789 | S42.6.20 |
津波によって土地が流出した後に住宅適地造成組合によって造成された土地の所有権の取得時効につき、相続による占有者が土地登記簿を調査しなかったことをもって占有のはじめに過失があったとはいえないとした事例 |
||
| 790 | S42.6.6 |
不動産の所有権が順次甲、乙、丙と譲渡された場合に、甲が乙に対し所有権移転登記をする意思で、登記申請書類を交付していたときは、丙が同書類を利用して甲から丙に直接所有権移転登記をしても同登記は無効になるものではないとした事例 |
||
| 791 | S42.5.30 |
法人の代表者は、現実に被用者の選任・監督を担当していた場合に限り、民法715条2項の代理監督者に当たるとされた事例 |
||
| 792 | S42.4.28 |
家屋賃借人が死亡し、唯一の相続人も行先不明で生死も判然とない場合において、家屋賃借人の内縁の夫が家屋賃借人の賃借権の援用により家屋に居住できるとした事例 |
||
| 793 | S42.4.7 |
甲が、共同相続により持分を取得した不動産につき、単独相続したとして所有権登記を経由し、乙と不動産について抵当権設定契約を締結し登記を経由したときは、甲は、乙に対し、自己の持分を超える部分について抵当権が無効であると主張しその抹消(更正)登記手続を請求することは、信義則に照らし許されないとした事例 |
||
| 794 | S42.4.6 |
宅地転用を目的とした農地の売買契約がなされた場合において、売主が知事に対する許可申請手続に必要な書類を買主に交付したのに、買主が特段の事情もなく許可申請手続をしないときには、売主はこれを理由に売買契約を解除することができるとした事例 |
||
| 795 | S42.3.17 |
地役の性質を有する入会権が解体消滅したと認められた事例 |
||
| 796 | S42.2.24 |
贈与税課税権の消滅時効の起算日は、贈与によって財産を取得した年の翌年の3月1日であるとした事例 |
||
| 797 | S42.2.21 |
家屋賃借人の内縁の妻は、賃借人が死亡した場合には、相続人の賃借権を援用して賃貸人に対し当該家屋に居住する権利を主張することができるが、相続人とともに共同賃借人となるものではないとした事例 |
||
| 798 | S42.1.20 |
県知事の許可がないかぎり、農地の買戻は効力を発生しないから、売戻人の目的物の明渡義務も発生しないとした事例 |
||
| 799 | S42.1.20 |
相続人が、相続の放棄をした場合には相続開始時にさかのぼって相続開始がなかったと同じ地位に立ち、当該相続放棄の効力は、登記等の有無を問わず、何人に対してもその効力を生ずるとされた事例 |
||
| 800 | S41.12.23 |
甲の所有地上に乙が家屋を建て、当該家屋を乙が一年間使用したら甲に所有権を移転し、以後甲・乙間で相当賃料で賃貸する契約をしたところ、家屋が完成直後に火事で焼失し乙が火災保険金を受取った事案において、代償請求として、甲の乙に対する乙の受取った火災保険金の引渡請求が認められた事例 |
||
| 801 | S41.12.1 |
賃料の催告と、賃料不払による賃貸借契約解除の意思表示との間に約14年の隔たりがあっても、相手方において催告に基づく解除権の行使はないと信ずべき正当な事由が生じたといえない事情のもとでは、意思表示のときまで解除権は有効に存続しているとした事例 |
||
| 802 | S41.11.22 |
不動産の時効取得者は、取得時効の進行中に原権利者から当該不動産の譲渡を受けその旨の移転登記を経由した者に対しては、登記がなくても、時効による所有権の取得を主張することができるとした事例 |
||
| 803 | S41.11.18 |
・登記申請行為自体には、表見代理に関する民法の規定の適用はないとされた事例 |
||
| 804 | S41.10.7 |
書面によらない農地の贈与契約は、農地法第3条第1項による知事の許可を受けるまでは、農地の引渡があった後でも、取り消すことができるとした事例 |
||
| 805 | S41.10.7 |
15才位に達した者は、特段の事情のないかぎり、不動産について、所有権の取得時効の要件である自主占有をすることができるとした事例 |
||
| 806 | S41.7.14 |
遺留分権利者の減殺請求権は形成権であるとされた事例 |
||
| 807 | S41.6.9 |
民法第192条(即時取得)により動産の上に行使する権利を取得したことを主張する占有者は、同条にいう「過失なき」ことを立証する責任を負わないとした事例 |
||
| 808 | S41.6.2 |
不動産の買主甲が売主乙に対し、所有権移転登記手続履行の請求訴訟を起こし勝訴判決得た場合において、乙から同一不動産の二重譲渡を受けた丙が、訴の事実審の口頭弁論終結後にその所有権移転登記を経たとしても、丙は前示確定判決について、民訴法第201条第1項の承継人にあたらないとした事例 |
||
| 809 | S41.5.31 |
農地法第4条第1項違反の罪は、宅地化の目的でなされる場合、家屋の建築工事に着手し、あるいは完全に宅地としての外観を整えるまでに至らなくとも、農地の肥培管理を不能もしくは著しく困難にして、耕作の目的に供される土地とはいいがたい状態にしたときに成立し、その時から時効が進行するとした事例 |
||
| 810 | S41.5.19 |
共有物の持分の価格が過半数をこえる者は、共有物を単独で占有する他の共有者に対し、当然には、その占有する共有物の明渡を請求することができないとした事例 |
||
| 811 | S41.4.27 |
土地賃借人は、土地上に自己と同居する未成年の長男名義で保存登記をした建物を所有していても、その後当該土地の所有権を取得した第三者に対し、「建物保護ニ関スル法律」第1条により、土地の賃借権をもって対抗することができないとした事例 |
||
| 812 | S41.4.22 |
借地権者が従前土地上に登記ある建物を所有している場合でも、借地権の申告に基づいて施行者が仮換地上に使用収益部分の指定をしなければ、仮換地上に使用収益権は生じないとした事例 |
||
| 813 | S41.4.20 |
・消滅時効完成後に債務の承認をした場合において、そのことのみによって、同承認はその時効が完成したことを知ってしたものであると推定することはできないとされた事例 |
||
| 814 | S41.4.15 |
民法第162条第2項にいう平穏の占有とは、占有の取得・保持について、暴行強迫などの違法な行為を用いていない占有をいい、不動産所有者その他占有の不法を主張する者から異議をうけ、不動産の返還、占有者名義の所有権移転登記の抹消請求があっても、その占有が平穏でなくなるものではないとした事例 |
||
| 815 | S41.3.18 |
未登記の建物の所有者甲が、所有権を移転する意思がないのに、建物について、乙の承諾を得て乙名義の所有権保存登記を経由したときは、民法第94条第2項を類推適用して、甲は、乙が建物の所有権を有していないことをもって善意の第三者に対抗することができないとした事例 |
||
| 816 | S41.3.3 |
共有物に対する不法行為による損害賠償請求権は、各共有者が自己の持分に応じてのみこれを行使しうるとした事例 |
||
| 817 | S41.3.1 |
抵当権の設定登記後に当該不動産について所有権移転請求権保全の仮登記を経由した者は、その後に登記された抵当権の実行による競落人に対し、その権利を対抗することができないとされた事例 |
||
| 818 | S41.2.8 |
技術士国家試験の合格、不合格の判定は、司法審査の対象とならないとした事例 |
||
| 819 | S41.1.21 |
所有権移転請求権保全の仮登記のなされた土地の仮換地の上に存する土地所有者の所有建物について抵当権が設定された場合には、建物の競落人は、法定地上権を取得するが、仮登記に基づいて所有権移転の本登記を経た者に対しては、法定地上権をもって対抗することができないとした事例 |
||
| 820 | S41.1.13 |
不動産の贈与を予定して、登記権利者たる受贈者の関与なく不動産の所有権取得登記がなされた場合でも、後日不動産の贈与が行われたときは、受贈者は不動産所有権の取得をもって第三者に対抗することができるとした事例 |
||
| 821 | S40.12.7 |
使用貸借の終了した敷地上に建築された仮店舗の周囲に、敷地所有者(終了前の敷地使用貸主)が仮店舗所有者(終了前の敷地使用借主)の承諾を得ないで板囲を設置した場合に、仮店舗所有者が板囲を実力をもって撤去することが私力行使の許される限界を超えるとされた事例 |
||
| 822 | S40.12.3 |
代物弁済の予約をした債権者が、その妻名義で所有権移転請求権保全の仮登記をした事案において、その仮登記は実体関係に符合しないことから第三者に対して順位保全の効力を有しないとした事例 |
||
| 823 | S40.9.24 |
第三者の債務の担保に供された抵当不動産が競売に付せられ競落代金が納付された場合には、求償権が事実上取立不能であっても譲渡所得は成立するとした事例 |
||
| 824 | S40.9.21 |
不動産の所有権が甲乙丙と順次移転したのに、登記名義は依然として甲にある場合には、丙が甲に対し直接自己に移転登記を請求することは、甲および乙の同意がないかぎり許されないとした事例 |
||
| 825 | S40.9.17 |
不動産所有権の移転行為を詐害行為としてその取消を請求する場合に、債務者より受益者への所有権移転登記の抹消に代えて、受益者より債務者への所有権移転登記手続を求めることが許されるとした事例 |
||
| 826 | S40.9.8 |
・売買代金債権は、法律上これを行使することができるようになったときに、所得税法第10条第1項後段にいう「収入すべき金額」となるとした事例 |
||
| 827 | S40.7.23 |
一筆の土地全部を賃借した者でも、賃借土地の仮換地を現実に使用収益するためには、土地区画整理事業の施行者から土地区画整理法第98条第1項所定の権利の目的となるべき土地としての指定通知を受けることを要するとされた事例 |
||
| 828 | S40.6.30 |
特定物の売買契約における売主のための保証人は、特に反対の意思表示のないかぎり、売主の債務不履行により契約が解除された場合における原状回復義務についても、保証責任を負うとした事例 |
||
| 829 | S40.6.18 |
無権代理人が本人を相続し、本人と代理人との資格が同一人に帰した場合には、本人がみずから法律行為をしたのと同様な法律上の地位を生じたものと解されるとした事例 |
||
| 830 | S40.5.27 |
相続放棄につき民法95条(錯誤)の適用があるとした事例 |
||
| 831 | S40.5.25 |
建築材料の一切を請負人において支給し請負代金の前渡もなされていない請負契約においては、特別の意思表示のないかぎり、契約に基づき建築された建物の所有権は、建物が請負人から注文者に引渡された時に注文者に移転するとされた事例 |
||
| 832 | S40.5.20 |
土地の共有者は、その土地の一部が自己の所有に属すると主張する第三者に対し、各自単独で、係争地が自己の共有持分権に属することの確認を訴求することができるとした事例 |
||
| 833 | S40.5.4 |
滅失建物の登記を、その跡地に新築された建物の所有権保存登記に流用することは許されないとした事例 |
||
| 834 | S40.4.16 |
農地法第5条の規定に基づく知事の許可は、当該農地についての私法上の行為の取消または解除によってその効力を失うものではないとした事例 |
||
| 835 | S40.4.6 |
土地を目的とする代物弁済予約に基づく完結権を行使しうる時から約15年後に完結の意思表示がなされた場合でも、予約による所有権移転請求権保全の仮登記が経由されているときは、いわゆる権利失効の原則により権利が失われることなく、完結権の行使は有効であるとした事例 |
||
| 836 | S40.4.2 |
土地の賃借人は、登記した建物を有しないかぎり、当該土地賃借権の存在を知って土地所有権を取得した第三者に対しても、土地賃借権を主張することができないとした事例 |
||
| 837 | S40.3.26 |
不動産の贈与契約に基づいて、不動産の所有権移転登記がなされたときは、その引渡しの有無をとわず、民法550条にいう贈与の履行が終ったものと解されるとした事例 |
||
| 838 | S40.3.17 |
地上権ないし賃借権の設定された土地上の建物についてなされた登記が、錯誤または遺漏により、建物所在地番の表示において実際と多少相違していても、当該建物の同一性を認識できる程度の軽微な相違である場合には、「建物保護に関する法律」第1条第1項にいう「登記したる建物を有する」場合にあたるとした事例 |
||
| 839 | S40.3.10 |
従前の土地の一部を賃借する者は、土地区画整理法第85条の定める権利申告の手続をして土地区画整理事業の施行者から仮に使用収益しうべき部分の指定を受けないかぎり、仮換地につき現実に使用収益をすることができないとされた事例 |
||
| 840 | S40.3.2 |
従前の土地の地積は土地台帳の地積による旨の土地区画整理施行規程の規定に基づき、土地台帳の地積によってした換地予定地指定処分は、憲法第29条に違反しないとした事例 |
||
| 841 | S40.2.23 |
処分禁止の仮処分の登記後に仮処分債務者から第三者に対し所有権の移転登記がされた場合において、仮処分債権者は債務者との訴訟にて実体法上の権利の確定をしないかぎり、第三者に対し権利を主張し、所有権の移転登記の抹消登記を請求することはできないとした事例 |
||
| 842 | S39.12.25 |
抵当権設定登記をする前に被担保債権の一部が弁済されても、債権者はその債権全額について登記手続を請求することができるとした事例 |
||
| 843 | S39.12.18 |
期間の定めのない継続的保証契約は、保証人の主債務者に対する信頼が害されるなど保証人の解約申入の相当の理由がある場合には、解約により債権者が信義則上看過できない損害を被るような特段の事情がある場合を除き、保証人から一方的に解約できるとした事例 |
||
| 844 | S39.11.17 |
債務超過の債務者が、ある債権者だけに優先的に債権の満足を得させる意図のもと、通謀して重要な財産を右債権者に売却し、売買代金債権と右債権者の債権とを相殺する約定をした場合には、たとえ売買価格が適正価格であるとしても、右売却行為は詐害行為にあたるとされた事例 |
||
| 845 | S39.10.23 |
家屋賃借人の内緑の妻が賃借人死亡後も賃借権を有するとされ、選定家督相続人には右賃借権が相続されないと判断された事例 |
||
| 846 | S39.10.15 |
・法人に非ざる社団が成立するためには、団体としての組織をそなえ、多数決の原則が行なわれ、構成員の変更にかかわらず団体が存続し、その組織において代表の方法、総会の運営、財産の管理等団体としての主要な点が確定していることを要するとした事例 |
||
| 847 | S39.10.13 |
登記簿上表示された建物の一部である現存建物が、建物保護に関する法律1条にいう「登記したる建物」にあたるとされた事例 |
||
| 848 | S39.10.13 |
内縁の夫死亡後その所有家屋に居住する寡婦に対して、亡夫の相続人のした家屋明渡請求が権利の濫用にあたるとされた事例 |
||
| 849 | S39.9.8 |
建設業法第19条は、書面によらない建設契約を無効とする趣旨ではないとした事例 |
||
| 850 | S39.9.8 |
農地の買主は、その必要があるかぎり、売主に対し知事の許可を条件として、農地所有権移転登記手続請求をすることができるとした事例 |
||
| 851 | S39.7.24 |
甲の所有権保存登記がなされた甲所有の建物について、二重に乙名義の所有権保存登記がされ、次いで甲名義の登記が不法に抹消された後に、丙が乙名義の登記に基づき建物の所有権取得登記を経由した場合、丙は、甲名義の登記の抹消回復登記につき「登記上利害の関係を有する第三者」に当らないとした事例 |
||
| 852 | S39.5.26 |
入院中の内縁の夫が、同棲に使用していたその所有家屋を妻に贈与するに際して、自己の実印を家屋を買受けたときの契約書とともに妻に交付した事案において、簡易の引渡による家屋の占有移転があったとして、これにより贈与の履行が終ったものとされた事例 |
||
| 853 | S39.5.12 |
私文書の作成名義人の印影が当該名義人の印章によって顕出されたものであるときは、反証のないかぎり、民事訴訟法326条により、当該文書が真正に成立したものと推定されるとした事例 |
||
| 854 | S39.2.27 |
甲の相続権を乙が侵害している場合、甲の相続人丙の乙に対する相続回復請求権の消滅時効の期間20年の起算点は、丙の相続開始の時ではなく、甲の相続開始の時とであるとした事例 |
||
| 855 | S39.2.25 |
共有物を目的とする貸借契約の解除は、共有者によってされる場合は、民法第252条本文にいう「共有物の管理に関する事項」に該当し、解除については、民法第544条第1項(解除権の不可分性)の規定は適用されないとした事例 |
||
| 856 | S39.2.20 |
時効消滅後の債権による相殺は、相殺適状にあった時点の債権額の限度でなしうるものであって、相殺の意思表示の時点における債権額につき対当額で相殺されると解すべきではないとした事例 |
||
| 857 | S39.2.13 |
単に土地を譲渡した前所有者であるにすぎないものは、譲受人から権利を譲受けたた後者に対して登記の欠缺を主張するにつき正当の利益を有する民法177条の第三者に該当しないとした事例 |
||
| 858 | S39.1.30 |
甲乙両名が共同相続した不動産につき、乙が勝手に単独所有権取得の登記をし、さらに第三取得者丙が乙から移転登記をうけた場合、甲は乙丙に対し自己の持分を登記なくして対抗できるとした事例 |
||
| 859 | S38.12.27 |
売主およびその相続人の共有不動産が売買の目的とされた場合、当該相続人は当該売買契約における売主の義務の履行を拒むことはできないとした事例 |
||
| 860 | S38.12.24 |
発起人が会社の成立を条件としてなした法律行為のうち、単純な債務引受は財産引受にあたらないが、積極消極両財産を含む営業財産を一括して譲り受ける契約は、財産引受にあたるとした事例 |
||
| 861 | S38.12.13 |
他人の所有する土地に権原によらずして自己所有の樹木を植え付け、その時から立木のみにつき所有の意思をもって平穏かつ公然に20年間占有した者は、時効により立木の所有権を取得するとした事例 |
||
| 862 | S38.10.30 |
留置権の抗弁は、被担保債権の債務者が原告である訴訟において提出された場合には、当該債権について消滅時効中断の効力があり、かつ、その効力は抗弁の撤回されないかぎり、その訴訟係属中存続するとした事例 |
||
| 863 | S38.10.15 |
登記簿上の所有者名義人は、前所有名義人から不動産所有権を取得したと主張する場合には、前所有名義に対し登記の推定力を援用し得ないとした事例 |
||
| 864 | S38.10.4 |
共同相続した不動産につき、共同相続人の一人が勝手に単独の所有権登記を行い、この者から第三者が移転登記を受けた場合、他の共同相続人は第三者に対し自己の持分を登記なくして対抗できるとし事例 |
||
| 865 | S38.10.1 |
農地の売買において、売主の相続人らが買主に対して負う、知事に対する許可申請手続協力義務は不可分債務であるとされた事例 |
||
| 866 | S38.9.20 |
債務不履行により農地の売買契約を解除する場合には、農地法第3条の適用がないとした事例 |
||
| 867 | S38.9.18 |
建築主が建築主事の確認を受けないで、用途上不可分の関係の認められない1戸建住宅及び2戸建ないし5戸建長屋住宅合計38棟を建築したときは、38個の建築基準法違反罪が成立するとした事例 |
||
| 868 | S38.6.26 |
ため池の破損、決壊の原因となるため池の堤等の使用行為は、憲法、民法の保障する財産権の行使の埒外のものであるとして、ため池の堤等の所有権行使が著しく規制される「奈良県ため池の保全に関する条例」につき合憲性を認めた事例 |
||
| 869 | S38.6.13 |
弁護士の資格有しない者の弁護士法72条本文前段および同77条に抵触する契約は、公序良俗違反により無効とされた事例 |
||
| 870 | S38.5.31 |
主たる建物の登記部分のみが無効である場合は、その部分のみの抹消を許すべきであって、附属建物を含めた全部の登記の抹消を許すべきではないとした事例 |
||
| 871 | S38.3.28 |
・甲が登記簿上乙の所有名義となっている甲所有建物を丙に譲渡した後、丙の所有権登記前に、甲の債権者丁が建物になした、乙より甲への代位による所有権移転登記ならびに甲を債務者とする仮差押登記はいずれも有効であるとした事例 |
||
| 872 | S38.2.22 |
・相続財産に属する不動産につき単独所有権移転の登記をした共同相続人及び同人から単独所有権移転の登記をうけた第三取得者に対し、他の共同相続人は自己の持分を登記なくとも対抗できるとした事例 |
||
| 873 | S38.1.18 |
係争地域が自己所有であるとの主張は前後変わることなく、ただ単に請求を境界確定から所有権確認に変更したにすぎない場合は、境界確定の訴え提起によって生じた時効中断の効力には影響がないとした事例 |
||
| 874 | S37.12.26 |
土地区画整理中の土地の売買において、なんらの特約をしなかった場合、清算交付金は売主に帰属するとした事例 |
||
| 875 | S37.11.9 |
継続的売買取引について、将来負担することあるべき債務についてした責任の限度額ならびに期間の定めのない連帯保証契約における保証人たる地位は、特段の事由のないかぎり、当事者その人と終始するものであって、保証人の死亡後生じた債務については、その相続人においてこれが保証債務を負担するものではないとした事例 |
||
| 876 | S37.11.8 |
電気工作物に瑕疵があるとされた事例 |
||
| 877 | S37.10.12 |
債権者が受益者を相手どって詐害行為取消の訴えを提起しても、債権につき消滅時効中断の効力を生じないとした事例 |
||
| 878 | S37.10.4 |
弁護士でない者が報酬を得る目的で、債権者から債権取立の委任を受け、その取立のため請求、弁済の受領、債務の免除等の諸種の行為をすることは、弁護士法第72条の、「その他一般の法律事件」に関して、「その他の法律事務」を取り扱った場合に該当するとした事例 |
||
| 879 | S37.10.2 |
親権者が自己の借入金債務につき、未成年の子の所有不動産に抵当権を設定する行為は、借入金を未成年の子の養育費にする意図であっても、民法第826条にいう「利益が相反する行為」にあたるとした事例 |
||
| 880 | S37.9.13 |
土地の地目変更の登記申請書に、農地法第4条第1項による都道府県知事の許可を証する書面を添付しない違法があっても、登記官吏において申請を受理して土地の地目変更の登記をしたときは、同登記はその違法により当然に無効となるものではないとした事例 |
||
| 881 | S37.9.4 |
通行人の死亡による損害が、国道管理の瑕疵のため生じたものと認められた事例 |
||
| 882 | S37.3.29 |
石油タンクは、旧地方税法八八条にいう不動産に該当しないとされた事例 |
||
| 883 | S37.1.23 |
登記名義人を異にする二重の保存登記の一方の登記名義人を登記義務者とする所有権移転登記の申請がある場合において、不動産登記法第49条第6号の規定によりこれを却下することは許されないとした事例 |
||
| 884 | S36.12.22 |
借主が死亡しその相続人が複数いる場合、貸主からの契約解除には相続人全員に対して解除の意思を表示することを要するとした事例 |
||
| 885 | S36.12.15 |
共同相続財産たる不動産の売却による売主らの所有権移転登記義務は、不可分債務に当たるとされた事例 |
||
| 886 | S36.12.12 |
仮換地の指定にあたってなさるべき従前の宅地との照応考慮は、原則として、土地区画整理事業開始の時における状況を基準としてなすべきとした事例 |
||
| 887 | S36.11.28 |
連帯債務者の一人が死亡し、その相続人が数人ある場合に、相続人らは、被相続人の債務の分割されたものを承継し、各自その承継した範囲において、本来の債務者とともに連帯債務者となると解された事例 |
||
| 888 | S36.11.24 |
甲が乙から宅地を買受けその旨の所有権取得登記を経由したのち、乙の債務不履行を原因として売買契約が解除された場合、甲は乙に対し登記の抹消手続を求めることができるとした事例 |
||
| 889 | S36.9.15 |
工場財団を組成する動産についても、民法192条(即時取得)の適用があるとした事例 |
||
| 890 | S36.7.20 |
不動産の取得時効が完成しても登記を経なければ、その後に所有権登記を経由した第三者に対し時効による権利の取得を対抗できないが、第三者の登記後に占有者がなお引続き時効取得に要する期間占有を継続した場合には、その第三者に対し登記を経由しなくとも時効取得をもって対抗しうるとした事例 |
||
| 891 | S36.7.6 |
土地所有者が、仮設の建物により土地を不法占有する者との事態解決のため、期間を10年とした土地賃貸借契約について、借地法第9条にいう一時使用のための借地権に該当するとした事例 |
||
| 892 | S36.5.26 |
・知事の許可を得ることを条件として農地の売買契約をしたとしても、いわゆる停止条件を附したものということはできないとした事例 |
||
| 893 | S36.4.28 |
不動産につき甲、乙、丙と順次所有権が移転したものとして順次所有権移転登記がなされた場合において、各所有権移転行為が無効であるとき、乙は丙に対し抹消登記請求権を有するとした事例 |
||
| 894 | S36.3.16 |
建物が二重に譲渡された場合において、無効な登記を有するにすぎない譲受人は、建物所有者としてその建物を目的とする火災保険契約を締結するについて、被保険利益を有しないとした事例 |
||
| 895 | S36.3.7 |
従前の土地の一部について賃借権を有する者は、たとえその賃借部分が仮換地に含まれていても、賃借権について仮に権利の目的となるべき部分の指定を受けないかぎり、賃借部分の使用権を有しないとされた事例 |
||
| 896 | S35.12.27 |
登記簿上自己が所有名義人となる預り保管中の不動産につき、所有権移転登記手続請求の訴を提起された場合に、不動産に対する不法領得意思の確定的発現として、訴訟において自己の所有権を主張・抗争する所為は、不動産の横領罪を構成するとした事例 |
||
| 897 | S35.11.29 |
不動産売買契約に基づき買主に所有権移転登記がなされた後、契約解除により、不動産の所有権が売主に復帰した場合において、売主はその旨の登記をしなければ、契約解除後に買主から不動産を取得した第三者に対しては、第三者が善意であると否と、不動産に予告登記の有無にかかわらず、所有権の取得を対抗できないとした事例 |
||
| 898 | S35.11.29 |
杉立木の不法伐採による損害賠償額は、特別事情の認められない場合、伐採当時の時価相当額であるとされた事例 |
||
| 899 | S35.11.24 |
不動産売買予約上の権利を仮登記により保全した場合に、予約上の権利の譲渡を予約義務者その他の第三者に対抗するためには、仮登記に権利移転の附記登記をすれば足り、債権譲渡の対抗要件を具備する心要はないとした事例 |
||
| 900 | S35.11.1 |
契約解除に基づく原状回復義務の履行不能による損害賠償請求権の消滅時効は、契約解除の時から進行するとした事例 |
||
| 901 | S35.11.1 |
土地区画整理法99条2項は、換地予定地権利者の従前宅地と換地予定地との二重使用を禁止するとともに、換地予定地上に従前の権利者の建物などが存する場合に、その撤去または移転まで換地予定地権利者の換地予定地の使用を禁じた関係上、換地予定地権利者の従前の宅地使用を許容したものとした事例 |
||
| 902 | S35.9.2 |
民法160条(相続財産に関する時効の停止)は、相続財産の管理人の選任前、相続財産たる土地を、所有の意思をもって、平穏、公然、善意無過失で10年間占有した場合にもその適用があるとされた事例 |
||
| 903 | S35.7.27 |
時効期間は、時効の基礎たる事実の開始された時を起算点として計算すべきもので、時効援用者において起算点を選択し、時効完成の時期を早めたり遅らせたりすることはできないとした事例 |
||
| 904 | S35.7.8 |
農地の賃貸借が農地法19条により更新されたときは、以後期間の定めのない賃貸借として存続するものと解されるとした事例 |
||
| 905 | S35.6.28 |
債権及び根抵当権の譲渡が根抵当権者、譲受人及び債務者の合意によりなされたときは、債権及び根抵当権の譲渡ならびにこれに基いてなされた根抵当権取得登記を無効とすべき理由はないとした事例 |
||
| 906 | S35.6.21 |
賃借家屋を使用し家具の製造を業としている賃借人が住込で雇い入れた工員は、賃借家屋の使用については、賃借人の義務の履行補助者にあたるとした事例 |
||
| 907 | S35.5.6 |
商法520条にいう取引時間外に弁済がなされても、債権者が任意に弁済を受領し、それが弁済期日内であるときは、債務者は履行遅滞の責を負わないとした事例 |
||
| 908 | S35.4.21 |
・二重売買における他買主に対する対抗力は、登記がいわゆる中間省略登記であっても、その効力に異なるものはないとした事例 |
||
| 909 | S35.2.11 |
占有取得の方法が外観上の占有状態に変更を来たさない占有改定にとどまるときは、民法192条(即時取得)の適用はないとした事例 |
||
| 910 | S35.1.22 |
乙名義で不動産を競落した甲から所有権を取得した丙は、乙に対して移転登記の請求をすることができるとした事例 |
||
| 911 | S34.12.5 |
弁護士法第72条にいわゆる「業とする」とは、反覆継続して行う意思のもとに同条列記の行為をなすことをいうものであって、具体的になされた行為の多少は問うところではないとした事例 |
||
| 912 | S34.12.4 |
賃借土地の使用に事実上の支障がある場合において、特段の事情があるとして借主の賃料支払義務を認めた事例 |
||
| 913 | S34.11.26 |
土地共有持分の一部の譲受人が、他の共有者との間において、その土地の一部を分割し譲受人の単独所有として使用しうること及び分筆登記が可能となったときは直ちにその登記をなすことを約した場合は、その後同土地につき共有持分の譲受人に対して契約上の債権を行うことができるとした事例 |
||
| 914 | S34.7.14 |
登記申請が登記義務者の意思に基づいてなされ、その登記が実体的権利関係に合致するときは、たとえ申請の際に添付された印鑑証明書の日附が変造されたものであっても、登記の効力を有するとした事例 |
||
| 915 | S34.6.25 |
家屋の所有者がその敷地を占有する権原のない場合に、所有者を代表者とする会社がその家屋の全部を借受けて占有しているときは、会社は敷地の所有者に対し、敷地の不法占有による損害賠償責任を負うとした事例 |
||
| 916 | S34.2.12 |
真正なる不動産の所有者は、所有権に基き、登記簿上の所有名義人に対し、所有権移転登記を請求することができるとした事例 |
||
| 917 | S34.1.8 |
登記簿上の所有名義人は、反証のない限り、不動産を所有するものと推定すべきとした事例 |
||
| 918 | S33.11.6 |
再売買の予約完結権の消滅時効は、権利の行使につき特に始期を定め、または停止条件を附したものでない限りは、予約完結権の成立した時から進行する |
||
| 919 | S33.10.14 |
被相続人が不動産の譲渡をした場合、その相続人から同一不動産の譲渡を受けた者は、民法第177条にいう第三者に該当するとした事例 |
||
| 920 | S33.8.28 |
時効により不動産の所有権を取得しても、その登記がないときは、時効完成後旧所有者から所有権を取得し登記を経た第三者に対し、その善意であると否とを問わず、所有権の取得を対抗できないとした事例 |
||
| 921 | S33.6.14 |
甲乙間になされた甲所有不動産の売買が契約時に遡って合意解除された場合、すでに乙からこれを買い受けていたが、未だ所有権移転登記を得ていなかった丙は、合意解除が信義則に反する等特段の事情がないかぎり、乙に代位して、甲に対し所有権移転登記を請求することはできないとした事例 |
||
| 922 | S33.6.5 |
・知事の許可を停止条件として締結された農地の売買契約は、無効ではないとした事例 |
||
| 923 | S33.4.9 |
都市計画法施行令(昭和30年3月政令第47号による改正前)11条の2による建築許可に附した無補償撤去等の条件が憲法29条に違反しないとした事例 |
||
| 924 | S33.2.14 |
通行地役権の時効取得に関する「継続」の要件は、承役地たるべき他人所有の土地の上に通路の開設があっただけでは足りず、その開設は要役地所有者によってなされることを要するとした事例 |
||
| 925 | S32.12.19 |
他に連帯保証人がある旨の債務者の言を誤信した結果、連帯保証をした場合は、縁由の錯誤であって当然には要素の錯誤ではないとした事例 |
||
| 926 | S32.12.17 |
業務上過失致死傷罪成立の要件について、判示された事例 |
||
| 927 | S32.11.14 |
権利能力のない労働組合よりの脱退組合員は、その脱退が組合分裂に基づく場合であっても、当然には組合に対し財産分割請求権を有しないとした事例 |
||
| 928 | S32.9.27 |
処分禁止の仮処分登記の移記が遺脱されたまま、売買により甲に所有権移転登記がなされ、次いで甲より乙がが不動産を買受けた場合であったても、乙はその所有権の取得をもって仮処分債権者に対抗できないとされた事例 |
||
| 929 | S32.7.9 |
「失火ノ責任ニ関スル法律」但書にいわゆる「重大ナル過失」とは、通常人に要求される程度の相当な注意をしないでも、わずかの注意さえすれば、たやすく違法有害な結果を予見することができた場合であるのに、漫然これを見すごしたような、ほとんど故意に近い著しい注意欠如の状態を指すものとされた事例 |
||
| 930 | S32.6.18 |
仮登記のなされた不動産につき第三者のための所有権取得の登記がなされたときにおいても、仮登記権利者は本登記をなすに必要な要件を具備する場合は、仮登記義務者に対しては本登記、第三者に対しては抹消登記の請求をなし得るとした事例 |
||
| 931 | S32.6.7 |
甲所有の不動産につき、乙のため所有権移転請求権保全の仮登記がなされた後に、甲が不動産を丙に譲渡し移転登記をした場合に、乙は、丙の登記を抹消することなくして、甲に対し所有権移転登記を請求することができるとした事例 |
||
| 932 | S32.6.7 |
甲所有の不動産につき、一旦国税滞納処分による公売により落札者乙に所有権登記がなされた後、公売の取消処分があった結果、甲に所有権が復帰した場合であっても、その登記がないときは、甲は乙から公売取消後その不動産を譲り受けた丙に対し、所有権の復帰を対抗できないとした事例 |
||
| 933 | S32.5.30 |
不動産の所有権者でない者が所有権保存登記手続をして登記簿上所有名義人となったときは、真正の所有権者は、名義人に対し移転登記手続を求めることができるとした事例 |
||
| 934 | S32.5.21 |
死因贈与の方式については、遺贈に関する規定の準用はないとした事例 |
||
| 935 | S32.5.21 |
農地の贈与契約について、知事の許可により所有権の移転を生ずべき停止条件附贈与契約は有効であるとした事例 |
||
| 936 | S31.12.18 |
国が連合国占領軍の接収通知に応じ、建物をその所有者から賃借してこれを同軍の使用に供した場合には、国は、その建物の設置保存に関する瑕疵に基因する損害につき、民法717条にいう占有者としてその責に任ずべきであるとされた事例 |
||
| 937 | S31.11.27 |
・土地区画整理委員会の委見を聞かないでした換地処分も無効ではないとした事例 |
||
| 938 | S31.10.4 |
遺言者の生前における遺言無効確認の訴えは不適法であるとした事例 |
||
| 939 | S31.9.28 |
売買により不動産の所有権登記を得た者、および、同人から抵当権設定登記と代物弁済契約による所有権移転請求権保全の仮登記を得た者を共同被告として、不動産の所有者として売買の不存在を主張する者からの登記抹消を求める訴は、必要的共同訴訟にあたらないとされた事例 |
||
| 940 | S31.8.30 |
・不動産質権は、質物を留置することをうる効力も、登記なき限り第三者に対抗できないとした事例 |
||
| 941 | S31.7.20 |
換地予定地指定の通知を受けた土地所有者は、従前の土地について賃借権を有する者として第三者に対してなされた換地予定地指定の通知の取消を求める法律上の利益を有するとした事例 |
||
| 942 | S31.6.5 |
未登記建物の譲受人は、判決を得て自己の所有権を証明し単独に保存登記をなすことを得るが、譲渡人に対し保存登記をした上で移転登記をすることを請求することもできるとした事例 |
||
| 943 | S31.5.10 |
不動産共有者の一人は、その持分権に基づき、単独で当該不動産につき登記簿上所有名義を有する者に対しその登記の抹消を請求することができるとした事例 |
||
| 944 | S31.4.6 |
鉱業権の売買契約において、買主が排水探鉱の結果品質良好と認めたときは代金を支払い、品質不良と認めたときは代金を支払わない旨を約しても、売買契約は民法134条にいわゆる条件が単に債務者の意思のみにかかる停止条件付法律行為とはいえないとした事例 |
||
| 945 | S31.1.27 |
書面によらない不動産の贈与において、所有権の移転があっただけでは履行を終ったものとすることは出来ず、その占有の移転があったときに履行を終ったものと解すべきであるとした事例 |
||
| 946 | S31.1.26 |
土地の賃借人が、賃貸人たる土地所有者に代位して、土地の不法占有者に対しその明渡を請求する場合には、直接自己に対し明渡しを求めることができるとした事例 |
||
| 947 | S30.12.26 |
通行地役権の時効取得については、いわゆる「継続」の要件として、承役地たるべき他人所有の土地の上に通路の開設を要し、その開設は要役地所有者によってなされることを要するとされた事例 |
||
| 948 | S30.10.28 |
・他人の借地契約上の債務について連帯保証契約をすることは、特段の反証のない限り会社の目的の範囲内の行為であるとされた事例。 |
||
| 949 | S30.9.23 |
一筆の土地全部の賃借人が地上に登記のある建物を所有した時は、その後土地が分筆され、建物の存在しない部分について所有権が移転された場合においても、移転された土地所有者に対し賃借権を対抗することができるとした事例 |
||
| 950 | S30.9.23 |
立木とその土地が同一所有者に属するときは、立木の所有権は土地の所有権に包含され一個の土地所有権となるものであるから、土地を立木とともに買い受けた者が、土地の所有権取得登記をしたときは、例えその後立木につき前所有者のため保存登記がなされても、この登記は無効であるとされた事例 |
||
| 951 | S30.9.9 |
農地の贈与についての知事の許可は、贈与の成立前になされることを要せず、許可のあったときから贈与は効力を生ずるものであり、許可当時贈与者が既に死亡していても、その効力の発生を妨げないとした事例 |
||
| 952 | S30.7.19 |
換地予定地の指定通知を受けた者は、指定された土地の上に、これを使用収益すべき権利を取得するが、従来の事実上の占有状態に変更のない限り、指定があっただけでは当然には占有権の変動移転を生ずるものではないとした事例 |
||
| 953 | S30.7.5 |
不動産の登記簿上の所有名義人は真正の所有者に対しその所有権の公示に協力すべき義務を有するものであるから、真正の所有者は所有権に基き所有名義人に対し、所有権移転登記の請求ができるとした事例 |
||
| 954 | S30.6.28 |
不法な手段により抹消された所有権移転請求権保全の仮登記につき、その抹消登記を真実と信じ登記を得た善意無過失の第三者は、特段の事情がない限り、回復登記手続を承諾する義務はないとした事例 |
||
| 955 | S30.6.24 |
1筆の土地を区分した「土地の一部」を売買の目的とすることは可能であり、「土地の一部」が、売買の当事者間において具体的に特定している限りは、分筆手続未了前においても買主は売買によりその「土地の一部」につき所有権を取得することができるとした事例 |
||
| 956 | S30.5.31 |
相続財産の共有は、民法249条以下に規定する「共有」とその性質を異にするものではないとした事例 |
||
| 957 | S30.5.31 |
不動産の二重売買において、登記を受けた第二売買の買主は、第一売買について知っていたとしても、それだけで第一売買の買主に対する不法行為責任を負うものではないとされた事例 |
||
| 958 | S30.4.19 |
家屋賃借人の妻の失火により、家屋が滅失したときは、賃借人の責に帰すべき事由により賃借物の返還義務が履行不能になったと解され、賃貸人は、契約を解除することなくして填補賠償の請求をすることができるとした事例 |
||
| 959 | S30.3.25 |
賃借人の失火により賃貸中の家屋が焼失した場合における、賃貸人から賃借人に対する賃貸借契約上の家屋返還義務の債務不履行については、「失火ノ責任ニ関スル法律」の適用はなく、借主は貸主に対し損害賠償責任を負うとした事例 |
||
| 960 | S30.3.23 |
4月1日に始まる年度の固定資産税につき、その納期において土地所有権を有するか否かにかかわらず、土地台帳もしくは土地補充課税台帳にその年の1月1日に所有者として登録されている者が納税義務を負う地方税法は、憲法に違反しないとした事例 |
||
| 961 | S29.12.24 |
相続が発生した不動産について、相続登記をせず相続後の日付にて、直接被相続人から買主宛に行われた所有権移転登記は有効であるとした事例 |
||
| 962 | S29.12.23 |
共有土地につき、地上権を設定したものと看做すべき事由が単に土地共有者の一人だけについて発生した場合、このために他の共有者の持分が、その意思如何に拘わらず無視さるべきいわれはないことから、法定地上権は成立しないとした事例 |
||
| 963 | S29.9.24 |
建物の賃借人は、貸主たる建物所有者に代位して、建物の不法占拠者に対しその明渡しを請求する場合、直接自己に対して建物の明渡しをするよう請求することができるとした事例 |
||
| 964 | S29.9.10 |
民法951条の法人たる相続財産は、被相続人が生前になした不動産の贈与につき、登記の欠缺を主張できないとした事例 |
||
| 965 | S29.3.12 |
共同相続人の一人が相続財産である家屋の使用借主である場合、他の共同相続人による使用貸借の解除は、民法252条本文の管理行為にあたるとした事例 |
||
| 966 | S29.1.28 |
仮装の売買契約に基づき所有権移転登記を受けた者が、その後真実の売買契約により所有権を取得し、登記が現在の実体的権利状態と合致した時は、以後その所有権の取得を第三者に対抗することができるとした事例 |
||
| 967 | S28.1.23 |
民法242条は、不動産の付合物が、取引上当該不動産と別個の所有権の対象となるものであっても、当該不動産の所有権が当然付合物に及ぶことを規定するものであって、付合物に対する所有権が当該不動産の所有権の外に独立して存することまでを定めているものではないとした事例 |
||
| 968 | S27.12.4 |
抵当権設定登記において、消費貸借契約成立日の年月日が、実際の成立日より前の年月日として登記されていた事案において、同一の消費貸借を表示するものである以上登記は有効であるとされた事例 |
||
| 969 | S27.9.30 |
借地権及び建物の登記がなければ、土地を買い受けた第三者に対しては、たとえ第三者が買受当時借地権及び建物の存在を知っていたとしても、それだけでは借地権をもって対抗することはできないとした事例 |
||
| 970 | S26.4.19 |
土地の共有者が共同でその土地を使用することは共有土地の利用方法であって、民法667条の「共同の事業を営むこと」にあたらないとした事例 |
||
| 971 | S25.12.19 |
不動産の不法占有者は、民法177条にいう「第三者」に当たらないとした事例 |
||
| 972 | S17.9.30 |
・売主が詐欺による売買取消しの意思表示をした後に、その詐欺による取消しの事実を知らないで買主より権利を取得した第三者は、民法96条第3項の善意の第三者に該当しないとした事例 |
昭17(オ)4号(大審院) |
|
| 973 | S15.11.26 |
抵当権は後順位抵当権者及抵当物件の第三取得者に対しては被担保債権と離れ単独に20年の消滅時効に因り消滅するとされた事例 |
昭15(オ)750号(大審院) |
|
| 974 | S15.9.18 |
地方慣習法により排他的支配権が認められる温泉使用権は、第三者がその権利の変動を明認できる公示方法を構じなければ、当該権利変動を第三者に対抗できないとした事例 |
昭14(オ)1701号(大審院) |
|
| 975 | S15.5.10 |
民法715条の被用者がその事業の執行につき加えた損害とは、使用者の事業執行自体によつて第三者に加えた損害に限らず、事業と不離の関係にある被用者の行為、事業遂行を助長する性質に属する被用者の行為、および、外観上業務執行と同一の外形を有する被用者の行為により生じた損害を含むとした事例 |
昭14(オ)823号(大審院) |
|
| 976 | S14.7.7 |
不動産売買契約により買主に所有権移転登記がなされた後に、当該契約が解除され原状に回復した場合においても、売主がその旨の登記をしなければ、契約解除後に買主から不動産所有権を取得した第三者に対して、自己の所有権を対抗することができないとした事例 |
昭13(オ)2179号(大審院) |
|
| 977 | S13.7.7 |
甲所有の一筆の土地の一部を買い受けた者が、当該土地の全部の移転登記を受け、更にその全部を自己の所有地として乙に売り渡し移転登記をしたとしても、乙は、甲より一筆の土地の他の一部を買い受けた丙に対し、その登記の欠缺を主張できる第三者に該当しないとされた事例 |
昭13(オ)485号(大審院) |
|
| 978 | S13.2.4 |
・未成年者が法定代理人の同意を得ずした債務の承認は取り消すことができるとした事例 |
昭12(オ)1810号(大審院) |
|
| 979 | S13.1.31 |
賃借人の保証人は、賃借人の賃料延滞を理由とする契約解除においても、賃借人が賃借物の返還義務を履行しないことによる賃貸人の損害についても賠償責任を負うとした事例 |
昭12(オ)1581号(大審院) |
|
| 980 | S12.11.19 |
隣地が所有地内に崩壊する危険性がある場合、土地の所有者は、その危険が隣地所有者によるものかどうか、また隣地所有者の故意過失の有無にかかわらず、隣地所有者に対し危険の防止に必要な措置を請求できるとした事例 |
昭12(オ)1065号(大審院) |
|
| 981 | S12.7.17 |
電気事業者が高圧電線を設置したところ、後に樹木が育成しそれに登った者が感電死した事案において、事業者に外部の状況の変化に対応した安全処置を尽くさなかった工作物責任があるとされた事例 |
昭11(オ)1489号(大審院) |
|
| 982 | S12.6.30 |
民法第715条により使用者が負担する損害賠償義務の消滅時効と、被用者が第三者に対して負担する損害賠償義務の消滅時効とは、それぞれ別々に進行するとした事例 |
昭11(オ)844号(大審院) |
|
| 983 | S12.6.15 |
賃借人の保証人は、賃借人が死亡しその相続人が賃貸借関係を承継した場合においても、承継後に生じた相続人の債務につき保証人たる責任を免かれないとした事例 |
昭10(オ)2737号(大審院) |
|
| 984 | S10.10.1 |
住宅用建物にして屋根瓦を葺き荒壁を付け了りたるものは、未だ床及天井を備えていないとしても登記し得べき建物であるということを妨げないとした事例 |
昭10(オ)752号(大審院) |
|
| 985 | S9.9.15 |
定期預金の返還期が当事者双方のために定められている場合であっても、預り主は預け主が返還期の到来までに享くべき利益の喪失を填補するときは、期限の利益を放棄することができるとされた事例 |
昭8(オ)49号(大審院) |
|
| 986 | S9.3.29 |
債権の譲渡を主たる債務者に通知しない限り、連帯保証人にその通知をしても、その譲渡をもって連帯保証人に対抗することはできないとした事例 |
昭8(オ)656号(大審院) |
|
| 987 | S8.10.13 |
保証人は当事者として、主たる債務に関する消滅時効の援用をなすことができるとした事例 |
昭8(オ)1092号(大審院) |
|
| 988 | S8.4.6 |
賃借人が賃料の支払をしないで相当期間経過したのにもかかわらず、賃貸人が契約解除をしないときは保証人は一方的意思表示により保証契約を解除することができるとした事例 |
昭7(オ)1492号(大審院) |
|
| 989 | S7.7.19 |
家屋の賃借人の連帯保証人は、賃貸借に期限の定めがなく、保証人の責任期間に限定がなくても、賃貸借終了前に連帯保証人の一方的意思表示により保証債務を免れることはできないとした事例 |
昭6(オ)3677号(大審院) |
|
| 990 | S6.6.4 |
連帯債務者の一人又は主債務者が完成した時効の利益を放棄しても、他の連帯債務者又は主債務者と連帯する保証人に対して何らの効力を及ぼさないとした事例 |
昭5(オ)3259号(大審院) |
|
| 991 | S6.5.29 |
同一不動産につき二重売買の行われた場合において、所有権の取得を登記した第二の買受人は、単に仮登記であっても、第一の買受人に対し登記欠缺を主張することができるとされた事例 |
昭5(オ)3300号(大審院) |
|
| 992 | S4.3.30 |
使用者たる債務者は、その履行につき使用する者の故意または過失について責任を負うとした事例 |
昭3(オ)第77号(大審院) |
|
| 993 | S3.6.7 |
土地の工作物の設置または保存の瑕疵により他人に損害が生じた場合は、所有者に過失がない場合といえども賠償責任を負うとした事例 |
昭3(オ)341号(大審院) |
|
| 994 | S2.9.19 |
通路を設けないで一定の地上を通行しても、時効により地役権を取得することはできないとした事例 |
昭2(オ)456号(大審院) |
|
| 995 | S2.6.15 |
未登記建物の所有権を取得した者が、移転登記をしないで直ちに保存登記をし、その所有権を第三者に対抗することができるとした事例 |
昭2(オ)413号(大審院) |
|
| 996 | S2.6.15 |
民法715条(使用者等の責任)は、事業の執行につき被用者がある程度において使用者の意思に服従すべき場合に適用あるとされた事例 |
昭2(オ)161号(大審院) |
|
| 997 | S2.3.22 |
本人が無権代理行為の追認または追認の拒絶を行わず死亡し、無権代理人が本人を相続したときは、本人自ら法律行為としたのと同一の地位を有するものとする。 |
大15(オ)1073号(大審院) |
|
| 998 | T15.6.12 |
火災保険契約において、地震のため生じた火災・延焼、その他の損害につき保険者において責任を負わない旨の特約は公序良俗に反せず有効であるとした事例 |
大14(オ)792号(大審院) |
|
| 999 | T14.7.8 |
時効により不動産の所有権を取得したがその登記を受けなかった者は、時効完成後保存登記を受けた旧所有者より所有権を譲受け登記をした第三者に対して、所有権の取得を対抗することができないとした事例 |
大13(オ)482号(大審院) |
|
| 1000 | T14.1.20 |
自己に所有権ありと信じて他人の所有家屋に居住していた者は、その居住により受けた利得を所有者に返還することを要しないとした事例 |
大13(オ)566号(大審院) |
|
| 1001 | T13.10.7 |
土地の一部は、分筆の手続がなされていなくても、時効による所有権取得の目的となるとした事例 |
大12(オ)672号(大審院) |
|
| 1002 | T13.10.7 |
土地の一部は、分筆手続をする以前でも所有者においてこれを譲渡することができるとした事例 |
大12(オ)664号(大審院) |
|
| 1003 | T12.2.23 |
売主らの共有財産である立木の売買において、売主の買主に対する引渡し義務は不可分債務であるとされた事例 |
大11(オ)963号(大審院) |
|
| 1004 | T11.11.24 |
共同賃借人の賃料支払債務は反対の事情のない限り不可分債務であるとした事例 |
大11(オ)760号(大審院) |
|
| 1005 | T10.10.15 |
権利の行使を妨げるものがあるときは、債権といえどもその妨害排除をなし得るとした事例 |
大10(オ)669号(大審院) |
|
| 1006 | T10.7.11 |
不動産の賃借人は賃貸借の登記をなすことの特約がない場合には、特別の規定がない限り、賃貸人に対して賃貸借の本登記請求権は勿論、その仮登記をなす権利をも有しないとした事例 |
大10(オ)245号(大審院) |
|
| 1007 | T9.1.20 |
土地上に立木が生立する場合において、その土地と立木が同一人の所有であるときは、土地と立木とは一個の土地所有権の目的であって、別個に所有権が存在するものではないから、土地所有権につき移転登記がなされたときは、これにより土地のみならず立木に関しても所有権の移転を第三者に対抗するできるとされた事例 |
大8(オ)955号(大審院) |
|
| 1008 | T7.3.19 |
共同賃借人の賃借物返還債務は不可分債務であり、賃貸人は各賃借人に賃借物全部の返還請求ができるとした事例 |
大7(オ)136号(大審院) |
|
| 1009 | T7.3.2 |
時効による不動産所有権の取得は、第三者に対抗するには登記を必要とするが、時効完成時における所有者に対しては登記を必要としないとした事例 |
大6(オ)888号(大審院) |
|
| 1010 | T5.4.1 |
・売買による所有権登記は、買主への所有権移転を完全にするための必須の手続きであることから、登記請求権は独立して消滅時効にはかからないとした事例 |
大4(オ)879号(大審院) |
|
| 1011 | T4.7.13 |
民法第145条のいわゆる当事者には、主たる債務が時効により消滅した場合における保証人も含まれるとされた事例 |
大4(オ)189号(大審院) |
|
| 1012 | T3.4.4 |
地上権者又は賃借人が1筆の土地の上に1棟でも登記した建物を有するときは、同一の土地の上に他の登記しない建物を有すると否とに拘わらずその土地の全部にわたり地上権又は賃借権をもって第三者に対抗することができるとした事例 |
大2(オ)659号(大審院) |
|
| 1013 | T1.12.6 |
「土地ノ工作物」とは、建物墻壁地窖のように、土地に接著して築造した設備をいい、機械のように、工場内に据付けられたものは含まないとした事例 |
大元(オ)94号(大審院) |
|
| 1014 | M44.12.25 |
二重売買において、第一の売買による登記がなされないうちに、第二の売買の買主が悪意で登記を行い、このため第一の売買の買主の利益を害したとしても、第二の売買の買主に不法行為の責任はないとされた事例 |
明44(オ)334号(大審院) |
|
| 1015 | M44.11.14 |
売主の買主に対する登記移転義務は、所有権移転義務に付随するものであり、登記義務の不履行は民法541条(履行遅滞による解除権)の債務不履行にあたるとした事例 |
明44(オ)359号(大審院) |
|
| 1016 | M43.7.6 |
甲より不動産を購入した乙の転売により不動産を購入した丙は、乙よりの所有権移転登記がなされない場合は、民法423条(債権者代位権)により、乙の甲に対する登記手続の請求権を行使することができるとした事例 |
明43(オ)152号(大審院) |
|
| 1017 | M41.12.15 |
民法177条(不動産に関する物件の対抗要件)の第三者とは、 当事者もしくはその包括承継人以外の者で、不動産物権の得失及び変更の登記欠缺を主張する正当の利益を有する者をいうとした事例 |
明41(オ)269号(大審院) |
|
| 1018 | M40.6.18 |
主たる債務に付き弁済期限が延長された場合、その効力は当然保証債務に及ぶとされた事例 |
明39(オ)666号(大審院) |
|
| 1019 | M40.6.13 |
本来一個の債権でも、時期を定めて数回にこれを分割弁済すべき場合には、各弁済期の到来により、その期に弁済せられるべき部分に応じ一部づつ時効にかかるとされた事例 |
明40(オ)105号(大審院) |
|
| 1020 | M40.5.6 |
民法第550条は贈与の意思の明確を期するとともに、軽忽な贈与を予防しようとする趣旨の規定であり、当事者双方の意思表示につき書面の作成を命じたものではないとされた事例 |
明39(オ)260号(大審院) |
|
| 1021 | M38.12.19 |
当事者が保証契約を締結する縁由に錯誤があっても、特にその縁由の実在をもって契約の要件としなかった以上は契約は無効とはならないとされた事例 |
明38(オ)404号(大審院) |
|
| 1022 | M36.11.16 |
地上権を譲受けた者は前地上権者の承継人であるから、その地上権をもって土地所有者に対抗するには登記を必要とせず、その土地所有者は民法177条(不動産に関する物件の対抗要件)の第三者に該当しないとした事例 |
明36(オ)535号(大審院) |
RETIO : (一財)不動産適正取引推進機構 機関誌