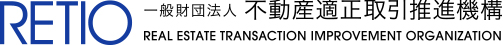| 制作:国土交通省 |
| 運営:不動産適正取引推進機構 |
| 1 本システムは、これまでに発生した不動産取引をめぐる他のトラブル事例をもとに、消費者の皆様が、トラブルの未然防止や万一トラブルに発展した場合に円滑な解決が図れるよう、情報を提供するものです。 2 掲載内容は、①裁判事例、②国土交通省各地方整備局や各都道府県で宅建業者に対して行った行政処分、③(一財)不動産適正取引推進機構で調整した特定紛争処理案件の中から基礎的で有用と思われる事例を抽出し、項目ごとに整理したうえ、事案の概要や紛争の結末等について要約して記載しています。 |
最新の情報については、
「RETIO判例検索システム」
「特定紛争案件検索システム」
「ネガティブ情報等検索サイト」(国土交通省)
「不動産のQ&A」
をご活用ください。
検索ボタンをクリックして頂くと、該当する事例の一覧が表示されます。
| トラブル事例大項目:土地建物の賃貸借契約に関するもの (原状回復を除く) |
トラブル事例中項目:賃料等 | トラブル事例小項目: |
タイトル:裁判事例地代自動改定特約と借地借家法の地代等増減請求権
最高裁判決 平成15年6月12日
(判例時報 1826号 47頁)
(判例タイムズ 1126号 106頁)
《要旨》
地代自動改定特約があっても、借地借家法に基づく地代等増減請求権の行使が可能とされた事例
(1) 事案の概要
借地人Xは、昭和62年7月、スーパー建設・賃貸のため、賃貸人Y所有の土地について35年間の賃貸借契約を締結した。X及びYは、権利金の授受はせず、月額賃料633万円余(土地価格の8%の1/12)、賃料は3年後に見直して当初賃料の15%増、次回以降は3年ごとに10%増額とする旨の特約を合意した。なお、経済情勢の変化によっては別途協議とされた。
Xは、約定に従って、平成9年6月までの賃料を支払ったが、平成9年7月には、地価の下落を考慮すると、地代を更に10%増額するのはもはや不合理であると判断し、従来通りの地代を支払い続けたところ、Yは特段の異議を述べなかった。しかし、平成9年12月、Xが本件土地の地代を20%減額して、月額640万円余とするよう請求したが、Yはこれを拒否した。
Yは、平成10年10月、平成9年7月以降の賃料は、10%増額後の月額881万円であるとして既払賃料との差額の支払を催告した。一方、Xは、20%減額した額を支払うようになった。X及びYは、その主張が相当であることの確認を求め、それぞれ提訴した。
(2) 判決の要旨
(ア)借地借家法11条1項の規定は、強行法規(きょうこうほうき)
法律の規定のうち、当事者がそれと異なる。としての実質を持つものである。他方、地代等の額の決定は、本来当事者の自由な合意にゆだねられているのであるから、将来の地代等の額をあらかじめ定める内容の特約を締結することもできるというべきである。
(イ)地代等自動改定特約は、地代等改定基準が借地借家法11条1項の規定する経済事情の変動等を示す指標に基づく相当なものである場合には、その効力を認めることができる。しかし、その改定基準を定める際に基礎となっていた事情が失われることにより、地代等の額を定めることが借地借家法11条1項の趣旨に照らして不相当なものとなった場合には、同特約を争う当事者は、もはや同特約に拘束されるものではない。
(ウ)本件賃貸借契約の締結当時は、バブル経済の崩壊前であって、時の経過に従って地代の額が上昇していくことを前提として定めた本件増額特約の効力を否定することはできない。しかし、土地価格が下落に転じた後の時点においては、不相当なものとなったというべきである。土地が当初の半額以下になった平成9年7月時点では、Xはもはや本件増額特約に拘束されない。
(エ)よって、Yの地代増額請求を棄却し、Xが地代減額請求をした平成9年12月の時点における相当な地代の額について審理を尽くさせるため、原審に差し戻す。
(3) まとめ
本判決は、地代等自動改定特約において、地代等の改定基準を定めるに当たって基礎とされていた事情が失われることにより、同特約によって地代等の額を定めることが、借地借家法11条1項の規定に照らして不相当なものとなった場合には、同条項に基づく地代等増減請求権の行使が可能との判断を示している。
| 本システムの掲載情報の正確性については万全を期しておりますが、利用者が本システムの情報を用いて行う行為については本システムの制作者、運営者は何ら責任を負うものではありません。また、同種の事案について、必ず同様の結果が得られるものではありませんのでご承知おきください。なお、個別に発生したトラブル等については、管轄の行政庁等の相談窓口等にお問い合わせください。 |