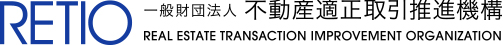| 制作:国土交通省 |
| 運営:不動産適正取引推進機構 |
| 1 本システムは、これまでに発生した不動産取引をめぐる他のトラブル事例をもとに、消費者の皆様が、トラブルの未然防止や万一トラブルに発展した場合に円滑な解決が図れるよう、情報を提供するものです。 2 掲載内容は、①裁判事例、②国土交通省各地方整備局や各都道府県で宅建業者に対して行った行政処分、③(一財)不動産適正取引推進機構で調整した特定紛争処理案件の中から基礎的で有用と思われる事例を抽出し、項目ごとに整理したうえ、事案の概要や紛争の結末等について要約して記載しています。 |
最新の情報については、
「RETIO判例検索システム」
「特定紛争案件検索システム」
「ネガティブ情報等検索サイト」(国土交通省)
「不動産のQ&A」
をご活用ください。
検索ボタンをクリックして頂くと、該当する事例の一覧が表示されます。
| トラブル事例大項目:土地建物の賃貸借契約に関するもの (原状回復を除く) |
トラブル事例中項目:管理等に関するもの | トラブル事例小項目: |
タイトル:裁判事例水漏れ事故の損害賠償債務と連帯保証契約
甲府地裁判決 平成17年9月16日
(ホームページ下級裁主要判決情報)
《要旨》
階下の事務所を水浸しにした加害者である賃借人の損害賠償責任とその父親及び賃貸人が被害者と締結した損害に対する連帯保証(れんたいほしょう)
債務者の債務を、他人が保証することを「保証」
という(民法第446条)。この「保証」の特殊な
形態として、保証人の責任を強化した「連帯保証」
がある(民法第454条)。契約の効力が認められた事例
(1) 事案の概要
Y3の所有するビルの3階居室を借り受けている賃借人Y1は、平成14年2月、ユニットバスの洗面台の蛇口を閉め忘れたため、床に水がたまり、同じくY3から借り受けている賃借人Xの2階事務所に水漏れによる損害を与えた。
XのA社長は、現場に来ていたY1の父親Y2に対し、「私は下記の件に付損害を与えそれに対して保証、弁済することを確約いたします。」と書かれた連帯保証(れんたいほしょう)
債務者の債務を、他人が保証することを「保証」
という(民法第446条)。この「保証」の特殊な
形態として、保証人の責任を強化した「連帯保証」
がある(民法第454条)。契約書面に、Y1とY2に署名を求めた。Y2はなかなか署名に応じなかったが、A社長のしつこい求めに根負けし、署名に応じた。また、A社長は、水漏れ事故が2回目であることから、本件ビルには構造上の問題があることを疑い、所有者・賃貸人Y3にも本件書面への署名を求めた。Y3も署名に躊躇したが、最後には署名に応じた。
Xは、Y1、Y2、Y3に対して、連帯保証(れんたいほしょう)
債務者の債務を、他人が保証することを「保証」
という(民法第446条)。この「保証」の特殊な
形態として、保証人の責任を強化した「連帯保証」
がある(民法第454条)。契約等に基づき損害賠償金3,940万円余を請求した。
(2) 判決の要旨
(ア)Y1のXに対する過失不法行為(ふほうこうい)
他人の権利・利益を違法に侵害したことによって
損害を与える行為をいう。
このような行為によって生じた損害については、
加害者が被害者に賠償する責任を負わなければならない。責任の成立には争いがない。
(イ)Y2は、具体的な保証意思はなかったと主張するが、Y2は、本件書面を読んだ上で署名したと認めざるをえない。また、25歳のひとり暮らしの息子が不始末をしでかした場合、被害者がその父親に対して賠償を求めるのは、法律上はともかく、社会通念上それほどおかしいとはいえないのが実情であるから、A社長の意図を、Y2は十分理解していたと認められる。また、警察への提出書類と認識したとの錯誤(さくご)
意思表示をした者の内心の真意と表示されたことが、
重要な点(要素)で食い違いがあることをいう(民法95条)。の事実は認められない。
(ウ)Y3は、冷静に考慮し、署名しており、被害現場の状態も自分自身で見ていたのであるから、Xに相当大きな被害が発生することも予想できたはずである。Y3は、十分承知したうえで署名したのだといわざるをえないから、保証意思があったのは明らかである。心裡留保(しんりりゅうほ)
本人の真意とは異なる内容を、本人が外部に
表示することをいう。例えば、ある品物を買
う意思がまったくないのに、冗談で「その品
物を買います」と店員に言う行為が該当する。の事実は認められない。「家主としての管理責任があると誤解した」としても、動機の錯誤(さくご)
意思表示をした者の内心の真意と表示されたことが、
重要な点(要素)で食い違いがあることをいう(民法95条)。に過ぎず、これが表示された事実はないから、錯誤(さくご)
意思表示をした者の内心の真意と表示されたことが、
重要な点(要素)で食い違いがあることをいう(民法95条)。無効は成立しない。脅迫の事実も認定することができない。
(エ)Xは、Y1に対しては不法行為(ふほうこうい)
他人の権利・利益を違法に侵害したことによって
損害を与える行為をいう。
このような行為によって生じた損害については、
加害者が被害者に賠償する責任を負わなければならない。に基づき、Y2とY3に対してはいずれもその連帯保証(れんたいほしょう)
債務者の債務を、他人が保証することを「保証」
という(民法第446条)。この「保証」の特殊な
形態として、保証人の責任を強化した「連帯保証」
がある(民法第454条)。契約に基づき、3,940万円余を支払うよう請求することができる。原告の主張は全部正当である。
(3) まとめ
本件では、保管されていた商品が被害にあったことから損害額が大きなものとなった。裁判所は、原告の損害額を4,110万円と認定したが、請求額が3,940万円余であることから、原告の請求を全部認容するにとどめている。
| 本システムの掲載情報の正確性については万全を期しておりますが、利用者が本システムの情報を用いて行う行為については本システムの制作者、運営者は何ら責任を負うものではありません。また、同種の事案について、必ず同様の結果が得られるものではありませんのでご承知おきください。なお、個別に発生したトラブル等については、管轄の行政庁等の相談窓口等にお問い合わせください。 |