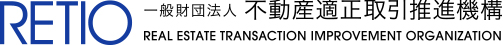| 制作:国土交通省 |
| 運営:不動産適正取引推進機構 |
| 1 本システムは、これまでに発生した不動産取引をめぐる他のトラブル事例をもとに、消費者の皆様が、トラブルの未然防止や万一トラブルに発展した場合に円滑な解決が図れるよう、情報を提供するものです。 2 掲載内容は、①裁判事例、②国土交通省各地方整備局や各都道府県で宅建業者に対して行った行政処分、③(一財)不動産適正取引推進機構で調整した特定紛争処理案件の中から基礎的で有用と思われる事例を抽出し、項目ごとに整理したうえ、事案の概要や紛争の結末等について要約して記載しています。 |
最新の情報については、
「RETIO判例検索システム」
「特定紛争案件検索システム」
「ネガティブ情報等検索サイト」(国土交通省)
「不動産のQ&A」
をご活用ください。
検索ボタンをクリックして頂くと、該当する事例の一覧が表示されます。
| トラブル事例大項目:瑕疵担保責任に関するもの | トラブル事例中項目:建物の瑕疵 | トラブル事例小項目:マンション |
タイトル:裁判事例建物の瑕疵と設計者・施工者の不法行為責任
最高裁判決 平成19年7月6日
(判例時報1984号 34頁)
(判例タイムズ1252号 120頁)
《要旨》
建物の設計者、施工者、工事管理者は、安全性に配慮すべき注意義務を負い、これを怠ったために生じた瑕疵により居住者等の生命、身体または財産を侵害した場合には損害賠償責任を負うとされた事例
(1) 事案の概要
Aは、建築業者Y1との間で建築請負契約(うけおいけいやく)
家の建築工事など、当事者の一方がある
仕事を完成することを約束し、相手方が
その仕事の結果に対して報酬を支払うこ
とを約束するような契約を「請負契約」という。を締結し、設計及び工事監理を設計監理業者Y2に委託した。平成2年3月、Y1はAに本件建物を引き渡し、同年5月、XはAから本件建物を購入したが、本件建物には、はりや壁等のひび割れ、床スラブのたわみ、鉄筋露出等の瑕疵があった。
Xは、本件建物の瑕疵を理由に、Y1に対し請負契約(うけおいけいやく)
家の建築工事など、当事者の一方がある
仕事を完成することを約束し、相手方が
その仕事の結果に対して報酬を支払うこ
とを約束するような契約を「請負契約」という。上の瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)
特定物の売買契約において、その特定物に
「隠れた瑕疵(かし:「きず」「不具合」
「欠陥」のこと)」があったときに、売主
が買主に対して負うべき損害賠償等の責任
を「瑕疵担保責任」と呼んでいる(民法570条)。及び不法行為(ふほうこうい)
他人の権利・利益を違法に侵害したことによって
損害を与える行為をいう。
このような行為によって生じた損害については、
加害者が被害者に賠償する責任を負わなければならない。に基づき、Y2に対しては不法行為(ふほうこうい)
他人の権利・利益を違法に侵害したことによって
損害を与える行為をいう。
このような行為によって生じた損害については、
加害者が被害者に賠償する責任を負わなければならない。に基づき、本件建物の瑕疵補修費用及び瑕疵に伴う損害の賠償を請求した。
地方裁判所は、Yらの不法行為(ふほうこうい)
他人の権利・利益を違法に侵害したことによって
損害を与える行為をいう。
このような行為によって生じた損害については、
加害者が被害者に賠償する責任を負わなければならない。責任を認め、7,393万円余の支払を命じた。Yらは控訴し、高等裁判所は、(ア)XはAからYらに対し瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)
特定物の売買契約において、その特定物に
「隠れた瑕疵(かし:「きず」「不具合」
「欠陥」のこと)」があったときに、売主
が買主に対して負うべき損害賠償等の責任
を「瑕疵担保責任」と呼んでいる(民法570条)。を追及しうる契約上の地位を譲り受けていない。(イ)建物の瑕疵については、違法性が強度である場合に限って請負人や設計・監理者に不法行為(ふほうこうい)
他人の権利・利益を違法に侵害したことによって
損害を与える行為をいう。
このような行為によって生じた損害については、
加害者が被害者に賠償する責任を負わなければならない。責任が成立する余地がある。(ウ)Yらに所有者の権利を積極的に侵害する意図はなく、本件建物の瑕疵は耐力構造上の安全性を脅かすものではない。(エ)不法行為(ふほうこうい)
他人の権利・利益を違法に侵害したことによって
損害を与える行為をいう。
このような行為によって生じた損害については、
加害者が被害者に賠償する責任を負わなければならない。責任を問うような強度の違法性があるとはいえないから、Xの請求は理由がないとして、Xの請求を棄却した。Xが上告した。
(2) 判決の要旨
(ア)設計者、施工者、工事監理者は、建物の建築にあたり、契約関係にない居住者等に対する関係でも建物としての基本的な安全性が欠けることがないよう配慮すべき注意義務を負う。設計・施工者等がこの義務を怠ったために建物に基本的な安全性を損なう瑕疵があり、居住者等の生命、身体、財産が侵害された場合には、特段の事情がない限りこれによって生じた損害について不法行為(ふほうこうい)
他人の権利・利益を違法に侵害したことによって
損害を与える行為をいう。
このような行為によって生じた損害については、
加害者が被害者に賠償する責任を負わなければならない。による損害賠償責任を負うというべきである。
(イ)原審は、設計・施工者等に不法行為(ふほうこうい)
他人の権利・利益を違法に侵害したことによって
損害を与える行為をいう。
このような行為によって生じた損害については、
加害者が被害者に賠償する責任を負わなければならない。責任が成立するのはその違法性が強度である場合、例えば建物の基礎や構造躯体にかかわる瑕疵がある、社会公共的にみて許容し難いような危険な建物なっている場合等に限られ、本件建物に強度の違法性があるとはいえないとする。
(ウ)しかし、建物の基本的な安全性を損なう瑕疵がある場合には不法行為(ふほうこうい)
他人の権利・利益を違法に侵害したことによって
損害を与える行為をいう。
このような行為によって生じた損害については、
加害者が被害者に賠償する責任を負わなければならない。責任が成立すると解すべきであって、違法性が強度の場合に限る理由はない。例えば手すりの瑕疵であっても生命または身体を危険にさらすものもあり得るので、基礎や躯体に瑕疵がある場合に限り不法行為(ふほうこうい)
他人の権利・利益を違法に侵害したことによって
損害を与える行為をいう。
このような行為によって生じた損害については、
加害者が被害者に賠償する責任を負わなければならない。責任が認められると解すべき理由はない。
(エ)Yらの不法行為(ふほうこうい)
他人の権利・利益を違法に侵害したことによって
損害を与える行為をいう。
このような行為によって生じた損害については、
加害者が被害者に賠償する責任を負わなければならない。責任の有無について更に審理を尽くさせるため、本件を原審に差し戻すこととする。
(3) まとめ
建物に基本的な安全性を損なう瑕疵があった場合に、売主のみならず、直接の契約関係にない設計者、施工者、工事監理者に対して不法行為(ふほうこうい)
他人の権利・利益を違法に侵害したことによって
損害を与える行為をいう。
このような行為によって生じた損害については、
加害者が被害者に賠償する責任を負わなければならない。責任を認めた判決である。建物の安全性の確保について、関係者には高度な注意義務が求められている。
| 本システムの掲載情報の正確性については万全を期しておりますが、利用者が本システムの情報を用いて行う行為については本システムの制作者、運営者は何ら責任を負うものではありません。また、同種の事案について、必ず同様の結果が得られるものではありませんのでご承知おきください。なお、個別に発生したトラブル等については、管轄の行政庁等の相談窓口等にお問い合わせください。 |