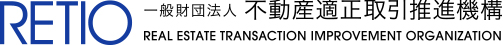| 制作:国土交通省 |
| 運営:不動産適正取引推進機構 |
| 1 本システムは、これまでに発生した不動産取引をめぐる他のトラブル事例をもとに、消費者の皆様が、トラブルの未然防止や万一トラブルに発展した場合に円滑な解決が図れるよう、情報を提供するものです。 2 掲載内容は、①裁判事例、②国土交通省各地方整備局や各都道府県で宅建業者に対して行った行政処分、③(一財)不動産適正取引推進機構で調整した特定紛争処理案件の中から基礎的で有用と思われる事例を抽出し、項目ごとに整理したうえ、事案の概要や紛争の結末等について要約して記載しています。 |
最新の情報については、
「RETIO判例検索システム」
「特定紛争案件検索システム」
「ネガティブ情報等検索サイト」(国土交通省)
「不動産のQ&A」
をご活用ください。
検索ボタンをクリックして頂くと、該当する事例の一覧が表示されます。
| トラブル事例大項目:重要事項説明に関するもの | トラブル事例中項目:都市計画等の法令上の制限 | トラブル事例小項目: |
タイトル:裁判事例接道要件を具備しない宅地についての金融機関の説明義務
最高裁判決 平成15年11月7日
(判例時報 1845号 58頁)
(判例タイムズ 1140号 82頁)
《要旨》
金融機関の従業員が、接道要件(せつどうようけん)
建築基準法第43条の規定によれば、建築物の
敷地は原則として、建築基準法上の道路と
2メートル以上の長さで接しなければならない。を具備していない土地である旨説明しなかったことが、顧客に対する不法行為(ふほうこうい)
他人の権利・利益を違法に侵害したことによって
損害を与える行為をいう。
このような行為によって生じた損害については、
加害者が被害者に賠償する責任を負わなければならない。を構成するとはいえないとされた事例
(1) 事案の概要
買主Xは、昭和62年7月ころ、金融機関Yの従業員であるAの勧めで、宅地造成がされて分譲中の土地の1区画を、Yから1200万円の融資を受けて購入した。本件土地の前面道路は、売主Bの所有する私道であり、登記上の地目は「公衆用道路」であったが、建築基準法所定の道路ではなかった。
売買契約締結には、Bのほか、売主側の媒介業者Cが立ち会った。その際、Xは、Cから重要事項説明書の交付を受けており、そこには6m幅の私道に接している旨の記載があった。
Xは、空き地のままにしていたが、前面道路部分は、平成6年5月にBの相続人が相続し、平成8年6月には、Cへ売買された。
平成11年ころ、建築確認申請をしたところ、接道要件(せつどうようけん)
建築基準法第43条の規定によれば、建築物の
敷地は原則として、建築基準法上の道路と
2メートル以上の長さで接しなければならない。を満たさないものであったため確認を受けられなかったため、Xは、Cに対し、前面道路部分について道路位置の指定(どうろいちのしてい)
都道府県知事や市町村長などの特定行政庁から
道路位置指定を受けた私道を、一般に
「位置指定道路(いちしていどうろ)
都道府県知事や市町村長などの特定行政庁から
道路位置指定を受けた私道を、一般に「位置指
定道路」と呼んでいる。位置指定道路は「建築
基準法上の道路」であるので、位置指定道路に
面する土地では、建築物を建築することができる。」と呼んでいる。位置指定道路(いちしていどうろ)
都道府県知事や市町村長などの特定行政庁から
道路位置指定を受けた私道を、一般に「位置指
定道路」と呼んでいる。位置指定道路は「建築
基準法上の道路」であるので、位置指定道路に
面する土地では、建築物を建築することができる。は
「建築基準法上の道路」であるので、
位置指定道路(いちしていどうろ)
都道府県知事や市町村長などの特定行政庁から
道路位置指定を受けた私道を、一般に「位置指
定道路」と呼んでいる。位置指定道路は「建築
基準法上の道路」であるので、位置指定道路に
面する土地では、建築物を建築することができる。に面する土地では、建築物を
建築することができる。 を受けることなどについて協力を求めたが、これを拒否された。
Xは、Yに対し、Aは接道要件(せつどうようけん)
建築基準法第43条の規定によれば、建築物の
敷地は原則として、建築基準法上の道路と
2メートル以上の長さで接しなければならない。を満たさない土地であることの説明義務を怠ったとして、損害の賠償を求めた。一審では請求棄却となったが、二審は、Aは、信義則(しんぎそく)
権利の行使および義務の履行は、信義に従い
誠実に行なわなければならないとする原則をいう。上、説明義務があるとして200万円の支払を求める限度で認容した。そこでYが上告に及んだ。
(2) 判決の要旨
(ア)Aは、XとYとの間の融資契約を成立させる目的で本件土地の購入にかかわったものである。このような場合に、Aが接道要件(せつどうようけん)
建築基準法第43条の規定によれば、建築物の
敷地は原則として、建築基準法上の道路と
2メートル以上の長さで接しなければならない。が具備していないことを認識していながら、Xに殊更に知らせなかったこと、Yが売主や販売業者と業務提携等をし、Yが販売活動に深くかかわっており、Aの勧誘もその一環であることなど、信義則(しんぎそく)
権利の行使および義務の履行は、信義に従い
誠実に行なわなければならないとする原則をいう。上、Aの説明義務を肯認する根拠となり得るような特段の事情を原審は認定しておらず、また、記録上もうかがうことはできない。
(イ)本件売買契約締結当時、Bの協力が得られることについては、十分期待することができたのであり、本件土地は、建物を建築するのに法的な支障が生ずる可能性の乏しい物件であった。
(ウ)本件土地が接道要件(せつどうようけん)
建築基準法第43条の規定によれば、建築物の
敷地は原則として、建築基準法上の道路と
2メートル以上の長さで接しなければならない。を満たしているかどうかという点は、仲介業者であるCがその説明義務を負っているのであって、Aに同様の義務があるわけではない。よってXに対する不法行為(ふほうこうい)
他人の権利・利益を違法に侵害したことによって
損害を与える行為をいう。
このような行為によって生じた損害については、
加害者が被害者に賠償する責任を負わなければならない。とはならない。
(3) まとめ
不動産取引において金融機関が関与する場面は多いと思われるが、本件ではその従業員の説明義務を肯認するには「特段の事情」が必要とされた。ただし、媒介業者Cが説明義務を負うのは判示のとおり当然である。
| 本システムの掲載情報の正確性については万全を期しておりますが、利用者が本システムの情報を用いて行う行為については本システムの制作者、運営者は何ら責任を負うものではありません。また、同種の事案について、必ず同様の結果が得られるものではありませんのでご承知おきください。なお、個別に発生したトラブル等については、管轄の行政庁等の相談窓口等にお問い合わせください。 |