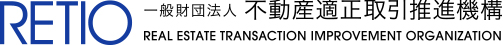| 制作:国土交通省 |
| 運営:不動産適正取引推進機構 |
| 1 本システムは、これまでに発生した不動産取引をめぐる他のトラブル事例をもとに、消費者の皆様が、トラブルの未然防止や万一トラブルに発展した場合に円滑な解決が図れるよう、情報を提供するものです。 2 掲載内容は、①裁判事例、②国土交通省各地方整備局や各都道府県で宅建業者に対して行った行政処分、③(一財)不動産適正取引推進機構で調整した特定紛争処理案件の中から基礎的で有用と思われる事例を抽出し、項目ごとに整理したうえ、事案の概要や紛争の結末等について要約して記載しています。 |
最新の情報については、
「RETIO判例検索システム」
「特定紛争案件検索システム」
「ネガティブ情報等検索サイト」(国土交通省)
「不動産のQ&A」
をご活用ください。
検索ボタンをクリックして頂くと、該当する事例の一覧が表示されます。
| トラブル事例大項目:瑕疵担保責任に関するもの | トラブル事例中項目:建物の瑕疵 | トラブル事例小項目:マンション |
タイトル:裁判事例建物の瑕疵について、建設会社及び設計監理者の責任
札幌地裁判決 平成17年10月28日
(ホームページ下級裁主要判決情報)
《要旨》
建物に施工上の瑕疵があるとして、建設会社及び設計監理者の連帯責任を認容した事例
(1) 事案の概要
Xは、宅地建物取引主任者(とりひきしゅにんしゃ)
宅地建物取引主任者のこと。宅地建物取引主任者
資格試験に合格・登録し、宅地建物取引主任者証
の交付を受けた者。であるBから紹介された建設会社Aとの間で、平成8年2月、5階建て賃貸マンションの設計及び施工に係る工事請負契約(うけおいけいやく)
家の建築工事など、当事者の一方がある
仕事を完成することを約束し、相手方が
その仕事の結果に対して報酬を支払うこ
とを約束するような契約を「請負契約」という。を締結し、工事代金合計1億641万円余を支払い、同年11月に引渡しを受けた。
しかし、Xは、本物件には、建築基準法等の建築関連法規に違反する瑕疵があるとして、A、Aの代表取締役A1、同取締役A2(裁判中に死亡したため、A2の相続人であるA1及びA3がその訴訟を承継)、B、設計監理をしたCに対し、不法行為(ふほうこうい)
他人の権利・利益を違法に侵害したことによって
損害を与える行為をいう。
このような行為によって生じた損害については、
加害者が被害者に賠償する責任を負わなければならない。に基づき、本件建物の補修費相当損害金等の賠償を求めて訴訟を起こした。
(2) 判決の要旨
(ア)本件瑕疵はAが不適切な施工をしたことによって生じた人為的瑕疵であり、Aは一般建設業者で、そもそも鉄筋コンクリート造5階建ての建物を建築するのに必要な人的、物的条件がないにもかかわらず、本件工事請負契約(うけおいけいやく)
家の建築工事など、当事者の一方がある
仕事を完成することを約束し、相手方が
その仕事の結果に対して報酬を支払うこ
とを約束するような契約を「請負契約」という。を締結し、建設業法26条1項により必要とされる主任技術者を置いていなかったことなど、ずさんな工事について、少なくとも過失があったことは明らかである。
(イ)A1は、Aの代表取締役として本件工事を統括しており、実際にも工事現場で本件工事を施工しており、作業員や下請けに対する必要な管理監督を怠り、その結果、本件瑕疵を発生させたものと認められる。Cについては、工事監理者として建築士法等に定める義務を履行していれば、本件瑕疵の発生を防止し得たことも明らかである。
(ウ)亡A2は、本件工事の施工について指示等を行い得る立場にあったと認めることができず、その承継人のA3に対する請求は理由がない。また、Bは、道義的責任は免れないものの、瑕疵についての予見可能性や結果回避可能性がない以上、説明義務や信義誠実義務違反を理由とする過失があるとすることはできない。
(エ)以上によると、本件における原告の損害につき、A、A1、Cは責任を負い、これらの被告は共同して損害賠償責任を負う。そして、補修工事に必要な費用5,104万円余、補修期間中(6カ月間)の代替建物の賃料相当損害金等約890万円、Xの精神的損害に対する慰謝料200万円、訴訟に要した費用等約969万円の合計7,163万円余が損害として認められる。
(3) まとめ
本件では、建設会社らに対する損害賠償請求を認めたものの、原告に当該建設会社を紹介した取引主任者(とりひきしゅにんしゃ)
宅地建物取引主任者のこと。宅地建物取引主任者
資格試験に合格・登録し、宅地建物取引主任者証
の交付を受けた者。については、その法的責任を否定した。しかし、宅建業者又は取引主任者(とりひきしゅにんしゃ)
宅地建物取引主任者のこと。宅地建物取引主任者
資格試験に合格・登録し、宅地建物取引主任者証
の交付を受けた者。が、一般個人から、人的つながりや過去の取引を頼りに宅地建物取引に関すること以外の事項について相談された場合(いわゆるコンサルタント業務として引き受けた場合)においては、自己の立場や関与・責任の範囲、相談料の有無等を予め明確に伝えるなどの対応が必要であろう。
| 本システムの掲載情報の正確性については万全を期しておりますが、利用者が本システムの情報を用いて行う行為については本システムの制作者、運営者は何ら責任を負うものではありません。また、同種の事案について、必ず同様の結果が得られるものではありませんのでご承知おきください。なお、個別に発生したトラブル等については、管轄の行政庁等の相談窓口等にお問い合わせください。 |