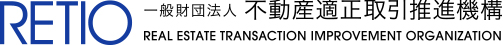| 制作:国土交通省 |
| 運営:不動産適正取引推進機構 |
| 1 本システムは、これまでに発生した不動産取引をめぐる他のトラブル事例をもとに、消費者の皆様が、トラブルの未然防止や万一トラブルに発展した場合に円滑な解決が図れるよう、情報を提供するものです。 2 掲載内容は、①裁判事例、②国土交通省各地方整備局や各都道府県で宅建業者に対して行った行政処分、③(一財)不動産適正取引推進機構で調整した特定紛争処理案件の中から基礎的で有用と思われる事例を抽出し、項目ごとに整理したうえ、事案の概要や紛争の結末等について要約して記載しています。 |
最新の情報については、
「RETIO判例検索システム」
「特定紛争案件検索システム」
「ネガティブ情報等検索サイト」(国土交通省)
「不動産のQ&A」
をご活用ください。
検索ボタンをクリックして頂くと、該当する事例の一覧が表示されます。
| トラブル事例大項目:瑕疵担保責任に関するもの | トラブル事例中項目:建物の瑕疵 | トラブル事例小項目:戸建て |
タイトル:裁判事例シロアリ被害による暇疵担保責任
東京地裁判決 平成18年1月20日
(判例時報1957号 67頁)
(判例タイムズ1240号 284頁)
《要旨》
シロアリ被害のある建物について、売主業者の瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)
特定物の売買契約において、その特定物に
「隠れた瑕疵(かし:「きず」「不具合」
「欠陥」のこと)」があったときに、売主
が買主に対して負うべき損害賠償等の責任
を「瑕疵担保責任」と呼んでいる(民法570条)。が認められ、売主業者及び媒介業者の不法行為(ふほうこうい)
他人の権利・利益を違法に侵害したことによって
損害を与える行為をいう。
このような行為によって生じた損害については、
加害者が被害者に賠償する責任を負わなければならない。責任等は否定された事例
(1) 事案の概要
買主Xは、平成13年6月、業者Y3の媒介で、売主代理人である業者Y2を介して、業者Y1の所有する築21年の土地付戸建住宅を購入した。本件建物はリフォーム済みとはいえ築年数が古いことから、現況有姿売買であることが合意された。
同年7月、Xは本件土地建物の引き渡しを受けた後、1階和室の巾木に虫食いがあることに気付き、床下を確認したところ、土台がシロアリの被害にあっていることが判明した。
Xは、専門業者による駆除を行った上で、Y1・Y2・Y3に対して、シロアリ被害を知りながら告げなかった不法行為(ふほうこうい)
他人の権利・利益を違法に侵害したことによって
損害を与える行為をいう。
このような行為によって生じた損害については、
加害者が被害者に賠償する責任を負わなければならない。による損害賠償として4,375万円を、またY1に対し瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)
特定物の売買契約において、その特定物に
「隠れた瑕疵(かし:「きず」「不具合」
「欠陥」のこと)」があったときに、売主
が買主に対して負うべき損害賠償等の責任
を「瑕疵担保責任」と呼んでいる(民法570条)。による損害賠償として1,860万円を請求した。これに対してYらは、瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)
特定物の売買契約において、その特定物に
「隠れた瑕疵(かし:「きず」「不具合」
「欠陥」のこと)」があったときに、売主
が買主に対して負うべき損害賠償等の責任
を「瑕疵担保責任」と呼んでいる(民法570条)。について、Xは本件土地建物の引渡しを受けた平成13年7月にシロアリ被害を発見しており、それから1年以内に損害賠償の請求をしておらず、除斥期間(じょせききかん)
権利行使の期間が限定され、その期間内に
権利行使をしないと権利が消滅する場合をいう。
中断(ある事由により経過した期間が消え
ること)がないこと、相手方の援用(この
規定により利益を受けることの意思表示)
がなくても効果が生じることなどで消滅時効
とは異なる。が経過している等として争った。
なお、本件土地建物はY1が、平成13年2月に、競売(けいばい)
債権者が裁判所を通じて、債務者の財産(不動産)
を競りにかけて、最高価格の申出人に対して売却し、
その売却代金によって債務の弁済を受けるという
制度のこと。手続により取得し、リフォームを行った上でXに引き渡したものであるが、競売(けいばい)
債権者が裁判所を通じて、債務者の財産(不動産)
を競りにかけて、最高価格の申出人に対して売却し、
その売却代金によって債務の弁済を受けるという
制度のこと。手続における現況調査書及び報告書には、シロアリ被害等の欠陥をうかがわせる記載は全くなかった。
(2) 判決の要旨
(ア)本件売買契約時すでに本件建物は土台がシロアリに侵食され、構造耐力上危険性を有しており、欠陥を有していたと認めることができる。
(イ)Y1及びY2は、競売(けいばい)
債権者が裁判所を通じて、債務者の財産(不動産)
を競りにかけて、最高価格の申出人に対して売却し、
その売却代金によって債務の弁済を受けるという
制度のこと。の現況調査書に本件欠陥をうかがわせる記載がなく、土台を見ていないこと、またシロアリによる建物被害について特別な知識を持っているとはいえないことから、リフォームがシロアリ被害を隠すためと推認することはできず、本件欠陥を把握していたとはいえない。また、過失により認識しなかったともいえない。
(ウ)以上によればY1及びY2に対する重要な事実の不告知による不法行為(ふほうこうい)
他人の権利・利益を違法に侵害したことによって
損害を与える行為をいう。
このような行為によって生じた損害については、
加害者が被害者に賠償する責任を負わなければならない。は成立しないというべきである。
(エ)Xが契約時に本件欠陥を知らなかったことに過失はない。取引通念上、目的物たる建物は安全に居住することが可能であることが要求され、本件建物が21年を経過した中古建物であり、現況有姿売買とされていたことを考慮しても、本件欠陥に関しては隠れたる瑕疵といわざるをえず、Y1には瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)
特定物の売買契約において、その特定物に
「隠れた瑕疵(かし:「きず」「不具合」
「欠陥」のこと)」があったときに、売主
が買主に対して負うべき損害賠償等の責任
を「瑕疵担保責任」と呼んでいる(民法570条)。が認められる。
(オ)本件における除斥期間(じょせききかん)
権利行使の期間が限定され、その期間内に
権利行使をしないと権利が消滅する場合をいう。
中断(ある事由により経過した期間が消え
ること)がないこと、相手方の援用(この
規定により利益を受けることの意思表示)
がなくても効果が生じることなどで消滅時効
とは異なる。の起算点は、少なくとも、シロアリ被害が土台の大部分に及び、建物の効用が相当程度減殺されることを認識した時点であり、瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)
特定物の売買契約において、その特定物に
「隠れた瑕疵(かし:「きず」「不具合」
「欠陥」のこと)」があったときに、売主
が買主に対して負うべき損害賠償等の責任
を「瑕疵担保責任」と呼んでいる(民法570条)。の除斥期間(じょせききかん)
権利行使の期間が限定され、その期間内に
権利行使をしないと権利が消滅する場合をいう。
中断(ある事由により経過した期間が消え
ること)がないこと、相手方の援用(この
規定により利益を受けることの意思表示)
がなくても効果が生じることなどで消滅時効
とは異なる。は経過していない。
(カ)Y3は土台を見ることはなく、シロアリについて特別に知識があるとはいえないことから、本件欠陥を認識し、または過失により認識しなかったということはできない。
(キ)以上から、Xの請求のうち、Y2及びY3に対する請求はこれを棄却することとし、Y1に対する瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)
特定物の売買契約において、その特定物に
「隠れた瑕疵(かし:「きず」「不具合」
「欠陥」のこと)」があったときに、売主
が買主に対して負うべき損害賠償等の責任
を「瑕疵担保責任」と呼んでいる(民法570条)。に基づく請求は718万円余(補修費用500万円、引越費用・家賃等218万円余)の支払を求める限度で理由があるので一部認容する。
(3) まとめ
中古住宅の売買においては、売主も十分に建物の状態を把握していないことがある。現況有姿売買としても隠れたる瑕疵が免責とならない点に注意が必要であり、媒介業者にも、専門業者による建物診断を勧めるなどトラブルを防ぐ工夫が求められる。
| 本システムの掲載情報の正確性については万全を期しておりますが、利用者が本システムの情報を用いて行う行為については本システムの制作者、運営者は何ら責任を負うものではありません。また、同種の事案について、必ず同様の結果が得られるものではありませんのでご承知おきください。なお、個別に発生したトラブル等については、管轄の行政庁等の相談窓口等にお問い合わせください。 |